
ブリテンが《戦争レクイエム》に込めた追悼と反戦への渾身の想い

数あるクラシック音楽作品の中でも印象的なタイトルをもつ《戦争レクイエム》。作曲したのは20世紀英国を代表する作曲家ベンジャミン・ブリテン。徹底した平和主義者だったブリテンが、詩や音楽、初演の歌手にまでこだわって込めた想いを、後藤菜穂子さんが解説します。
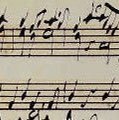
桐朋学園大学卒業、東京芸術大学大学院修士課程修了。音楽学専攻。英国ロンドン大学留学を経て、音楽ライター、翻訳家。訳書に「オックスフォード・オペラ事典」(共訳、平凡社)...
平和主義者・ブリテン
20世紀を代表する英国の作曲家ベンジャミン・ブリテン(1913〜76)が《戦争レクイエム》という直裁的なタイトルを持った鎮魂歌を作曲したのは、第2次世界大戦の終結から15年ほど後のことであった。戦時中にドイツ空軍による爆撃を受け破壊されたコヴェントリー大聖堂が1962年に再建され、その奉献式を記念する合唱とオーケストラのための大規模な作品を委嘱されたのである。

イングランド中部の都市コヴェントリーの新しい大聖堂は、旧聖堂の跡を残す形で隣に建てられた象徴的な建物であり、その意味でも、戦争の犠牲者を悼むレクイエムはこの機会にふさわしいものであった。
2012年、初演から50年を記念してコヴェントリー大聖堂で演奏された《戦争レクイエム》
ブリテンは1913年、東部サフォーク州ローストフト生まれ。少年時代から繊細な気質を持ち、戦争はもちろん、一切の争いごとや暴力を嫌悪していた。大人になってからは終始平和主義(pacifism)の立場を貫き、そうした団体のために音楽を書くなどの活動もしていた。
当然ヨーロッパにおけるナチズムの台頭には脅威を感じていたが、それでも彼にとっては武器を手に取るという選択肢はありえなかった。開戦当時、彼とパートナーのピーター・ピアーズ(テノール歌手)は米国に住んでいて(日本政府からの委嘱を受け、彼のもう一つのレクイエムである《シンフォニア・ダ・レクイエム》が作曲されたのもこの頃)、徴兵は免れていたのだが、その後帰国を決意、英国で良心的徴兵拒否者(conscientious objector)としての申し立てを行ない、彼とピアーズは徴兵免除を認められた。
もちろん、徴兵を拒否したことで世間の風当たりは強く(そもそも同性愛者であることでも風当たりは強かった)、戦地に赴く友人たちも多い中、内心さまざまな葛藤があったことと思われる。それでも彼の反戦の気持ちは揺らぐことはなかった。

典礼文と戦争に散った若き詩人の言葉が合わさった「レクイエム」
《戦争レクイエム》を普遍的であると同時にパーソナルな作品にしているのは、第一にその構成であろう。全体は、ヴェルディのレクイエムなどと同様に「レクイエム・エテルナム」、「ディエス・イレ」、「オッフェルトリウム」、「サンクトゥス」、「アニュス・デイ」、「リベラ・メ」の6つの部分から成るが、そのラテン語の典礼文のあいだに、第一次世界大戦に従軍し、終戦間際に亡くなった英国の詩人ウィルフレッド・オーウェン(1893〜1918)の詩が巧みに挟み込まれている。
ブリテンは、オーウェンの詩を1930年代ころに知って強い関心を持ち、すでに歌曲集《ノクターン》でも用いていた。オーウェンはみずからの意思で従軍したのだが、戦場で見た現実は想像をはるかに超える凄惨なものだった。その詩の多くは戦争の無益さおよび哀れさを歌っており、ブリテンの心を捉えたことは想像に難くない。

みずからが前線で戦っていた第一次世界大戦を題材にした詩で知られる英国の詩人。休戦の1週間前に戦死、母の元に死亡通知が届いたのは休戦当日の朝だった
一方、曲の編成は、3人の独唱者(ソプラノ、テノール、バリトン)、混成合唱と少年(児童)合唱、そしてフル編成のオーケストラに加えて別途室内オーケストラという大所帯だが、それらは明確に3つのグループに分けられている。
すなわち、ラテン語部分を担当するのが合唱/ソプラノ/大編成オーケストラのグループと、少し離れて配置される少年合唱のグループ、そしてオーウェンの詩はテノール/バリトン/室内オーケストラが担当する。これによって、兵士たちの現実世界、彼らを悼む人々、そして少年合唱による天上の声が、音楽的にもくっきり描き分けられる。
戦場を思わせる金管や打楽器の鋭利な響き、室内オーケストラの卓越した器楽書法、テノールとバリトンの切々とした語り、そして慰めに満ちた合唱。
テノールとバリトンが唯一、対話の形で歌うのは、第6部「リベラ・メ」の中の「奇妙な出会い(Strange Meeting)」である。ここでは、死後の世界で一人の兵士(テノール)が自分が殺した敵方の兵士(バリトン)と遭遇するという印象的な場面が語られるが、やがて二人は和解を果たし、眠りにつく。そして合唱およびソプラノ独唱が「イン・パラディスム(楽園へ)」と締めくくる。
大戦で敵対した国の歌手たちの共演を望んだブリテン
1962年5月30日に行われた初演において、テノール独唱に英国人のピアーズ、バリトン独唱にドイツ人のディートリヒ・フィッシャー=ディスカウを配したのは、大戦で敵対した国の歌手を起用することとで和平の象徴としたかったからであろう。
一方、ソプラノ独唱には、前年、ブリテンが主催するオールドバラ音楽祭に出演したロシア人のガリーナ・ヴィシネフスカヤ(ロストロポーヴィチ夫人でもあった)を起用しようとしたが、残念ながらソビエト政府の許可が降りず、初演では英国人のヘザー・ハーパーが歌った。とりわけ第2部でソプラノが合唱を従えて切々と歌う「ラクリモーサ(涙の日)」が胸を打つ。
なお、翌年デッカからでた録音(ブリテン自身の指揮による)ではヴィシネフスカヤが歌い、ようやく3か国の歌手が揃った。

Harry Pot - [1] Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANeFo), 1945-1989, Nummer toegang 2.24.01.05 Bestanddeelnummer 914-7822

Dietrich Fischer-Dieskau at the public presentation of his book “Töne sprechen, Worte klingen” in Berlin; May 29, 1985
ちなみに初演ではブリテンは室内オーケストラのグループのみを指揮、オーケストラ(バーミンガム市交響楽団)と合唱(アマチュア合唱団の寄せ集め)の指揮はメレディス・デイヴィスが行なった。
《戦争レクイエム》は4人の亡き友——第二次世界大戦で命を失った3人および戦後みずからの命を絶った友——に捧げられているが、古今東西すべての戦争の犠牲者への哀悼(ブリテンは広島や長崎への原爆投下にも心を痛めていたことが知られている)と反戦への渾身の思いが込められているのだ。
初演の翌年にセッション録音された「ブリテン:戦争レクイエム」。この録音は世界中で評価され、日本でも第一回レコード・アカデミー賞を受賞している
関連する記事
-
イベント【2025年 夏休み】親子で楽しめるクラシック・コンサート
-
イベント東京芸術劇場がまるごと楽しめる特別な1日「芸劇大公開!」
-
レポート近藤 譲の唯一のオペラ『羽衣』が サントリー音楽賞受賞記念コンサートで日本初演
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest















