
ホスピタルアートでより良い医療現場を——アートや音楽を導入する耳原総合病院

医療現場にアートや音楽を導入することで、現場職員の「働く場所」をより良いものにする……そんな病院がある。どのような活動を行なっているのか。いかに職員の自主性を引き出すのか?その取り組みをレポート!

1997年大阪生まれの編集者/ライター。 夕陽丘高校音楽科ピアノ専攻、京都市立芸術大学音楽学専攻を卒業。在学中にクラシック音楽ジャンルで取材・執筆を開始。現在は企業オ...
「スタッフ」をメインターゲットとしたアートを
人々の健康を守る上で欠かせない、病院。そこにアートを導入すると、もしかするとポジティブな変化が生まれるかもしれない。
そんな期待を形にするかのように、医療現場にアートを導入する「ホスピタルアート」を実践しているのは、大阪府堺市にある耳原総合病院だ。

耳原総合病院は、世界文化遺産の「百舌鳥古墳群」の近くに位置し、どこか歴史と文化の匂いが漂う場所にある。
約30科・386床を兼ね備え、約800名の職員が在籍しており、規模が大きい総合病院。それだけに多くの人が病院を訪れる、流動的な場所だ。
「ホスピタルアート」とは、病院にアートを導入することで、空間内をより快適で癒しとなる場にすること。アート作品を飾ったり、患者さんが実際に絵を描いたり、と導入方法は病院によって異なる。
耳原総合病院の場合、少し特殊かつ積極的だ。病院の随所に散りばめられたアートや音楽は、第一にそこで働く医師や看護師、職員によってより良い「働く現場」を実現するためのものであるから。彼らにとって良い医療現場をアートで実現できれば、患者さんにも良い医療を提供できる——。そんなビジョンを持っている。




それを実現するためには、アートディレクターの存在が欠かせない。チーフの室野愛子さんを中心に、アートや音楽に造詣の深いメンバーがディレクション務めている。
彼女たちは、実際に絵を描いたり作品を創作したりするわけではない。医師・看護師・スタッフが、自らアートで現場を良くするために動き出すよう後押しするのが仕事だ。


病院特有の音環境に合わせた音楽を
では、アート作品を飾るだけでない、「ホスピタルアート」とはどんなものなのか。2つの事例を紹介しよう。
1つ目は、音楽的な観点から。
アートを用いて現場の職員の「働く場所」を整えているのは、視覚的なアートだけではない。院内に流れている「音楽」を工夫し、聴覚的な観点から整えているのも同院の大きな特徴だ。
病院空間のために作曲した作品を使用し、院内にいる人々の聴覚的な負担を軽減させる工夫が施されている。作曲を担当したのは、ピアニスト・作曲家であり、京都精華大学教授の小松正史さん。

小松さんは、公園や美術館など、多くの公共施設の環境音楽を手がける「音環境デザイナー」。空間の特有の音環境を把握し、その場に適した音楽を作るのが小松さんの仕事だ。制作した音楽を導入し、空間と音環境を「デザイン」する。
小松さんは、耳原総合病院に適した音楽を制作するために、最初に院内フィールドワークを実施。音環境を観察したところ、病院特有の特徴が見えてきたという。それは、ナースコールや呼び出し放送、多く行われる院内の人々の会話の声、足音など、多様な音が存在したこと。それらは、人々が必ずしも意図的に意識している音ではなく、活動の結果として発生した音である。しかしながら、意識に届き疲弊感や緊張感の原因にもなり得る。人間はそのような音を意識の領域で捉えるため、院内にある音の数々に不快感をもたらしている可能性が高い。意識と前意識に作用するような音楽を作ることが大切であると、
「目の場合、人にはまぶたがあるため、見えるものを取捨選択することができますよね。でも、耳には同等の役割を果たすものがなく、代わりに脳がコントロールしているんです。そんな聴覚的フレームに負担をかけない音楽が、環境音楽なのです」(小松さん)
また、院内のアートにより視覚的には充実しているが、音環境は何も整っていない、という聴覚とのギャップも課題に。限定された空間内に、多様な音がこもっているようにも聞こえたという。
またもともと使用していたBGMに関しては、現場職員から「現場と調和していない」といったネガティブな声もあったそう。
では、そのような課題を踏まえて、小松さんはいかに音楽制作を行なったのか。
「音環境がもたらす心理的な負担を軽減するために、『
「マスキング」が意味するものは、2つ。1つ目は、意識で認識される院内の音(ナースコールや、人々の会話…など音の数々)を、「散らす」こと。
「前意識で認識する音を、『意識的』な音でマスキングして、そちらに院内の人々の耳を傾けさせること。ではどんな音でマスキングするかというと、音楽の旋律です。とはいっても、
ここでポイントなのが、知っている音楽や、「思わずうっとり聴き入ってしまう」というような要素を避けること。「人々の意識の“間”にあるような音楽。注意すれば聴こえるけど、注意しなければ聴こえない。音楽の流れとしては、大きな変化を与えないようにしました」
もう1つは、院内の雰囲気を柔らかくするための「ソフトな響き」を作り出すこと。
「意味のない響きを音楽に取り入れます。例えば、“もわん”としたメロディ以外の和音を、院内の音環境に加える。そうすることで、前意識的な音をマスキングし、心理的に感じるうるささを減らすことができます」
他にも、「飽き防止」のために音楽を流す時間を指定したり、5分程度の音楽を入れ替えたり、といった工夫も施した。
完成した環境音楽は、ピアノソロとアンサンブルによる優しい作風のもの。「ピアノの音色は、急激な感情の変化を表に出さない特徴がある」と小松さんが話すように、人の聴覚に自然に浸透していくように、旋律が奏でられる。
では、完成した環境音楽は、現場の職員に対して何らかの効果を与えたのだろうか。
小松さんは、職員を対象にアンケートをとることで、実際に結果を示している。以前使用されていたBGMの音環境、無音の状態、そして新しく制作された環境音楽が流れる音環境、3パターンにおける職員たちの「音環境への印象」を調査。
その結果、新しく制作されたBGM評価がポジティブな方向へ有意に変化する
また、以前使用されていたBGMには「違和感がある」と評されることもあったが、新しい環境音楽には「違和感はない」「気持ちが安らぐメロディ」「院内の雰囲気と合っている」という声も。
「今、ここで職員がどのように感じて働いているのか。音に対してどんな意識を持っているのか」といった現状を踏まえて、音楽的なアプローチから職場環境を整える。目に見えて魅力的な視覚による「アート作品」と、目に見えなくともいつもそばにあるような「環境音楽」。室野さんは、「人が話す声で人柄を印象づけるように、病院がまとう音も病院の印象を作ります。小松先生の作る音楽は、当院と相性がぴったりだと思いました。院内のアートと合わさって一つの作品になったように思います」と話す。
自らの働く場所の「音」を、意図的に認識する人は多くないはず。しかし、このポイントを抑えるだけで、「働きやすい環境づくり」を醸成し、それがより良い働き・医療提供につながるのではないだろうか。
病院に集う人々の「声」を引き出すワークショップ
2つ目は、病院に集う人々の声で作品を作り上げる、「希望のともしびプロジェクト」。病院全体を「絵本」とし、建物の外壁を「表紙」、院内を「物語」に見立てて、各階に鳥の絵が描かれた。
鳥は、かつて室野さんが同院の歴史を物語にしたときに象徴的に描かれたキャラクターだ。それを建物にも描くことで、立体的に具現化することができる。
このプロジェクトの肝は、職員・患者・地域住民による3回にわたるワークショップ。「何を描こうか」と参加者でアイデアが交わされた。地域に馴染み深い住民は「この地域はかつて……」と、職員は「この病棟にはこんな患者さんが多いから……」などと各々の立場から知識を交わし、具体的なアイデアが生まれた。
こうして各階に描く鳥のテーマが決定し、実際に鳥が描かれた。壁画は、原画をもとに職人が手掛けたそうだが、職員も仕上げの色塗りに参加するなど、積極的な姿勢が見られたという。室野さんは、「このプロジェクトから、耳原のホスピタルアートの形ができあがったと思います」と話す。




目の前の患者さんのために、できることは何か?主体的に考える職場を目指して
音楽という目に見えないものによって良い職場づくりが促進されたり、職員の「声」が重視されたりするなど、あらゆる側面から「アート」が施されている耳原総合病院。実際に職員満足度も高い。ホスピタルアートに積極的に関わってきた岩﨑桂子医師は、「ホスピタルアートは、医療現場のさまざまな環境をより良くしたい、と思う職員の姿勢を後押ししてくれる」と話す。
「医師以外の個人の意見が埋没するパターンが多いなか、アートを通して『医師以外のスタッフも意見や思いを表現してもいいんだ』という雰囲気になりました」
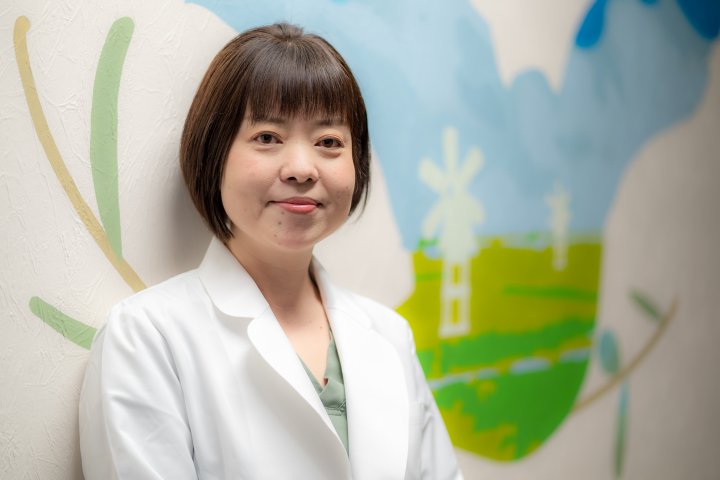
その例として、利用者から意見を聞くための部屋や、病状を伝えるための部屋について、「アートを施せば、もっと良くなるのでは」と声を出した職員もいた。もともと真っ白だった部屋に色が増えることで、そこにいる職員や患者さんが安心できることを目指したという。
同院のホスピタルアートでは、アートディレクターの室野さんが単独で起案を行なうわけではない。現場職員が「アートを使えば、こんなところはもっと良くなるのでは」と発案するところから始まる。

岩﨑先生は、「ホスピタリティを大事にする職場は、そのお客さんのために、何ができるか? 何をしたら喜んでもらえるか? を考えられる職場だ思います」と話す。
「病院も同じです。キッチリ考えるだけではなく、違う意見や突出した意見が出てこそ磨かれていくもの。医療的なマニュアルをこなすだけではつまらないですよね。自分が積極的に関わろう、考えを深めていこう、と自主体的に医療や患者さんに関わっていきたい、というマインドがアップしていると思います」
岩﨑先生には、アートで実現したい病院の形がある。それは、「優しい病院にする」ことだ。
「患者さんやご家族、職員にとって、分け隔てなく包み込む空間がいいですね。疲れてしまうとギスギスすることもあり反省してしまいますが、自分自身が優しくされないと、患者さんにも優しくできません。アートがそんな現場スタッフのさまざまなマインドを具現化してくれたことで、病院の想いやビジョンが統一感を持つようになってきたと思います。それをもっとクリエイティブに表現していきたいです」
耳原総合病院がアートを通じて実現したいビジョン
アートディレクターの室野さんや虎頭さん、岩﨑先生がアートに関して口を揃えて話したのは、「多様性」や、「違う立場の人への理解」。
「職員も、患者さんも、分け隔てなくバックボーンを捉えること。アートを媒介して生まれた言葉を拾い、その一言をどう理解できるのかが重要なのだと思います」(虎頭さん)
「耳原は無差別平等や平和、マイノリティの方も受け入れる、という理念を掲げています。多様性や、寛容に物事を受け入れる姿勢をアートで具体化していきたい。そんなマインドを膨らませていきたいです」(岩﨑医師)
「職員や患者さん、地域住民の言葉や物語を引き出し、表現することで、芸術・文化の側面から理念の土台を支えていければと思っています」(室野さん)
職員同士、職員と患者さんなど、同じ立場でも、違う立場でも、他者を理解すること。そんな違いを思い合う土台を、アートや音楽で作り出す。相手を思いやる心を、心地よい空間で生み出していく。
それは、「健康のライフライン」である病院だからこそ重要なことではないだろうか。大切な命を守るための手段として、アートは何よりも有効なのかもしれない。
関連する記事
-
レポートガジェヴが巨匠メータと共演でインド・デビュー!~西洋圏外でのクラシック受容を考え...
-
イベントろう者・難聴者の方も音楽を視覚的に体感できるコンサートが無料ライブ配信
-
イベント東京音大で社会学者・宮台真司が「アーティストにしかできないこと」をテーマに特別講...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest

















