
ギリシャ悲劇の現代にも通じる人間模様を描く――生田斗真主演、新国立劇場『オレステイア』

歴史の授業で習った「ギリシャ悲劇」。長い神様の名前や、複雑なストーリーからちょっと敬遠してしまいそうですが、実は現代人の我々も共感できる「人間臭い」ドラマが詰まっているようです。
新国立劇場で2019年6月に上演される『オレステイア』は、そんなギリシャ悲劇の人間模様によりクローズアップした、イギリスの劇作家ロバート・アイクよる翻案版。高橋彩子さんが、すべての舞台芸術の生みの親「ギリシャ悲劇」の復習も兼ねてナビゲートしてくれました。

早稲田大学大学院文学研究科(演劇学 舞踊)修士課程修了。現代劇、伝統芸能、バレエ、ダンス、ミュージカル、オペラなどを中心に執筆。『The Japan Times』『E...
西洋発祥の舞台芸術の原点はどこにあるかと問われれば、多くの人は古代ギリシャの演劇と答えるはずだ。俳優が演じる劇の登場人物たちの言葉・行動と呼応する形で、集団=コロスが語り歌い踊った古代ギリシャ劇。ワーグナーは著書『芸術と革命』の中で、音楽と演劇が一体となった古代ギリシャ劇を一つの理想形とした。いや、そもそもオペラ自体、ギリシャ悲劇の再興を期して生まれたとさえ言われている。
永遠に新しい、ギリシャ悲劇の世界
古代ギリシャ演劇には悲劇・喜劇・サテュロス劇などの種類があったが、中でも王道とされたのが、悲劇だ。その“三大悲劇詩人”は、アイスキュロス(『ペルシャ人』『オレステイア』三部作など)、ソポクレス(『アンティゴネ』『エレクトラ』『オイディプス』など)、エウリピデス(『メデイア』『エレクトラ』『アウリスのイピゲネイア』『タウリケのイピゲネイア』など)。
彼らの作品群のタイトルを見れば、今もしばしば上演されるのみならず、その後の数多の芝居やオペラのもとにもなったことがわかるだろう。19〜20世紀のドイツの思想家ニーチェが処女作『悲劇の誕生』で著したのも、ギリシャ悲劇の成立および盛衰だった。ギリシャ悲劇はそれだけ、西洋の文学・芸術史において欠かせない存在なのだ。
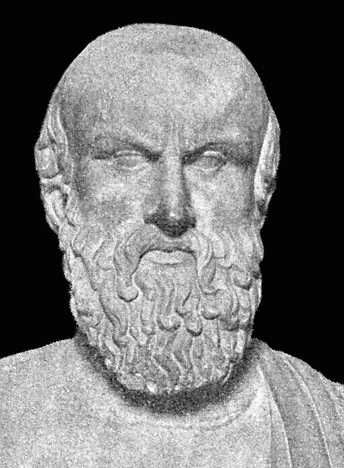

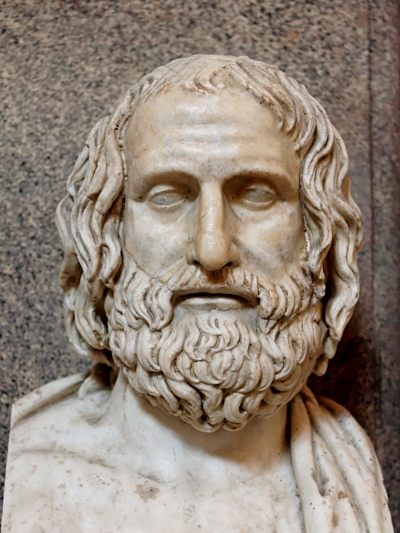
上:ソポクレス(497/6年頃-406/5年頃)
左:エウリピデス(紀元前480年頃-406年頃)
ギリシャ悲劇の中心人物となるのは王族など、神ともつながりの深い高貴な人物たち。だが、彼らの欲望、嫉妬、怒り、葛藤、悲嘆などは実に人間的で、現代の私たちにも共感できるものとなっている。人の心理を表すのに「エディプス(=オイディプス)・コンプレックス」や「エレクトラ・コンプレックス」などといった言葉が使われるのも、このことを裏付けるだろう。
神々が人々を直接的に動かすところは現代的な感覚と異なるかもしれないが、その神々もまた、夫婦喧嘩をしたり競い合ったりと、何とも“人間的”。というより、ギリシャ悲劇における人間同士の諍いは時に、神々がそれぞれに応援する人物たちのぶつかり合い、つまり、神の代理戦争ですらある。
説明のつかない何かによって動かされる運命の歯車と、手に取るようにわかるリアルな人間模様が、ギリシャ悲劇の妙味かもしれない。その世界は、現代の作家をも刺激し続けている。
ギリシャ悲劇を血の通ったリアルなドラマに。アイク版『オレステイア』
さて、イギリスの劇作家・演出家のロバート・アイクが2015年に初演した『オレステイア』は、アイスキュロスの『オレステイア』と、その前日譚とも言うべきエウリピデスの『アウリスのイピゲネイア』などをもとにした芝居だ。
物語の中心となるのは、ギリシャとトロイアが戦った“トロイア戦争”において、ギリシャ軍の総大将を務めたアガメムノンの一族。
実は、この戦争を企てたのは、増え過ぎた人類を減らそうと考えた大神ゼウスだった。彼はまず、3人の女神、ヘラ、アテナ、アフロディテが、自分たちのうち誰が一番美しいかを競い合うよう仕向ける。女神たちは羊飼いパリスに審判を頼み、自分を選んだ報酬として、ヘラが権力、アテナが武力、アフロディテが世界一の美女を持ちかけたところ、パリスはアフロディテを選び、美女ヘレネを入手。だがヘレネにはメネラオスという夫がおり、しかも結婚にあたって幾多の求婚者たちは、選ばれた花婿が困難に遭った際は全員で力を合わせて助けるという誓いをしていた。そこで、メネラオスの兄アガメムノンがこの誓いを持ち出し、ヘレネ奪還のための戦争が幕を開ける。


ところが、アガメムノンが女神アルテミスの怒りを買ってしまったことから、ギリシャ軍は出帆できず、アガメムノンの長女イピゲネイアを生贄に捧げるようにとの神託が出る。アガメムノンはこれに応じ、戦争はギリシャの勝利に。
これに怒ったのが、アガメムノンの妻でありイピゲネイアの母であるクリュタイメストラだ。彼女は愛人アイギストスと計って、帰国した夫および彼が連れ帰ったトロイア王女カッサンドラを殺害。しかしそのクリュタイメストラも、次女のエレクトラ、そして父の仇を討つようにとの神託を受けた長男オレステスによって、アイギストスと共に殺される。親殺しをしたオレステスは復讐の女神エリニュスに責め苛まれることになり……。物語の背後には、彼らアトレウス家にかけられた呪いの存在もあるから、コトは一筋縄ではいかない。

アイクはこの大筋はそのままに、神々の思惑や呪いといった超自然的な力よりも、ごく自然な人間たちの心理や行動に焦点を当て、現代の感覚で作品世界を読み解いていく。どこにでもある家族団らんの光景、袋小路に陥った政治家としてのアイギストスの姿など、原作にもある要素を活かしながら、血の通ったリアルなドラマを再構築するアイクの手つきは鮮やか。
手に取るように伝わる登場人物それぞれの状況や思いを追ううち、物語は原作と同じラストの法廷シーンへ。罪と正義について問いかける結末は、必見だ。なお、ギリシャ悲劇のようなコロスは登場せず、俳優たちが同時に発声することでその役割を果たす。
気鋭・上村聡史の演出で、生田斗真が主演する日本初演
新国立劇場では、このアイク版『オレステイア』を、気鋭の演出家・上村聡史の演出で日本初演する。上村は文学座出身の39歳。レバノン出身の劇作家ワジディ・ムワワドが自身のレバノン内戦の体験を色濃く反映した“約束の血四部作”の2作『岸 リトラル』『炎 アンサンディ』や、太平洋戦争終戦7年後の人々の不安や虚無や焦燥・狂騒を鮮烈に描き出した三好十郎の『冒した者』、10本のギリシャ悲劇をまとめた約10時間の芝居『グリークス』などなど、骨太な作品の演出に定評がある(なお、『グリークス』は11月、KAAT神奈川芸術劇場で杉原邦生の演出で上演予定)。
新国立劇場では既に、14年にジャン=ポール・サルトルの『アルトナの幽閉者』、17年に安部公房の『城塞』で、演出を手がけた上村。『アルトナの幽閉者』は第二次大戦後、部屋に閉じ篭る息子、富める父、義理の妹らの姿を通して、神なき時代の絶望、閉塞状況、加害と被害、罪と罰などを扱った作品。『城塞』は、終戦を機に自らの時間を止める「拒絶症」にかかった父とその息子が終戦時を繰り返し再現する姿を通して、戦後17年目の1962年(初演と同じ年)から戦争をみつめる作品。共に、20世紀の戦争と向き合った2作を痛烈に問いかけた上村は今回、人間の罪と裁きをどのように描くのだろうか。
オレステスには生田斗真。蜷川幸雄演出『わが友ヒットラー』ヒットラーや『サド侯爵夫人』アンヌ、ケラリーノ・サンドロヴィッチ演出『かもめ』トレープレフ、小川絵梨子演出『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』ローゼンクランツなど、数々の名作舞台を経験してきた生田のオレステス像が楽しみだ。エレクトラを音月桂、アガメムノンを横田栄司、クリュタイメストラを神野三鈴、イピゲネイアを趣里が演じるほか、音月桂、松永玲子、倉野章子……と役者が揃う。上演は4時間を超えるようだが、息もつかせぬ迫真のドラマが展開されるに違いない。

会期: 2019年6月6日(木)~6月30日(日)
会場: 新国立劇場 中劇場
チケット: S席8,640円 A席6,480円 B席3,240円 Z席(当日券)1,620円
原作:アイスキュロス
作:ロバート・アイク
翻訳:平川大作
演出:上村聡史
出演:
生田斗真
音月桂
趣里
横田栄司
下総源太朗
松永玲子
佐川和正
チョウヨンホ
草彅智文
髙倉直人
倉野章子
神野三鈴
関連する記事
-
記事第3回ワールド・オペラ・フォーラムが2028年に新国立劇場で開催!
-
イベント新国立劇場オペラの新シーズンはプッチーニとラヴェルが描く「母子の愛」で開幕!
-
イベント臨場感と本気度が違う!新国立劇場が『ラ・ボエーム』で初のライブ配信&オンデマンド...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest


















