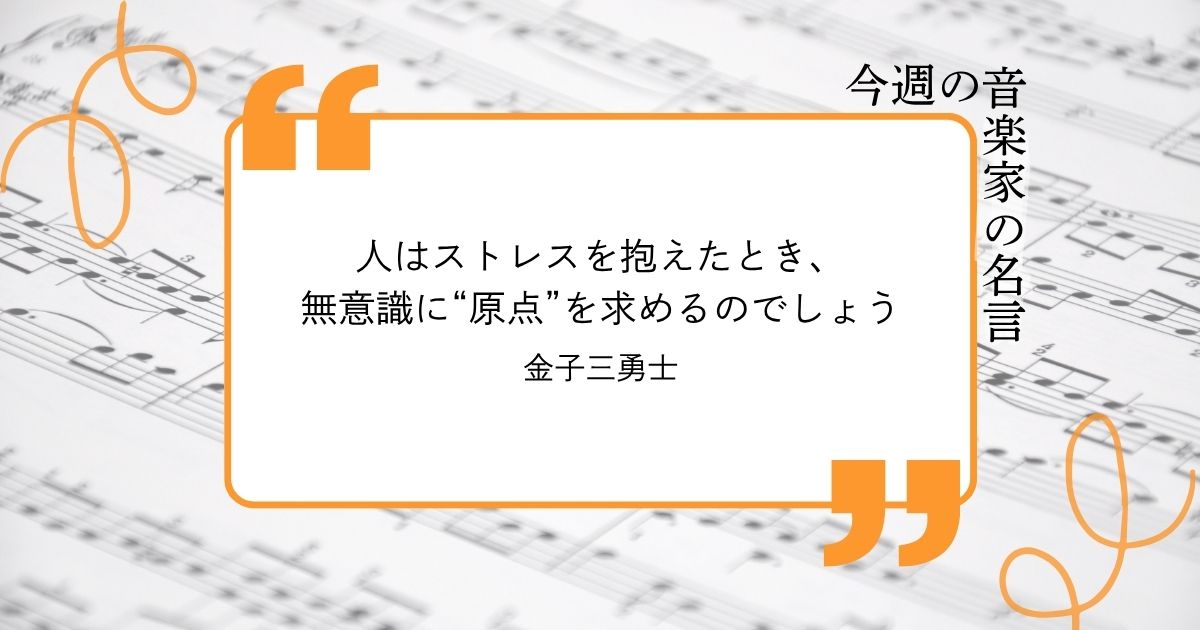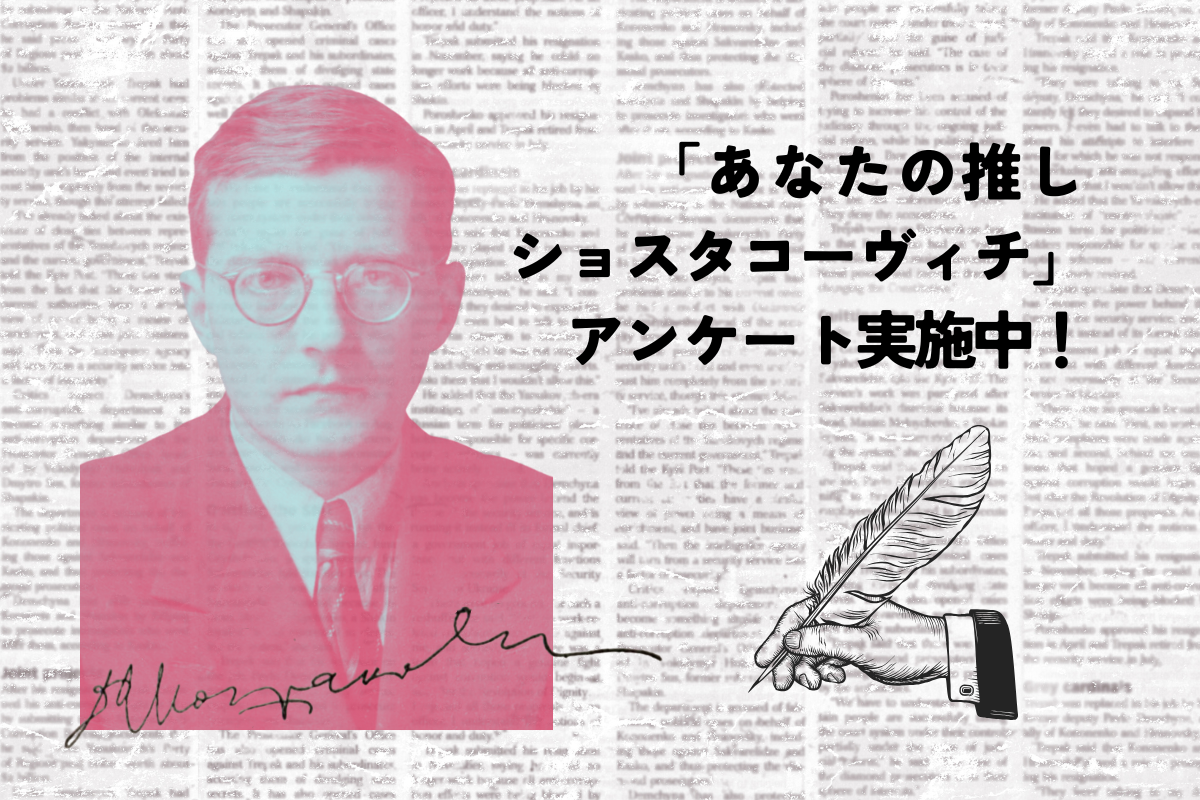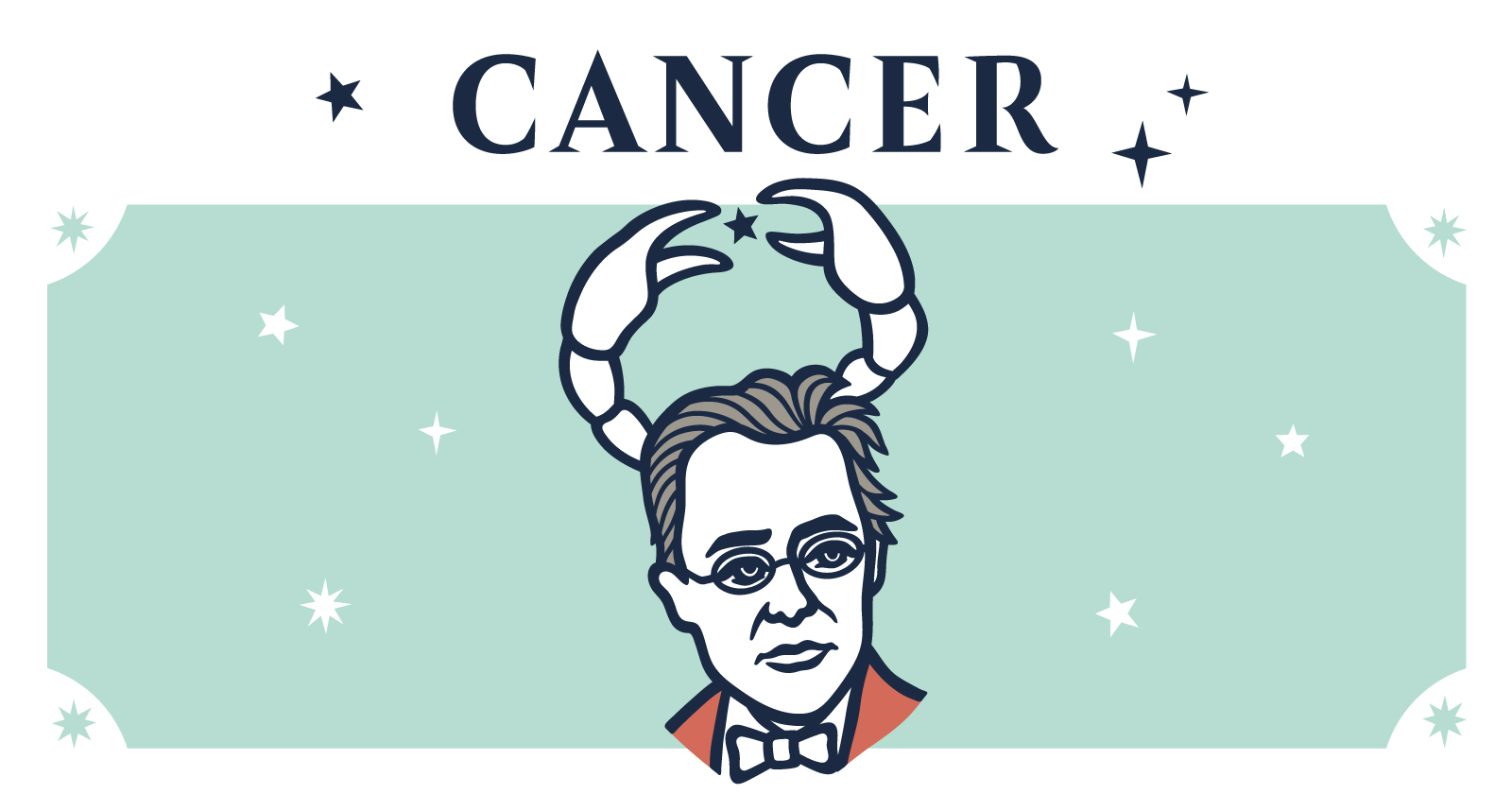ルターを匿い、ワーグナーが描いた「歌合戦」の舞台〜ドイツ・ヴァルトブルク城の物語

西洋史の重要エピソードを、絵画や音楽で紐解き、今につながるヒントを得る連載。第2話は、中世の歌合戦、ルターの聖書翻訳、ワーグナーのオペラと、ドイツの文化を長きにわたって見守ってきた「心のふるさと」、ヴァルトブルク城のお話。

東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、同大学院博士課程満期退学(音楽史専攻)。音楽物書き。主にバッハを中心とする古楽およびオペラについて執筆、講演活動を行う。オンライン...
ワーグナーも心震わせた伝説を生む古城
歴史を変えた「人」がいるように、歴史を見つめた「場所」がある。何世紀もその場にあり続け、人々の心の拠り所となり、新しい芸術を生み出すきっかけとなった「場所」が。
ドイツのちょうどまんなかあたりに建つヴァルトブルク城は、数々の伝説を生み、歴史を変える出来事が起こった、ドイツ人にとって特別な場所である。十字軍から宗教改革、ドイツ統一まで、ドイツ史の転換点にはこの城の姿が燦然と輝いている。
ヴァルトブルク城は、アイゼナッハの郊外、岩山のいただきに迫り出すように聳える山城だ。車で街に近づくと、目の前の高みに城のシルエットが飛び込んでくる。その光景は感動的だ。
作曲家リヒャルト・ワーグナーは、作品が認められずに不遇をかこったパリからドレスデンに向かう途中、この城の姿を目撃して心を震わせた。その3年後、ワーグナーはこの城で行なわれたという伝説の歌合戦をハイライトにしたオペラ《タンホイザー》をドレスデンで初演している。
《タンホイザー》は、中世の宮廷で活躍していた騎士歌人の物語である。11世紀に南フランスで誕生した「騎士歌人(トルバドール、ドイツ語でミンネゼンガー)」は、十字軍がきっかけとなって大流行した騎士道の産物で、遠征先の中近東の音楽に刺激を受けて生まれたという。南フランスが発祥の地なのは、十字軍が始まった場所だからだ。
ワーグナー:楽劇《タンホイザー》〜歌合戦が描かれる第2幕
「伝説の歌合戦」と「聖エリザーベトの奇跡」
要塞として建てられたヴァルトブルク城が歴史のスポットを浴びるのは、「騎士歌人」たちによる「歌合戦」が最初である。この辺りを治めていたテューリンゲン方伯ヘルマン1世が、1206/7年ごろに騎士歌人たちによる「歌合戦」を開催したという伝説があるのだ。
ヘルマンもまた十字軍に参加し、騎士歌人に魅せられて自分の城に招くようになった。「歌合戦」と言っても、当時のそれは私たちが想像するような優雅なものではなく、負ければ処刑されてしまうこともある粗野な催しだった。
ワーグナーのオペラでは、主人公のタンホイザーはキリスト教で禁じられていた「官能の愛」を賛美して袋叩きにあうが、伝説上の歌合戦では、ヘルマン1世を褒め称えずに自分の領主を賛美した歌人が吊し上げられ、あわや処刑というときにヘルマンの妃によって救われたという。
城内にはそれにちなんだ「歌合戦の間」があり、19世紀の画家モーリッツ・フォン・シュヴィントが、この劇的なシーンを色鮮やかな壁画に仕上げている。

画面右手で、足を投げ出してリュートを手にしているのはワーグナー。画面中央、ヘルマン夫妻の右手にいるのは、有名な歌人ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデと重ね合わされたリスト。画面左端で、修道僧の黒衣をまとってリュートを手にしているのはルター。
中世ドイツにおける最高の抒情詩人で、騎士歌人のヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ(1170頃〜1230頃)の詩、「菩提樹の下で」。
そのヘルマンの息子に嫁ぎ、後に「聖人」になったハンガリー王女エリーザベト(エルジェーベトとも)は、ヴァルトブルク城のヒロインというべき存在だ。《タンホイザー》のヒロインのエリーザベトのモデルは「聖エリーザベト」である。
エリーザベトは本連載の第1回で取り上げた聖フランチェスコの思想に触れて感動し、福祉活動に情熱を注いだ。貧者への施しのパンを夫に見咎められたとき、籠に入っていたパンがいつの間にか薔薇に変わっていたという「薔薇のエピソード」は有名だ。

十字軍に参戦した夫が軍中で亡くなると、エリーザベトは城を出て救貧院で働き、24歳の若さで逝くが、死後まもなく列聖されて「聖エリーザベト」となった。薔薇はエリーザベトのシンボルとなり、ヴァルトブルク城では薔薇をあしらったアクセサリーや薔薇のジャムが売られている。
ルターによ聖書ドイツ語訳が行なわれた小さな部屋
それから3世紀。ヴァルトブルク城に一人の修道僧が逃げ込んできた。カトリック教会の腐敗を糾弾し、教皇から破門され、神聖ローマ皇帝から追放になったその僧の名はマルティン・ルター。
お尋ね者と知りながら彼をかくまったのは、ザクセン選帝侯フリードリヒ3世である。選帝侯もまた、俗世の欲にまみれた聖職者たちにうんざりしていたのだ。
かつては牢獄だった質素な部屋をあてがわれたルターは、うなぎの寝床のような狭いスペースに寝起きし、時にこっそり里帰りしながら、わずか3ヶ月足らずで『新約聖書』をドイツ語に訳した。ちょうど活版印刷が盛んになってきた時期で、1522年に初版が出版されたルター訳の『新約聖書』はたちまちベストセラーになる。

©︎Ingersoll
それまで聖職者が独占し(ルターが初めて目撃した聖書は、鎖で繋がれていたという)、信者は教会に描かれた壁画で知るのがせいぜいだった『聖書』の内容が、一般に開かれたのだ。
ルターからバッハのカンタータに受け継がれた「賛美歌」
ルターは音楽を愛し、伝道に活用した。信徒が歌えるシンプルな「讃美歌(コラール)」を提唱し、自分で作詞作曲もした。「讃美歌」はルターの教えが広がった地域に行き渡り、教会学校の必須科目になり、礼拝で讃美歌を伴奏するオルガンは、信徒たちの声に負けないように大きくなり、発展した。
ルターの親友だった画家のルーカス・クラナッハ(父)は、ルターの肖像画を描きまくり、強い意志を感じさせるその顔つきは、讃美歌と同様、ルター派地域のアイコンになった。ルターもまた薔薇を好んで紋章にしたので、「薔薇」は二重にヴァルトブルク城で愛されるようになった。

それから1世紀半ほどあと、ヴァルトブルク城の麓に広がるアイゼナッハの街で、ヨハン・セバスティアン・バッハが生まれる。およそ2世紀続く音楽一家、バッハ一族の最大のスターである。
その一族は、ルター派の一族でもあった。バッハ少年は、かつてルターが通ったアイゼナッハの教会学校に通い、町楽師と宮廷楽師を兼ねていた父に連れられてヴァルトブルク城に登った。
バッハとルターは似ている。働き者で、家庭人で、社交好き。バッハは繰り返し、ルターの讃美歌に曲づけした。ルターの讃美歌に基づいたカンタータ第80番《我らが神は堅き砦》は、ルターとバッハの繋がりから生まれた名曲の代表格だ。
J.S.バッハ: カンタータ第80番《我らが神は堅き砦》
ドイツ統一を見届けた、文化的な「心のふるさと」に
それからおよそ1世紀後。ヴァルトブルク城を「ドイツ文化の精髄が残っている場所」だと感じたゲーテは、荒れていた城の修復を提言する。その提言が形になるころ、ドイツは統一への道をたどっていた。
栄光の歴史をもつヴァルトブルク城は、時にドイツ統一を要求した学生結社の集会所になり、時にワーグナーのロマンティックなオペラの舞台になって、ドイツ人の意識に繰り返し刷り込まれた。
ヴァルトブルク城に登るには、今でもかなりの数の石段を上がらなければならない。けれど、「テューリンゲンの森」と呼ばれる森を見渡す城からの眺めは最高だ。
ここでは文化と自然が手を取り合って微笑んでいる。「ドイツ人の心のふるさと」と呼ばれるのも、もっともなのである。それも激動の19世紀に、ドイツ文化のシンボルとして復興したおかげだ。文化は、不要不急のものではない。それは荒波に揉まれる時にこそ、心を支えてくれるものなのだ。

関連する記事
-
インタビュー京都市交響楽団コントラバス奏者・出原修司さん(Juvichan)〜「ジュビレーヌ...
-
イベント2025年、ショスタコーヴィチを聴く―主要演奏会一覧
-
イベント現代最高のチェリスト、ジャン=ギアン・ケラスがバッハ《無伴奏》を語る
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest