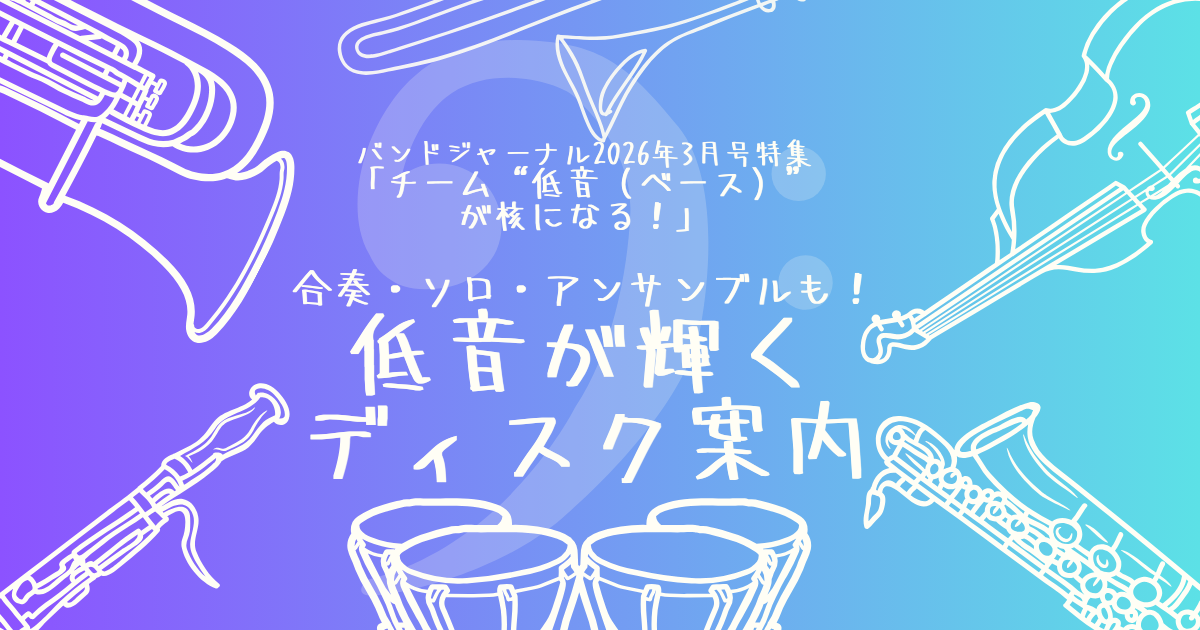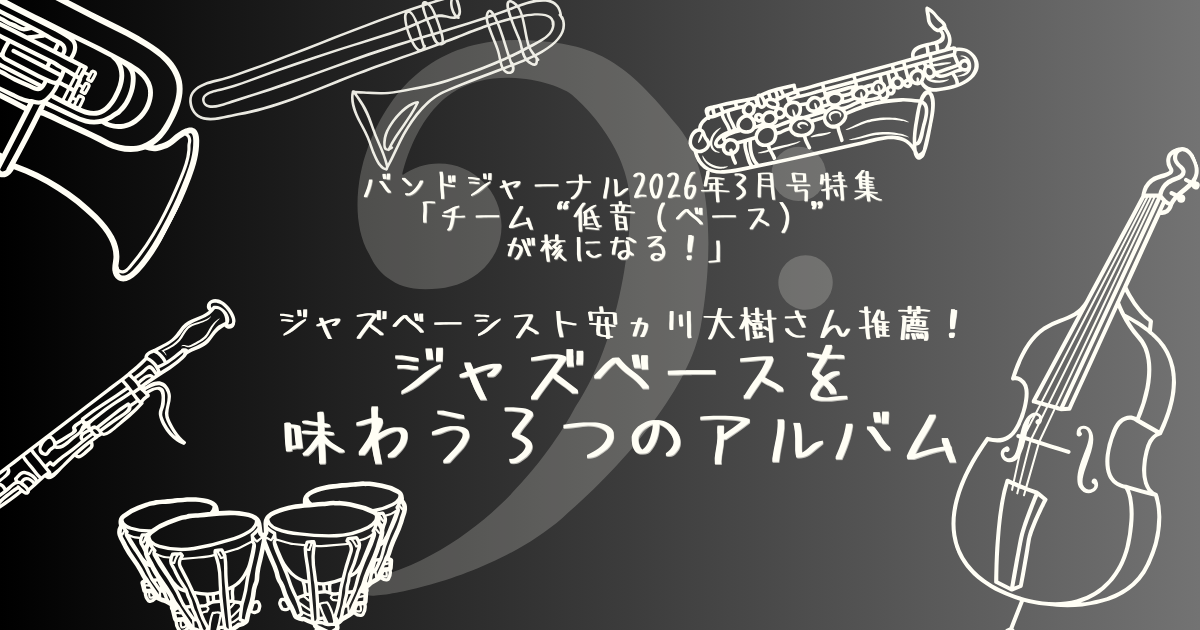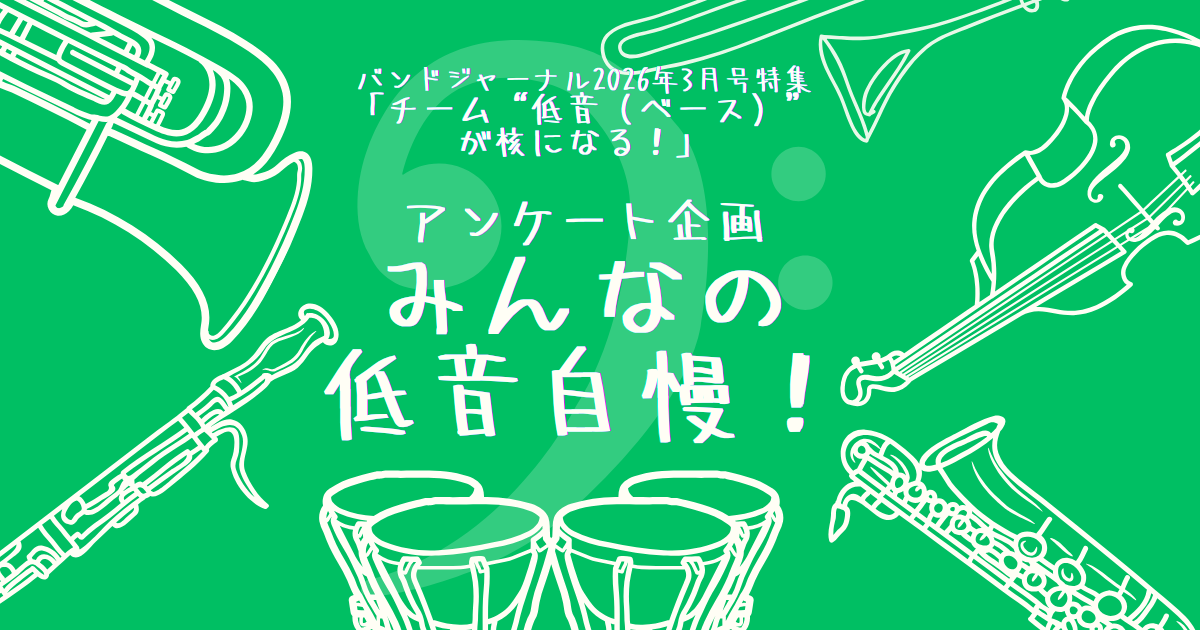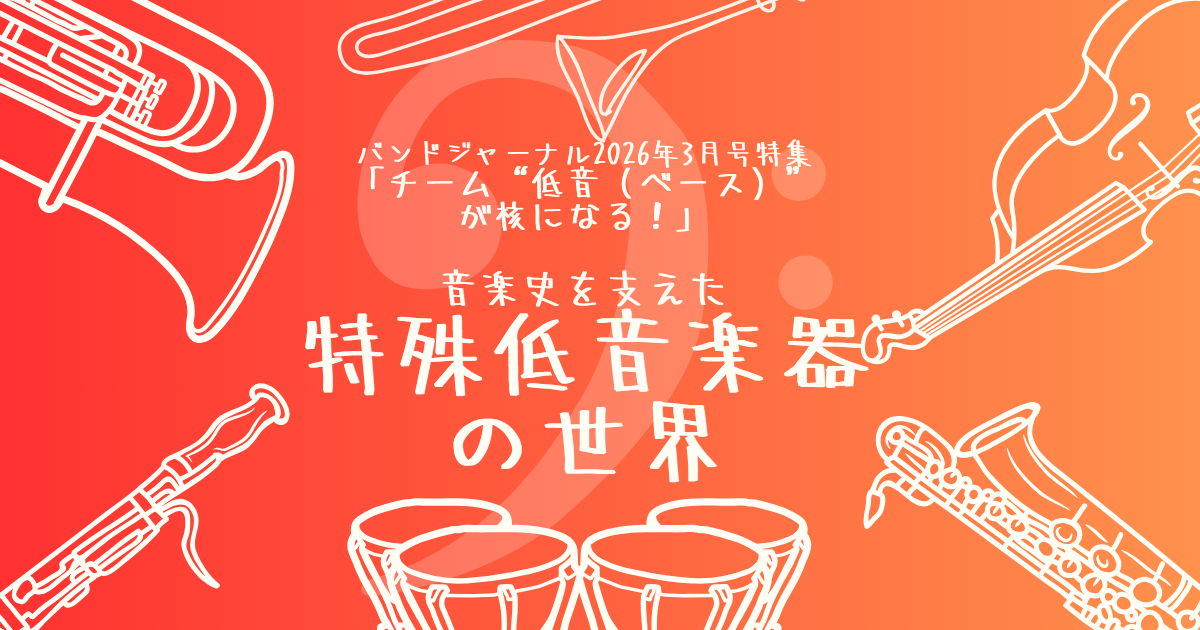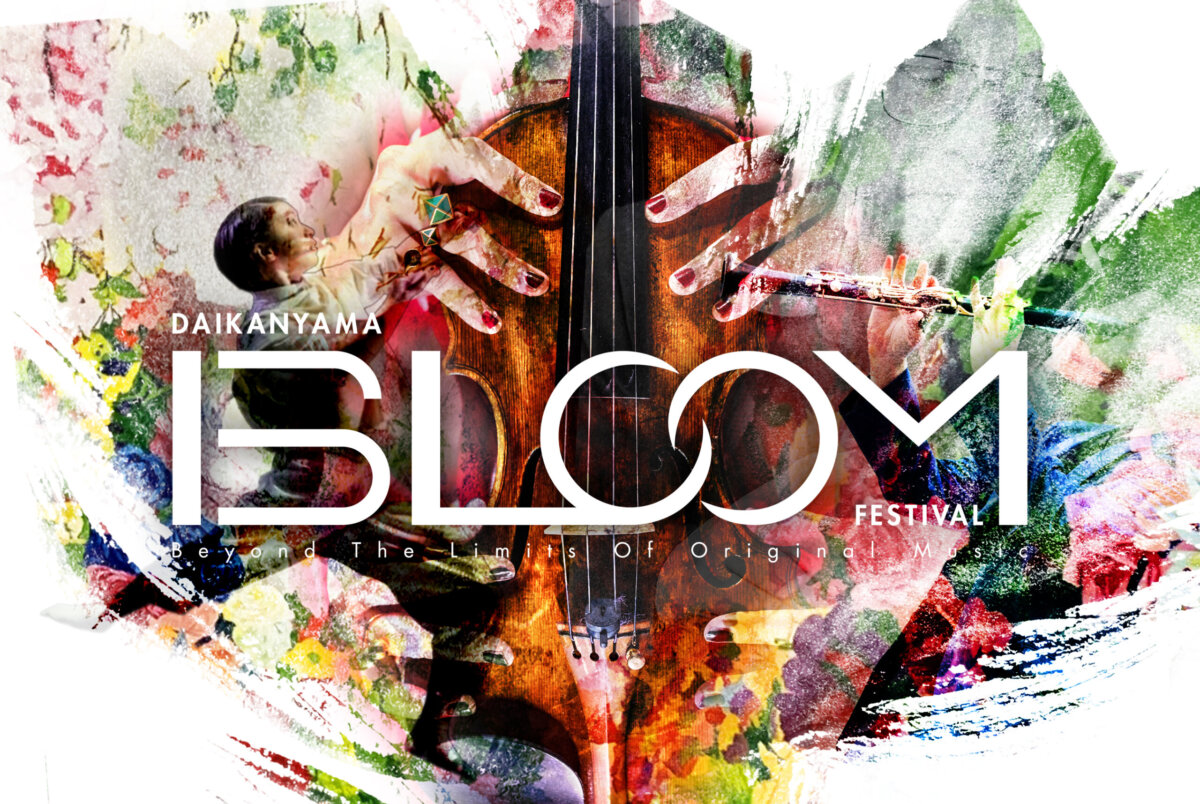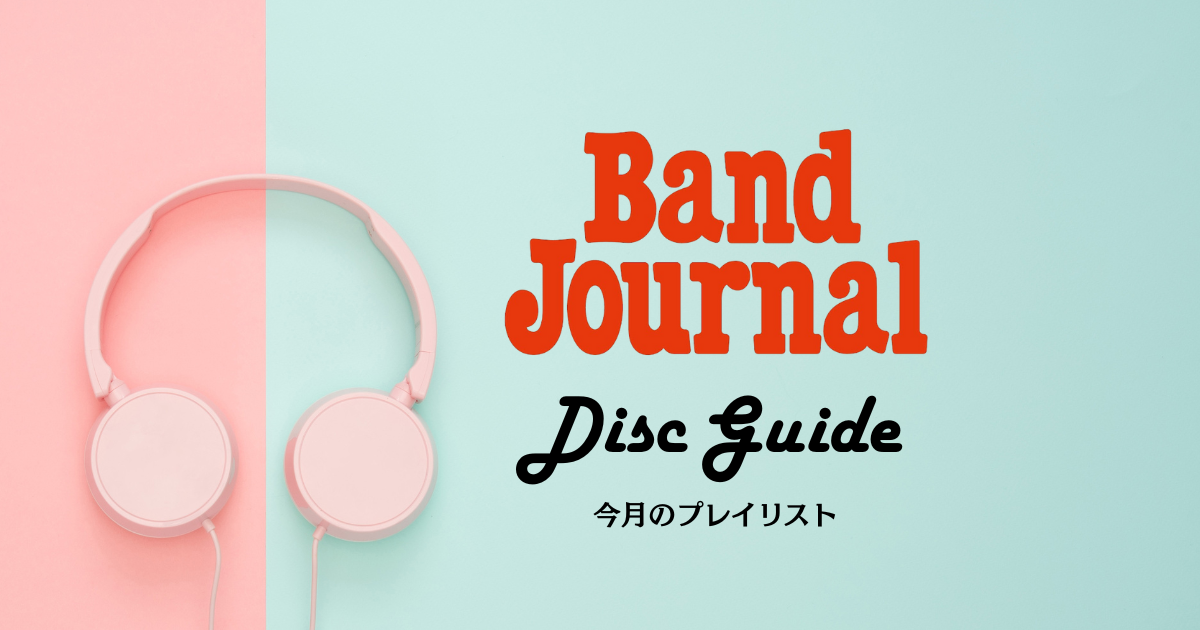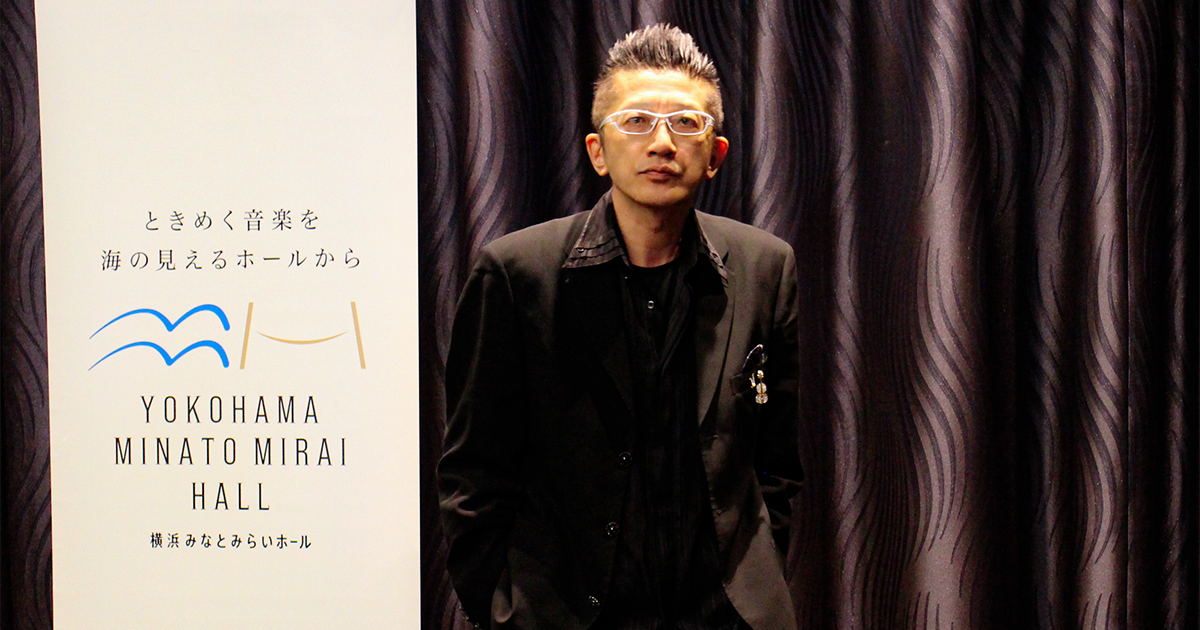津波で倒れた松でつくられた鍵盤ハーモニカ奏者・吉田絵奈さんが音楽に込める思い

約2万2千人が犠牲となった、東日本大震災から10年。避難生活を送る人々は今なお4万人を超え、福島県では避難指示が解除されていない帰還困難区域も残されています。一方、この10年間で、音楽を通じた支援活動も多く見られました。鍵盤ハーモニカ奏者・吉田絵奈さんもその1人です。津波で倒れた松の木でつくられた楽器を手に活動する吉田さんの思いを伺いました。
復興支援として被災松で鍵盤ハーモニカをつくる
──愛知を拠点に活躍中の吉田さんが、岩手県陸前高田市で演奏活動を始めた経緯とは。
吉田 震災から約6年後の2017年2月、私の手元に「被災松」でできた鍵盤ハーモニカが届きました。材料となった松の木は、岩手県陸前高田市の「奇跡の一本松」と同じ場所に生えていた木で、津波によって倒されてしまったものです。
東日本大震災で壊滅的被害を受けた岩手県陸前高田市の名勝高田松原の約7万本の松のうち、津波に耐えてただ1本残った樹齢270年の松(アカマツとクロマツの交雑種)をさす。海水をかぶったため根が腐り立ち枯れたが、復興の象徴として防腐処理などを行い永久保存されることになった。(小学館「デジタル大辞泉」より)
陸前高田市と友好都市の協定を結ぶ名古屋市から、復興支援の一環として、被災地の人たちを勇気づけるため「高田松原で被災した松を使って、鍵盤ハーモニカをつくれないか」という相談を受けたんです。そこで、私がお世話になっている鍵盤ハーモニカの「生みの親」の会社、鈴木楽器製作所(静岡県浜松市)に相談したところ、二つ返事で快諾してくださいました。当初、「鍵盤はプラスチックで、ボディだけ松」というお話だったんですけど、楽器が届いて見てみたら、鍵盤も松でできていて、驚きました。
──初めて息を吹き込み、音を奏でたときのことを覚えていますか。
吉田 もう、涙が止まりませんでした。「良い音!」という感動もあったのですが、この楽器に、いろんな人の思いが込められているということを実感したんです。そして、この木とともに、たくさんの人が流されてしまった。一音吹いただけで涙が止まりませんでした。……楽器をご覧になりますか。(楽器を取り出し、オンライン取材の画面に提示する)

楽器となっても木は生きている
──ああ、ほんとうに美しい楽器ですね。松の木でできた鍵盤がシックです。
吉田 本体はちょっと重いんです。ずっと演奏していると、腱鞘炎になってしまいそう(笑)。でも、鍵盤のタッチ感は通常の楽器より軽いんです。これも不思議なのですが、通常の金属製の楽器のほうが大きな音量が出る、と思われがちなんですが、このほうが遠くまで響くんです。広いホールで、生音だと、木のほうが届く。
──演奏家としての吹き心地は、いかがですか。
吉田 音になるまでにほんの少しだけ時間がかかるんですよ。通常の金属製だと、フッと息を出すと、すぐに音になる。ところが木は、すぐ音にはならないんですね。「フウウッ」って、木に息が混ざって、それが音にちょっとずつなる、みたいな。
──木管楽器のような響き方なのでしょうか。面白いですね。ほんの少しだけタイムラグがある。
吉田 そうですね、それに近いですね。すごく歌いやすい。あと、最初に手元に届いたときと、今とでは、音がまったく変わってきています。「木は生きている」って実感します。最初は、自分の出したい音がコントロールできず、滑らかに旋律を奏でられませんでした。でも、吹けば吹くほど馴染んできています。出したい音が出せるようになっている気がします。
──まるで木が生きていて、吉田さんに寄り添っていくみたいに。
吉田 応えてくれている気がするんです。日によっても全然違います。天気も影響するとは思うんですけど、それだけではない気もします。100年後、どんな音がするのか、楽しみです。

──ただ、お手入れが大変そうです。
吉田 松を提供して下さった、陸前高田市のかたにお伺いしたところ、「人の手の脂が良いから、とにかくたくさん演奏してください」。だから、たくさん吹き続けているんです。
「言葉で伝わってくる」オリジナル曲「光の音」で風化させないように
──吉田さんご自身は、それまで東北とはご縁があったのですか。
吉田 仙台に演奏に行った経験はありましたが、陸前高田には1度も行ったことがありませんでした。楽器が完成した年の6月、松を提供してくださったかたに会いに、初めて陸前高田に行きました。「こんな素晴らしい楽器になりました」というご報告と、演奏会を通じ、松の音色を陸前高田の方々に間近で聴いて頂く機会を頂きました。演奏会場となった診療所には、約30名の方々が集まってくださいました。瓦礫の撤去はされていたのですが、周囲には何もないところに診療所の建物があり、言葉を失いました。
──会場では、どんな曲を演奏したのですか。
吉田 日本の童謡や、「見上げてごらん夜の星を」。陸前高田の皆さんにとって、「高田松原」は思い出の場所です。なくなったことがいまだに信じられない。「被災松」の楽器の演奏を、皆さん、涙を流しながら聴いてくださいました。「なくなった松が楽器となって、音楽となって甦ったことが嬉しいです」と、泣きながら感想をいただきました。
──それから毎年、陸前高田での演奏活動が始まったのですね。
吉田 「皆さんに会いたい」という一心です。松を提供してくださったかたは「今度は小学校で演奏して」などと、企画をいっぱい立ててくださるんです。「音楽を届けに、励ましに行く」という感覚よりも、ひとえに「皆さんに会いに行く」。の前夜には、ふるまってくださる手料理をいただき、皆さんと楽しく話します。ほとんどのかたが家族の誰かを亡くされています。私たちが想像を絶するぐらい、たいへんなご経験をされています。でも、明るく、逞しくて、私のほうがパワーをいただくことが多々あります。
──そして、この楽器で演奏するオリジナル曲「光の音」を作曲したのですね。ニ長調の静謐な旋律が、聴く者の心をしずかに癒します。曲をつくるに至った経緯は。
吉田 「この楽器で、私の音楽で、震災に遭った方々を元気にしたい」という思いを抱きました。誰かがつくった曲でももちろん良いのですが、私の思いを旋律にして、この楽器で奏でたかった。私、夢を見ることが多いんです。「何をテーマにしようかな」と考えて眠っていたある夜、夢を見たんです。
──どんな夢だったのですか。
吉田 真っ暗のなかから、突然、光が射してきて、たくさんの人が、笑顔でそこに佇んでいました。両親や、近しい人もたくさんいました。皆、私のほうを見て、愛をくれている感覚になったんです。朝、起きたら、涙が流れていました。希望、光、そのときに感じた愛を旋律にしたい。そう思ってつくったのが「光の音」です。

──ふだんは超絶技巧の難曲をこなす吉田さんが紡いだ「光の音」は、あくまで静かで穏やかで、親密な印象を抱きます。曲想にはどんなコンセプトを盛り込んだのですか。
吉田 (少し考えて)希望、やっぱり希望を失ってほしくない。希望があれば必ず光は見える。Bメロで私、最初、短調にしたんですけど、アレンジをして下さった藤谷一郎さんと相談して、それを途中で変えて、全部明るくつくり直したんです。この曲を聴いて希望を持ってほしい、と思ったから。
──たしかに、短調はどうしても物悲しさ、喪失感が出てしまう。それをやめようと。
吉田 全部やめました。2回目に陸前高田を訪れたときから演奏を続けているのですが、皆さんやはり涙を流して聴いてくださいます。
──「被災松」の楽器が奏でる「光の音」、陸前高田の人々の背中をそっと押しているのでは。
吉田 木を提供してくださったかた曰く、「この松と一緒にたくさんの人が流されてしまった。だから、この松にはたくさんの人々の魂が宿っている」。鍵盤ハーモニカは、息を使う楽器です。だから、話せなくなった方々の代わりになって演奏したい。そんな思いを持っています。
──息を吹き込み、伝える。鍵盤ハーモニカという楽器の特性が発揮されていると思います。
吉田 曲を聴いてくださった人からは「言葉で聴こえてきます」と言われるんです。インストゥルメンタル曲なので、もちろん言葉はありません。でも「話しているように聴こえる」と言ってくださる。特に「光の音」の曲は、「言葉で伝わってくる」と評してくださいます。
──希望を失ってほしくない、との吉田さんの思いが通じたのだとしたら……。
吉田 嬉しいです。言葉ではないのに、言葉で伝えられるなんて。鍵盤ハーモニカは、ため息ぐらいの小さな息でも音になるほど、ダイレクトに表現が伝わる楽器です。思いが音に届き、音に気持ちを乗せ、届けられたらと思います。
──コロナ禍が明けたら、真っ先に陸前高田を目指しますか。
吉田 昨年は行けませんでした。叶うなら毎年行きたいんです。また、私の演奏する場所では必ず、この楽器で、震災を風化させないよう演奏を続けようと思っています。陸前高田の「高田松原」はなくなってしまった。けれど、楽器となって今も演奏され、音楽として甦っていく。そうして「ああ、生きている」という思いを実感してくださればと思っています。
吉田絵奈「光の音」
関連する記事
-
読みものはじめての点字と点字楽譜~世界点字デーに知っておきたい音楽との関係
-
レポート角野隼人、デュトワ、ゲルギエフらが名を連ねる北京の音楽風景
-
レポート小澤征爾を讃え、ボストン市に「セイジ・オザワ・スクエア」が誕生!
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest