
ドラクロワとアングルの作品をつないだヴァイオリン ~フィリップス・コレクション展より

日曜ヴァイオリニスト兼、多摩美術大学教授を務めるラクガキストの小川敦生さんが、美術と音楽について思いを巡らし、素敵な“ラクガキ”に帰結する大好評連載の第6回。
「ヴァイオリン」をテーマとしたドラクロワとアングルについて。2人の巨匠に共通するのは、ヴァイオリン弾きだったということ。音楽がつないだ巨匠の2作品に小川さんが見出したのは、20世紀前半に活躍した米国生まれの美術家マン・レイの作品だった。
ラクガキスト・小川さんの筆が冴え渡る!
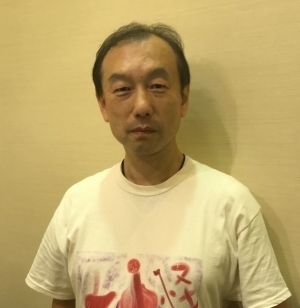
1959年北九州市生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業。日経BP社の音楽・美術分野の記者、「日経アート」誌編集長、日本経済新聞美術担当記者等を経て、2012年から多摩...
ドラクロワがパガニーニを描いた本当の理由を探る
東京・丸の内の三菱一号館美術館で開かれている「フィリップス・コレクション展」の会場で、筆者の血を騒がせる展示があった。
まず目に止まったのは、19世紀フランスの画家ドラクロワが描いた《パガニーニ》という油彩画だ。パガニーニは、ヴァイオリン愛好家なら必ず知っているであろう稀代の名ヴァイオリニストである。
美術館でこの種の絵に遭遇すると、日曜ヴァイオリニストを自称する筆者はどうしてもチェックが厳しくなる。「そんな持ち方で弾いてもいい音が出ないよ」「ヴァイオリンじゃなくてヴィオラだろ」など、ほとんど言いがかりのような文句をつけたくなってしまうことがあるのである。
だが、ドラクロワの《パガニーニ》と対面したときには、「余裕で弾いているな」という感想が最初に頭に浮かんだ。弓の持ち方や左手の構えはとても自然だ。左手の親指が指板の上に出ているところは、時代を感じさせる。左足に重心が偏っているのは瞬間を捉えたためもありそうだが、床を通して確固たる響きを伝えることを考えると合理的だ。茫洋とした筆致は、音楽が名ヴァイオリニストの周りを渦巻いているような感興を抱かせ、何よりも、パガニーニの顔の表情が音楽への没頭を感じさせる。縦45センチ程度の小品なのだが、見つめれば見つめるほど絵のよさが伝わってきたのである。

描写が正確だった理由は、展覧会図録の解説を読んでわかった。ドラクロワは、趣味でヴァイオリンを弾いており、イタリア出身のパガニーニの1831年パリ・デビューに立ち会ったあとに描いたのが、この絵だったという。ヴァイオリン無伴奏曲として著名な「24のカプリース」をパガニーニが作曲したのは1824年なので、超絶技巧をもつスーパーヴァイオリニストであることはすでにフランスでも知られていたのではないだろうか。ドラクロワは自分が弾く楽器のことゆえに正確に描けたのだろうが、熟視して描きとめることで名人の技を〝盗もうとした〟のではないかと筆者はにらんでいる。
その後、筆者はこの絵を思い浮かべながら楽器を弾いてみるという無駄としか思えないあがきをしてみた。ところが、それだけでも何となく上手くなった気がする。パガニーニとドラクロワ、どちらのおかげかはわからないが、芸術の力というのは素晴らしいものだと思った。
ドラクロワの《パガニーニ》と並べられてかけられた、アングルの《水浴の女(小)》
さて、長々とドラクロワの絵について語ってきたが、この日の本当の発見は別のところにあった。
コレクションの主、ダンカン・フィリップスは、ドラクロワのこの絵と、やはり同展に出品されているアングルの《水浴の女(小)》という油彩画を自邸で並べてかけることがよくあったという。
《水浴の女(小)》は、裸婦の後ろ姿をとらえた作品だ。アングルはこのモチーフをほかの絵でも何度か登場させており、その中の1枚に《ヴァルパイソンの浴女》(ルーヴル美術館蔵)という作品がある。背景と作品サイズは異なるものの、裸婦は《水浴の女(小)》とまったく同じポーズ、同じ構図で、同じ視点から描かれている。


ここで思い出すのが、20世紀前半にフランスで活躍した米国生まれの美術家マン・レイの《アングルのヴァイオリン》(1924年)という写真作品だ。座った裸婦の後ろ姿の写真の上に弦楽器のf字孔を2つ描き加えて再撮影することでヴァイオリンを表現している。そしてこの作品の発想源になったのが、アングルの《ヴァルパイソンの浴女》だった。だから《アングルのヴァイオリン》というタイトルなのである。
実は、アングルもヴァイオリンが弾けた。しかもパガニーニと一緒に弾いた逸話も残っているほどの腕達者だったそう。それゆえ、《アングルのヴァイオリン》というタイトルには「玄人はだし」という意味が込められているともいわれる。

アングルとドラクロワの2作品がフィリップス家で並べて掛けられたのは、アングルの厳格な描線とドラクロワのダイナミックな筆致を対比させるためだったという。しかし、本当に理由はそれだけだったのだろうか。
ヴァイオリンの形は女性を模しているとよく言われる。楽器の胴体に弓の通り道を確保して演奏の自由度が高めるためというのが、ヴァイオリンに女性的なくびれがある本来の理由だろう。くびれのおかげでヴァイオリニストたちは4本の弦を自由に往来して音楽を奏でることができるのである。
しかし、職人が楽器を美しい工芸品に仕立てた際に、機能から生まれた姿と女性の姿を重ねたという類推は、けっこう的を得ているのではなかろうか。女性像とヴァイオリニストの像を描いた、フランス同時代の巨匠アングルとドラクロワを米国のコレクター宅でつないだのは、やはりヴァイオリンだったのではないかと、筆者は密かに思っている。



会期: 2018年10月17日(水)〜2月11日(月・祝)
開館時間: 10:00〜18:00 ※入館は閉館の30分前まで(祝日を除く金曜、第2水曜、会期最終週平日は21:00まで)
会場: 三菱一号館美術館(東京・丸の内)
料金: 一般 1,700円/高校・大学 1,000円/小・中学生 500円
公式サイト:https://mimt.jp/pc/
関連する記事
-
読みもの【音楽を奏でる絵】ターナーからメンデルスゾーン、ワーグナーへ~「自然」への想像力
-
読みもの【音楽を奏でる絵】ヴァトーからドビュッシーへ~時代を超えて音楽の霊源となった絵
-
読みもの【音楽を奏でる絵】ラファエロからパレストリーナ、リストへ~美の回顧から生まれる新...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest















