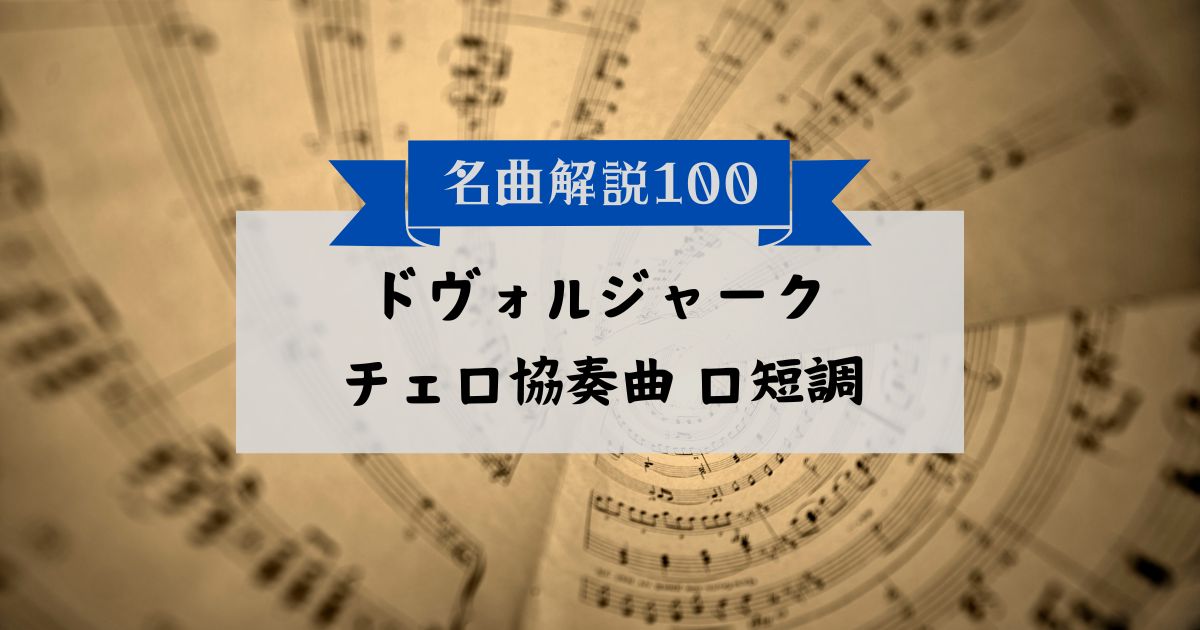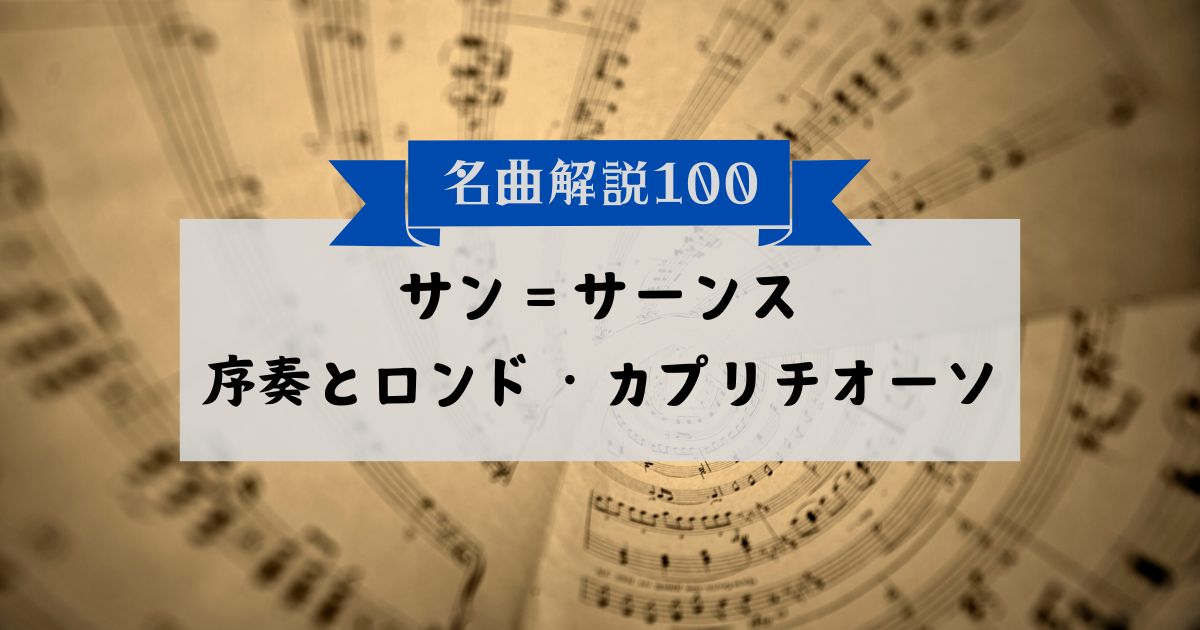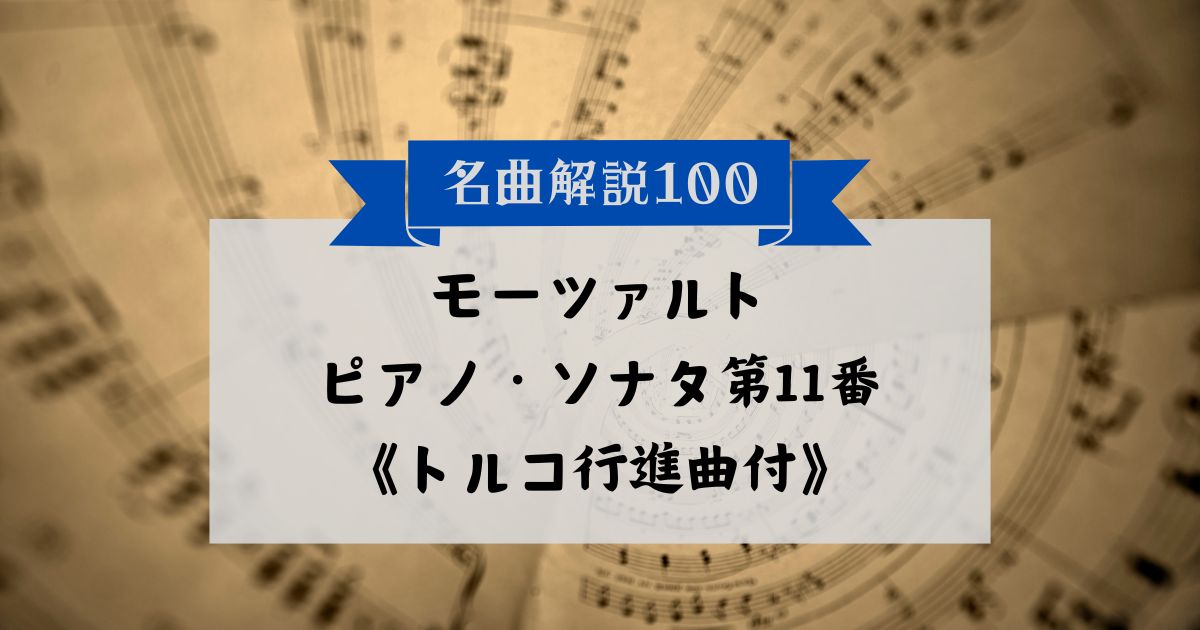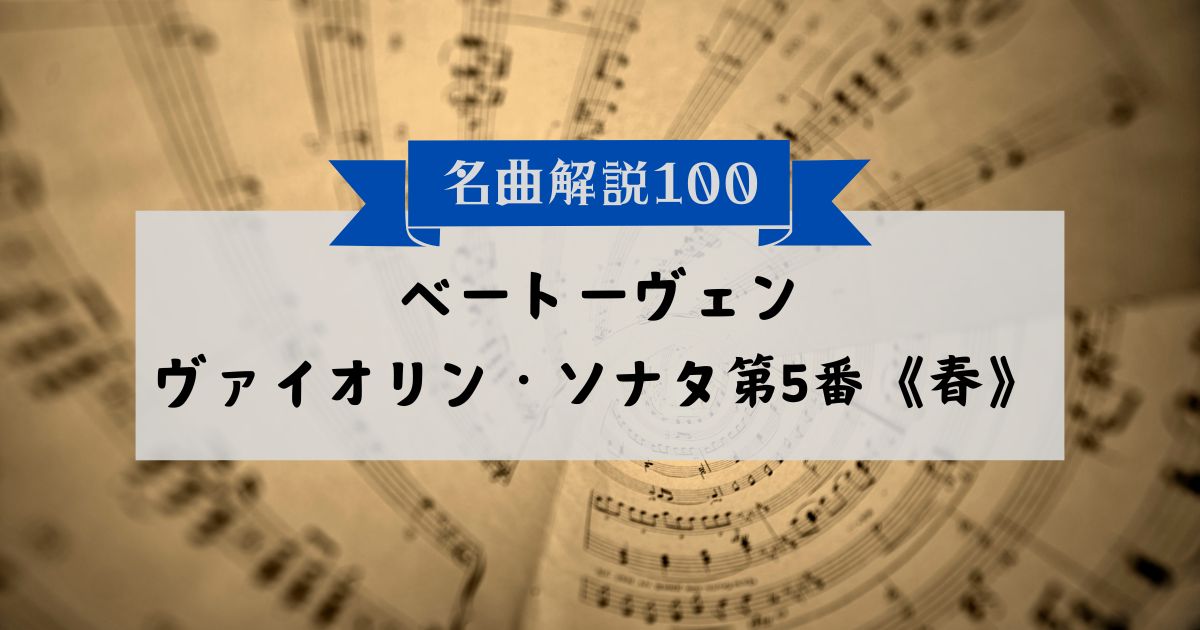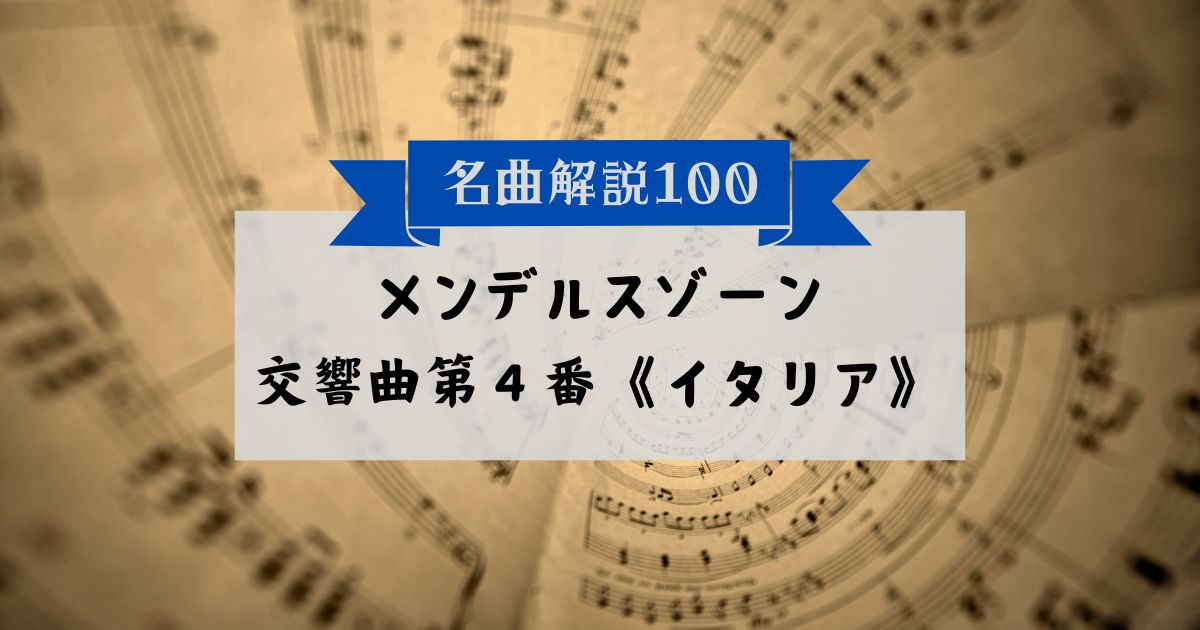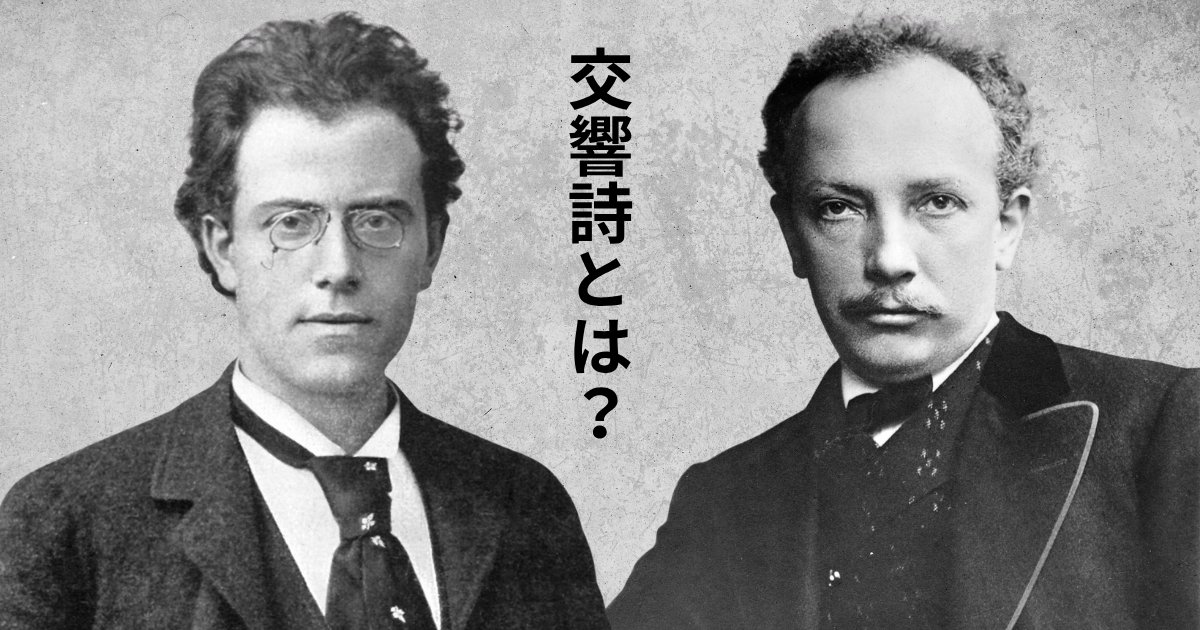ティエンヤオ・リュウ&ピオトル・パヴラク&イェフダ・プロコポヴィチにインタビュー!

第19回ショパン国際ピアノコンクール第3ステージ2日目に登場した3人を直撃!
若干16歳ですっかり聴衆を魅了したティエンヤオ・リュウさん、大人気で地元メディアからも引っ張りだこののピオトル・パヴラクさんとイェフダ・プロコポヴィチさん、それぞれにコンクールやショパンについてうかがいました。

フランス文学科卒業後、大学院で19世紀フランスにおける音楽と文学の相関関係に着目して研究を進める。専門はベルリオーズ。幼い頃から楽器演奏(ヴァイオリン、ピアノ、パイプ...
ティエンヤオ・リュウ「ショパンが感じていたことを心で感じながら演奏している」
——演奏前はどうやって集中していますか?
リュウ そうですね……実はあまり意識したことがないんです。いつも、舞台に上がったその瞬間に、自然と集中できるんです。あまり考えすぎないようにしています。

——あなたの演奏には驚くほどのエネルギーを感じますが、その力はどこから来るのでしょう?
リュウ 心の中からだと思います。私は、音の大きさはショパンが伝えたかった一番大事なことではないと思っています。彼が表現しようとした感情のエネルギーは、音量をはるかに超えるものです。だから私は、彼がかつて感じたであろうことを、心で感じながら演奏しています。
ピオトル・パヴラク「音楽は言葉では言えないことを表すために存在する」
——マズルカを演奏するとき、何を大切にされていますか?
パヴラク マズルカでは、二つのものの間でバランスを取ることがとても大切です。ダンスとしての要素と、ショパン的な表現とのバランスです。
私は、この音楽を「踊れる音楽」として忠実に扱いたいと思っています。もちろん、ショパンのマズルカは踊ることができますが、そのリズムは安定しているようでいて、少し不規則なんです。ときにはジャンプの位置が違っていたりします。
ですから、その二つの間のバランスを見つけること、そしてショパンの繊細な表現、たとえば感情を映すような美しい旋律とのつながりを見出すこと。それが、私にとって本当に大切な課題なんです。

——コンクールの出場者としてではなく、ひとりのアーティストとして、ショパンのどんな面を表現したいと思いますか?
パヴラク もちろん、いちばん表現したいのは感情です。感情やフィーリング……本当にたくさんあります。
そして、そうしたもののために私たちは音楽を作り、音楽を聴くのだと思います。言葉では言えないことがあるからこそ、私たちは別の方法でそれを表現しようとするのです。
そこに芸術というものの存在意義があります。ショパンは、自身の作品を通して本当に多くのことを語る美しい機会を残してくれました。だから私はその中で、できる限り多くのことを表現しようとしています。
イェフダ・プロコポヴィチ「ショパンの中にあるものを全部表現したい」
——演奏前はどうやって音楽に集中していますか? 第2ステージでは観客を見渡しているように見えたのが印象的でした。
プロコポヴィチ 集中するうえで一番大切なのは、「緊張しすぎないこと」だと思います。 でも、まったく緊張しないのもよくないんです。なぜなら、まったく緊張していないと、頭がちゃんと働かないというか、気持ちが舞台に向かっていかないからです。
逆に、集中しすぎても難しくなってしまう。だから、ちょうどいいバランスが必要なんです。少しだけ緊張を受け入れて、でもそれに飲まれないようにする。そして深呼吸をして、「自分の音楽を聴きたいと思ってくれている人たちがここにいる」ということを思い出すんです。

——コンクールの出場者としてではなく、ひとりのアーティストとして、ショパンのどんな面を表現したいと思いますか?
プロコポヴィチ うーん、ひとつだけというのはないですね。僕は全部、表現したいんです。
自分の演奏のなかで、できるかぎりショパンの「考え」や「想い」をくみ取ろうとしています。だから、ある特定のひとつの感情というよりは、彼の中にあるすべてのものを汲み取りたい。もしそれがうまくできたら素晴らしいけれど、そうでなくても、やっぱり全部を感じ取ろうとすることが大事だと思っています。
——その中でも、特に大切にしていることはありますか?
プロコポヴィチ それは曲によって違いますね。たとえばスケルツォでは「ロマンス」だし、ソナタではもちろん「死」についての部分。そしてマズルカの場合は、マズルカごとにまったく違うんです。マズルカは数が多すぎて、ひとつだけを選ぶのは難しいんですよ。
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest