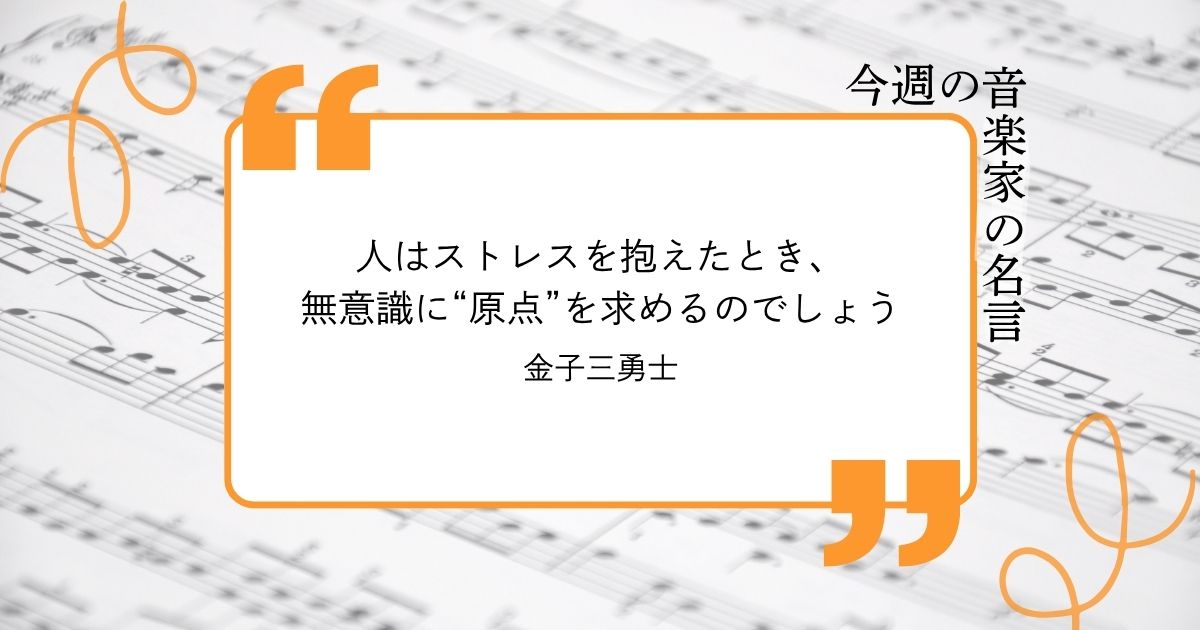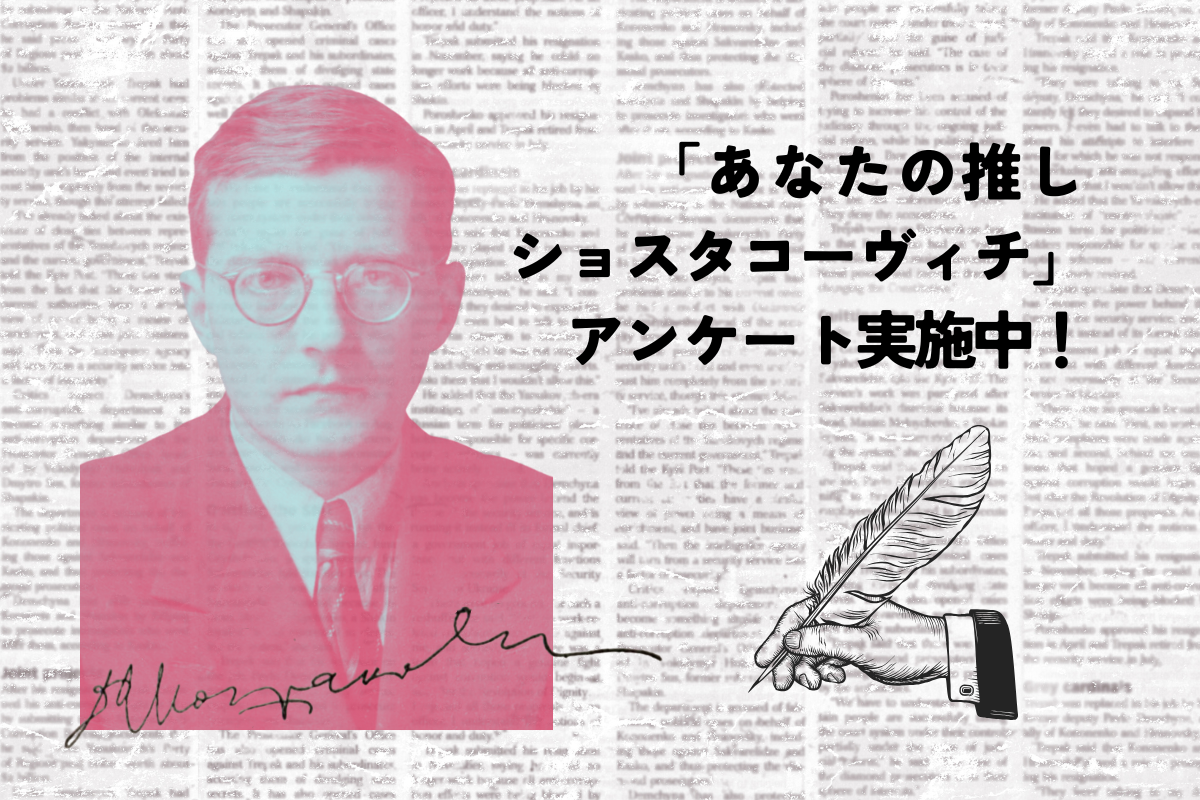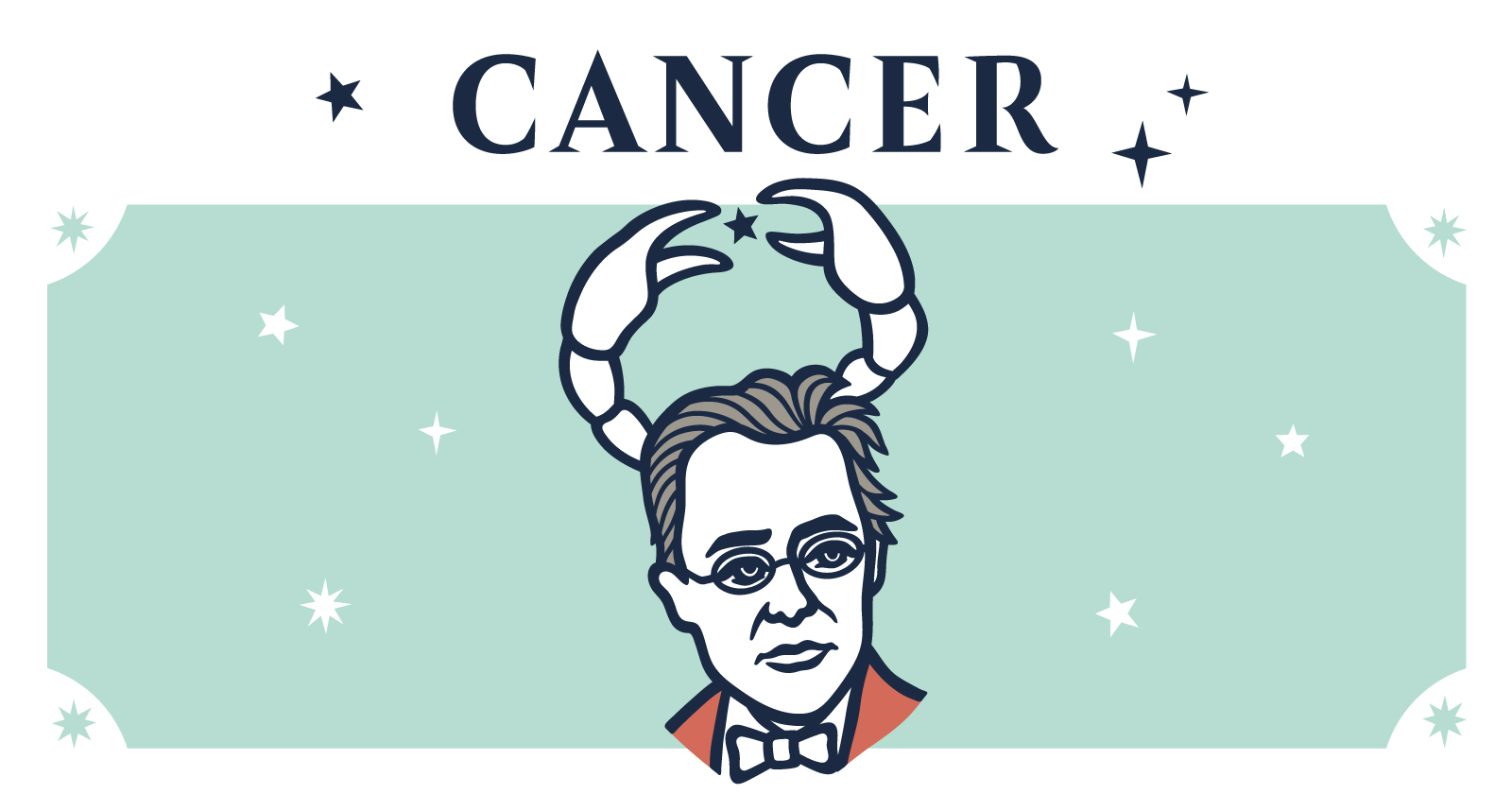総監督のマエストロ佐渡裕が「サントリー 1万人の第九」で伝えつづけるメッセージとは?

毎年12月に大阪城ホールで開催される「サントリー 1万人の第九」。その指揮者に任命されてから今年で21回目となる佐渡裕さんは、この大イベントに何を思い、参加者にどう伝えてきたのか。

1997年大阪生まれの編集者/ライター。 夕陽丘高校音楽科ピアノ専攻、京都市立芸術大学音楽学専攻を卒業。在学中にクラシック音楽ジャンルで取材・執筆を開始。現在は企業オ...
12月1日、大阪城ホールで行なわれた「サントリー 1万人の第九」。8月からコツコツとレッスンが積み重ねられ、参加者は本番にのぞむ。
イベントの総監督を務めるのは、指揮者の佐渡裕さん。彼が「1万人の第九」で大事にしているのは、大阪城に1万人が集まることへの意義。ともに歌うことで、第九の詩にある「すべての人が兄弟となる」を実現できる。そんな人と人が共振するための第一歩となるのが、佐渡さん自身によって行なわれる練習、通称「佐渡練」だ。「1万人の第九」に携わること21回目、イベントへのこだわり、そして「第九」への熱い想いを、佐渡さんに聞いた。

バーンスタイン、小澤征爾に師事。毎年ヨーロッパの一流オーケストラへ多数客演を重ねている日本人指揮者。2015年9月よりオーストリア、ウィーンの名門で110年以上の歴史を持つトーンキュンストラー管弦楽団音楽監督に就任した。国内では兵庫県立芸術文化センター芸術監督、シエナ・ウインド・オーケストラ首席指揮者を務める。
ベートーヴェンの思い描く「音楽の神殿」を作りたかった
——佐渡さんがこのイベントに携わるのは21回目だそうですが、今年のみどころは何でしょうか。
佐渡 今年は令和という時代になった、特別な1年でしたね。新しい時代での、最初の第九になります。
毎年、本当にいろんなことが起きますよね。今年だと、ラグビーに国民が湧きましたし、なんといっても「令和」に変わった特別な1年でした。
このイベントも長く続いているので、中にはベテランで歌い続けている方もいれば、ビギナーの小学生もいる。また、スーパー・キッズ・オーケストラといった若いオーケストラも演奏しますし、ゲストとして雅楽奏者の東儀秀樹さんやアーティストの山崎まさよしさんも登場します。たくさんの意味で、世代や時代を超えてつながっている、というのがこのイベントのテーマになります。バラバラに生まれ育ってきたたくさんの人が、8月から練習を続けてきて、大阪城ホールに一堂に会する。その人のつながりは、大きな虹になると思います。
——佐渡さんは前任の山本直純さんから引き継ぎ、1999年から指揮者を務めています。そこで初めて「佐渡練」というものを始めたそうですが、どのような意図があったのでしょうか?
佐渡 大先輩の山本直純さんが築き上げてきた「1万人の第九」ですが、僕に引き継がれた時に、もう一歩具体的に「こんな第九をしたいんだ!」ということを伝えたいと思ったんです。「はい、1万人集まりました」で終わるようなイベントではなく、やるからにはベートーヴェンの思い描く「音楽の神殿」を作りたかった。
いちばん最初は3000人ずつで練習を行なって、体育館のようなところでやってみたところ、やっぱり効果がありました。そこからだんだん人数を減らし、音響の良いところで、という風にグレードアップし、今の練習(1回あたりの練習はおよそ1000人。場所は新大阪のメルパルクホール)のようになりました。参加者一人ひとりに、技術的・精神的なこと、歌う喜びを伝えることができていると思います。
1万人が熱狂しているというのは想像しやすいけど、逆に1万人が冷めている状況も簡単に起こってしまうんですよね。だからみんなで手をつなぎ肩を組んで練習することで、集まることに意義を感じたり、「音楽ってこんなに自由なんだ」と感じてもらえたりできれば、「佐渡練」は意味があるのだと思います。
——8月から始まったレッスンも、いよいよ締めの段階。この時期に「佐渡練」を行ない、参加者に伝えたいことは何ですか?
佐渡 これまで3ヶ月ほど100人や200人くらいでレッスンをしていたのが、今日は1千人になり、本番では1万人になる。そういう意味でいうと今日の佐渡練は、まだスタートに過ぎないわけです。
今まで10回や20回第九を歌ってきた、という方もいますし、僕自身もこの「1万人の第九」を20年は指揮してきました。その中で作品自体は何一つ変わっていないのに、中の言葉を伝える意味が変わってきたりする。それはやはり時代の変化、災害、戦争、喜び、たくさんのことが起こり続けているから。
だから、今日の練習はもう一度新しい創造物を作るためのスタートラインです。しかも、本番に1万人集まると、また新しいものが作られるんです。それが音楽の良さなんですよね。
——長い間「1万人の第九」に携わられ、これはきっと佐渡さんの中でも特別なイベントになっているかと思います。佐渡さんにとって、「1万人の第九」とは?
佐渡 僕は、音楽や人が好きで指揮者をしています。
僕が「1万人の第九」に携わり始めたとき、最初は音程やリズムやテンポ、バランスを整えることが自分の役割だと思っていました。だけど、ずっと続けていく中で、時代は変わっていく。毎日いろんなことがニュースになっていて、本当に複雑な時代になりましたね。僕が「1万人の第九」を振り始めたときは、まだ家庭用コンピューターが普及し始めたときだったのに……。
そんな中で、みんなバラバラな場所で生まれていて、個性を大事にすることが大前提になった。周りの声に耳を傾けて、自分の意見も言って…。そうやって言葉や宗教も乗り越えて一緒に生きていることが面白い。音楽の神様は、そんな喜びを感じさせてくれるために我々に音楽を与えてくれたんだと思うんです。
だから、このイベントに参加する人たちが「人間って捨てたもんじゃないな」と思える時間が作れると、作品を残したベートーヴェンが一番喜ぶのではないでしょうか。
一人ひとりのフロイデ、ストーリーがある
そんな思いのもと、行なわれた佐渡練。筆者が潜入したのは、11月24日の新大阪メルパルクホールでの練習。今まで各クラス100人~200人程度で行なわれていた練習が、一気に増えて1000人近くの参加者が集まった。佐渡さんが考える「第九」への思いを共有する、貴重な時間となった。
佐渡さんは冒頭から、何度も詩に登場する「フロイデ」という単語について説明。合唱パートが最もはじめに発する単語だが、佐渡さんはこれについてこう語る。
「フロイデ、というのは喜びを意味します。これは一人一人違っていていい。鈴木さんのフロイデがあれば、佐藤さんのフロイデもある。心の中にある喜びを具体的に思い浮かべてください。それを重ねて立体化しましょう」
「作品は変わらないが、時代や人によってその作品のメッセージ性は変わる」というマエストロの思いが、そのままレッスンへと反映された。

手をつなぎ肩を組んで感じる、第九のメッセージ
佐渡練の特徴は、難しい練習を繰り返すことでなく、参加者同士のふれあうことで第九のメッセージを理解できること。
練習の端々で、マエストロは「参加者と手をつないで!」と指示する。拍に合わせて手に力を入れ、お互いの手を「にぎにぎ」とする。もちろん隣にいるのが見知らぬ人であることもあり得るわけだが、そんなのお構いなし。
「拍ごとに手をにぎにぎしますが、みなさんがキュッと力を入れたときが、旋律の大事な柱になる場所です」

有名な「喜びの歌」で知られる旋律では、特に頻繁に手をつながせた。
「このメロディは、子どもから高齢の方まで誰でも歌えるように、とベートーヴェンが意図的に書いたと思うんです。『あなたの不思議な力が、すべての人々をひとつにする。兄弟にする』というメッセージを宣言する大切なシーンです」
実際に手を「にぎにぎ」するだけで、マエストロは「まったくテンポの感じ方が違う!」と褒める。「当日は1万人で手をつなぐ気持ちでいてください」
そして毎回恒例なのが、男性パートによる肩組み練習。男性パートのみで歌われる箇所に、マエストロはそれを取り入れる。
「ここまでのストーリーでは、僕たち登場人物は『音楽の神殿』に向かってきたけれど、ケルプという門番がそこに入ることを許してくれないんです。この男性パートは、再びそこに向かって一人一人の民衆が行進しているシーンだと考えてください」
マエストロは肩を組むにあたり、前列の何人かに年齢を聞いた。「63歳です」「51歳です」「81歳です」「10歳です」。
「みなさん年齢は違いますね。でも、肩を組むことでみんな同級生になったと思ってください!」

男性全員が肩を組み、歌う光景は、ケルプに許されなくても神殿に向かうために、「すべての人が兄弟に」なったようだった。
場面の捉え方、オーケストラとのコラボレーション、表情や声色まで、「第九」が多角的に見えたレッスン。佐渡さんが「第九」を通して伝えたいメッセージは、「年齢も、職業も、性別も違う、すべての人々がひとつになる」。だからブレない。「佐渡練」で、大阪城ホールが神殿となる道が拓けたようだった。
ついに迎えた音楽の祭典
いよいよ迎えた本番。イベントは2部構成で、前半には雅楽奏者の東儀秀樹さんや女性ダンスチームのファビュラスシスターズなどが登場。また、アーティストの山崎まさよしさんもゲストとして出演し、1万人の合唱とともに「セロリ」を披露し、華やかに会場を盛り上げる。まさに佐渡さんが思い描く「音楽の祭典」が繰り広げられ、来たる第九の出番に向けて熱気を帯び始めた。


第2部は、「第九」の詩の日本語朗読によりスタート。例年、役者やアナウンサーが務めることが多いこの大役を、今年はお笑い芸人・霜降り明星の粗品さんが務めた。もともとアマチュアオーケストラに所属し、クラシック音楽を嗜んでいた粗品さんは、この朗読をするにあたって佐渡さんとの打ち合わせを重ねたという。
フリップ漫談を得意とする粗品さんは、例年行なわれる朗読とは一風変わったショーを披露。詩に基づいてフリップを挟み聴衆に笑いを誘うが、詩を読む声は堂々としている。
「『世界中の友よ! こんな音楽ではない。もっと心地よい、もっと歓びに満ちた調べに、声を合わせようではないか』。こんな世の中ではないはず。いかに人類がひとつになれないかということ歌っているのが、第九です。それでも、それを実現する大きな第一歩が、今日行なわれる『1万人の第九』だ!」

最後は力強く決め、会場の人々の高揚感を高めた。
第1、2、3楽章と続き、第4楽章はついに合唱の登場。バリトンのソロの合図で男声合唱の「フロイデ!」が活気よく響く。
ソリストによる有名な「喜びの歌」の旋律に誘われ、合唱もついで「Deine Zauber~」と歌いだす。やはり、さすが1万人の迫力。大阪城ホールという広い空間の中で、反響しあう声の重なりをコントロールしていくが、それは容易いことではないはず。
しかし、音楽が進むにつれ、参加者は空間に慣れ始めたのだろうか。「佐渡練」で経験した手つなぎや、肩組みを思い出したのかもしれない。響きのマッチングの度合いがどんどん高まり、難易度の高い二重フーガ(前回のレッスンレポート参照)もこなし、会場を包み込む音のミルフィーユのよう。
時を経るごとに声が調和していく様子は、佐渡さんが目指す「ベートーヴェンが描いた音楽の神殿」そのもの。佐渡さんは練習中、「ケルプという天使は途中、音楽の神殿への道を妨げる。だけど、あなたたち英雄が再びそれに向かうことで、その門は開けてくる、そんな様子を第九は描いている」と話したが、幾度と練習を積み重ねてこの日を迎えることで、参加者は自ら「音楽の神殿」にたどり着けたのだろう。

「1万人の第九」を終えて、佐渡さんは「山崎さんの『セロリ』をともに演奏できたことや、大阪の文化ともいえるお笑いを取り入れた粗品さんの朗読も合わせて、ベートーヴェンの大きな世界観と合致し、成功した」と誇らしげに語った。
山崎まさよしさんも同じく、「この会場に1万人が集まることへの意味深さを感じた。日本にはたくさんの災害や、世界でも争いが絶えないが、それらの傷を癒す行為になると思う」と語る。
絶え間ないスピードで流れていく時の中でも、「第九」は変わらず存在する。目を瞑りたくなるような悲しみが起きても、「第九」が希望の光となり得るし、それをもっとも実感したのは1万人の参加者かもしれない。これから続いていくであろう「1万人の第九」にも期待したい。
関連する記事
-
読みもの「第九」で学ぶ!楽典・ソルフェージュ 第2回 音名
-
読みもの《第九》が年末に演奏される理由とは?《第九》トリビアを紹介!
-
読みもの交響曲第9番ニ短調《合唱付き》〜作曲当時の様子、創作から初演までの流れ
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest