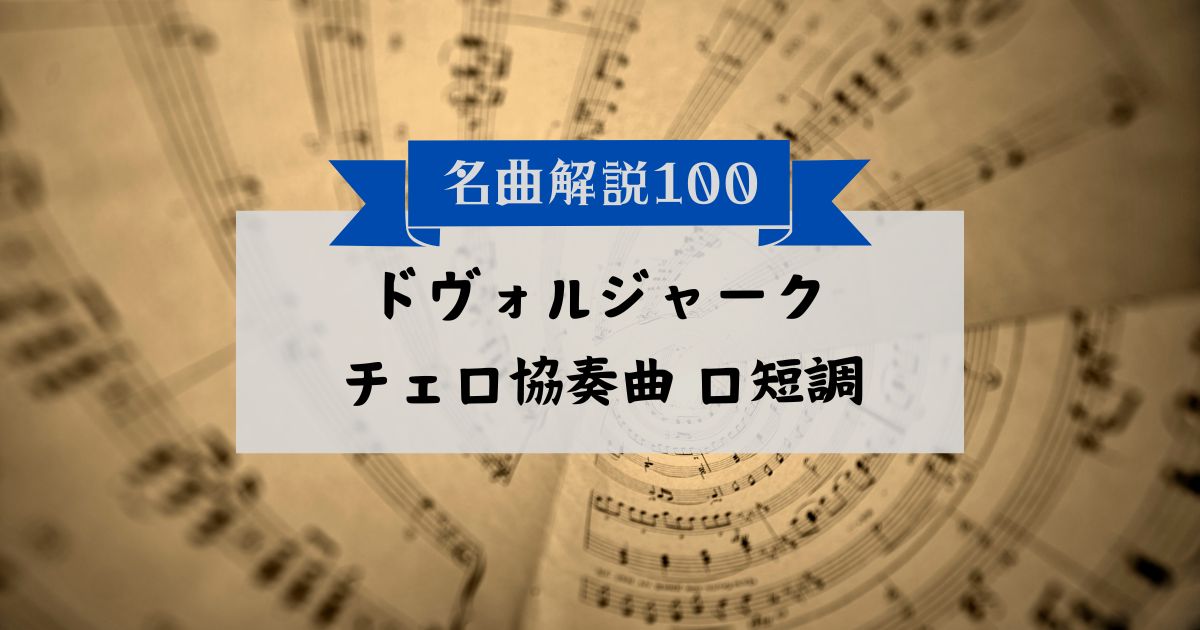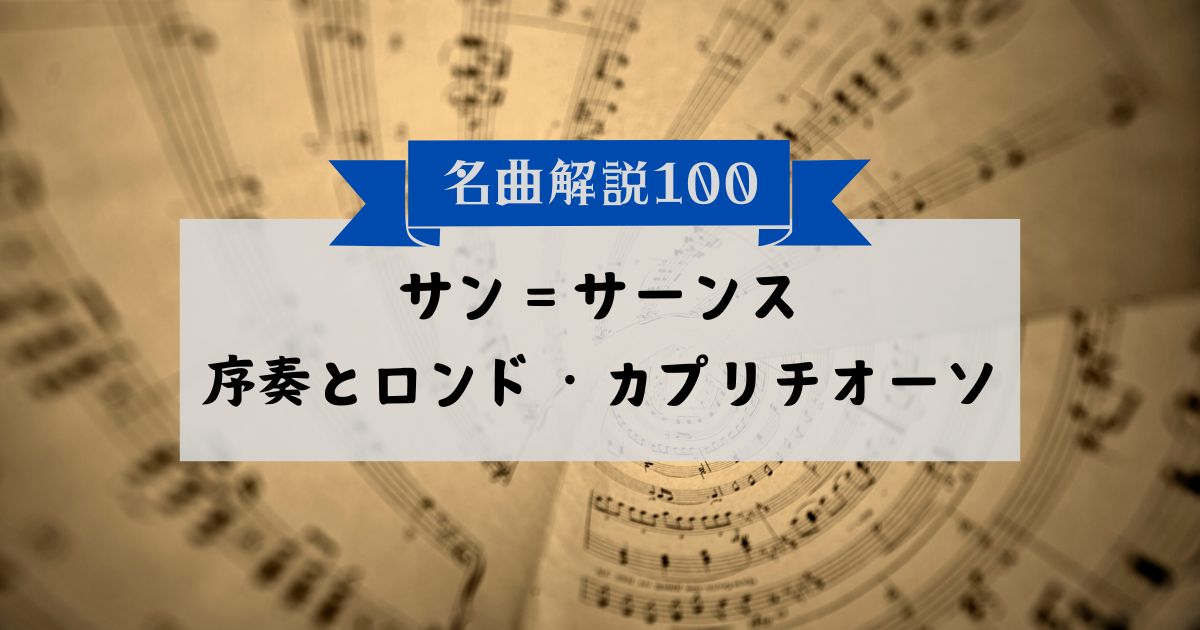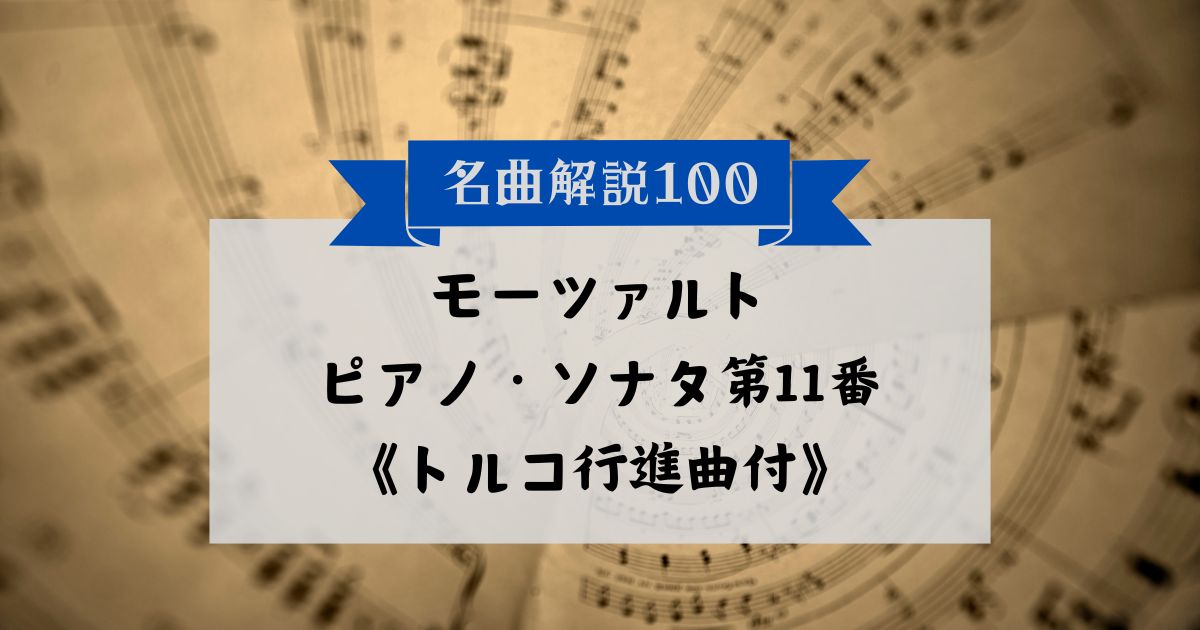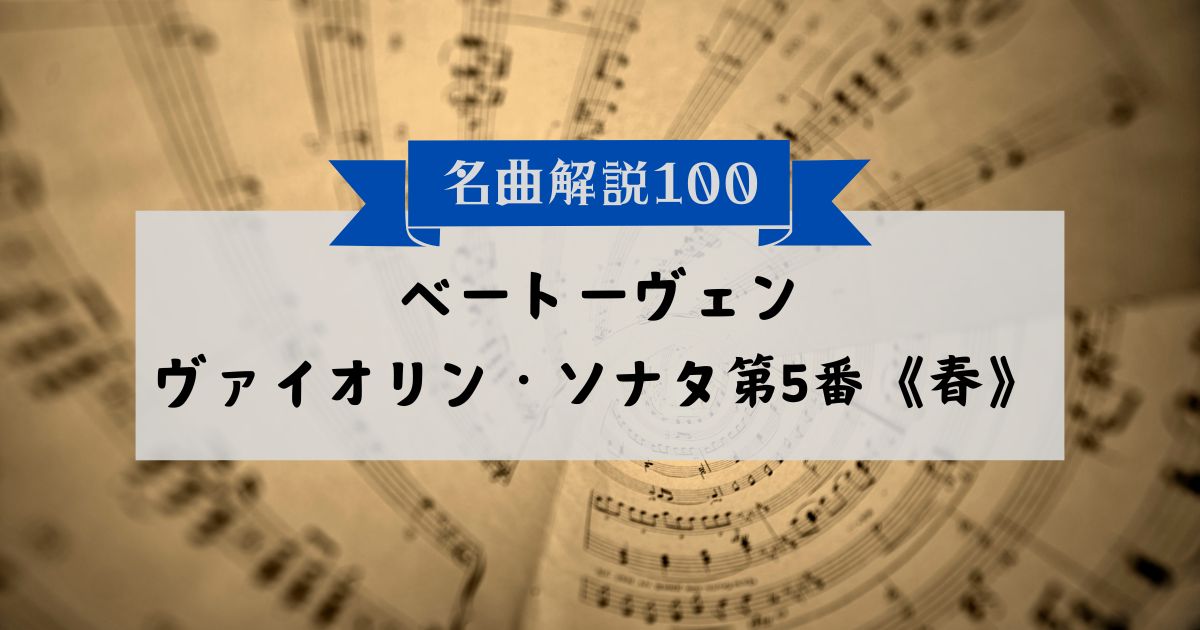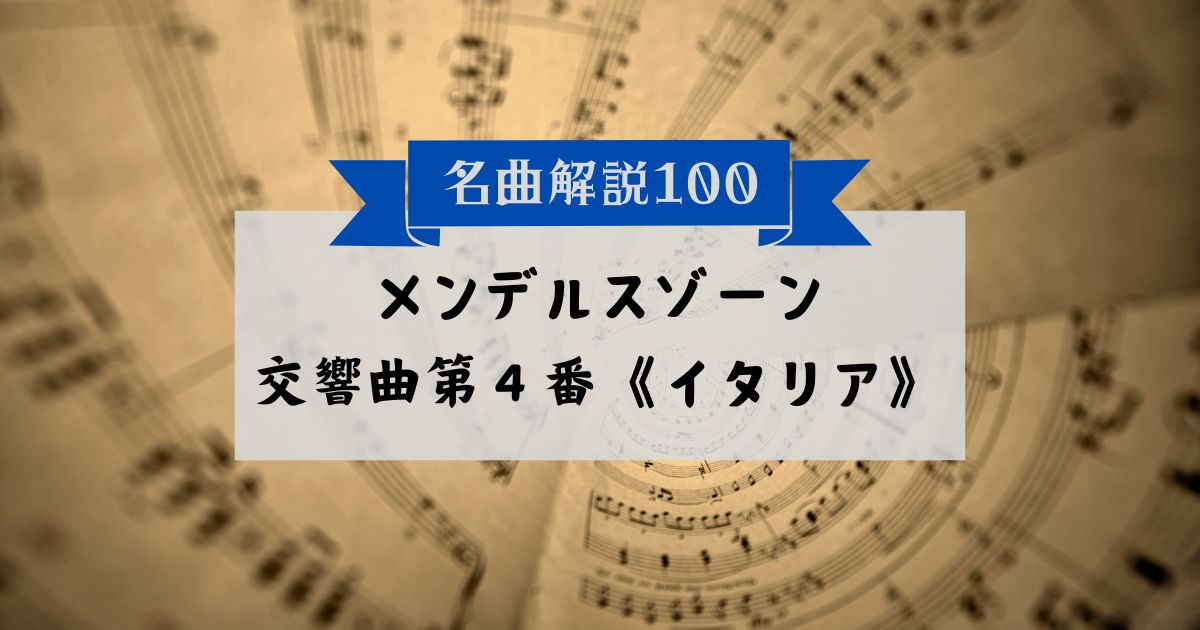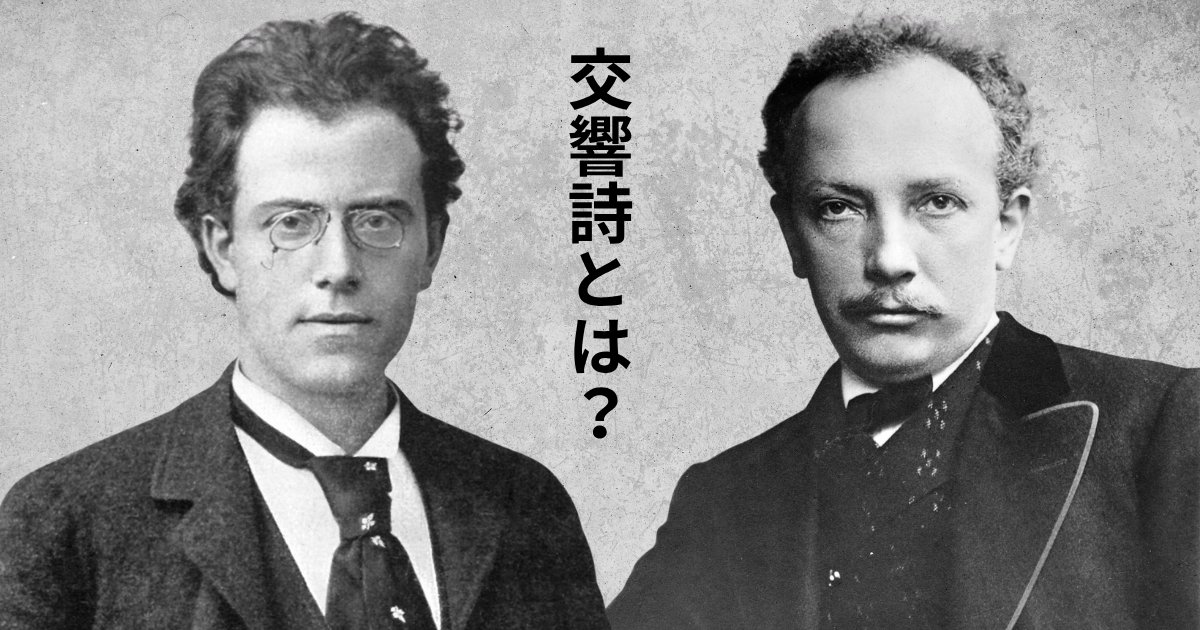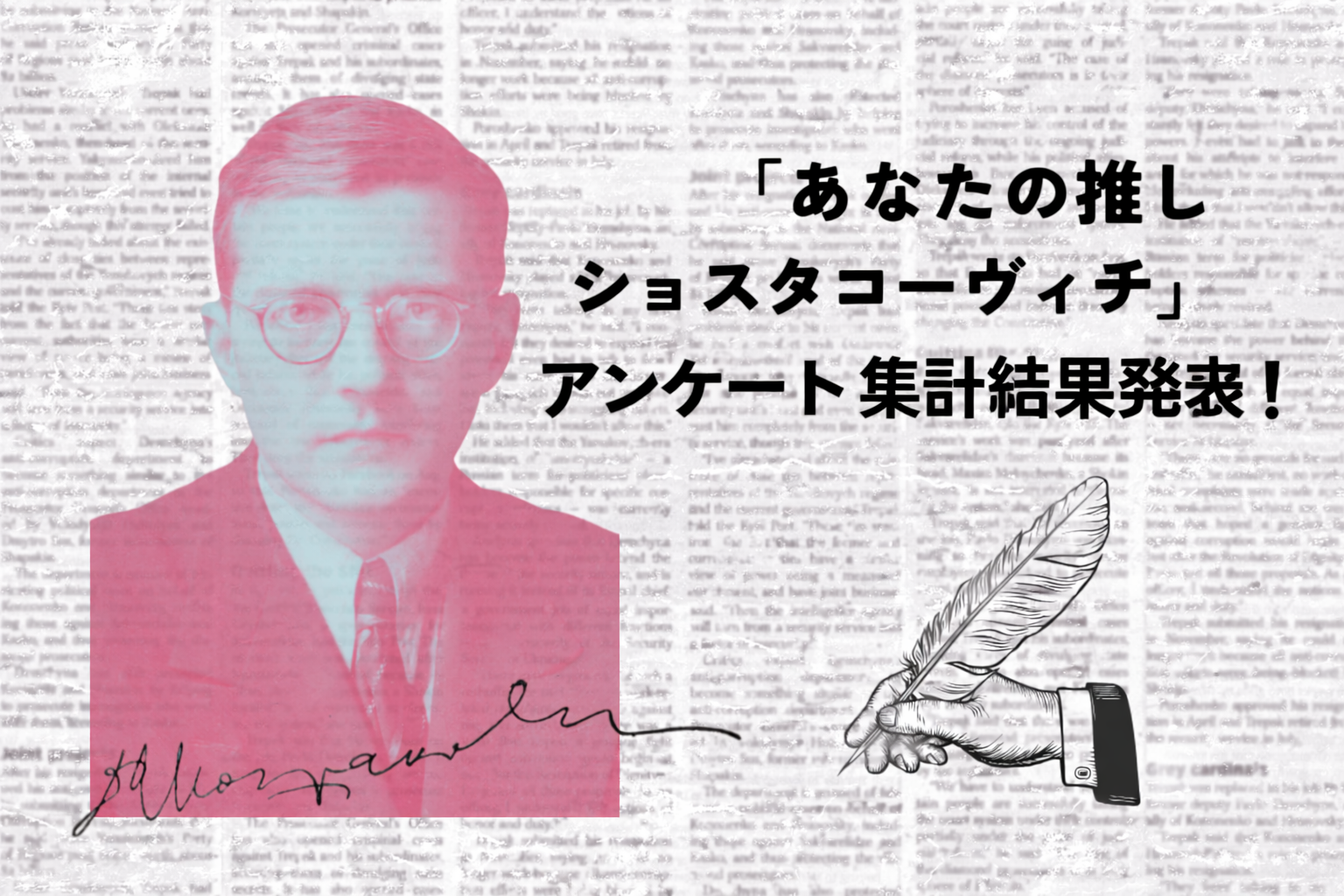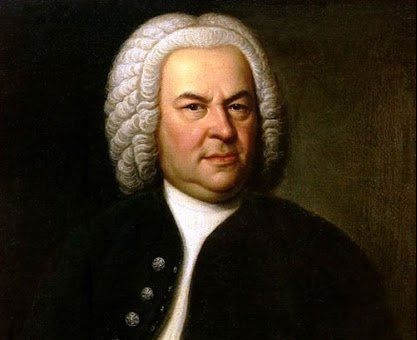【音楽が「起る」生活】ノット&スイス・ロマンド管、《イオランタ/くるみ割り人形》

音楽評論家の堀内修さんが、毎月「何かが起りそう」なオペラ・コンサートを予想し、翌月にそこで「何が起ったのか」を報告していく連載。7月は、ノット指揮スイス・ロマンド管、ソリストにリーズ・ドゥ・ラ・サールを迎えるカンブルラン指揮読売日響第684回名曲シリーズ、東京二期会《イオランタ/くるみ割り人形》を予想。6月の結果報告は、ロッシーニ《スターバト・マーテル》が上演された東響第731回定期、カウンターテナーの中嶋俊晴、チェンバーミュージック・ガーデンにおける《月に憑かれたピエロ》です。

東京生まれ。『音楽の友』誌『レコード芸術』誌にニュースや演奏会の評を書き始めたのは1975年だった。以後音楽評論家として活動し、新聞や雑誌に記事を書くほか、テレビやF...
何かが起りそう(7月のオペラ・コンサート予想)
1.スイス・ロマンド管弦楽団(ジョナサン・ノット指揮)(7/8・ミューザ川崎シンフォニーホール)

ジョナサン・ノットとスイス・ロマンドの組み合わせだけだって十分興味深いのに、プログラムが加わるとさらに興味深い。
《ペトルーシュカ》はともかく、オネゲルの《ラグビー》とショスタコーヴィチのチェロ協奏曲が一緒だと、やっぱり何が起るか興味津々だ。もちろん指揮者がいまのスイス・ロマンドの個性を考慮して選んだ曲目だろうから、聴き終えればきっと理由がよくわかる。
20世紀のリズム重視という以外に、何か共通する魅力を引き出してくれるはず。昔一世を風靡した華やかなスイス・ロマンドを知る者には、こういう曲を並べてくれると、一種のなつかしさだって感じてしまう。聴きに行くのが大いに楽しみなコンサートだ。
2.読売日本交響楽団(カンブルラン指揮)第684回名曲シリーズ(7/15・サントリーホール)


7月の暑さをリズムに乗って楽しさに変えてしまうのはどうだろう。カンブルランがまず指揮するのはバーンスタイン《キャンディード》の序曲だ。
これにガーシュウィンのピアノ協奏曲が続く。ピアノのリーズ・ドゥ・ラ・サールはフランスの若手ピアニストで、現代的感覚のピアニストだから、それは楽しいガーシュウィンが聴けそう。うまくいったら踊り出したくなるコンサートになるのではないだろうか。猛暑には水浴びよりこのコンサートがよさそう。
3.《イオランタ/くるみ割り人形》東京二期会、パスカル指揮、デ・ベア演出、梶田真未/川越未晴(S)他、東京シティ・バレエ団(7/18~21・東京文化会館)


ウィーンで上演されて大評判だったチャイコフスキーのオペラとバレエの合体上演がついに聴ける・見られる。
一晩で上演するよう作られながら、ずっとバラバラに上演されてきたオペラ《イオランタ》とバレエ《くるみ割り人形》を一晩で上演する試みが始まったのはつい最近のこと。パリ・オペラ座でのチェルニャコフ演出の舞台が話題になったけれど、それ以上に評判だったのが、演出家ロッテ・デ・ベアがウィーンのフォルクスオーパーで制作した舞台だった。少女イオランタが目覚める物語として、オペラの中にバレエが入り込む上演だ。少女の不思議な夢としての《くるみ割り人形》も斬新だし、オペラとバレエが見事に一つになっている。映像で見られるのだが、今度は実際の舞台で味わえる。
演出家や振付師が日本できっちりリハーサルをして臨む舞台は大いに楽しみ。そして指揮するマキシム・パスカルは、今度ミラノ・スカラ座で《ペレアスとメリザンド》を振る予定になっている注目の指揮者だが、日本への初登場はパリ・オペラ座バレエ団の公演だった。本領を発揮するのは間違いなさそう。
何が起ったのか(6月のオペラ・コンサートで)
1.東京交響楽団 第731回定期演奏会 ミケーレ・マリオッティ(指揮)ロッシーニ《スターバト・マーテル》他(6/8・サントリーホール)⇒⇒⇒「悲しみの浄化」が成し遂げられた
至福の悲しみだった。なんと美しい響きの《スターバト・マーテル》だったことか。難点は聴きながらつい幸福感に満たされてしまうことだった。
《ウィリアム・テル》でロマン派の激しい感情に足を踏み入れたロッシーニは、悲しみの浄化をずっと信じ続けていた。それが伝わったのは、はっきり方向を示し、浄化を成しとげたマリオッティの指揮の力が大きいが、歌手たちも申し分なかった。
ソプラノのトロシャンは柔らかい曲線の歌唱がすばらしかったし、メゾのバルチェッローナはいまも安定した歌の力を維持している。テノールのマキシムは現在の充実ぶりが伝わってくる歌だったし、バスのミミカも名前を覚えておかなくては、と思う。そして、驚いたことにオーケストラと合唱が常にも増してベルカントのロッシーニに奉仕していた。コンサートホールでは時にこういうことが起る。
2.中嶋俊晴(カウンターテナー)&白取晃司(ピアノ)(6/12・Hakuju Hall)⇒⇒⇒なじみのない歌も説得力をもって届く
椅子の背を後ろに倒して聴く「リクライニング・コンサート」の1曲目がブラームスの子守歌なんて、さあ、お休みくださいと言ってるようなものではないか。でも1時間のコンサートで眠くなったりしなかった。
中嶋俊晴はいま勢いに乗るカウンターテナーだ。安定した発声でたっぷりの声が生かされ、グアスタビーノの2曲や上田知華の「枕草子」からの4曲で、説得力ある歌を聴かせる。なじみのない歌の魅力が届いた。それでも最初の3つのブラームスの歌の、素直な表現が印象に残ったのはどうしてだろう?
3.シェーンベルク《月に憑かれたピエロ》北村朋幹(ピアノ)郷古廉(ヴァイオリン、ビオラ)横坂源(チェロ)中江早希(ソプラノ&シュプレッヒシュテンメ)他(6/16・サントリーホール ブルーローズ)⇒⇒⇒ピエロの歌の新しい地平が開かれた
いま第一線で活躍する音楽家たちの演奏は思わずたじろいでしまうほど覇気に満ちている。前半のドビュッシーやシェーンベルクはいずれも緊張感いっぱいの演奏だったけれど、いろいろ言いたくなるのはやはり《月に憑かれたピエロ》だった。
やりがいのある曲だから、これまで我こそはという歌手をまん中にすえた、凄みのある演奏が重ねられてきた。でも思い出すとそれらの名演奏は、いずれもロマン的あるいは人間的情感を排除する方向だった。作者シェーンベルクがそう望んでいるのだから正しいに違いない。だが本当にそれが唯一の方向なのだろうか? 死に病む月の下で真っ黒で大きな蛾たちが飛ぶ世界の、冷たさを競うだけがピエロの歌なのか?
中江早希はこの特異な歌……ではなくて語りに勇敢に挑戦した。凄みの点からいえば過去の成功した歌手に及ばないかもしれないが、精度は十分で、硬い詞の歯車はかなり正確に作動した。
今回は字幕付き、それも対訳の字幕付きだったので、とてもわかり易かった。おかげで挑戦の成功も、過去の成功モデルからはみ出しているところも伝わった。
そして冷気が足りない、というか、冷然と語らず、つい歌ってしまいそうになるところに魅力があるのに気づいた。
いくら《月に憑かれたピエロ》だって、そろそろ新しい地平を開いたっていいはず。「月の光は櫂、睡蓮が舟」なんて、ロマン的な歌でもあると思わないだろうか? この夜聴いたのは、新しい魅力をまとった「歌」だった。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest