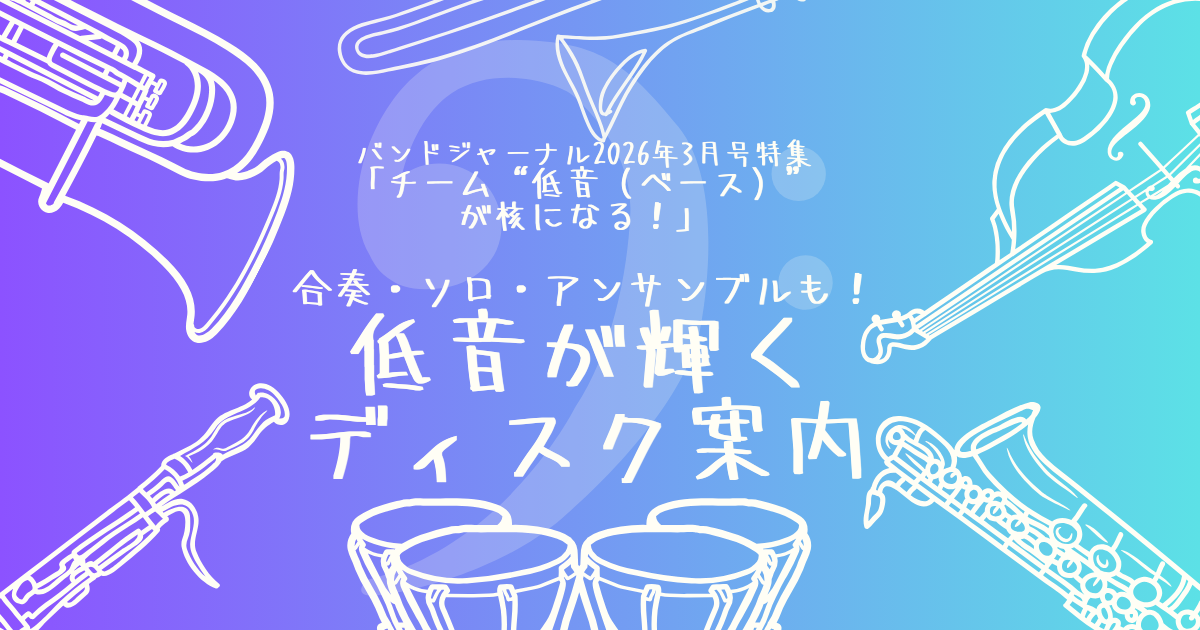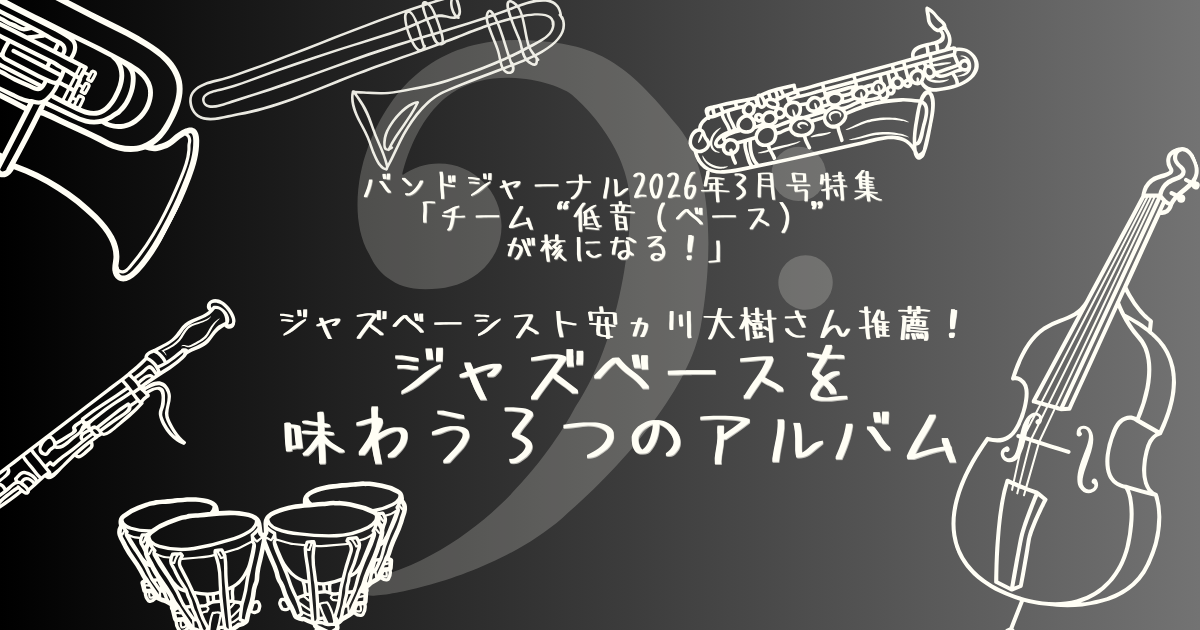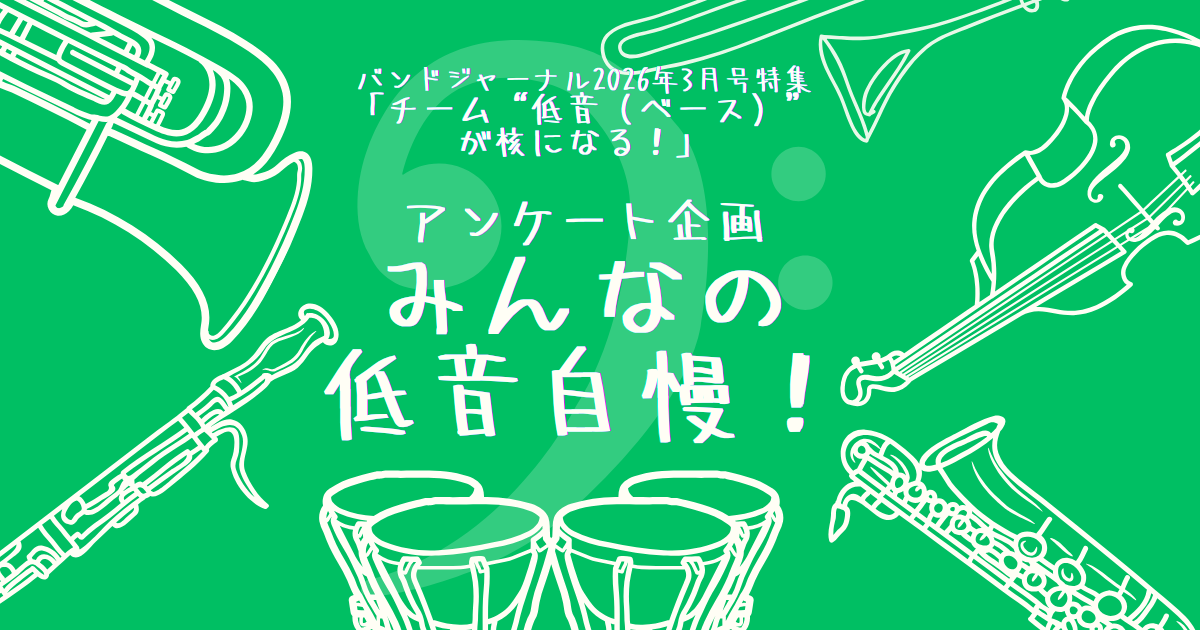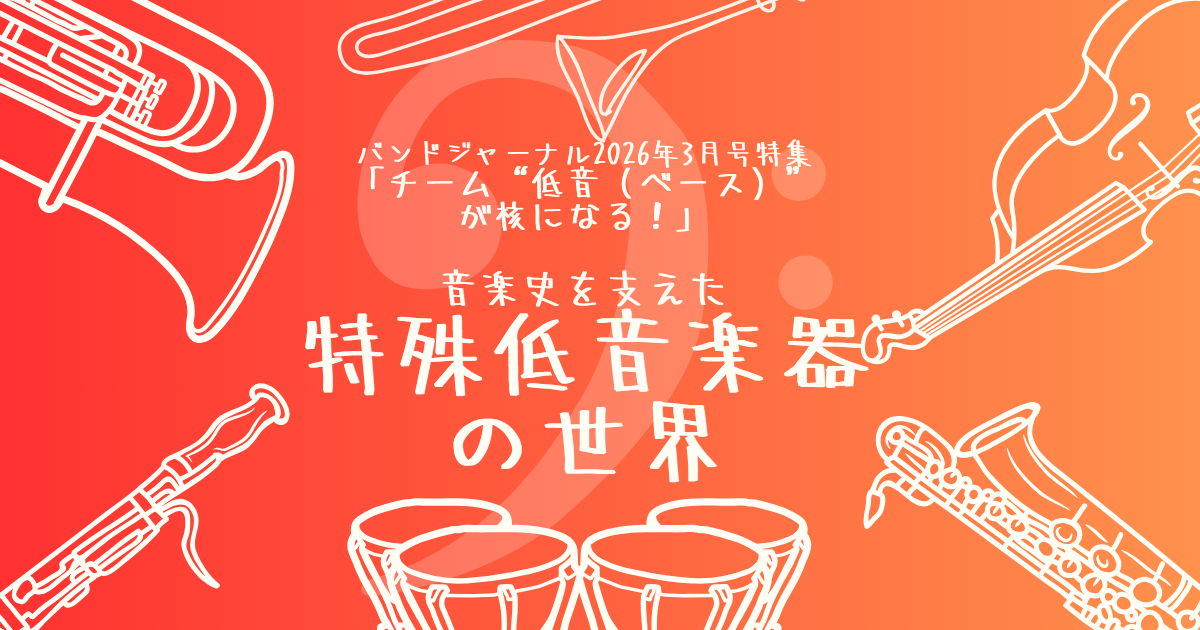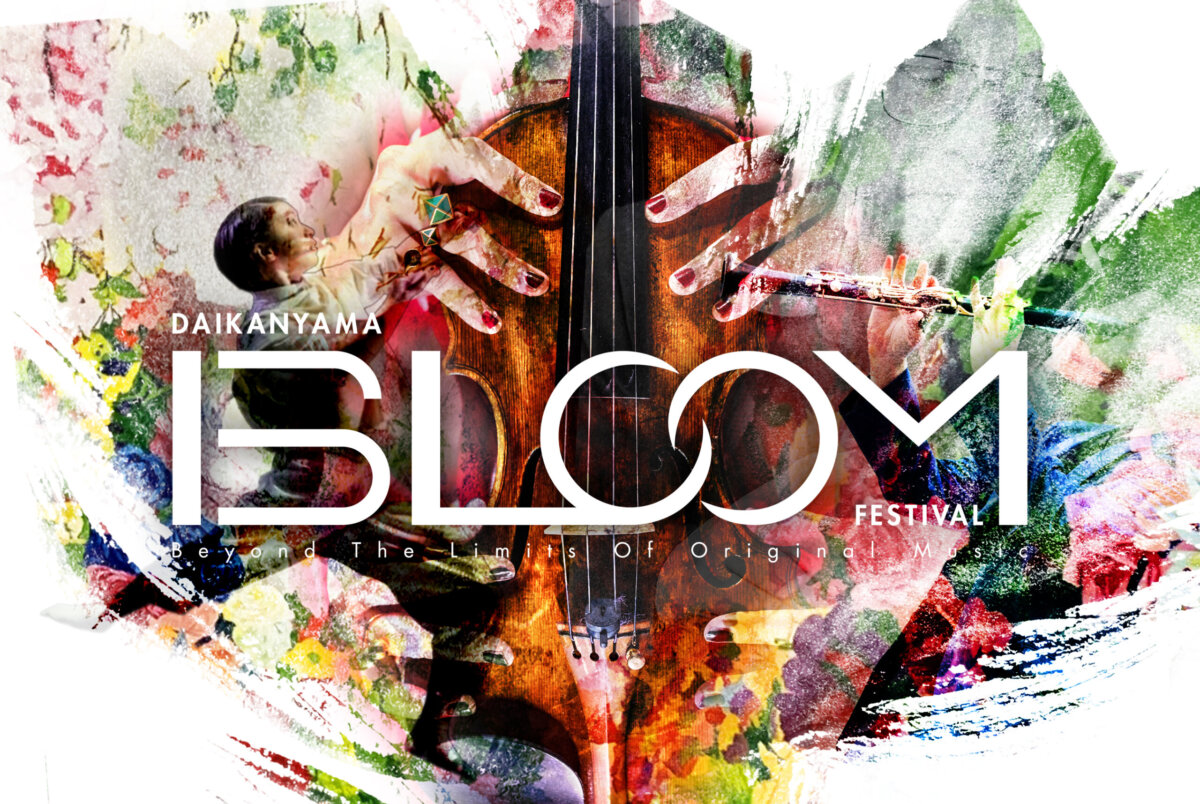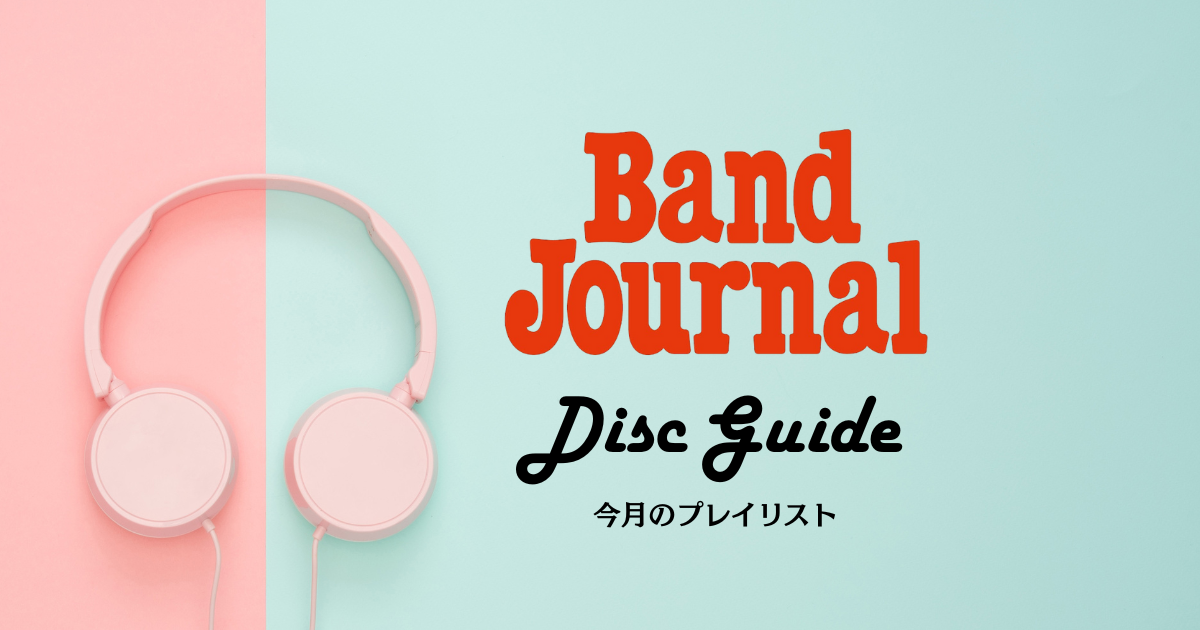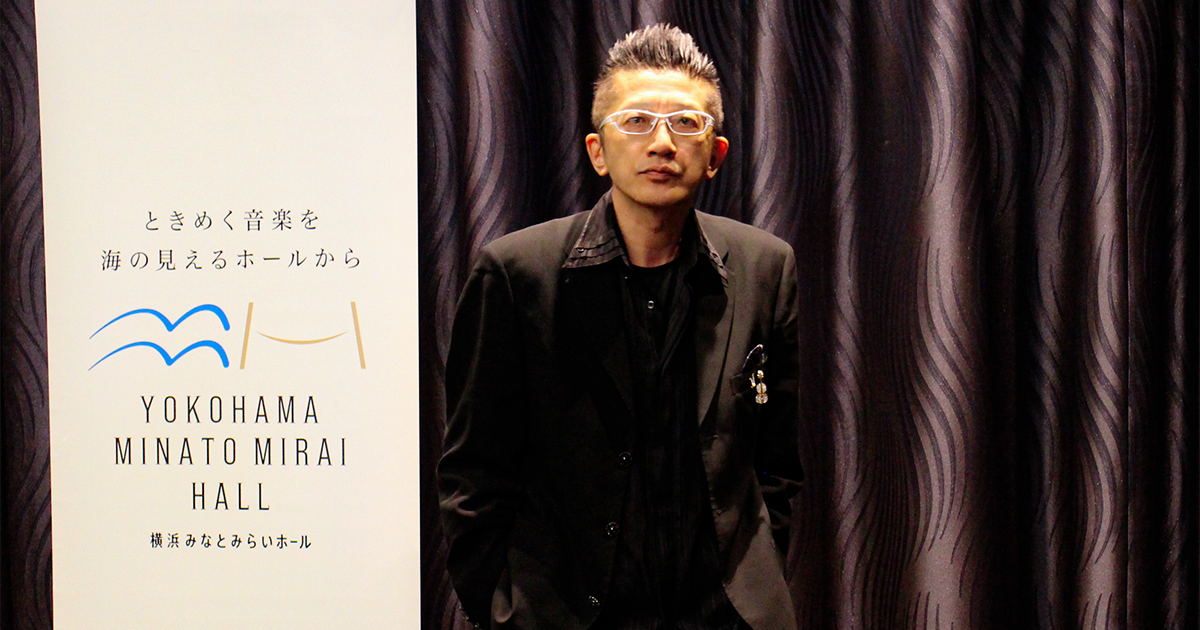【音楽が「起る」生活】ヤーコプスのバロック最先端、期待のムーティ「ローマの松」

音楽評論家の堀内修さんが、毎月「何かが起りそう」なオペラ・コンサートを予想し、翌月にそこで「何が起ったのか」を報告していく連載。4月は、ルネ・ヤーコプス(指揮)ビー・ロック・オーケストラの《時と悟りの勝利》、ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ、リセット・オロペサのソプラノ・コンサートを予想。3月の結果報告は、ベルリン・フィルのメンバーによる室内楽、読売日響による《ヴォツェック》、サー・アンドラーシュ・シフ&カペラ・アンドレア・バルカ、東京春祭ワーグナー・シリーズ 《パルジファル》の4つです。

東京生まれ。『音楽の友』誌『レコード芸術』誌にニュースや演奏会の評を書き始めたのは1975年だった。以後音楽評論家として活動し、新聞や雑誌に記事を書くほか、テレビやF...
何かが起りそう(4月のオペラ・コンサート予想)
1. ルネ・ヤーコプス(指揮)ビー・ロック・オーケストラ ヘンデル《時と悟りの勝利》(4/4・東京オペラシティ コンサートホール)

新しい演奏家ってわけじゃない。むしろ現在のバロックの草分けだ。でもルネ・ヤーコプスのヘンデルは、いまなお最先端の演奏を期待させる。ビー・ロック・オーケストラは若いアンサンブルだし、スンへ・イムやカテリーナ・カスパー、それにカウンターテナーのポール・フィギエやテノールのトーマス・ウォーカーは、いま第一線に立ったという若く有望な歌手たちだ。
ヘンデルのオラトリオ《時と悟りの勝利》をこのメンバーで演奏するとなると、バロック好きはもちろん、現代のバロック芸術の最先端を求める人ならとびつきたくなる。さあとびつこう。
2. リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ (4/11、12・東京文化会館 大ホール)

もう何も言うことはない「巨匠」がリッカルド・ムーティだが、それでも詣でたくなる。しっかりヴェルディの序曲を鳴り響かせた後、レスピーギ《ローマの松》なのだから、期待して聴きたい。期待通りの演奏が聴けるのがムーティってものだ。
オペラの序曲を演奏するコンサートの定番というべきがヴェルディ《運命の力》序曲で、期待通りの演奏になる確率が低いのもこの曲なのだが、ムーティは別だ。もちろん《ローマの松》だって望み通りになるはず。輪郭のはっきりしたムーティならではの演奏が、間違いなく聴ける。
3. リセット・オロペサ(ソプラノ)(4/10、13・サントリーホール)

1度くらいオロペサの歌うベッリーニ《夢遊病の女》の舞台を見てみたい、と願うファンもきっといるだろう。ウィーンやロンドンなど各地の歌劇場でベルカント・オペラのヒロインを歌うオロペサの映像を見れば、つい口惜しく思ってしまうからだ。これからもオロペサは活躍し、日本でもオペラの舞台に立ってくれそうだが、コロラトゥーラの妙技で客席を圧倒することのできるソプラノとしては、いま絶頂期を迎えている。
その時機を逃すまいと思うなら、このコンサートに行くほかない。オペラの舞台ではないけれど、そのかわりいろんなヒロインを歌うオロペサが聴ける。満開の花の季節がやってくる。
何が起ったのか(3月のオペラ・コンサートで)
1.ベルリン・フィルのメンバーによる室内楽(3/14・東京文化会館 小ホール)
塵ひとつない演奏、なんて言い方があるのだろうか? なくてもそう言いたくなるシューマンのピアノ三重奏曲だった。清潔でまったく濁りがない。すべての音がきれいに磨かれ、互いに寄りかかったりしない。「『仕立て屋カカドゥ』の主題による変奏曲とロンド」、というベートーヴェンの面白い曲だって、泥臭さはまるでない。少しだけ、あってもいいのになあ、と思ったりするくらい。東京・春・音楽祭は実にキレイに始まった。
2. 読売日響第646回定期 ベルク《ヴォツェック》演奏会形式(3/12、13・サントリーホール)
とがった20世紀音楽の金字塔ではなく、いまやオペラとしてなじみ、聴き慣れている名作《ヴォツェック》としてヴァイグレが指揮した。展開も響きも、言ってしまうのがちょっとためらわれるけれど、滅法面白かった。
マリー役のアリソン・オークス(ソプラノ)が強力で、ちょっと「マリーの悲劇」みたいになったが、ベンヤミン・ブルンスの鼓手長やファルク・シュトゥルックマンの医者などもぴったりはまり、サイモン・キーンリーサイドのヴォツェックだって演技の巧さが効いた。休む間のない《ヴォツェック》の時間だった。
3. サー・アンドラーシュ・シフ カペラ・アンドレア・バルカ(3/21・ミューザ川崎シンフォニーホール、3/22・フェニーチェ堺、3/23・京都コンサートホール、3/25、26・東京オペラシティ コンサートホール)
ピアノと管弦楽がひとつになって音楽の模様を描いていく。まず幾何学模様、つぎはアラベスクというように。3楽章のピアノ協奏曲が6曲だから、次から次へと異なる模様が演奏される。一休みするのは4曲終えての休憩時間だけ。とてもなじんだ音楽とは思えない新鮮さなので、あっという間にバッハの6つの協奏曲が終ってしまう。
6曲を終えたあと、「ブランデンブルク協奏曲第5番」からのアンコールが始まった時、これは蛇足だと思った。でもすぐに、これが庭園の扉が閉まる音なのだと気づく。見事な音楽のフォーマル・ガーデン(整形式庭園)の扉が閉じた。
4. ワーグナー《パルジファル》演奏会形式(3/27、30・東京文化会館 大ホール)
聖杯の儀式が執り行なわれた。1か所の齟齬もなく。ゲルハーヘルの歌うアンフォルタスの嘆きだけだって聴き入るに価するが、その嘆きも荘厳な儀式の1部だった。すべてのネジを締め上げたような演奏が、《パルジファル》をそびえ立たせた。
時に冷徹だとさえ思えるヤノフスキの指揮が3幕を貫くと、確固とした《パルジファル》の全容が現われる。グルネマンツのタレク・ナズミやクンドリのターニャ・アリアーネ・バウムガルトナーなど歌手たちが見事に揃っていただけでなく、オーケストラから合唱団から隙がない、ワーグナーの「演奏される芸術」が聴けた。
こうなると、演奏会形式の先にある「舞台神聖祝典劇」の実現を望みたくなる。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest