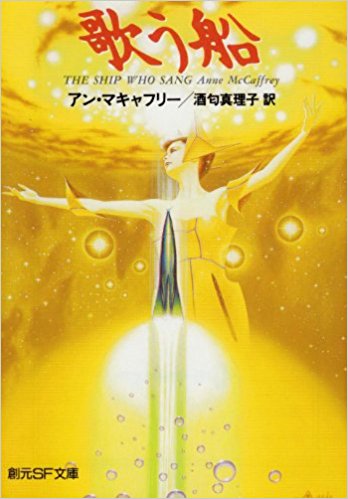SFに登場する未来の音楽 押さえておきたい3冊!


音楽ジャーナリスト。都内在住。著書に『はじめてのクラシック マンガで教養』[監修・執筆](朝日新聞出版)、『クラシック音楽のトリセツ』(SB新書)、『R40のクラシッ...
バッハで道を踏み外した未来の天才音楽家
100年前の音楽は「歴史」だが、100年後の音楽は「ファンタジー」だ。だれも未来の音楽を予測することはできない。でも、未来の音楽がどう描かれているか、ということだったら語れる。SF作品にはどんな未来の音楽が登場するだろうか。
まずは正攻法(?)と言えそうなのが、オースン・スコット・カードの短篇『無伴奏ソナタ』。人々の才能や適性が厳格に測定され、それに従って職業が与えられる管理社会のなかで、主人公クリスチャンは2歳にして音楽の神童であると判定される。そして、クリスチャンは両親から隔絶され、森の奥深くであらゆる他人の音楽や人工的な音から隔絶されて育てられる。彼が聴くことを許されるのは、鳥の歌や風の歌、雷鳴といった自然が奏でる音のみ。孤独なクリスチャンは、唯一与えられた万能の「楽器」を友として、これを操って、真の天才のみに許された音楽を創造する……。
なにせ小説なのでクリスチャンの音楽がどのような音なのかは想像するほかないわけだが、この小説内世界では「天才が創造的であるためには無垢であるべき」という考え方が浸透しているのが興味深い。というのも現実の音楽史では、大作曲家たちは先人たちから影響を受けることで、創造的な作品を生み出している。これは一種のディストピア小説と呼ぶべきだろう。
ちなみに純粋培養で才能を育んできたクリスチャンは、あるときバッハの音楽と禁断の出会いを果たしてしまうことから、道を踏み外してしまう。バッハ、恐るべし。
アン・マキャフリーの長篇『歌う船』では、タイトル通り、宇宙船が歌う。宇宙船といっても、これは女の子なのだ。女の子の脳に生命維持装置と宇宙船を制御するための入出力装置がつながれたサイボーグ宇宙船という設定。1960年代に書かれたことを考えると、時代を先取りした趣向といってもいい。なかなか女子力の高い宇宙船で、がんばり屋さんでもあるのだが、特技は歌。未来の音楽を言葉で表現するのは難しいのか、どんな音楽なのかについての具体的に描写は見当たらないのだが、サイボーグ歌唱という発想はありかもしれない。また、登場人物に音楽を武器として人々の潜在意識に主張を浸透させることを仕事とする「ディラニスト」なる人物が出てくるのもおもしろい。
未来の音楽は案外今と変わらない!?
ところで、今年公開されて話題を呼んだ映画『ブレードランナー2049』では、主人公の携帯端末の着信音(みたいなもの)に、プロコフィエフの《ピーターと狼》が設定されていた。「ん、なんでその曲なの?」という問いにはいろんな答えを返せるとは思うのだが、ひとつ真実味があると思うのは、未来になっても人々がなじんでいる音楽は今と案外変わらないんじゃないか、ということ。クラシック音楽のレパートリーに関して言えば、この半世紀くらいにオーケストラやオペラの世界に定着した新作はかなり少ない。すぐれた新曲はたくさん書かれているのだろうが、レパートリーとして世界各地で演奏されるためのハードルは極端に高くなっている。

そう考えると、現代と同じような名曲が愛好されているという未来図も十分にありうる。であれば、ジャック・ヴァンスの荒唐無稽な冒険譚『スペース・オペラ』で、おなじみのオペラの名作がいくつも登場するのも納得がゆく。ここで描かれるのは宇宙歌劇団の物語。オペラ界の有力パトロンであるお金持ちのマダムが、地球の芸術を宇宙に知らしめるべく、宇宙歌劇団を結成する。そして彼らは異星の知的種族たちを訪れて、ロッシーニの《セビリアの理髪師》やワーグナーの《トリスタンとイゾルデ》、ベルクの《ヴォツェック》などを上演するのだ。マダムの熱い思いに反して、異星人たちはまるで期待通りの反応を示してくれず、途方もない誤解を生み出すばかり(もちろん、これはコメディだ)。
「音楽は世界の共通語」どころか、「音楽ってホントにハイコンテクストで分かり合えないよね」という認識が背景にあって、笑えるうえに味わい深い。ヴァンスのいじわるさがよく出ている。
関連する記事
-
イベント巨匠シフが大阪フェニーチェ堺でカペラ・アンドレア・バルカと奏でるバッハ
-
読みもの【林田直樹の今月のおすすめアルバム】ピアノデュオの既成概念をくつがえす、坂本姉妹...
-
読みもの【林田直樹の今月のおすすめアルバム】何度見ても新鮮なベルリン・フィルの子ども向け...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest