
シューベルトのピアノ五重奏曲《ます》を作曲当時のピアノと弦楽器で聴く魅力とは?

かつて小学校の音楽鑑賞教材になっていた、シューベルトのピアノ五重奏曲《ます》。その「アンサンブルの面白さ」を、サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン2022の6月12日(日)11:00開演「室内楽のしおり~ピアノと弦楽器のアンサンブル」と18:00開演「フォルテピアノ・カレイドスコープ Ⅰ」に出演する、デンハーグピアノ五重奏団の小川加恵さん(フォルテピアノ)と角谷朋紀さん(コントラバス)に聞きました。
取材場所は、小川さんのご自宅。昔の美しいフォルテピアノとコントラバスのつくりの細部を、たくさんの写真で紹介します。
作曲された当時の楽器で18世紀末から19世紀前半のレパートリーを演奏する、その魅力とは?

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...
《ます》を聴くときは、淡水魚のイメージを想像しても大丈夫?
——シューベルトのピアノ五重奏曲《ます》って、印象的なタイトルですよね。初めて聴く人なら、この曲は淡水魚の鱒(ます)について何か表現しようとしている曲なのかなって思う人もいるかもしれない。第4楽章の優雅なメロディの原曲は、もともと歌曲から取られていますが、その歌詞は、透明な川の流れのなかで用心深く泳いでいたマスが、あっけなく狡猾な釣り人に釣られてしまうという、残酷な内容です。
ピアノ五重奏曲として演奏するとき、その辺の歌の意味はどのくらい意識されますか? 小川や魚のイメージを持っていいのかどうか……。
小川 曲自体は、シューベルトの作品のなかでも至極明るいんですよね。それもユニークなくらいに。22歳(1819年)のときの作品ですが、2年前に書かれた歌曲の詩に潜んでいるストーリーの危うさを、一種オブラートに包んだ感じで表現しているのかも知れません。
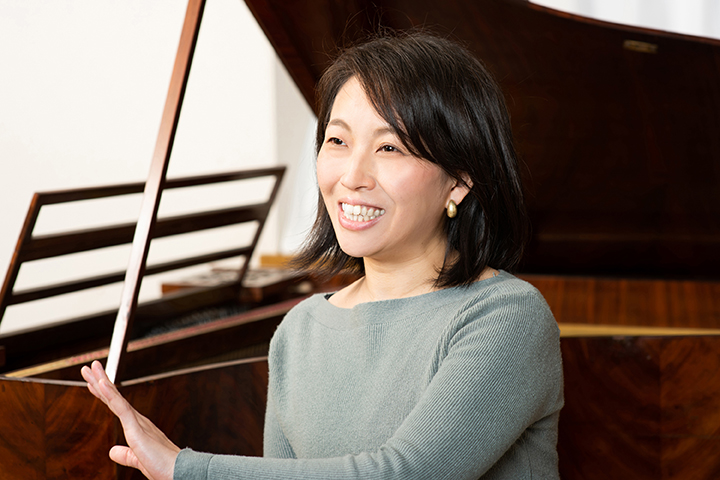
東京藝術大学、オランダのデンハーグ王立音楽院修了。国内外でソリスト、アンサンブル奏者として活躍。第16回ファン・ワセナール国際古楽コンクール第1位受賞。オリジナル楽器による室内楽の普及に努め、第8回浜松国際ピアノコンクールの関連事業として、レクチャーおよび室内楽公演を行った。また、国立音楽大学音楽研究所「楽譜を読むチカラ」プロジェクト講師、第31回国際古楽コンクール〈山梨〉審査員を務めた。テレビ朝日「題名のない音楽会」などメディアへの出演も多い。
角谷 明るいなかでも、たまにふと暗い表情にいくときがあるのですが、暗い部分をフォルテじゃなくて、ピアニッシモで強調していく。そういうところにシューベルトらしさが出ていますね。もともとの歌曲を、シューベルトがどのくらい意識していたのかは判断が難しいです。五重奏曲は、独自の世界を追求しているかもしれません。
小川 もともとの歌曲も、歌い出しはすごく軽やかで、きらきらとした感じですけれど、少しだけ愁いが入る。五重奏曲は、歌詞こそつきませんが、その代わりに多彩な楽器の音色が加わることで、歌詞に描かれているシーンをもうちょっと劇的に増幅したような感じですかね。
あの当時は、フンメルのピアノ七重奏曲 作品74がすごい人気を博していたんですね。後にその作品をフンメル自身が五重奏曲に編曲しているんですが、それと同じ編成で書いてほしいというアマチュア・チェリスト(音楽好きの工場主パウムガルトナー。音楽の集いをよく催していたウィーンの富裕市民層の一人)からの依頼で書いた作品です。つまり、人気の編成や手法を使ってほしいという依頼主の要望に応えたという意味で、歌曲から離れたプラスアルファのところはあったはずですね。
シューベルト:ピアノ五重奏曲《ます》第4楽章(演奏:デンハーグピアノ五重奏団)
——シューベルトの曲では、例えば《美しき水車小屋の娘》という連作歌曲集が後に書かれますけれど、そこには小川の流れが物語のなかで大切な役割を果たしています。歌曲集《冬の旅》も、雪や氷や霜のイメージが重要で、単独の歌曲でも水にまつわる曲はたくさんあります。シューベルトは“水の作曲家”と言ってもいいんじゃないかというくらい。
そういう意味では、《ます》も水の音楽の系譜に入りそうな気もします。
角谷 そうですね。《ます》の第4楽章に出てくる変奏曲ごとの情景の変化は、やっぱり川の流れと関係あるように感じます。ヴィオラの音型にも、明らかに水を思わせるところがあるし、小さな水滴が落ちるような感じもある。ゆったりしたなかに機敏な動きが入ってくる場面は、どうしても魚のイメージを連想しますね。

東京藝術大学、デンハーグ王立音楽院修了。ガーディナー、クイケン、アルフェンなどの指揮のもと、イングリッシュ・バロック・ソロイスツ、ラ・プティット・バンドなどのオーケストラに多数参加。第16回ファン・ワセナール国際コンクールでは、第1位および最優秀演奏者賞受賞。第32回国際古楽コンクール〈山梨〉審査員。また、ウィーンのコントラバスや、ローマのガット弦の伝統的な製法についても研究を重ねる。
小川 演奏を通して何かを明らかに伝えようとするときには、はっきり具体的にイメージしていないと伝わらない。それは、一つの基本かなと思います。19世紀のフォルテピアノの特徴が生きるのも、そこにつながると思います。つまり、音の減衰の速さ。これが音型をより顕著に、クリアに表現してくれるのです。
現代のピアノで弾くと、残響が多いぶん、どうしても重くなってしまう……。
——つまり、何か機敏な動きを表現するのは、むしろフォルテピアノに向いていると?
小川 はい。我々の演奏を聴いて、皆さんはフレッシュだと言ってくださるんですけれども、そう聴こえるのは、このウィーンのフォルテピアノであれ、当時の弦楽器であれ、音の減衰の速さが要因になっていますね。
《ます》の第4楽章では、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ピアノがそれぞれの変奏曲で主役として出てくるのも醍醐味かなと思っています。次はこの楽器、次はこの楽器と、楽しみながら聴いていただければ。
——ジャズもそうですが、主役がリレーしていくってことですね。
小川 さらには、その主役と脇役が入れ替わるところでは、実は脇役のほうにも注目して聴いていただきたいんです。
角谷 この第4楽章は、1日の中の情景がどんどん変わっていくような感じがあるんです。その頂点になるような変奏で、雷雨が来るようなところもある。ずっと同じアンダンテのテンポなのに、劇的に情景が変化する。
小川 予想外の展開がたくさんありますよね。あの優雅な歌がここまで激しくなるのかと。場面がガラリと変わるみたいに、転調の仕方にもとても斬新な仕掛けがあります。
美しすぎるフォルテピアノ、1835年製シュヴァルトリンクは、ウィーンの香りを伝える
——もう私は何が驚いたって、昨年サントリーホールのブルーローズ(小ホール)で聴いたときに、楽器とホールとの相性があまりにもバッチリだったことです。あたかも密封されていた香りが解き放たれたかのように、ホールの空間全体を満たしていったのが忘れられません。

今年も6月12日(日)11:00開演「室内楽のしおり~ピアノと弦楽器のアンサンブル」と18:00開演「フォルテピアノ・カレイドスコープ Ⅰ」の2つの公演で聴くことができる。

小川 本当にそうですね。このピアノはコンサートホールに行くと、秘めた力を解き放って、隅々までその多彩な音色を届けてくれる楽器です。
プラハに工房を構えていた楽器製作家アントン・シュヴァルトリンクはあまり知られていませんが、ウィーンの楽器工房で修行していたことはわかっていて、これもウィーン式アクションのピアノの造りになっています。
——近くで見ると、細やかな装飾が綺麗ですよね。楽器を前にしたときの気持ちが全然違いますよね。この輝くような鍵盤は……。
小川 白鍵は真珠層(貝殻の内面を覆う真珠色の陶器質の層)、黒鍵は鍵盤の木の上に金箔を貼って、その上に鼈甲(べっこう)をかぶせてあります。

——一つひとつの模様が全部違うのがいいですね。
小川 目立たないところにも、いっぱいこだわりの仕掛けや装飾が施されているんです。誰も見ないような場所すらも、凝ったデザインで満載です。たとえば、くびれた足は鷲の足の形です。

小川 ピアノの底板が開いていて、音のヌケを良くしているのは、このピアノの大きな特徴ですね。響板は木だけでできています。弦の張力を補強するために鉄柱を入れるようになる以前のつくりで、ガット弦を張った弦楽器とのアンサンブルの相性は抜群です。


小川 打鍵のしくみも現代のピアノとは違い、ハンマーを跳ね上げる形で弦を叩くウィーン式アクションで、そのハンマーは鹿の皮を何層にも巻いた造りになっています。軽やかで明瞭な音というのがウィーン式の特徴だと言われていますが、発音したあとスッと音が消えるわけです。だからモーツァルトの音楽など、とても軽やかに聴こえます。
ウィーンのフォルテピアノでは、有名な製作家アントン・ワルターの楽器でもそうなっているんですけど、シュヴァルトリンクのような鍵盤数が多くなってきた頃の楽器では、高音から低音のハンマーの大きさの差がかなり顕著になっています。
これが、低音、中音、高音それぞれの音域で、まったく異なる音色を出せる要因の一つとなっていて、その音色のキャラクターの違いが面白いんです。コントラバスが何台も一緒に演奏しているようなパワフルな音色の低音から、チェロが朗々と歌い上げるような中音域、煌びやかなフルートが軽やかに奏でられているような高音域と、実に表情豊かに奏でてくれます。

——ここまでピアノを分解して、楽器の構造の細部について語れるのは、フォルテピアノ奏者ならではのすごさですね。楽器そのものを隅々まで知ってますね。
小川 華奢ですから壊れることもいっぱいありますし、それを直しながら一緒に付き合っているのが、愛着にもつながるんだと思います。でも、私はこれを未発達の楽器だとは全然思っていなくて、この不完全なところを含めて、人間と同じような魅力を感じているんですよ。

昔のコントラバスを、ガット弦の製造法にまでこだわって復元
——19世紀初頭ウィーンのコントラバスは、当時の他の町のコントラバスとはかなり違うものだったんですか?
角谷 そうですね。18世紀のウィーンを中心としたエリアで作られたタイプの楽器は、チロル地方からだんだん広がっていったようなんですけれども、弦も5本あって、調弦もラ・♯ファ・レ・ラ・ファとなっていて、現代のコントラバス(標準は4弦)とはずいぶん違うんです。
——近くで聴くとすごいバイブレーションです。ガット弦の特別な低音は、ライブだときっと格別でしょうね。
ところで、ごめんなさい、コントラバスって何かぼんやり演奏する楽器の象徴みたいに思われるところがあるじゃないですか(笑)。
角谷 一般的には(笑)。ぼやっと聴こえる理由の一つに、現代のスチール弦は弓を返したときに、返したポイントがわからないぐらい長いフレーズが作れるという特徴があると思います。音の切れ目がわからないように、滑らかにずっと保てるように、というのは、現代の弦楽器の目的にかなっていて、よく歌わせるための手段としてのスチール弦ということもあるんです。
昔使われていたガット弦の場合は、まったく逆のコンセプトで、それぞれの音符をはっきりと聴かせ、語る、しゃべる感じを目的にしているんです。
——スチール弦は滑らかに歌う、ガット弦ははっきりと語ると?
角谷 なので、スチール弦で古典派以前の音楽を演奏すると、引っかかりが滑らかになってしまうんです。もちろんガット弦でも柔らかく弾くこともできるんですけれども、引っかかりというか、鋭さがあってこそ、思い通りに演奏できるという面があるんです。
(2種類の弦を出して)これは現在ガット弦として販売されている既製品で、こちらは僕が自分で作ったガット弦なんですけども、触っていただくとわかるんですが……。


——あ、全然違いますね。既製品のほうがツルツルですね。角谷さんが手づくりなさったガット弦は、すごいザラザラ感が。
角谷 それが大事なんです。表面を機械でこうツルツルに削ってしまうというのは、20世紀の初め頃にそういう機械ができてからです。しなやかで引っかかりのある音が欲しいので、ザラザラしてることが必要です。
——ご自身でガット弦を作っていらっしゃるというのは、羊の解体された腸ぐらいの段階からですか。
角谷 さすがに、ある程度きれいにされ、塩漬けになったもので入手します。羊にもいろんな種類がありますし、サイズや育て方によっても楽器の弦にする際に向き不向きがあります。18世紀当時、弦の一大産地はローマの近郊にあって、そこではイースターの頃に子羊を食べる習慣になっていて、そのときに取れる羊の腸がすごく細くて強いものだったんだそうです。冬の間、餌の少ない山岳地帯で育った羊の腸がよかったらしいです。でもさすがに今、それは入手が困難で。

——すごいこだわりですね。この手づくりの弦の太さ(太いもので直径4.4mm)は、すごいインパクトです。ボディの大きさやネックのついている角度も現代のものとは違っていたり、ボディの裏の下についている丸いコブのようなものにもこだわっておられるそうですね。
角谷 ええ、このようなコブは18世紀のウィーンでしか使われていなくて、当時の状態を復元して弾いている人は、そんなに多くないかなと思います。
ボウ(弓)も一応、19世紀初めごろのウィーンのタイプを使っています。バロックボウだと外側に反っていて、モダンボウは内側に反っているんですけど、身体の使い方もまったく変わってきます。
実はオリジナルの古い楽器は、これまでの過程で部分的にモダン楽器に変えられているので、僕としては可能な限り、1760年頃の当時の状態に忠実に復元したかったのです。



オーケストラ曲を編曲した室内楽版の面白みとは
——ところで、今回のサントリーホールでのコンサートでは、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番を、当時ヴィンツェンツ・ラハナー(1811-93)が編曲した室内楽版で演奏されますね。これは、従来オーケストラを中心に聴いてきたお客さんを、室内楽の世界へと引き寄せるきっかけになる楽曲ではないかと思うのですが。
小川 一人ひとりがオーケストラの中で群を成して演奏するよりも、1パートを一人が受け持つことによって、よりシャープに聴けて、何をやっているかが伝わりやすい。もちろんオーケストラでは管楽器が入っていますが、ファゴットをチェロが、フルートをヴァイオリンが音色を模して弾く、そういう工夫もまた違和感なく面白く聴いていただけると思うんです。
あとは、それぞれの奏者の間の丁々発止のやりとりですね。そこにこそ室内楽の醍醐味はあるので。それをより緊密に味わっていただけるのではないかと思います。
——指揮者がいないことによって得られる強みも、そういうところにありそうですね。
小川 これは、我々がずっと前から取り組んできた「伴奏つきソナタ」の経験も生きてくると思います。それは、ただの「伴奏」で終わらない、タイミングを合わせるだけの役割ではないということです。ピアノパートが何かを弾いているとき、それに合わせる側は自分の役割をどうするか。それが、この室内楽バージョンで聴ける醍醐味だと思います。
角谷 一人ひとりの奏者がより自発的に、音楽に関わっていくことだと思います。自分が弾いているパートが、他のパートにとってどういう意味を持っているのか。それを考えて、他のパートをよく聴きながら合わせていく。指揮者の指示があっての受け身ではなく、自ら積極的に音楽に関わっていく。それは大きな違いとなって現れるのではないかなと思います。
——オーケストラが一番偉いということは全然ないと私も思うんです。室内楽編曲版は、小さな会場で演奏するために、省略して小さくした代用品というわけではなくて、室内楽版だからこそ伝わるものって、実はとても大きいですよね。
小川 たとえばフンメルも、尊敬してやまないモーツァルトのピアノ協奏曲を、どうしても一人でも多くの人に聴かせたいと思って、参加する演奏者の人数や使用楽器の種類がより少なくなる室内楽版を作っているわけです。そこには、編曲した作曲家のオリジナル作品に対する憧れと畏敬の念が詰まっていて、楽譜になった時点で、すでに熱いものがあるわけじゃないですか。どうしてもこの曲をこういうふうに聴いてもらいたいみたいな意図が、そこには感じられるんです。
当時の編曲した作曲家と、現代に生きる我々演奏家との共同作業の魅力があると思います。
——編曲とは、翻訳であり、編集であり、そして解釈なんでしょうね。
お話をうかがっていて印象的だったのは、小川さんが話をしながら、いとおしそうに楽器を撫でていたことだった。木の温もりがあるから触ってみて、とおっしゃるので触ってみると、本当に温かい感じがじんわりと伝わってきて、少しまたフォルテピアノという楽器に近づけたような気がした。
18世紀のウィーンのコントラバスを探求しておられる角谷さんもそうだけれど、人間と楽器の関係が、とても密接で愛情に満ちていることが素敵だと思った。もちろん、現代の楽器でもそれは基本なのだろう。けれど、昔ながらの楽器は手がかかり、気難しいからこそ、とても人間的で、特別な魅力があるのだろう。
サントリーホールのチェンバーミュージック・ガーデンにおける「室内楽のしおり~ピアノと弦楽器のアンサンブル」「フォルテピアノ・カレイドスコープⅠ」で、その響きがアンサンブルとなって、どんな風に香り高く花開くのかが楽しみである。
林田直樹

関連する記事
-
インタビュー【Q&A】ヴァイオリニスト村田夏帆さん、世界が注目する17歳のオフ時間
-
インタビュー上野通明に50の質問!〈前編〉音楽家になると決めたのはいつ? 1日の練習時間は?...
-
記事チェリスト宮田 大にきく 多様なジャンルのプロ30人との“音楽の対話”から得たも...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest















