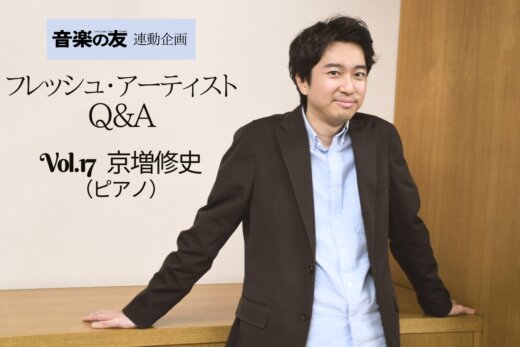快眠の専門家に聞いた、音楽とフットケアが導く快眠のヒント

「夜中に何度も目が覚める」「眠ったはずなのに疲れが取れていない」、そんな眠りの悩みを抱える現代人にいま注目されているのが、“五感”をととのえて眠るナイトルーティン。とくに注目されているのが、「足」と「音楽」による感覚へのアプローチです。
足の冷えやこわばり、そして日中に高ぶった神経を落ち着かせることが、睡眠の質を左右する大きなカギになります。今回は、睡眠の専門家・今枝昌子さん(日本快眠協会 代表理事)と、「おやすみフットケア」を開発したATEXの田代晶子さんに、心地よく眠るための新習慣について伺いました。

編集者、ライター。女性誌編集、ECサイト編集・ディレクター、WEBメディア編集長、書籍編集長などを経て現在。はじめてクラシック音楽を生で聞いたのは生後半年の頃。それ以...
途中で目が覚める……現代人の“眠りの質”の低下
「40〜50代に多い悩みが、寝つけないというより“途中で目が覚める”こと。これは今、ひじょうに増えています」と話すのは、日本快眠協会 代表理事の今枝さん。
「6〜7時間寝ているのに、疲れが取れていないという人が多いんです」とも指摘します。
睡眠時間ではなく、「休養感があるかどうか」が、睡眠の質を見極める重要なポイントになると言います。
途中で目が覚めてしまう原因はさまざまです。ストレスによる交感神経の過活動、体温調節の乱れ、寝室の環境(音・光・温度)、さらには加齢にともなう睡眠リズムの変化も関係しています。
「現代人は昼間に脳を使いすぎていて、上半身に熱がこもりやすいんです。対して足元は冷えている。この“熱のアンバランス”が、途中で目が覚める原因のひとつになっています」
こうした睡眠の質の低下を防ぐには、眠る前の“ととのえ方”がカギ。心を鎮め、五感をやさしく切り替えることで、自然な眠りに入りやすくなるといいます。

五感をととのえると、眠りは変わる
厚生労働省が発表した『健康づくりのための睡眠ガイド2023』でも、「睡眠による休養感の確保」が重視されています。
このガイドでは、睡眠時間の長さだけでなく、寝つき・中途覚醒・目覚めの良さなどを含めた“質”の改善が重要だとされ、生活習慣の見直しが強く推奨されています。
実は、快眠の準備は朝から始まっています。
『睡眠ガイド2023』によると、朝に1000ルクス以上の光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜になるとメラトニン(眠気を引き起こすホルモン)が分泌されやすくなることがわかっています。
朝の光をしっかり浴び、夜は光を落としていく。そんな“明暗のリズム”を生活に取り入れることが、自然な眠りへとつながっていくのです。
今枝さんも「音・光・香り・触感など、五感が眠りに大きく影響する」と語ります。
「眠る1時間前には、照明をオレンジ色に変えたり、スマホを手放すことが大切。照度は36ルクス以下が理想です。スマホはそのコンテンツの内容と照度によっては、脳が覚醒してしまいます」
また、聴覚へのアプローチとしては、クラシック音楽やヒーリングミュージック、カラードノイズなど、周波数が脳にやさしく作用する音楽を取り入れるのもおすすめです。
足裏から“眠れる体”をつくる
今枝さんのキャリアは、心療内科に勤務するセラピストとしてスタートしました。うつ病のリワーク支援などを通じて、多くの“眠れない”悩みと向き合う中で、「足の冷え」が深い眠りを妨げていることに気づいたといいます。
「診療内科の現場で、9割以上の患者さんが“眠れない”と訴えていました。毎週セラピストとして患者さんの足を見ていると、症状が改善した人の足の状態がどんどん変わっていきました。そこから“足から眠れる体をつくる”という考えにたどり着きました」
この実践をベースに、2009年から今枝さんが提唱しているのが「足裏快眠法」です。
反射区の集中する足裏にしっかり刺激を与え、下半身の血流を促進して“放熱の出口”をつくることで、深部体温を下げ、自然な眠りを導きます。
「足裏が冷たくて硬いままだと、脳の熱の逃げ場がなく、リラックスできない状態が続いてしまう。だから眠る前には、足をしっかりほぐしてあげることが大事なんです」
今枝さんは「足をもんで温めることは、就寝前の新しい習慣として広がっていってほしい」とも語ります。

快眠のために、足裏にはしっかりめの刺激を
そんな今枝さんの足裏快眠法の考え方をもとに開発されたのが、ATEXの「おやすみフットケア」。企画・開発を担当した田代晶子さんは語ります。
「ユーザーアンケートでも、足裏への強い刺激が“気持ちいい”という声が多く聞かれました。今回は寝たまま使えること、そして快眠につながる“しっかりめ”の刺激を入れることにこだわりました」
機能は、エアバッグによる圧迫・指圧、樹脂素材による足裏刺激、ふくらはぎを温めるヒーター、さらにやさしい肌触りの素材など。寝具としての使い心地にも配慮されています。
「そのまま寝落ちしてしまっても、タイマーで自動オフになりますし、足が抜けても“足枕”のように使える設計です」
さらに「おやすみフットケア」は、就寝時の姿勢のままベッドの上で使えることを意識した設計。足を入れやすい立体構造や、やわらかな素材感など、眠る直前でもストレスなく使える工夫が詰まっています。
「足をケアしたあとは、そのまま眠りに入ってもらいたい。そんな想いから、ベッド上での使用を前提にしたデザインになっています」と田代さん。
モードも2種類を搭載。おやすみモードは、足裏中心に心地よく刺激する仕様で、就寝前にぴったり。リフレッシュモードは、日中の疲れをしっかりケアしたいときに活用できる強めのマッサージです。

快眠への近道は“気持ちいい”を積み重ねること
快眠の鍵は、「体・心・環境」のすべてを整えること。とはいえ、いきなり完璧なナイトルーティンを目指す必要はありません。
「今日は音楽だけ、明日は足のマッサージだけでも、十分です」と今枝さんは言います。
大切なのは、“自分が気持ちいい”と感じられることを、ひとつずつ積み重ねていくこと。それが、眠りを変えるいちばんの近道になります。
たとえば、お気に入りのハーブティーを飲む、スマホを1時間だけ手放してみる、足をやさしくマッサージする。そんな何気ない習慣が、脳と体に「もう休んでいいんだよ」というサインを送ってくれます。
なかでも音楽は、日常から気持ちを切り替えるスイッチとして、とても効果的。静かなクラシック音楽など、聴覚からリラックスを促す音は、眠りの準備にぴったりです。
「私自身も、夜は照明を落として、ハーブティーを淹れ、音楽を流す。そんな時間を“ごほうび”のように感じています」と、今枝さんは自身のナイトルーティンについても教えてくれました。
忙しい毎日の中で、自分を大切にするための夜時間から、質のよい眠りは生まれていきます。一日の終わりに、自分のための静かな時間を持つこと。それが、次の日の元気な自分をつくる、大切な習慣になるかもしれません。
一般社団法人日本快眠協会 代表理事
CSAスリープケアマスター
心療内科でリワーク講師を9年とリフレクソロジストとして眠れない12,000本の足裏から生み出した独自のメソッド『足裏快眠法』を日本心身医学会発表。2012年日本快眠協会設立。企業10,000名以上に『睡眠力の鍛え方研修』を行う。公財)神経研究所機構の推進員として医師とのコラボ研修、睡眠改善プログラムを提供、眠育事業を行う。『1分間の深いイイ話』等TV、雑誌、新聞コラム多数掲載。書籍『生活習慣を変えなくても深い眠りは手に入る』
関連する記事
-
レポート石田泰尚さんが横浜みなとみらいホールプロデューサー“ラストイヤー”への意気込みを...
-
読みものスカラ座より熱い!? ミラノ五輪はサン・シーロから始まる
-
インタビューケヴィン・ケナーが語るショパン演奏「音楽はアイデアではなく、体験である」
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest