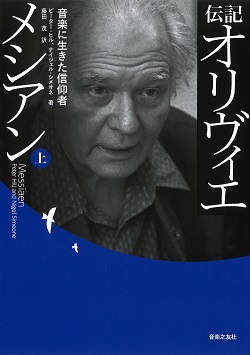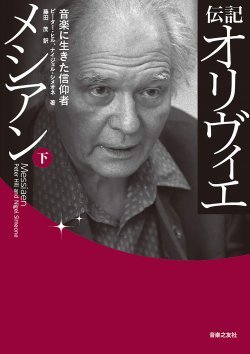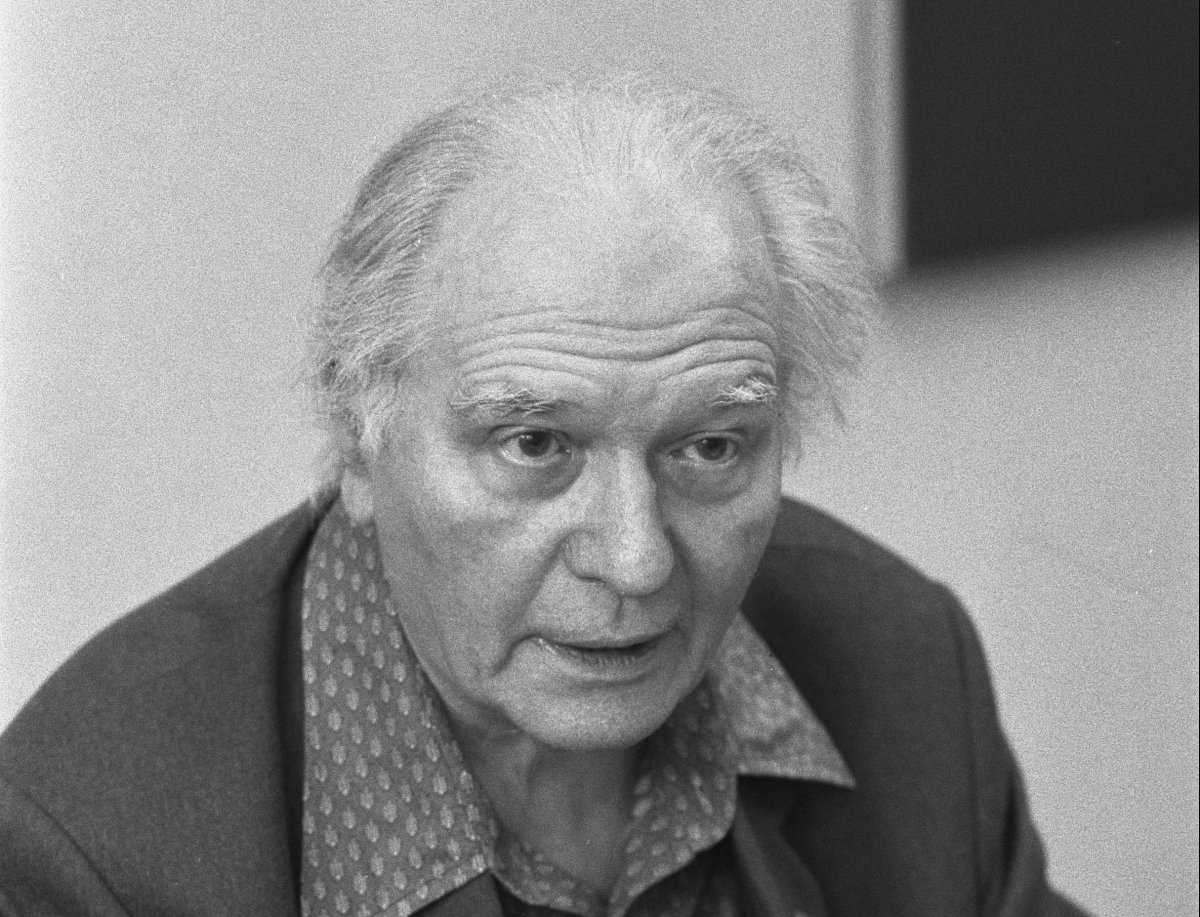鳥の声は「神が与えし秩序」? メシアン音楽と鳥の関係を深掘り!

前編ではメシアンのちょっと盛り気味? な鳥との出会いから、メシアンがどうやって鳥の声を楽譜にしていったのかを藤田先生に教えていただきました。後編ではさらにディープに......メシアンの音楽と鳥の関係を探っていきます。さらには、演奏が難しいことでも知られるメシアン音楽演奏の未来も考えます。

1974年生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学院修士課程修了。Maqcuqrie University(シドニー)通訳翻訳修士課程修了。2008年よりクラシ...
メシアンと鳥の声の関わりの変遷
——メシアンの鳥をモチーフにした作品は、いくつもありますね。それぞれ、鳥へのアプローチに違いはあるのでしょうか。
藤田 メシアンの鳥へのアプローチは、大きく3期に分けて捉えることができます
イメージを喚起させる素材としての「鳥の声」
初期は1940年代まで、鳥の声をあくまで素材として使用していた時代です。代表曲にはピアノ作品の《幼子イエスに注ぐ20の眼差し》(1944年。第8曲「高き御空の眼差し」には主にヒバリの鳥の声をモチーフとしている)。
そして、オーケストラ作品の傑作《トゥーランガリラ交響曲》(1946~48年)があります。とくに第6曲では、愛の主題をサヨナキドリの歌が装飾します。
これらの作品における鳥の歌の使い方は、ロマン派までの作曲家たちと同じようなものでした。
リストの《伝説》第1曲「小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ」や、もっと古くは、ベートーヴェンの交響曲第6番《田園》で鳥のモチーフが使われていたように、リアルに鳥を描くというよりも、夢を喚起する、鳥とともにあるイメージを喚起するものでした。
リアリズムの時代
それが、1950年代からは徹底的にリアリズムに振っていった時期に入っていきます。《鳥たちの目覚め》(1953)、《鳥のカタログ》(1956~58)といった作品です。具体的な鳥の名前が逐一楽譜の中に書き込まれ、生息地や時間帯までも正確に記されるようになります。
ピアノと管弦楽のための《鳥たちの目覚め》
そして重要なのは、この頃からは、鳥の歌1音1音に和音が付けられていきます。鳥の声というのは、もちろん単旋律というか、一本の線なわけですが、メシアンはそこに音色の特徴を聴き出していて、それを表現するために和音を付けたのです。
——和音といっても、古典派やロマン派時代の音楽に付けられていたような、機能和声、コード進行があるようなものとは違うんですね。
藤田 はい、あくまで、音色を表現・再現するための音の塊とでも言いましょうか。メシアン学者の間では「分厚いモノフォニー」と読んでいるんですけど。
——分厚いモノフォニー! わかりやすい例では、ハトの声を、やさしい三和音で、フルートのフラッター(細かいタンギングで音を震わせる奏法)で、という書き方がされています。
でも、もっと、わたしたちには感じ取りにくい鳥の声も、メシアンはちゃんと音色の特徴まで捉えていて、それをピアノなどで再現するために、音の集積として表現している、と。
藤田 そうですね。
——わぁ……不気味(笑)。
藤田 採譜旅行には、妻でピアニストのイヴォンヌ・ロリオさんが付いていき、テープレコーダーを回して録音しましたから、それを聴きなおすこともあったかもしれないけれど、メシアンはある程度記憶をもとにして、一つ一つの響きを再現してるんですね。もはや「ド」とか「レ」とかいう単位でもない。音色をすべて違う和音で表現している。
ふたたび素材として用いた集大成時代
徹底的にリアリズムを追求したあとは、再び鳥の歌を素材として用いるところに回帰していきます。例えば《峡谷から星たちへ…》(1971~74年)。アメリカの自然美を描いた小規模なオーケストラのための作品です。
第2楽章「ムクドリモドキ」、第4楽章「マミジロオニヒタキ」のように、鳥の名がタイトルになった楽章もありますが、それ以外の楽章にも大量に鳥の声が入っており、楽譜には鳥が登場するたびに名前が書かれています。
神より与えられし「セリー」に従う——人間が作り出すものよりも美しいものがある
——人間が作る作曲のルールなどとは、完全に違った音の動きというか、鳥の声はある意味ひとつの自然現象ですよね? 人間の作った秩序ではない……
藤田 そこが重要なポイントです。メシアンは、1940年代の終わりに、現在、メシアン学者のあいだで「実験期」と呼ばれる特別な時代を経験するのですが、ここでは、「セリー」のアイデアを活用した、非常に数的な操作に、あえて自分を向かわせたのです。あとに《4つのリズム・エチュード》となる作品は、この時期を代表するものですね。とりわけ、その第3曲〈音価と音強のモード〉は有名です。
でも、セリーはあくまで人間の頭がつくりだしたもの。そこに、鳥の歌の重要さがあったのです。なぜなら、鳥の歌とは、メシアンによって、人間の外にあるものであって、いってみれば、神さまが与えてくれたセリーだったわけです。だから、それに「ついていく」ことが、喜びになるのです。
(※セリー:「音列」の意味。音の高さ、長さ、強さといったもろもろの要素を、一定の規則に沿って並べた列のこと。それをベースとして楽曲を構成していく作曲技法が、20世紀前半に生まれた)
——メシアンについて語るときには、カトリシズムも重要な要素ですが、やはり鳥の歌を考える時にも「神」という視点に行き着くのですね。
藤田 世界の見方ですよね。人間が作り出すものよりも美しいものがある、という大前提がメシアンの中にある。
——しかしながら、人間であるメシアン自身は、五線紙を用いてそれを表現をしていかなければいけない。鳥の声も、あくまで12音の西洋音階に落とし込む。鳥は半音よりも間の狭い音程で歌っていても、広い音程はより広くすることで、比率を合わせ、12音音階で表現したそうですね。比率を合わせるというのは、「遅回し」と同じ原理ですね。
藤田 そうです。鳥の歌は、神さまが与えてくれたセリーですから、相互の音の「比率」を保つことが重要だったわけです。顕微鏡を覗くようなものでしょうか。極小のものが、顕微鏡のレンズを通して、われわれの眼に見えるようになるように、メシアンは、鳥の歌を、メシアンの驚異の耳の力のレンズで、遅くしたり、拡大したりして、われわれ人間の耳に届くようにしているわけです。メシアンの音楽を通じて聴く「鳥の声」は、我々が普段感じているのとは違う次元にまで広がっていて、自然の声がどれだけ豊かなものであるか気付かせてくれるように思うのです。
メシアンの音楽に触れていると、大きなものを前にしているという感覚を強烈に覚えます。ある意味、人間の外側にあるものに、ちょっと触れてしまった……みたいな。それは「理解する」というよりも、何か大きなものに「照らされる」感覚に近い気がしています。
——藤田さんがもっともお好きな、メシアンの鳥度の高い作品はなんですか?
藤田 歌劇《アッシジの聖フランチェスコ》の第6景ですね。2017年のカンブルランと読響による演奏も素晴らしいものでしたが、2004年、 同じカンブルランの指揮でパリのオペラ・バスティーユで聴いた「鳥たちの大合唱」は忘れられません。鳥たちの光に包まれたようでした。
メシアン作品もついに古典化? 余裕で演奏する人たち
——「レコード芸術」誌8月号で、ベルトラン・シャマユの演奏する《幼児イエズスに注ぐ20の眼差し》をお聴きになり、メシアンがすでに古典となってきたと感じられたそうですね。
藤田 かつては《20の眼差し》を弾くというのは本当に大変なことで、演奏家は何か「山を乗り越えてやる」みたいな感じで、メシアンの音楽にアプローチしていたところがありました。しかし今は演奏テクニックが上がり、弾けるものなんだ、という前提から入られるようになった。
それは良い面と悪い面も当然あって、かつては、メシアン作品に向かうことには、暗闇の中にみずから分け入っていくようなロマンティシズム、忘我感のようなものがあったけど、今はそれが減ってきたかなという印象。メシアンも古典化というか、レパートリー化された音楽として吸収されていますね。
余裕でメシアンを弾いてるな、という印象を与えてくれた、最初のピアニストはピエール=ロラン・エマールだったかもしれません。あと何十年かしたら、ショパンのエチュードをさらに難しくしたゴドフスキーみたいに、《20の眼差し》を2曲一緒に片手で弾くとか、すごい人が出てくるかもしれないですね(笑)。
ピエール=ロラン・エマール『メシアンへのオマージュ』
ロジェ・ムラロ『メシアン:ピアノ作品全集』
藤田先生が翻訳したメシアンの伝記はこちら
関連する記事
-
レポート鳥を呼んでみた――メシアンの書いた楽譜をフルートで吹いたら鳥たちはやってくるのか...
-
読みもの『伝記 オリヴィエ・メシアン』で振り返る大作曲家、晩年の足跡
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest