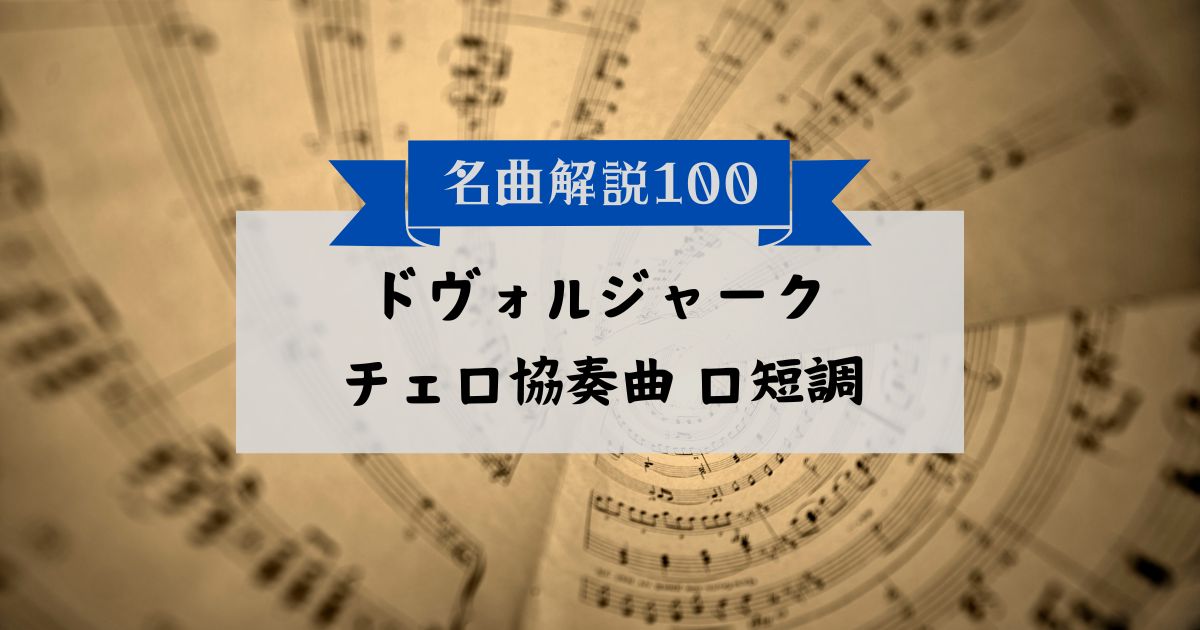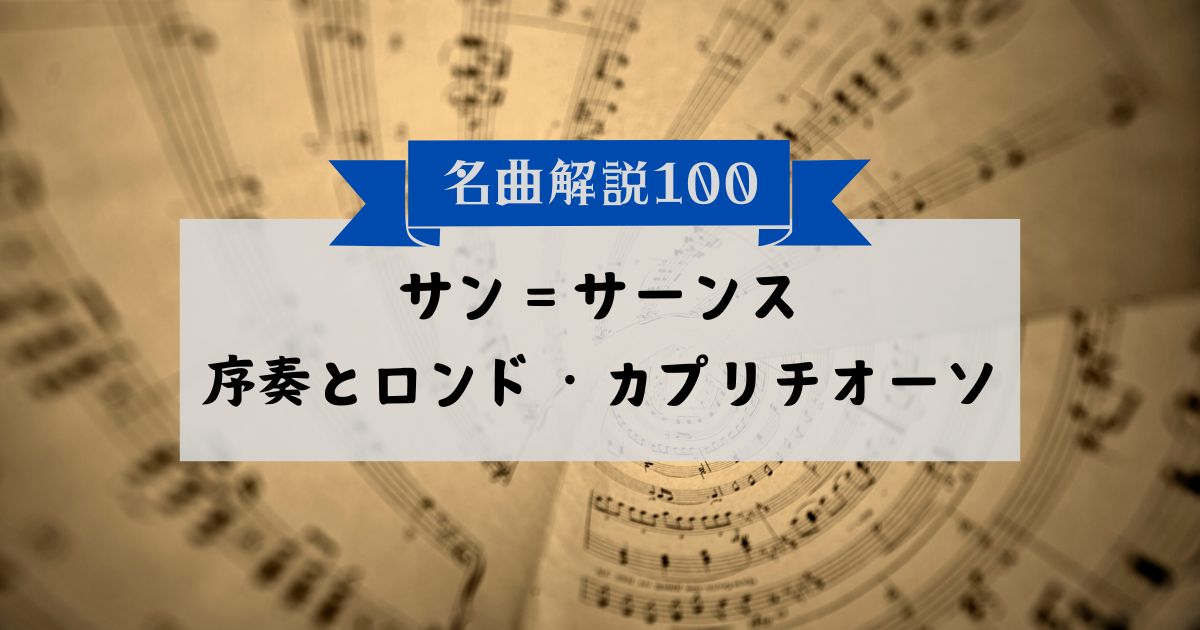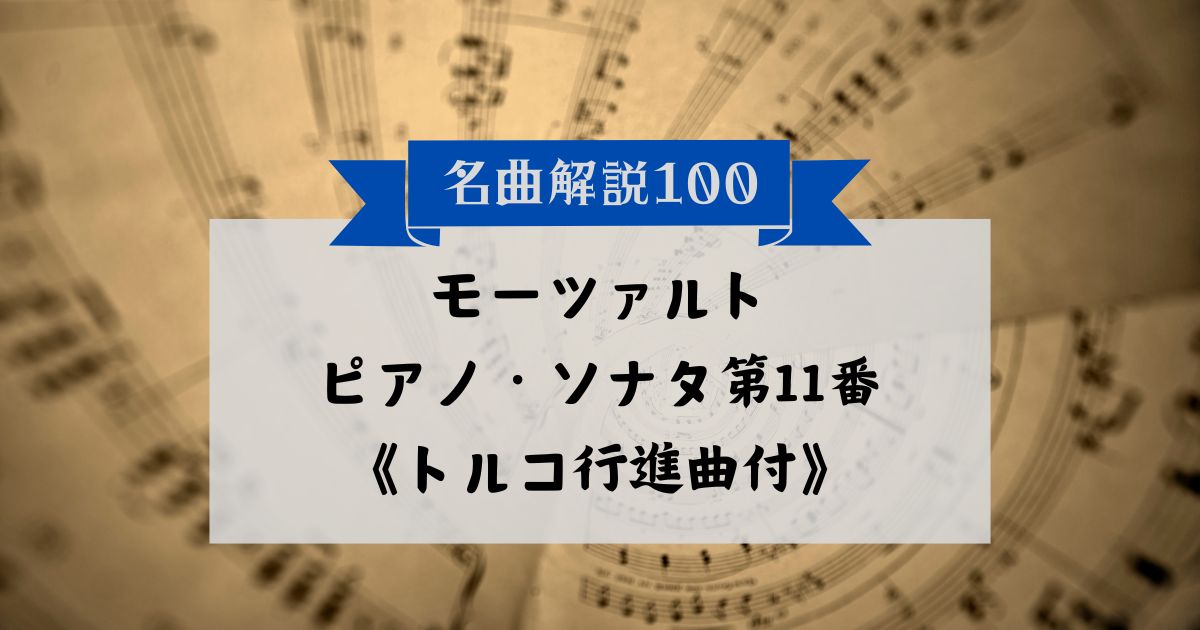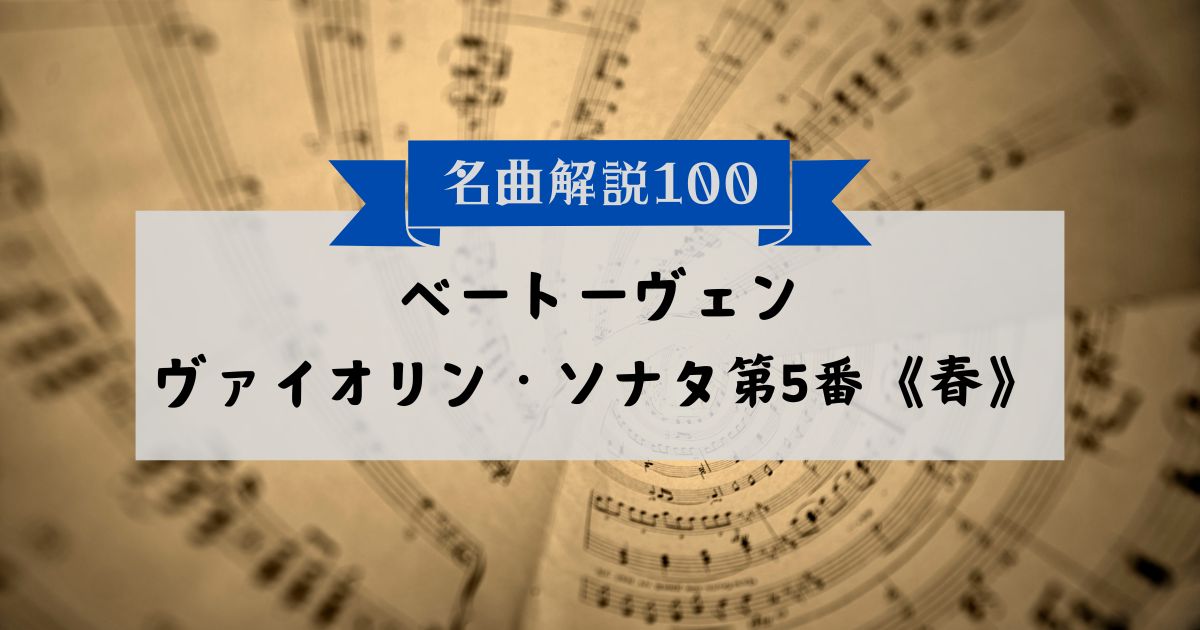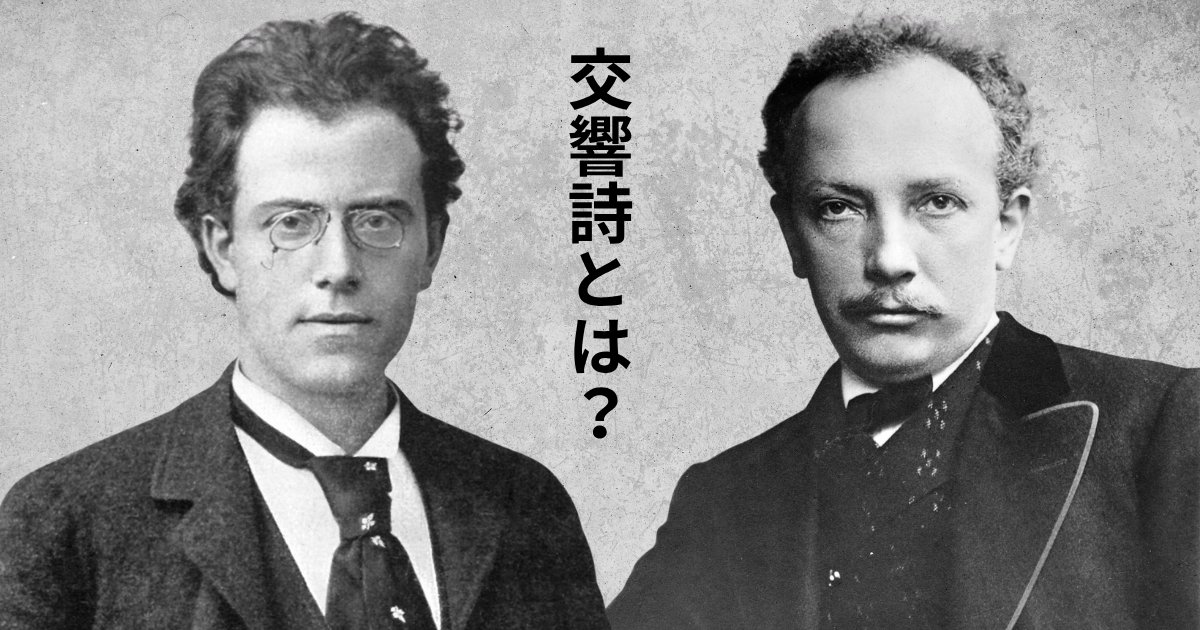ショパンコンクール ファイナルステージ~作曲家と心を重ね合せた11名の演奏を振り返る

10月18日から20日まで、第19回ショパン国際ピアノコンクールの本選ファイナルステージが開催。日本からは2名が出場しました。現地取材を行なっている音楽評論家の道下京子さんが、11名のファイナリストの演奏をレポートします。

2019年夏、息子が10歳を過ぎたのを機に海外へ行くのを再開。 1969年東京都大田区に生まれ、自然豊かな広島県の世羅高原で育つ。子どもの頃、ひよこ(のちにニワトリ)...
【リ・ティエンヨウ Tianyou Li (中国)】奇をてらわない誠実な演奏
《幻想ポロネーズ》は、音楽の呼吸にやや堅さが見られたものの、奇をてらうような表現はなく、誠実な演奏。「ピアノ協奏曲第1番」も、楽想や音の要素を極端に対比させず、音楽の流れを活かして作品を作り上げた。
(10月18日・スタインウェイ)

【エリック・ルー Eric Lu(アメリカ)】シューベルトのような歌の表現
シューベルトのような歌の表現が印象的である。《幻想ポロネーズ》では、重みを帯びた艶やかな音で、黄昏のような静けさのなかで晩年の作曲家の心情をゆったりと語っていく。
そして、「ピアノ協奏曲第2番」。第1楽章をやや速めのテンポで始めるが、第2主題では速度を落とし、メロディをささやくように甘美に歌う。第2楽章におけるモノローグのような語り口は見事。
(10月18日・ファツィオリ)

【リュウ・ティアンヤオ Tianyao Lyu (中国)】淡く透き通るようなサウンド
ワルシャワのこのコンクールで、人気コンテスタントの一人。《幻想ポロネーズ》の導入部では、過去に思いを寄せるような表現が心に残る。淡く透き通るようなサウンドで、音の綾をなめらかに織りなした。
「ピアノ協奏曲第1番」のほうが、伸び伸びとした演奏だったと思う。少しパワーに欠くが、年齢を重ねる中でさらに豊かな音の世界を開いていくことだろう。
(10月18日・ファツィオリ)

【ヴィンセント・オン Vincent Ong(マレーシア)】ショパンの時代の空気を伝える
《幻想ポロネーズ》では、テンポやリズムを正確に刻んでいく。ハーモニーやフレーズに呼応した細やかなデュナーミクの表出は、聴く者の心をしっかりと捉えた。
続いて、「ピアノ協奏曲第1番」。作品の細部まで読み解いた綿密さは見事である。また、第3楽章冒頭は少し緩やかであったが、実際の踊りを思い起こさせるような臨場感が醸し出されている。私たちが忘れてしまったショパンの時代の空気を伝えてくれるようなパフォーマンスであった。
(10月18日・カワイ)

【進藤実優】ショパンの豊かなメロディを熱く語りかける
《幻想ポロネーズ》導入部における、遥かな祖国を思い起こすような表現は感動的。主部に入ると、徐々に音の霧が晴れていき、スタインウェイの煌めくようなサウンドが優しく降り注ぐ。全体的に、音楽にしなやかな流れをもたらした演奏であった。
「ピアノ協奏曲第1番」でも、進藤らしいパッションあふれる音楽を披露した。ショパンの心の底からわき起こる豊かなメロディを、熱く語りかけるように歌い上げた姿が印象に残る。
(10月19日・スタインウェイ)

【ワン・ズートン Zitong Wang(中国)】作曲家の心の裡に潜む想いをしなやかに描き出す
第1ステージから注目されてきたワン・ズートンであるが、幻想ポロネーズ》ではミスが連続してしまった。しかし、「ピアノ協奏曲第1番」では、ドラマティックな音楽を聴かせてくれた。彼女が奏でるのは華やかで可憐なショパンではない。作曲家の心の裡に潜む恋焦がれるような想いをしなやかに描き出したその演奏は、聴く者の心を激しく揺さぶった。
(10月19日・カワイ)

【ウィリアム・ヤン William Yang(アメリカ)】ピュアなショパンを聴かせる
手垢にまみれたショパン演奏が多いなか、彼はピュアなショパンを聴かせてくれた。《幻想ポロネーズ》において、ひとつの大きな音楽の流れの中で、音楽を自然な形でまとめ上げる。「ピアノ協奏曲第2番」では、生き生きとしたタッチで潤いに満ちたサウンドを生み出していた。リズムにやや硬さが感じられたのは残念。
(10月19日・スタインウェイ)

【ピョートル・アレクセヴィチ Piotr Alexewicz(ポーランド)】透き通るような叙情性と作曲家の若いエネルギー
《幻想ポロネーズ》の冒頭では、余剰な感情をぬぐい去り、音そのものを立ち昇らせていく。主部に入っても、強い推進力を漲らせ、しなやかに音楽を作り上げた。後半の嬰ト短調の部分における独白のような表現に、作曲家の心の叫びを聴く思いがする。終盤の勇壮で輝きに満ちた音の世界は、かつてのギャリック・オールソンの演奏を彷彿とさせた。
彼が奏でる「ピアノ協奏曲第2番」には、どこかスラヴの香りが漂う。重みを帯びた音でメロディを自在に歌い上げていくが、タッチはすぐれて鋭敏で、クリアーな音楽を聴かせてくれる。透き通るような叙情性とともに、作曲家の若いエネルギーも感じられた。
(10月19日・カワイ)

【ケヴィン・チェン Kevin Chen(カナダ)】ショパンらしい気高さ
コンクールを通して安定したテクニックを披瀝したケヴィン・チェン。《幻想ポロネーズ》冒頭をゆっくりと奏でていく。大げさに表現するのではなく、丸みを帯びた美しい音で、作品のあるがままの姿を鍵盤に映していくような演奏であった。
「ピアノ協奏曲第1番」でも、滑らかな音で音の一つひとつを丁寧に紡ぎ出し、優美な情趣を醸し出す。ショパンらしい気高さを感じさせた。
(10月20日・スタインウェイ)

【ダヴィッド・フリクリ David Khrikuli(ジョージア)】透き通るようなリリシズム
《幻想ポロネーズ》の冒頭には、とくに遅く弾く指示などは書かれていないが、彼は一貫して速めのテンポで弾いていた。彼の演奏は、この作品のひとつの解釈であると思うが、時折、こまやかな音が聞こえてこなかったのは残念。
「ピアノ協奏曲第2番」でも、大きくテンポを変えることはなく、それが流麗さを醸し出す。また、繊細な息遣いを通してニュアンス豊かな音楽を生み出した。全体的に、透き通るようなリリシズムに満ち溢れていた。
(10月20日・スタインウェイ)

【桑原志織】品格を感じさせるショパン
桑原は、第1ステージから安定したパフォーマンスで、聴衆を魅了してきた。《幻想ポロネーズ》では、やや硬さが見られた点は惜しまれるものの、ペダルを抑制しきめ細やかな質感の音を生み出し、夢想的な雰囲気を漂わせていく。低音部のあたたかくまろやかな響きは、包み込むような平安に満ちていた。
「ピアノ協奏曲第1番」では、デリケートなタッチの変化や卓越したペダリングなどを駆使し、深い詩情をたたえた演奏を披露。桑原らしい品格を感じさせるショパンであった。
(10月20日・スタインウェイ)

第19回ショパン国際ピアノコンクールを聴き終えて
私は、2021年のショパン・コンクールを配信で視聴し、コンクールでのコンテスタントの演奏を月刊誌に紹介した。今回、初めてこのコンクールをフィルハーモニーホールで聴き、会場の響きの豊かさが体感できた。とくに、微細な音の遠近や響きの混濁は絶妙で、その場で演奏を聴くことに勝るものはないと実感した。しかし、日本からはるか離れたポーランドへ足を運ぶのは容易なことではない。その点で、配信は有効な手段である。
かつてないハイレヴェルの演奏が繰り広げられるなか、たとえば、マズルカやノクターンにおけるメロディやリズム、ペダリングについて、多くのことを考えさせられた。楽譜に記された音の細やかな抑揚を無視した表現や、音楽の流れに逆らうような作為的なリズムなど、ショパンの作曲意志から離れた自由なパフォーマンスも見られ、改めて原典とはなにかを考えさせられた。
そつのない演奏が多い一方、楽譜に忠実な表現に徹したパフォーマンスもあった。たしかに、ホールや楽器、時間の流れなど、ショパンが生きていたころとは大きく異なっている。だからこそ、ショパン国際ピリオド楽器コンクールの果たす役割も注目されるところである。
このコンクールでは、作曲家と心を重ね合わせ、自らの思考や深い思索を通して作品の素顔にどこまで迫ることができるかが問われる。その意味では、もっともハードルの高い試練の場であると言える。
関連する記事
-
インタビューワルシャワ・フィルのファゴット奏者がショパンコンクールを振り返る
-
インタビューワルシャワ・フィルのファゴット奏者がショパンコンクールを振り返る
-
インタビューワルシャワ・フィルのコンマスがショパンコンクールを振り返る
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest