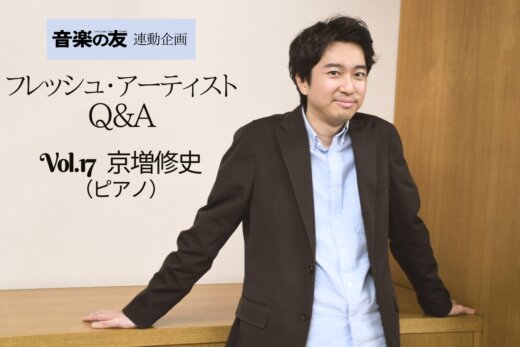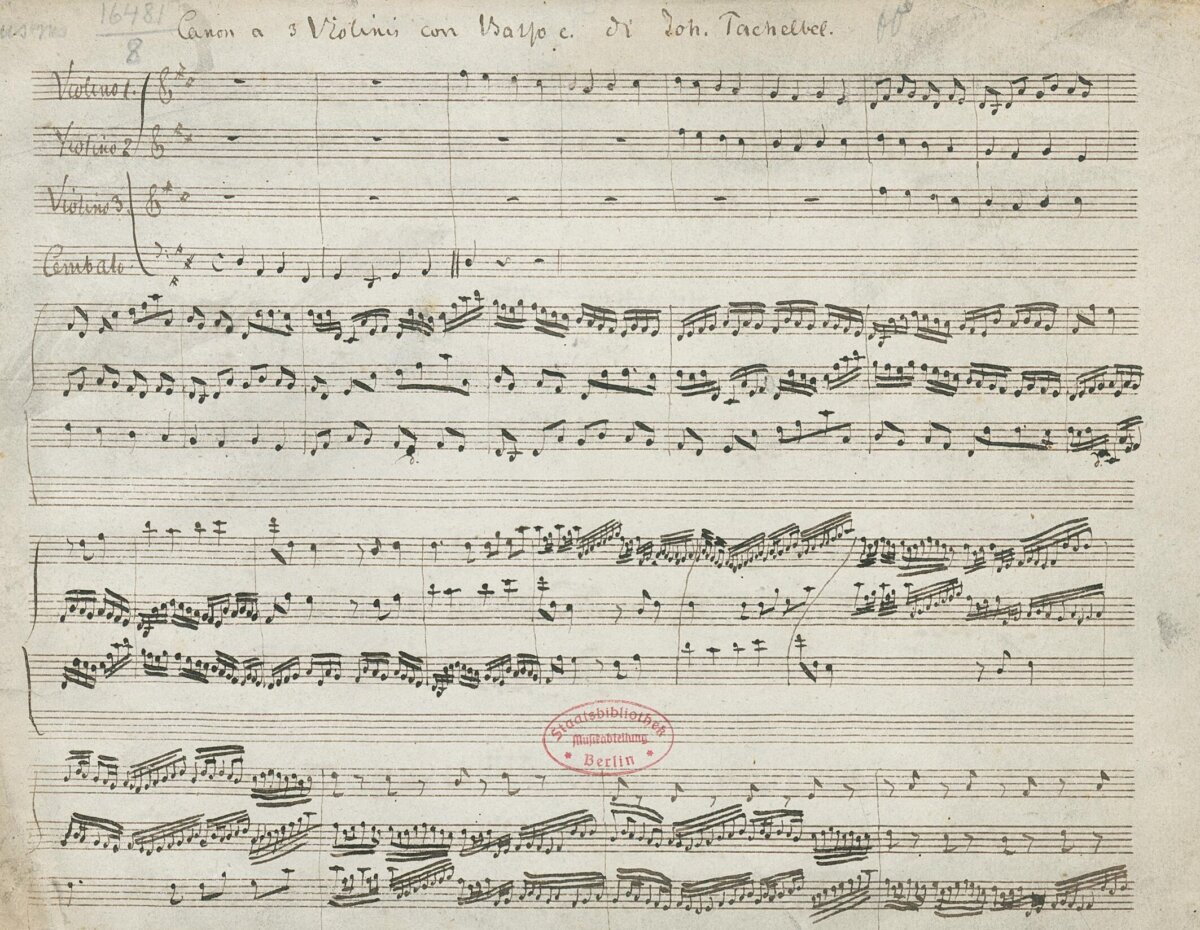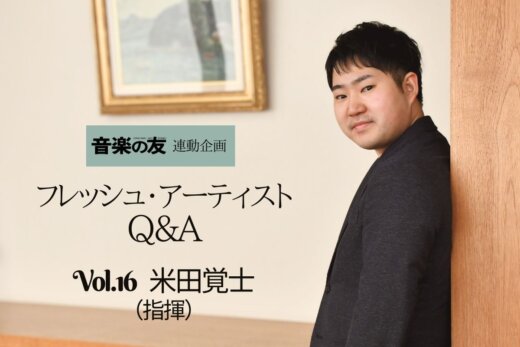【音楽が「起る」生活】新国立劇場《ナターシャ》と、松本での《夏の夜の夢》

音楽評論家の堀内修さんが、毎月「何かが起りそう」なオペラ・コンサートを予想し、翌月にそこで「何が起ったのか」を報告していく連載。8月は、新国立劇場における細川俊夫《ナターシャ》世界初演、セイジ・オザワ松本フェスティバルで沖澤のどかが指揮するブリテン《夏の夜の夢》を予想。7月の結果報告は、ノット指揮スイス・ロマンド管、カンブルラン指揮読売日響第684回名曲シリーズ、東京二期会《イオランタ/くるみ割り人形》です。

東京生まれ。『音楽の友』誌『レコード芸術』誌にニュースや演奏会の評を書き始めたのは1975年だった。以後音楽評論家として活動し、新聞や雑誌に記事を書くほか、テレビやF...
何かが起りそう(8月のオペラ・コンサート予想)
1.新国立劇場《ナターシャ》(8/11、13、15、17・新国立劇場オペラパレス)



大野和士時代の新国立劇場屈指の、重要な上演がある。多和田葉子が台本を書き、細川俊夫が作曲した新作《ナターシャ》の世界初演だ。夏休みまっただ中の上演で、新国立劇場の音楽祭みたいだがそうではなく、2024/25シーズンの掉尾を飾る上演となる。
指揮するのはもちろん新国立劇場のオペラ芸術監督・大野和士で、これまでウィーンの《魔弾の射手》などを手がけてきた若い演出家クリスティアン・レートが演出する。環境破壊をテーマにしたオペラで、ウクライナから逃れてきたナターシャと、世界をさまよっている青年アラトが「メフィストの孫」に案内されて「現代の地獄」をめぐる、というストーリーが伝えられている。日本語、ドイツ語、ウクライナ語などによる多言語オペラというのも特徴になる。
新作なので上演されてみないとわからないわけだが、新しいオペラ、それも大いに期待できる新作が生まれるのに立ちあえるのはめったにない機会ではないだろうか。
2.セイジ・オザワ松本フェスティバル ブリテン《夏の夜の夢》(8/17、20、24・まつもと市民芸術館 主ホール)

夏は音楽祭の季節だ。2025年のセイジ・オザワ松本フェスティバルでは、《フィガロの結婚》以来3年間途絶えていたオペラ上演が今年復活する。ブリテンの《夏の夜の夢》を指揮するのはこの音楽祭の首席客演指揮者、沖澤のどかで、日本でもこの音楽祭の《子供と魔法》などいくつもの作を手がけているロラン・ペリーが演出する。
歌手たちも、スター級を集めるというより、個性豊かな人物たちにふさわしい人材を選んでいるのは明らかで、ブリテンのオペラの、完成度の高い上演が期待できるのではないだろうか。シェイクスピアの原作をブリテンがいかにきれいにオペラ化したか、きっとわかる。このオペラのこれは!という上演はこれまで日本ではお目にかかれなかった。今度こそ本当の「夏の夜の夢」にひたれるかもしれない。
何が起ったのか(7月のオペラ・コンサートで)
1.スイス・ロマンド管弦楽団(ジョナサン・ノット指揮)(7/8・ミューザ川崎シンフォニーホール)⇒⇒⇒音楽とはこんなに運動するものだったのか
縦横無尽に走り回り、踊り回る。音楽ってこんなに運動するものだったっけ? 最初はオネゲルの「交響的運動」だから、素直に楽しめるのだけれど、次のショスタコーヴィチ、チェロ協奏曲でも、驚くべき活力で推進すると驚いてしまう。初めて聴くチェリスト、上野通明の精密無比な演奏とオーケストラが競い合うのも、何とか付いていくように聴くほかない。そして後半の《ペトルーシュカ》でパワーが全開になる。ノットとスイス・ロマンドは、音楽の運動能力を発揮して、聴く者をも走らせた。聴くための準備運動が必要なほど活気あふれるコンサートだった。
2.読売日本交響楽団(カンブルラン指揮)第684回名曲シリーズ(7/15・サントリーホール)⇒⇒⇒軽やかさと真逆の狂熱
活力いっぱいのスイス・ロマンドのあとなのだから、カンブルランの指揮する軽快なバーンスタインやガーシュウィンを楽しもう、なんて思ったのが大まちがいだった。《キャンディード》の序曲も、バルトークの「ルーマニア民俗舞曲」も、軽やかな踊りの音楽ではなかった。暑い夏をいっそう暑くするような熱気で満たそうとする、狂熱が待っていた。
リーズ・ドゥ・ラ・サールがピアノを弾いたガーシュウィンだって、軽やかさとはほど遠い。カンブルランはいま、足取り軽い音楽とは反対の方向に走っている。ムソルグスキー(ラヴェル編曲)の組曲《展覧会の絵》は、力のこもった、熱もこもった、堂々たる演奏だった。
3.《イオランタ/くるみ割り人形》東京二期会、パスカル指揮、デ・ベア演出、梶田真未/川越未晴(S)他、東京シティ・バレエ団(7/18・東京文化会館)⇒⇒⇒2作品が合わさり本物のハッピーエンドに
イオランタが目覚めようと決意すると、夢の、つまり《くるみ割り人形》の連中が「アラビアの踊り」の沈んだ音楽とともに退場していく。ここはゾクゾクするような、洗練された演奏、そして洗練された場面だった。パスカル指揮の演奏は、デ・ベアの構想した新しい《イオランタ》と《くるみ割り人形》を合体させたチャイコフスキーの世界を息づかせた。
イオランタを歌った梶田真未の歌も声のまろやかさを失わず、パスカルの指揮にもぴったり合って、洗練されていた。これなら愛するものを見出し、奇妙で奇怪で混とんとした《くるみ割り人形》の少女時代に別れを告げようと決めたイオランタを、心から祝福したくなる。本物のハッピーエンドが実現した。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest