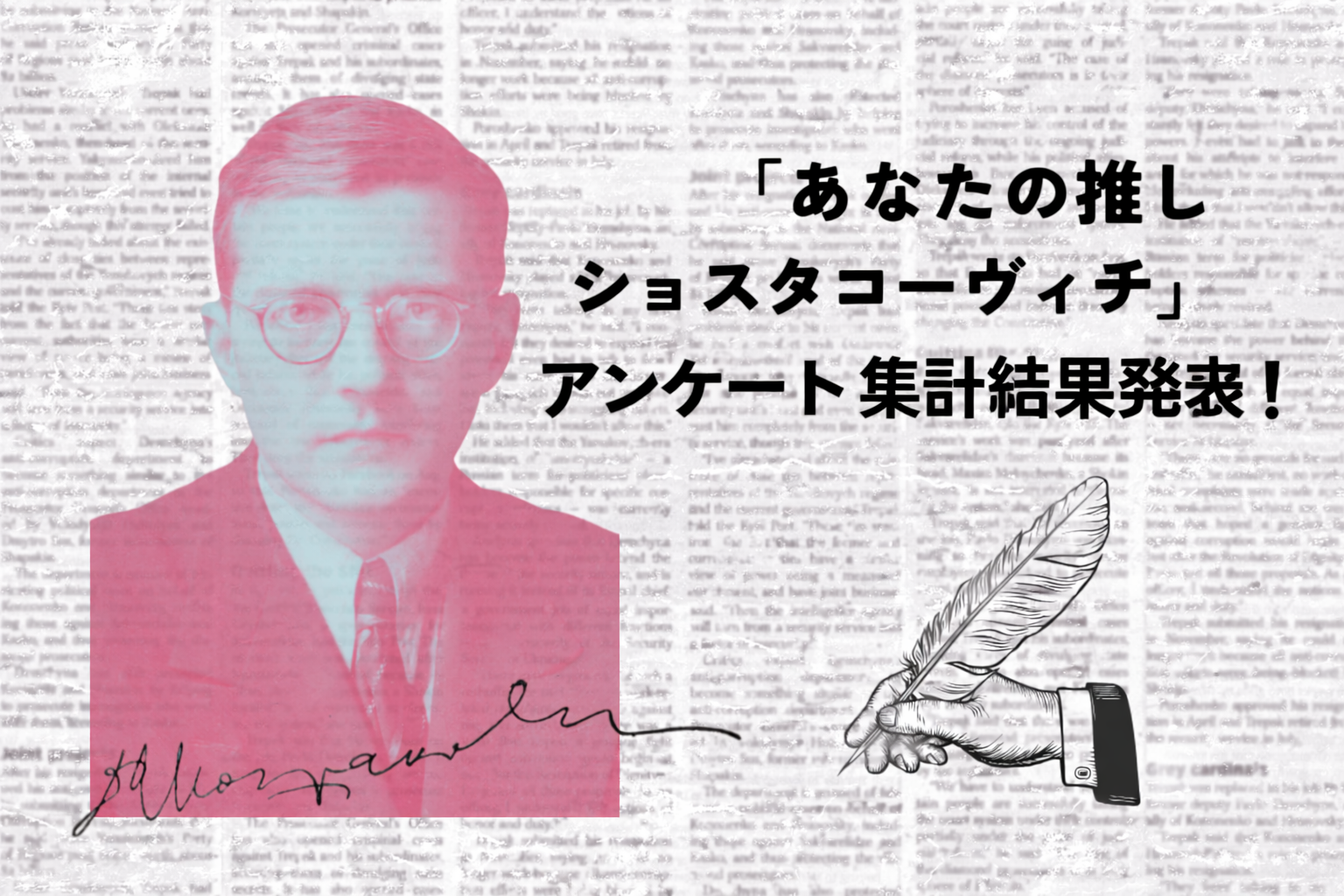ホルスト《惑星》~人間の運命を司る星々が、時代の不安を映し出す

クラシック音楽評論家の鈴木淳史さんが、誰でも一度は聴いたことがあるクラシック名曲を毎月1曲とりあげ、美しい旋律の裏にひそむ戦慄の歴史をひもときます。
宇宙時代のイメージとマッチした《惑星》
英国の作曲家って、音楽そのものはどちらかといえば穏健な姿のまま耳に入ってくるのだけれど、その音楽には含みが多いというか、なかには過激なほどの思想が入っているものもあって、よくよく聴いてみると、この人ってどこかぶっ飛んでおるよなと思わざるを得ないタイプが少なくない。
グスターヴ・ホルストもその1人といっていいだろう。《セントポール組曲》や《サマセット狂詩曲》といったオーケストラ曲、合唱や吹奏楽作品なども多少は知られているものの、やはりホルストといえば、組曲《惑星》だ。

作曲が始まったのは1914年。まず初めに〈火星〉から〈天王星〉までピアノ・デュオのための編成で、オルガン用に〈海王星〉が書かれた。1917年には管弦楽化が行なわれている。第一次世界大戦のさなかに作られた曲だといっていい。
1918年の初演以来、英国、そしてアメリカでは盛んに取り上げられた。1920年の全曲による初演(コーツ指揮ロンドン交響楽団)から3年後には初録音(作曲家指揮ロンドン交響楽団)も行なわれている。また、ボールトは生涯に5種類の録音を残すなど、この曲の普及に一役買った。
《惑星》をメジャーにしたのは、やはり1961年のカラヤン指揮ウィーン・フィルの演奏だろうか。この曲をアングロサクソンの文化圏から抜け出させた象徴的な録音だ。引き続き、マゼールやメータ、小澤征爾、ショルティといった指揮者も次々にこの曲を録音。ほぼ同時期に書かれたストラヴィンスキーの《春の祭典》と肩を並べるほどに知られる20世紀の管弦楽作品となった。
これらのレコードのジャケットには、天体が描かれるなど、宇宙空間を想起させるものがほとんどだった。人類が月に着陸するなど、宇宙時代が到来していたのだ。この《惑星》もそんな時代にふさわしいスペクタクルな音楽というイメージで演奏され、聴かれるようになっていったように思われる。
《惑星》のテーマは占星術?
しかし、この曲は決して、そんなリアルな宇宙をテーマにした作品ではなかった。そもそもホルストがこの曲を構想したのは、シェーンベルクの《5つの管弦楽曲》に触発されたからだった。その管弦楽の新しい響きに魅せられたのだろう。
シェーンベルク《5つの管弦楽曲》(トラック4~8)
ということもあって、当初は《7つの管弦楽曲》という極めてストイックなタイトルを考えていたらしい。だが、そんなふうに収まらぬのがホルストだ。占星術に強い関心があったホルストは、人間の運命を司る星を連ねることで、1つの組曲を作りあげた。そこには、第一次世界大戦を前にした不安感やオカルティズムが濃厚に表れることになった。
時代の不安感と神秘主義の影響
インドの神秘主義に影響を受けたという〈火星―戦争をもたらす者〉のオスティナートは、間近に迫る恐怖を感じさせる。以降、緩徐楽章風の穏やかな〈金星―平和をもたらす者〉、軽やかなスケルツォ楽章に相当するであろう〈水星―翼のある使者〉を経て、〈木星―快楽をもたらす者〉で一つのサイクルを作る。この曲の中間部にあたるホ長調の旋律は、聖歌に転用され、のちにラグビーワールドカップのテーマ曲やさまざまなポピュラーにアレンジされて親しまれることにもなった。
〈火星―戦争をもたらす者〉
〈金星―平和をもたらす者〉
〈水星―翼のある使者〉
〈木星―快楽をもたらす者〉
その次の〈土星―老いをもたらす者〉は、組曲のなかでもっとも重苦しく、作曲家自身がもっとも強いメッセージを込めた曲だ。〈天王星―魔術師〉は諧謔度の高いスケルツォ。そして、終曲は〈海王星―神秘主義者〉だ。静かに、ヴォカリーズで歌われる女声合唱で消えるように終わる。
〈土星―老いをもたらす者〉
〈天王星―魔術師〉
〈海王星―神秘主義者〉
もっとも人気を博したのは華々しい〈木星〉だが、ホルスト自身はこの曲で終わるような曲順で演奏することは認めなかったといわれている。シンプルで円満なハッピーエンド、つまりヨーロッパ的な解決を嫌ったのだ。やはり、最後は謎めいたように消えて行く、神秘主義による解決(というか消散)でなければと。なかなか危険なヤツじゃないか。
《惑星》を雑誌に喩えるならば、『天文ガイド』や『Newton』ではなく、『ムー』なのである。CDジャケットも、いっそ『ムー』っぽくしてもらいたい!
ホルストの音楽に潜む危険さを引き出した映像作品
この《惑星》がもつメッセージ性を雄弁に引き出した映像がある。映画監督のケン・ラッセルが、オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団による演奏とコラボレーションした映像作品だ。
ニュース用のフィルムなど多様な素材を中心にコラージュのように組み合わせる。英国人らしいドライな感覚で、ときにシニカルかつコミカルに、作曲家が《惑星》に込めた意味を懇切丁寧に視覚化してくれるのだ。
〈火星〉では、リーフェンシュタールによるナチスの映像、冷戦下のソ連やアメリカの軍事パレードの映像などが、まるでホルストがこの映像のために作曲したかのように構成される。〈木星〉は、長崎のおくんちも登場、世界の祭りを通して人々の悦びを描く。それに続く〈土星〉は儚さと死がテーマだ。廃車の山が映された後、大量の新車が船舶で運ばれるシーンは、その音楽と相まってゾッとするような美しさをもたらす。
〈天王星〉は、スターリンや毛沢東と並んでローマ法王といったカリスマが揶揄的に登場。魔術的ともいえる世界の奇妙な光景と組み合わされる。ぴりりと効いた風刺が音楽とばっちりシンクロ。驚異的なわかりやすさで、ホルストの音楽のなかに潜む危険さを存分に引き出してくれる。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest