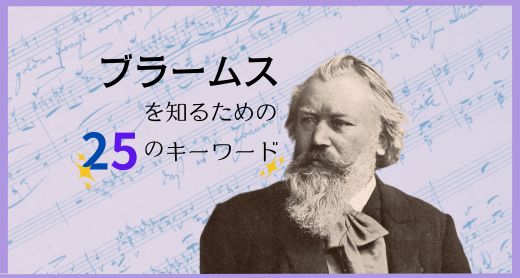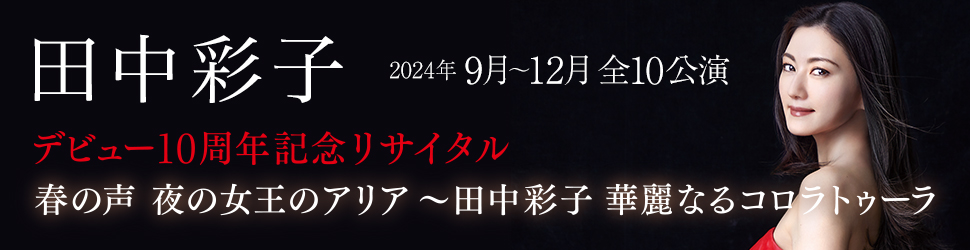ハイドン《十字架上のキリストの最後の7つの言葉》~気品ある作曲家に潜む毒

クラシック音楽評論家の鈴木淳史さんが、誰でも一度は聴いたことがあるクラシック名曲を毎月1曲とりあげ、美しい旋律の裏にひそむ戦慄の歴史をひもときます。
今では誰も驚かない「びっくり交響曲」
原作や映画にきちんと目を通していないので題材にするのはどうかと思われるけど、「テレビから出てくる貞子」のシーンは、確かにインパクトがあった。突拍子もない怪奇性が生々しかった。もう20年以上も前のことになる。
そういったシーンを何度も目にしたりするうちに、次第にそれはパロディにもなった。一人歩きを始めた「テレビから出てくる貞子」は、今では恰好のネタになっているかのようだ。もう何年か経てば、このシーンを見た人がみんなゲラゲラ笑い出す、といったことが当たり前になってくるようにさえ思われる。
《驚愕》という標題をもち、びっくり交響曲などといった愛称もあるハイドンの交響曲第94番も、「テレビから出てくる貞子」と同じ運命をたどったのではないかと思うことがある。

《驚愕》なる標題は、この交響曲の第2楽章に由来する。アンダンテの緩徐楽章だ。穏やかな主題が静かに2回繰り返されたあと、同じ旋律の終和音がフォルティッシモのトゥッティ(※)で鳴らされる。居眠りする聴衆に不意打ちを食らわせて驚かすという趣向である。
※トゥッティ:演奏に参加しているすべての奏者が同時に奏すること
当時は、さぞかし驚いた人もいただろう。しかし、現在のオーケストラが、どんなにがんばって大きな音を出しても、その「驚き」の効果はまったくない。
だいたい、このエピソードは有名すぎるし、最初から《驚愕》などというタイトルが付けられて演奏されているわけで、サプライズもへったくれもない。
さらに、マーラーだの、ストラヴィンスキーだのといった、より強烈な音響を日常的に聴かされることの多い聴衆にとっては、「昔はのんびりしてたのだなあ」とか「ハイドンってユーモアがあったよね」ぐらいにしか思ってもらえないのではないか。
次第に貞子から受ける恐怖感が薄れていったように、驚愕のインパクトも風前の灯、というかもう「ほほえましいエピソード」でしかない。
なかには、独自の方法を用いることで、マジモンで驚かしにかかる演奏家もいないわけではない。たとえば、ミンコフスキがグルノーブル・ルーヴル宮音楽隊を振った演奏は、近年もっとも成功した一つといえるだろう。
ハイドン:交響曲第94番《驚愕》第2楽章(マルク・ミンコフスキ指揮グルノーブル・ルーヴル宮音楽隊)
この演奏をヘッドフォンで大音量で聴いたときは、うわっと飛び上がりそうになった。やりやがったなハイドン! と生まれて初めて思った。ハイドンのアイディアをミンコフスキが現代人向けに蘇らせたのだ。
静けさの中の不穏が積み重なったとき
ハイドンには、こうした風変わりなアイディアを盛り込んだ交響曲がいくつかある。演奏者が次々に退場していく第45番《告別》や、調子外れの音高で演奏し、途中で調弦するという第60番《うかつ者》だ。
古典派のぴしっとした規範のなかにおけるちょっとした逸脱が、まったくかわいらしい。品がある人がやるからこそ映える、さりげないジョークみたいな。
こうやってみてみると、ハイドンという作曲家は、じつに安心・安全。だからこそ、ジョーク的なアイディアが入っても気品を失わない。ハイドン作品に危ないところがあったらさぞかし面白かろうと、見切り発車で書いてみたけど、ちょっと先行きが心配になった。ボツ原稿か。つい、「わが神よ、なぜ私を見捨てられたのですか」といった言葉が口を突いた。
そうだ。《十字架上のキリストの最後の7つの言葉》があった。
福音書のなかのキリストが十字架上で発した7つの言葉を読み、瞑想するための礼拝用に書かれたという作品だ。オリジナルは管弦楽版、ほかにも弦楽四重奏版、オラトリオ版、クラヴィーア独奏版もある。
ハイドン《十字架上のキリストの最後の7つの言葉》(弦楽四重奏版)
序奏で始まり、7つの言葉に相当する7つのソナタが続き、最後はキリストの復活を表わす「地震」で締めくくられる。序奏と7つのソナタはラルゴやアダージョ、レントなど、すべて緩徐楽章。ゆっくりとしたテンポの音楽をこれだけ並べる作品も珍しい。ハイドンにとっても唯一の作品なのでないだろうか。
美しい音楽が続く。感情を抑えた、静かな時間が流れ、ときおり柔らかに日が差すような作品だ。ただ、その静けさのなかに、どこか禍々しさが潜んでいて、それが曲が進むにつれてどんどんと沈殿していく。
つねに品のいいハイドン作品から、生々しさを感じ取ることはあま
いや、気品があるからこそ、そこにはごく微量の毒が含まれているの
ただし、最後の「地震」はどうも拍子抜けする。これまでのしめやかな音楽から一転して、動きの多いプレストに切り替わることで、キリストの復活という劇的な役割を負っている部分だ。しかし、地震国に住んでいる住民にとっては、いかにもチャチく感ぜられ、ドリフのコントの最後で家のセットが倒れるくらいの衝撃ぐらいしかないのは残念。いつか、ミンコフスキの《驚愕》に匹敵するアイディアを開陳する演奏に出会いたいものである。
さまざまなバージョンが楽しめる作品だが、もっとも毒があるのは弦楽四重奏版でないかと思う。
関連する記事
-
イベントP.ヤルヴィ&ドイツ・カンマーフィル “交響曲の飛躍”を現代最上の名演で聴く
-
読みもの近づくと火傷する、スクリャービン晩年のピアノ曲
-
読みもの氷のように美しいレコード盤から立ち上る、オラフソンの温かなピアノの音色
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest