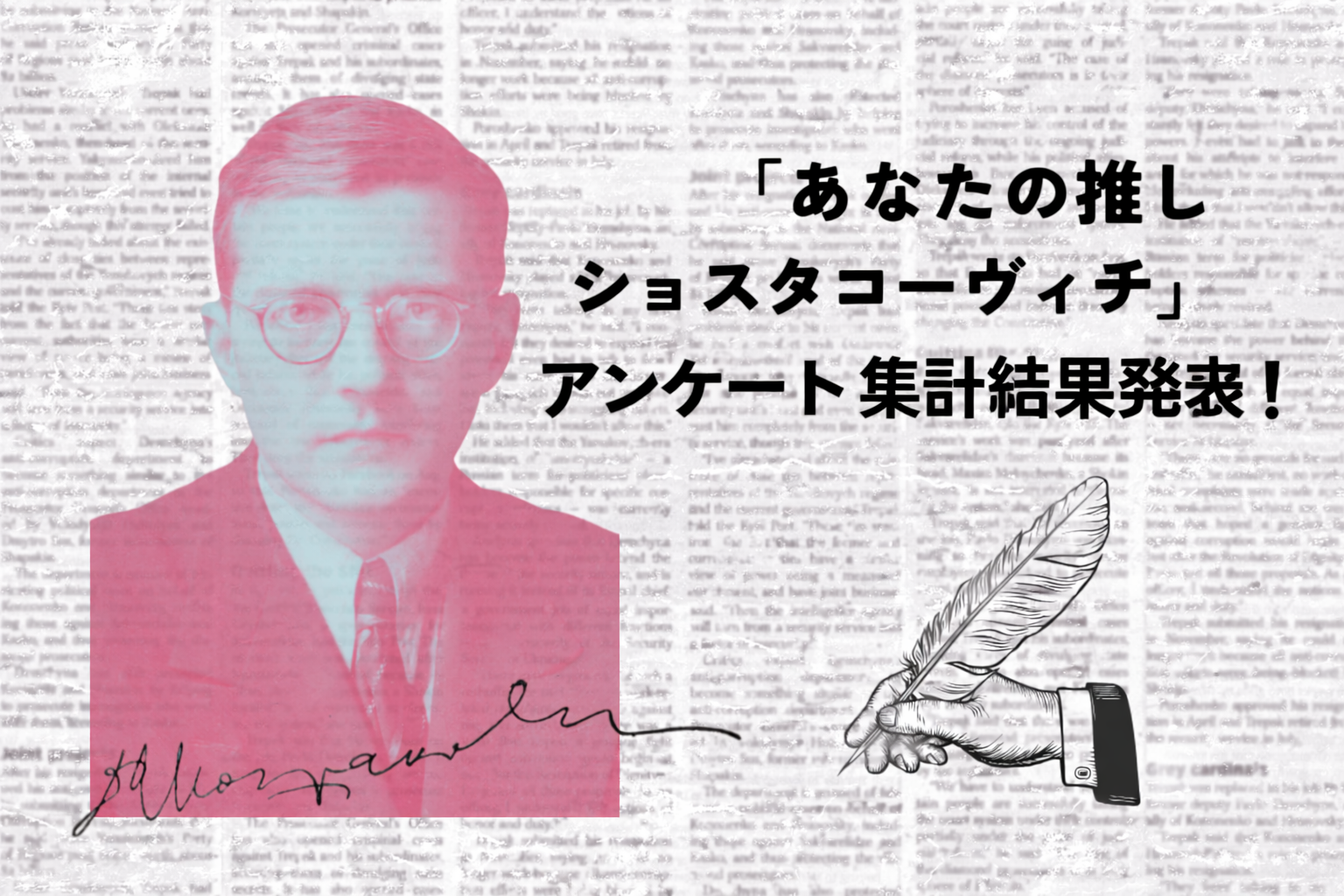
ショスタコーヴィチ「交響曲第5番」~仮面を被った音楽が心を徐々に侵食していく

クラシック音楽評論家の鈴木淳史さんが、誰でも一度は聴いたことがあるクラシック名曲を毎月1曲とりあげ、美しい旋律の裏にひそむ戦慄の歴史をひもときます。
子どものときは、しつけや教育と称し、理不尽なことを大人たちから要求されたものである。なんかおかしいなと直観的に感じつつも、それについて考え、反証するための語彙もない。なけなしのロジックで反論すりゃ、屁理屈だなどとぬかして逃げられる。あとから考えれば、自分のほうが正しかったのかと思うことのほうが少なくないが、そうした鬱憤は知らず知らずに積み重なっていく。
逃げ道は色々ある。「そんな大人の言うことなんて皆目くだらねえぜ」と早々とブレイクすること。あるいは、「たとえ理不尽でも、それに従っていたほうがベネフィットが得られるんじゃね?」とせっせと損得勘定に磨きをかけること。わたしは、そうした極端な思考ができなかった。せいぜい、猛禽がうろつく場所や羊の群れから離れ、岩陰に隠れて本を読むくらいの解決策しか見出せなかったのだ。
そんな鬱積が積もりに積もった、十五の夜(十六の昼だったかも?)。ラジオから流れてきた音楽に耳が吸い寄せられた。ショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲第3番。その妙に屈折しまくった旋律が、じつに身に沁みた。こういう音楽があるのなら、人生も捨てたもんじゃないとさえ思った。
ショスタコーヴィチ「弦楽四重奏曲第3番」(トラック1~5)
スターリン圧政下ゆえの創作意欲
ショスタコーヴィチは、スターリンの圧政の下をくぐり抜けた作曲家として知られている。この時代のソヴィエト、とりわけ大粛清期には1年間で70万人以上の人が死刑判決を受けるという惨状で、それは政治だけでなく、文化にも災厄をもたらした。
かの国家が唱える芸術は、社会主義リアリズムだ。芸術は労働者のため、国のために奉仕しなければならず、音楽の場合は民謡調の旋律を華やかに管弦楽で鳴らす、みたいな毒にも薬にもならないものが推奨された。
20世紀の音楽の可能性がぐんと広がった時期、こうしたアタマがおかしくなりそうな文化政策の下で、ショスタコーヴィチは創作活動を行なっていたのだった。
それでも彼はしたたかだった。その許される表現領域のギリギリを攻めつつも、交響曲などでは、音名にメッセージを託し暗号のように忍ばせたり、前衛的手法とレーニンを讃える合唱を組み合わせた。その一方、毒にも薬にもならないカンタータや映画音楽も手がけた。
いかに当局に目を付けられないように苦心しつつ、そこに自分の表現を盛り込むか。そんな綱渡りが彼の創作意欲に火を付けた、ギリギリを攻めることでアドレナリンがガバガバと湧き出す、そういう一面もあったと思われる。こんなふうにして書かれた作品が、危なくないわけはない。
もしも、と思うのだ。ショスタコーヴィチが国家に早々に見切りをつけてアメリカあたりに亡命したら。緊張状態からすっぽり抜けて、ハリウッドの寵児となって、それこそ毒にも薬にもならない音楽ばかり書いたのではないか。

関連する記事
-
レポートあなたの“推しショスタコーヴィチ”は? アンケート集計結果を発表します!
-
レポート角野隼人、デュトワ、ゲルギエフらが名を連ねる北京の音楽風景
-
読みもの「君もショスタコだ」井上道義が語る、“ねじれ”と“共感”の音楽論
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest


















