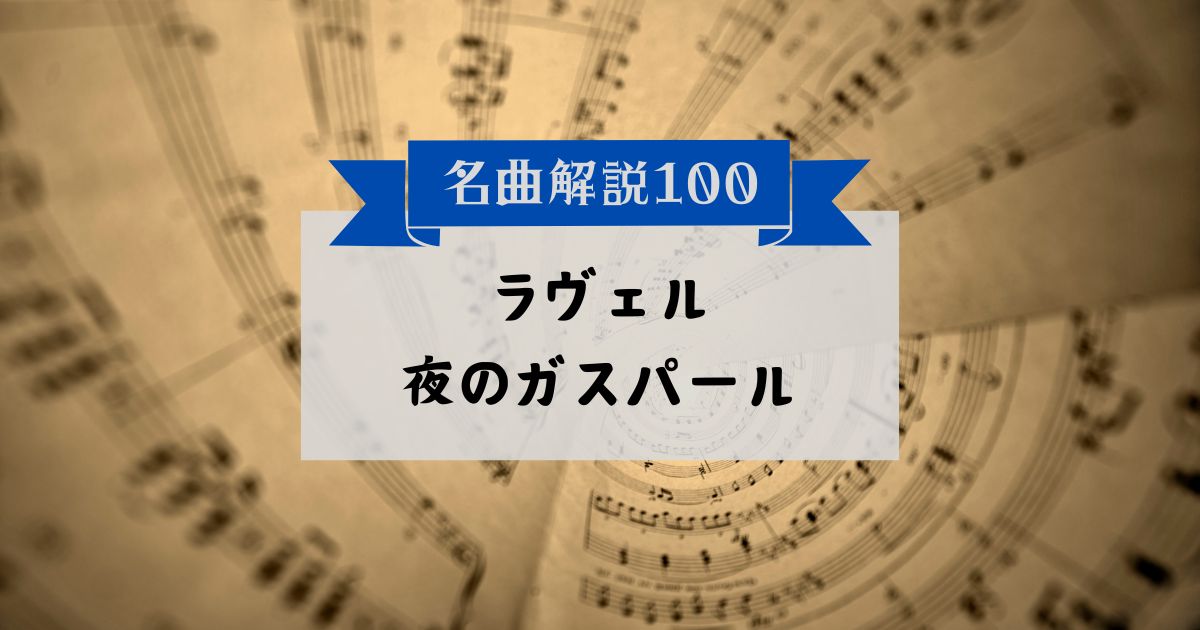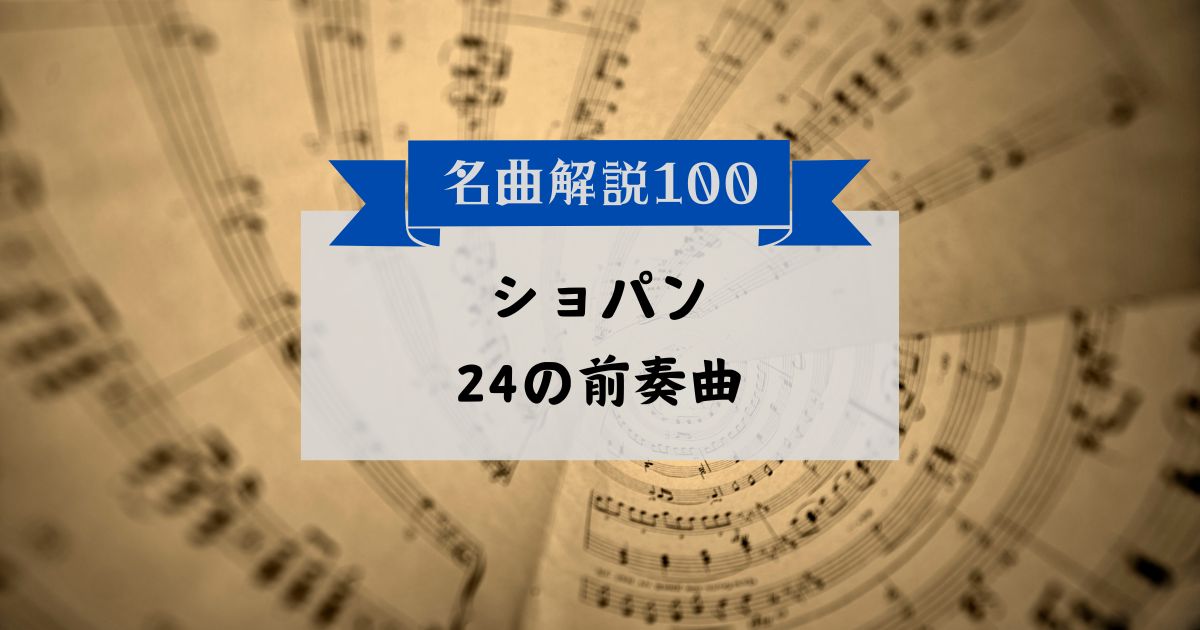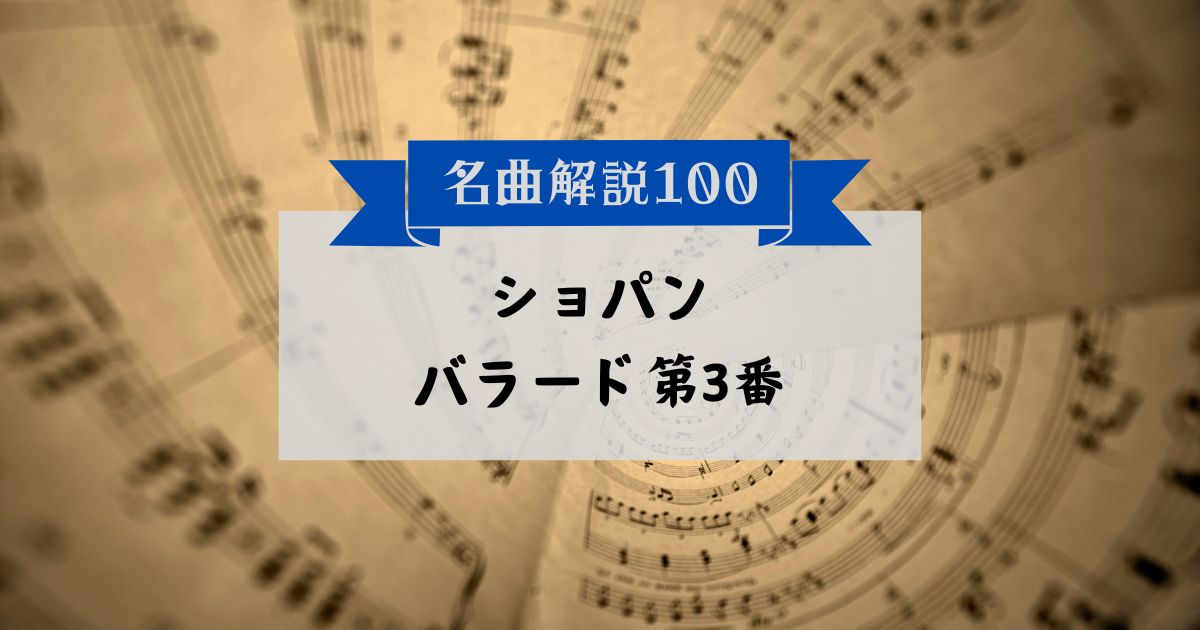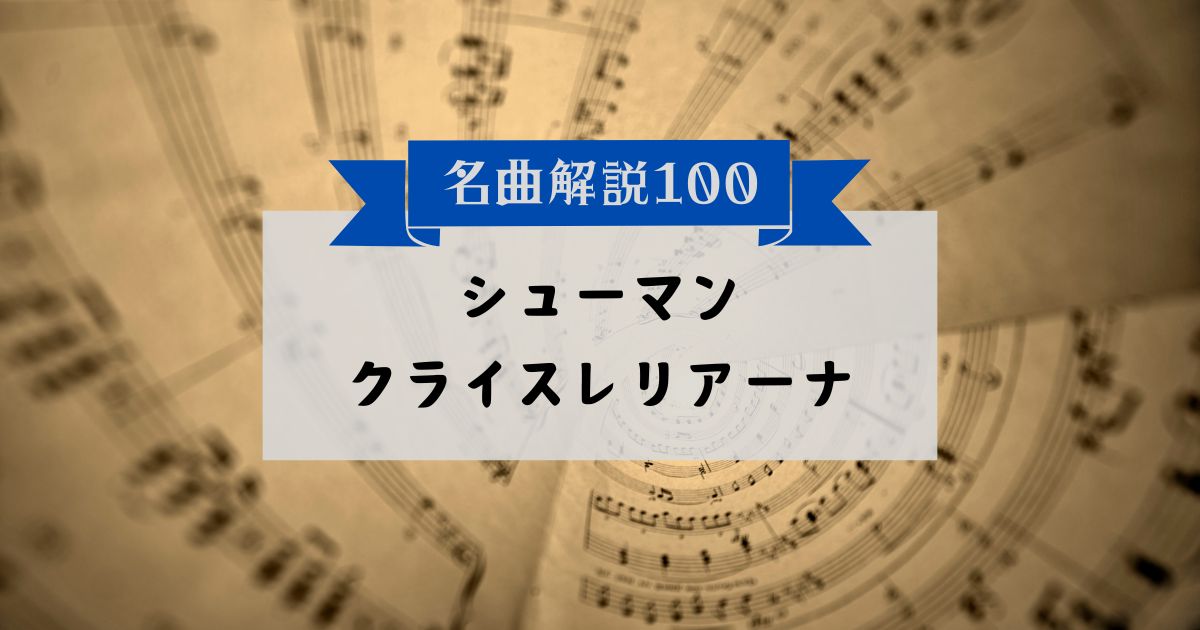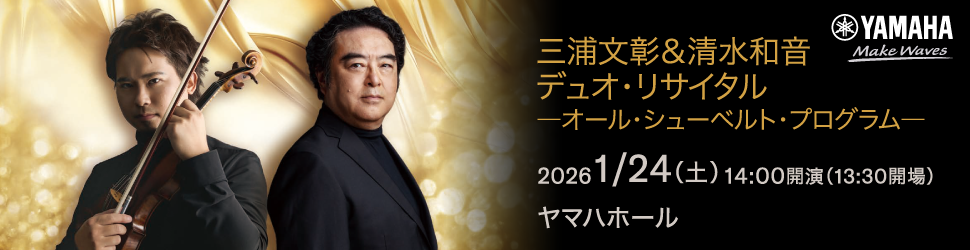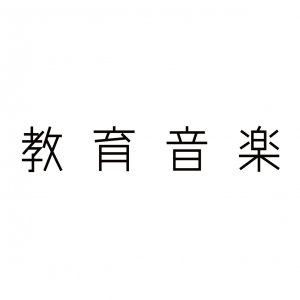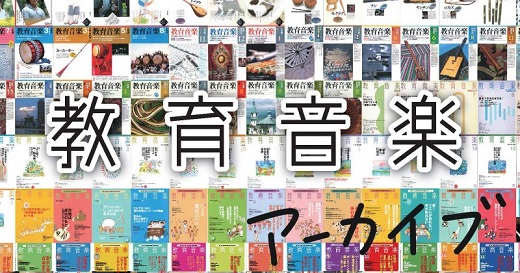動画で学ぼう!日本の歌のうたいかた#10(最終回)「日本の歌の正しいうたいかた」とは?

小、中、高校の音楽の授業で習う日本の歌を、児童生徒が動画で学習できるようにしたWeb教材の連載。日本語の美しい発声と発音を身につけましょう。音楽の先生はもちろん、大人の趣味やデイケアなどでも広くご活用ください。最終回は、この連載における教材動画の共同開発者である、上野学園短期大学教授の細谷美直先生にインタビューを行ないました。細谷先生は長年、日本歌曲の演奏研究をされ、教育にあたってきました。日本歌曲の価値と現在抱える課題を知ることで、日本の歌を子どもたちが学ぶ意義を考えていきましょう。
日本の歌の歴史〜西洋音楽受容から童謡誕生までの歩み
——西洋音楽様式による日本の歌の歴史は、明治期より始まりましたね。
細谷 日本語は古語から変遷がありましたが、日本人が本来持っている感性(独自の感覚など)が歌に表れていると思っています。日本の歌は、西洋のリートやオペラとは異なり、雅楽の朗詠や今様など、ふしに乗せて語るような歌です。このように日本には豊かな歌の文化がありました。
明治期に西洋音楽を受容した際に、当然、日本には西洋の歌がなかったわけです。当時は西洋に追いつけの時代にあって、それはコンプレックスであったのです。最初はスコットランド民謡や讃美歌に日本語の歌詞をつけて替え歌のように唱歌をつくり、子どもたちに学ばせようとしました。

東京藝術大学卒業。同大学院修了。在学時より各地で第九、メサイア、モーツァルトやフォーレのレクイエム等のソリストとして活躍する。新星日響、群響をはじめ多くのオーケストラとも共演。オペラでは《椿姫》フローラ、《こうもり》アデーレ、《カルメン》ミカエラ、国民文化祭千葉では創作オペラ《ミナモ》のタイトルロールで出演。
第18回日本演奏連盟新人オーディション、同年東京文化会館新人オーディションに合格。ソレイユ新人オーディションにおいて最優秀新人賞受賞。
これまでに畑中良輔、加宮 葵、ハンス・ホッターの各氏に師事する。
2000年2月20日 東京文化会館小ホールにて『畑中良輔の世界』、2001年10月23日同ホールにて『三善 晃の世界』リサイタルを開催する。
日本クラシックコンクール、Jr.クラシックコンクール他審査員。上野学園短期大学教授、声楽主任。日本音楽療法学会認定音楽療法士。
——最初は、替え歌である翻訳唱歌から始まり、道徳などを教え込むための手段とされましたね。明治43年になって、国が邦人の作詞者、作曲者による唱歌の創出に乗り出し、現在、小学校の共通歌唱教材として歌い継がれている文部省唱歌が生まれました。
細谷 やがて日本人がもっている感性や感情を表わす作品をつくっていこうという機運が高まっていき、大正期に童謡運動が起こります。道徳教育の手段のような稚拙な歌ではなく、北原白秋や三木露風、西條八十といった詩人、作曲家では成田為三、弘田龍太郎が率先して取り組み、芸術性が高い詩や曲が生まれました。
童謡雑誌『赤い鳥』に最初に掲載された楽譜が《かなりや》です。たいへん音楽的な歌で、そこには日本人の生活や文化、日本人がもつ特性が言葉や音楽に生かされています。こうした曲がたくさんつくられました。
日本歌曲の課題とは? 言葉と発音の壁
——日本の歌が抱える課題にはどのようなものがありますか?
細谷 日本の歌が広まらない大きな理由に、言葉の問題があります。文語と口語であったものが今は口語に統一されています。現代仮名遣い(五十音のこと)になって簡素化されたのですが、これによって複雑な母音や子音が表せなくなりました。母音は、あ、い、う、え、おの5つに大きく分類されてしまいました。私たちが自然に発音している言葉にも、さまざまな、あ、い、う、え、お、が存在するのですが、それが伝えきれない。
ヨーロッパの音楽大学では、たとえばドイツであれば、母国語であるドイツ語の舞台語の発音、発声のテクニックを学ぶカリキュラムがあります。日本の音楽大学では、母国語である日本語の舞台語の授業がありません。
——日本の音楽大学で日本歌曲における舞台語の授業がないとは驚きです。
細谷 たとえば「行く」という歌詞に対して、私たちはていねいに発音すると「いゅく」となります。表記するとすれば、YUKUと表せます。
「う」という母音においても、無声的な「う」、あいまいな「う」、深い「う」(うみはひろいなおおきいな)があります。こうした母音一つとっても整理され、系統的に教えることができない状況なのです。
私が学生のときにも、そのような授業はありませんでした。ドイツ・リートもフランスのメロディも、イタリアのベルカント唱法も語学とともにその発音と発声を学ぶのです。しかし日本の音楽大学では、個人のレッスンで日本歌曲を学ぶことがあっても、この場合はこのように発音する、というように系統的に日本語の舞台語を学ぶことができないのです。
——発音とともに発声の問題があると思います。日本歌曲の演奏では、何をうたっているのか分からない演奏が多く、山田耕筰の時代からその問題があったと聞いております。
細谷 ご自身が声楽家でもあった山田耕筰は、当時からその問題を指摘していました。山田だけでなく、西洋式の発声で日本語の歌詞をうたってしまうため、何をうたっているのか分からないという指摘は多くありました。
——なるほど。團 伊久磨は、自作の合唱曲を初演する際、一般大学の合唱サークルに依頼したと述べています。プロの合唱団に頼むと西洋式発声のため、歌詞が伝わらないという理由です。
細谷 日本の歌曲もそうですが、合唱にもその課題があります。先ほど例に挙げた「行く」ですが、合唱においてもYUKUをIKUと発音することに違和感をもたない人が多くなってきています。それは教育されていないため当然です。文語体の歌詞の発音を考えるべきという演奏者や作曲家もいれば、現代だからそれでよいとする方もいます。そうした状況の中で、残念ながら歌にのった詩が聞き取りにくい演奏が多い現実があります。
日本の歌と日本語の美しさを次世代へつなぐために
——この連載「動画で学ぼう!日本の歌のうたいかた」の教材動画は、小学校、中学校、高校の子どもたちが日本語の発音、発声を感覚的に学習することができるものです。
細谷 日本語の場合、1音符1音節になります。そうなると子音にも音符がつく可能性もあり、その処理の仕方に工夫が必要です。
今回の教材動画の収録に際しては、詩を語っているような表現になっています。子どもたちも大人たち、先生方もそれが自然な日本語であると感じられる、言葉が見えるかのような演奏をねらいました。
小学校1年生では、すべてひらがなです。中学生でしたらいろいろな感情や感性が豊かになり、心身が成長してきます。発達段階に応じて日本語の自然な発音、発声を子どもが感じ取り、表現できるように工夫しました。日本語として、詩として伝わるようにしたのです。
——これを使って授業された学校の校長先生から、“日本の歌は好き”と子どもたちが言うのですよ、というお話をいただきました。
細谷 それはほんとうにありがたいですね。日本語の美しさについては、小さな子どもであれ、大人であれ、共感できると思います。さまざまなものが西洋化されましたが、日本人のもつ言葉への音感覚を、歌を通して伝えていくことは私の願いです。私たち声楽家は、それを伝えていく立場にあります。

——冒頭に雅楽のうたい方について触れられていましたが、このうたい方の伝統は、西洋様式の音楽と融合することで変化はあったのでしょうか?
細谷 やはりありますね。リズム感や歌いまわしが異なりますし、西洋音楽様式のポルタメントと日本のポルタメントは異なるのです。
平安時代に、今様の歌い方が後白河法皇の『梁塵秘抄口伝集』に書かれています。「只一息に、聲(こえ)のたすけなく、さらさらと常のこと葉をいふ如く謡ふべし」。現代の言葉に訳すと、声を張らずに、言葉を語るようにうたうということです。
私はこの考え方を取り入れて日本歌曲の演奏表現を考えています。でも面白いことに、声を張ることなく語るようにうたうのは、バロック時代のベルカント唱法とも共通するのです。
私たちは西洋音楽様式の中でも、自然と日本的なものを表そうとします。そうした表現を幼い子どもたちも感じ取れるし、年齢を重ねて大人になったときに感じ取る力も豊かになるのではないでしょうか。
——そうしてみると、日本語の美しさを感じ取るという視点で開発した、この連載の教材動画の意義は大きいですね。最後にこれからの日本の歌のあり方についてどのようにお考えでしょうか?
細谷 J‐POPなどのように、踊りと融合した歌も現代の人々に受け入れられ、意味があるのです。その一方で、唱歌から始まり、童謡、日本歌曲に描かれている日本人の心情を歌い継ぐことは大切だと思っております。
文語は平安時代に生まれ、明治期までの長い歴史をもちます。文語の歌詞の言葉の響きの美しさを伝えている唱歌や童謡、日本歌曲をうたうことで、我々は言語文化を継承するのです。
また唱歌や童謡、日本歌曲は、曲が生まれた時代背景と関連しています。歌を通して、その時代の自然や社会、文化、人々の思いを理解することができるのです。
こうした価値をもつ日本の歌に、これからも取り組んでいきたいと考えています。
この連載の教材動画は、日本の歌が世代を超えた共有財産になることを願って開発しました。日本の歌における日本語の美しさが受け継がれるよう学校教育をはじめ、さまざまな場面で活用していただければ幸いです。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest