
今なぜ日本語のオペラか?

言葉が軽視される現代社会において、「日本語オペラ」の創造は喫緊の課題といえるのではないでしょうか。ONTOMOエディトリアル・アドバイザーの林田直樹さんが、自国語オペラの可能性を紐解きつつ、昭和音楽大学の試みをご紹介します。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...
自分たちの言語によるオペラを作るということ
言葉を愛し、言葉と格闘することは、音を愛し、音と格闘することと、何ら変わりない。
言葉がきらめくライヴな場が演劇であり、音楽がきらめくライヴな場がコンサートであるとすれば、その両方が結びついて稀有な輝きを示すのがオペラである。
17世紀以降のヨーロッパにおけるオペラとは、その両方が一致して力を発揮する、舞台芸術とエンターテインメントの最高峰であった。
オペラ史をひもとけば、作曲家たちは、オペラの発祥とされるイタリア語のみならず、自分たちの言語によるオペラを作ることに熱心であった。
モーツァルトの《魔笛》やウェーバーの《魔弾の射手》が出現したことが、ドイツ文化にとって、どれほど大きな意味をもっていたか?
チェコ語でスメタナやドヴォルザークやヤナーチェクがオペラを作曲したことが、チェコという国のアイデンティティと独立性にとって、どれほど重要だったか?
ガーシュウィンが英語以外の言語で《ポーギーとベス》を作曲することなど、考えられるだろうか?
では日本語のオペラは?
人々に愛されているか? 求められているか?
作曲家たちは、日本語のオペラを書きたいと望んでいるだろうか?
團伊玖磨・作曲、木下順二・台本の《夕鶴》(1952年初演)以降、繰り返し上演される日本語のオペラのスタンダードは生まれているだろうか?

あるとき、日本オペラ界の最長老の演出家・栗山昌良さんが嘆息とともにこう言っておられたのが忘れられない。
「いまほど、言葉が衰弱している時代はないよ」
この「言葉の衰弱」ということは、音楽の衰弱につながりかねない深い問題である。
いまほどSNSでもマスコミでも社会全般でも、言葉が軽視されている時代はない。
言葉がきらめきを取り戻すことは、音楽の問題でもある。
日本語を大切にしてきた音楽界の先人たち
これまで日本の音楽界の偉大な先人たちは、みな日本語を大切にしてきた。
指揮者の若杉弘(1935-2009)にせよ、歌手界のゴッドファーザーで音楽評論家の畑中良輔(1922-2012)にせよ、どれほど日本語のオペラということに心を砕いてきたか、計り知れないものがあった。
日本語のオペラで、世界に通用する名作を作り出すことは、長年音楽界の悲願でもあった。遠藤周作原作の「沈黙」(松村禎三作曲)、泉鏡花原作の「天守物語」(水野修孝作曲)、三島由紀夫原作の「鹿鳴館」(池辺晋一郎作曲)など、文学における名作をもとにオペラを作る取り組みも多かった。
すべて、作曲家が日本語と格闘し、音楽とドラマと一致させるために苦心に苦心を重ねた末の産物である。
この、日本語というシロモノがなかなかにやっかいで、技術的にオペラの世界とはなかなか親和しづらい。黛敏郎や細川俊夫のように外国語でオペラを書くことによって日本的美学を実現したケースさえあるのだ。
想像してみて欲しい。もし、三島由紀夫のあの華麗な文体が、そのまま音楽になったら、どんなに素晴らしくなるだろう!
だがそれはあまりにも難しい。
ひとつには台本作家の問題もある。
文学を音楽と一致させるのは、台本作家の仕事である。
モーツァルトにとってのロレンツォ・ダ・ポンテ、リヒャルト・シュトラウスにとってのホフマンスタール。
そういった存在が、日本語オペラの世界にも必要である。
日本のクラシック音楽界は、「輸入過多」という問題を常に抱えてきた。
外国の良質なものを輸入し、模倣し、消費することには熱心だが、それを消化したのちに、自分たちの言葉や音楽によって、新しく創造することにおいては、遅れをとってきた。
世界に通用し、過去も現代も未来も貫いて、深い音楽的真実に到達しうる日本語オペラを新しく創造することは、日本の音楽界の抱える根源的課題といっても過言ではない。
昭和音楽大学の「日本のオペラを作る」試み
いま、新しい試みが昭和音楽大学で始まろうとしているので、最後にそれをご紹介したい。「日本のオペラ作品をつくる~オペラ創作人材育成事業」(文化庁委託事業・平成30年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業)がそれである。
40歳前後までの作曲家と台本作家の枠に募集がかかっているが、これは専門家のおこなうワークショップによって3年をかけて日本語によるオペラ作品を創作していこうというものである。
沖縄を題材にしたオペラの創作で実績のある作曲家・中村透を中心に、オペラやミュージカルの演出助手として現場経験の豊富な演出家・齊藤理恵子(劇団青年座)、日本語のオペラ作品を上演する使命を担ってきた日本オペラ協会の総監督で声楽家の郡愛子の3名がファシリテータとなり、詩人や指揮者をゲスト講師に招く予定。実践面では最強の布陣が、作曲家と台本作家志望者をサポートする。




書類選考を経て決定した受講者には、
実は、母国語によるオペラという問題、韓国では先進的な成功例がある。2012年に開始された「世宗(セジョン)カメラータ」というプロジェクトによって、アジアにおけるオペラ創作の現場を強力に支援する体制がとられているのだ。
その立案者である作曲家の李建鏞(イ・ゴニョン)が今回アドバイザーに招かれている。
オペラという普遍的な手段によって、自国の文化を母国語とともに世界に発信できるようになることは、アジア共通のテーマでもあるのだ。
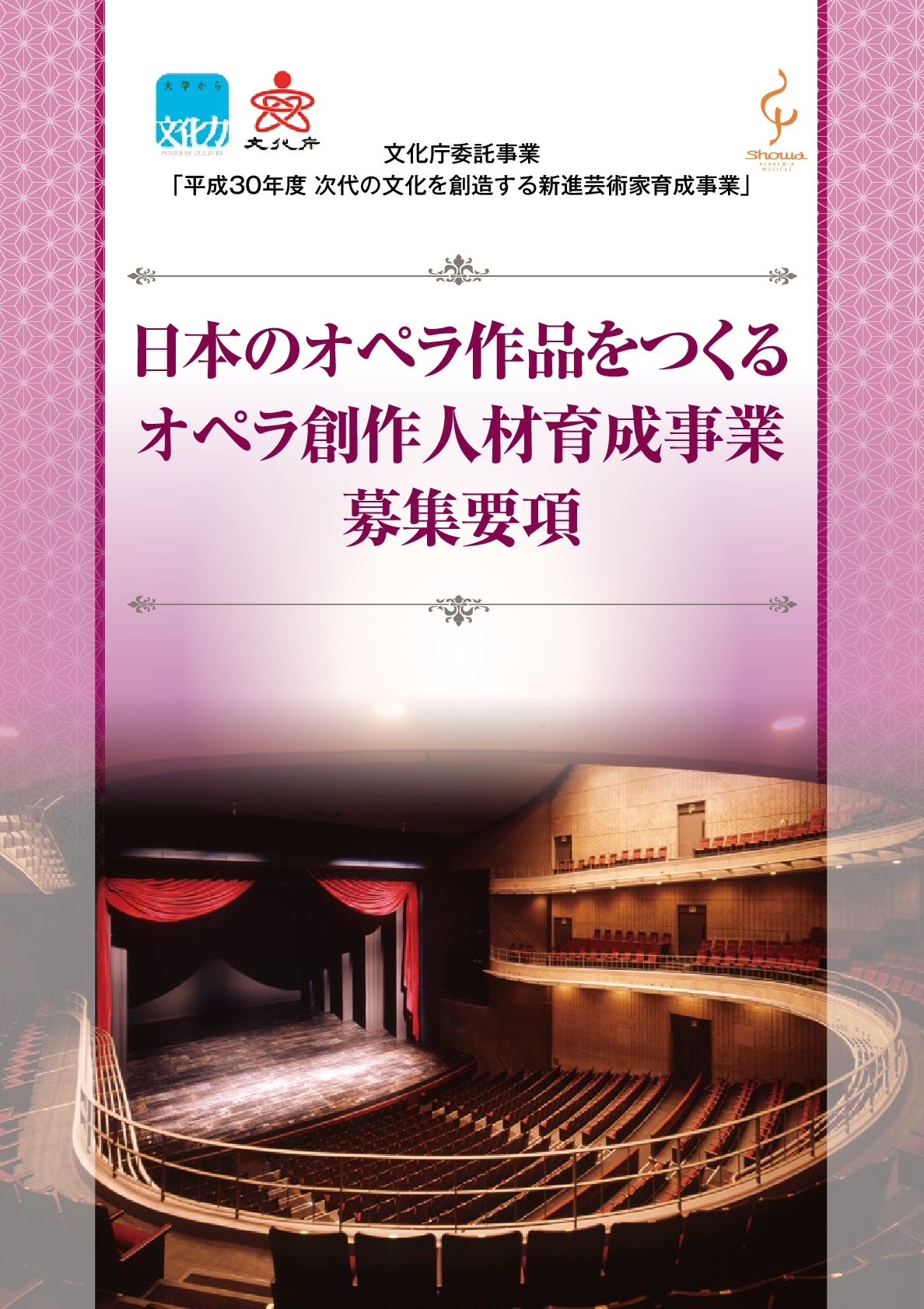
応募資格:
①作曲家
40歳前後まで
声楽作品、あるいはオペラに近い作品を創作した経験がある人材が望ましい。
②台本作家
40歳前後まで
舞台芸術に興味がある作家等の人材、オペラ台本の舞台化に意欲のある人材が望ましい。
③その他
ワークショップ全日程に参加ができること(日本語によるワークショップ)
ワークショップ日程や応募方法などの詳細については、募集要項にてご確認ください。
問い合わせ先: 昭和音楽大学演奏センター オペラ創作人材育成事業係り
Tel.044-953-9865
(平日10:00〜18:00、土日祝日および平日の12:00〜13:00を除く)
shinshin@tosei-showa-music.ac.jp
関連する記事
-
インタビュー当代最高のバリトン、レオ・ヌッチが最後の来日~83歳、輝く美声で得意のヴェルディ...
-
読みものいま聴きたいテノール ルチアーノ・ガンチの珠玉のイタリアン・プログラムを浴びたい...
-
インタビュー阪 哲朗が紡ぐ、喪失感を浄化するコルンゴルトの歌劇『死の都』の音楽世界
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest













