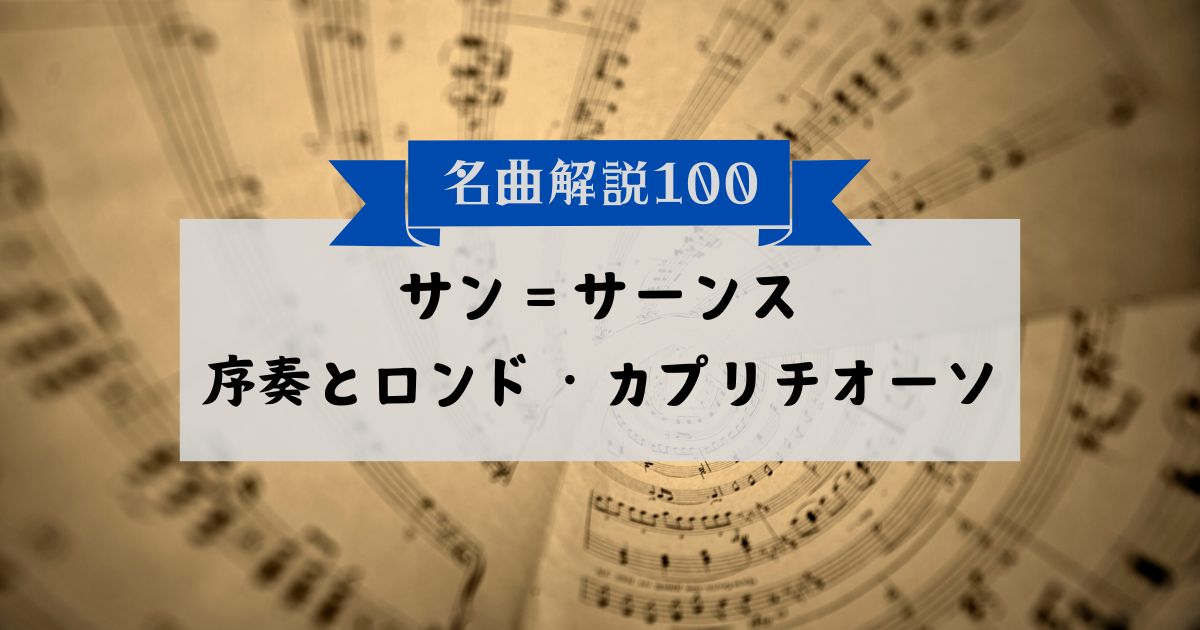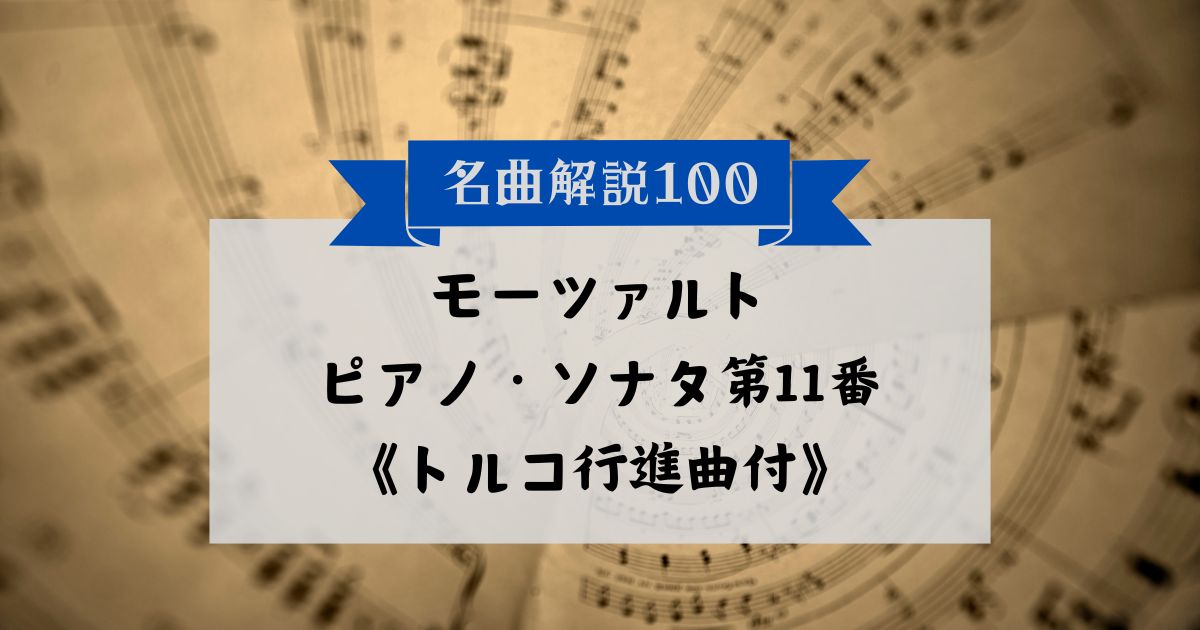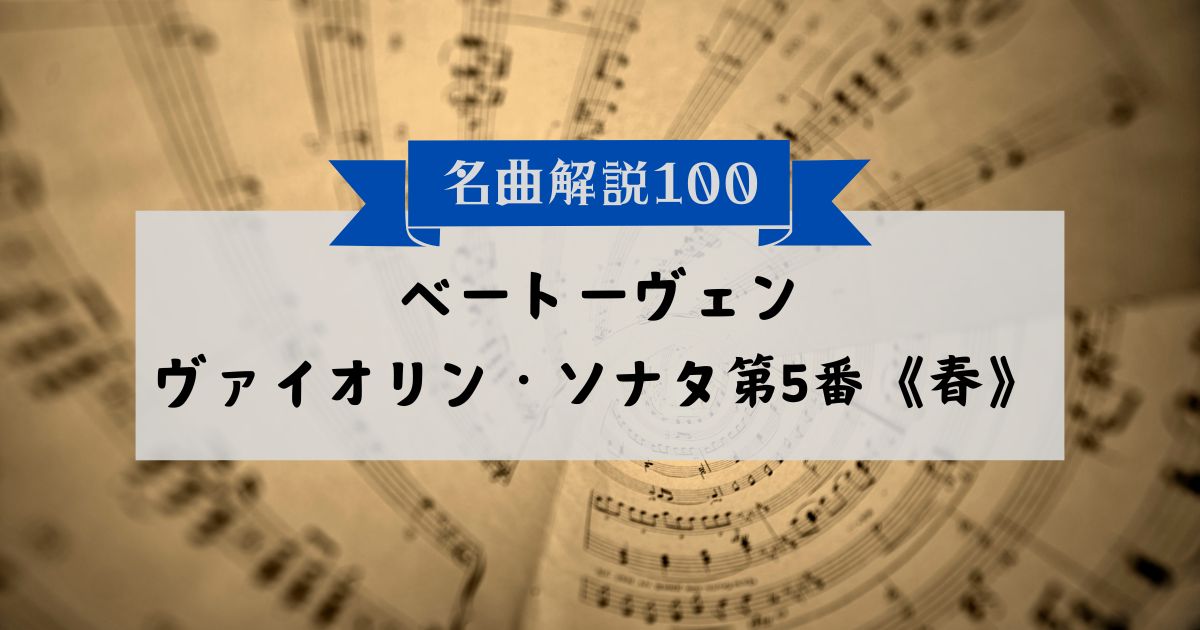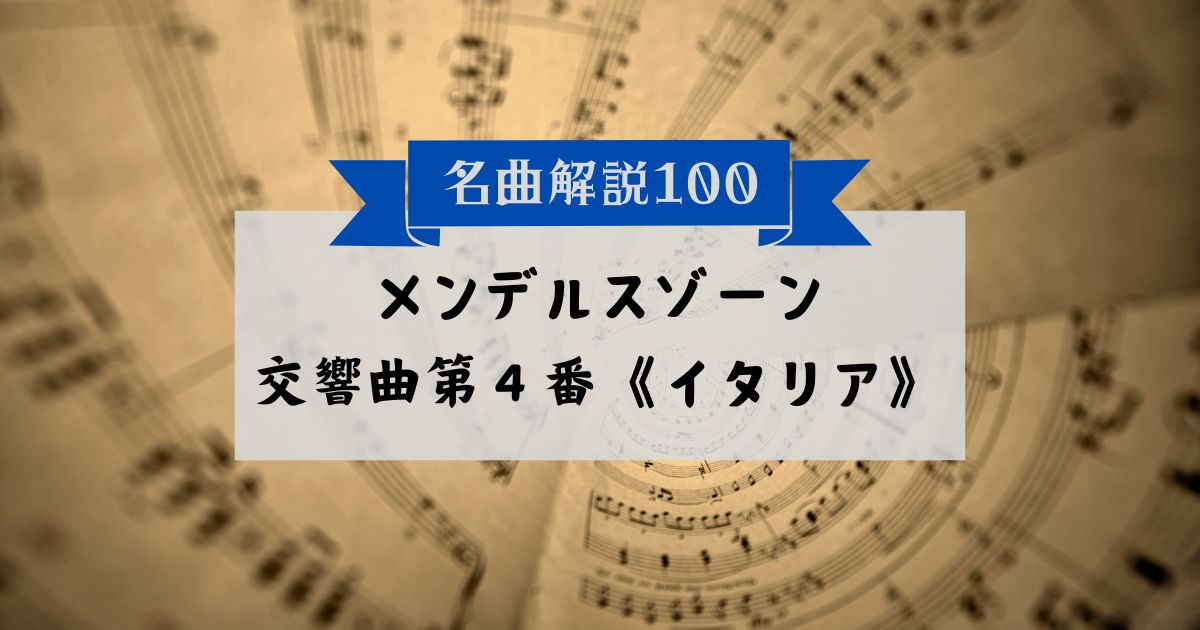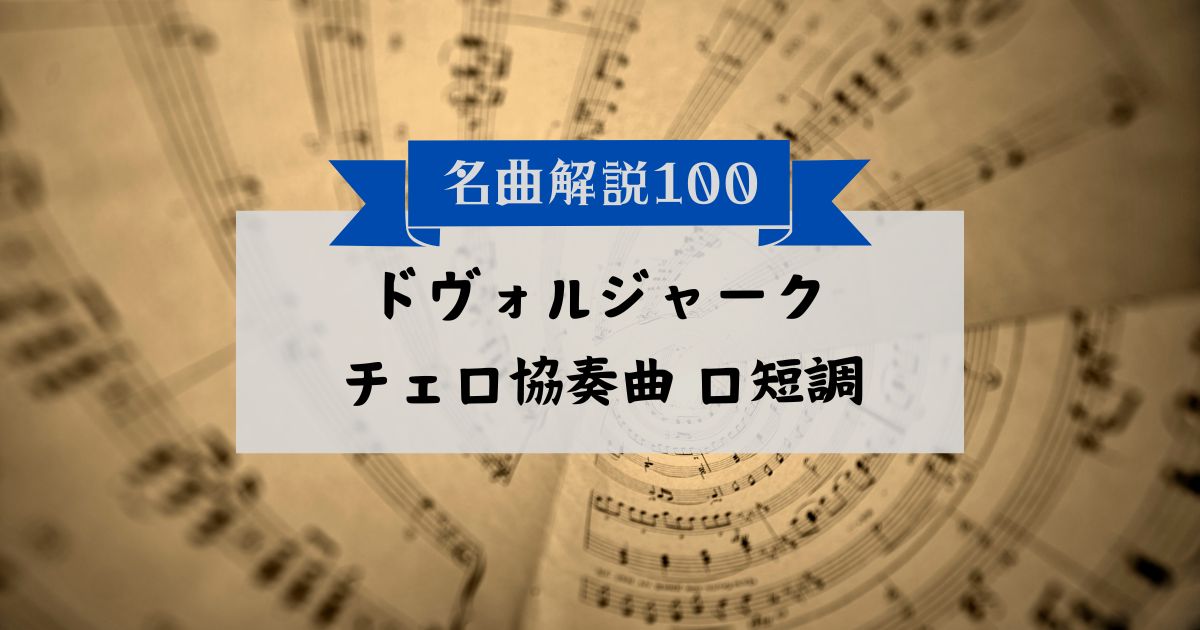
読みもの
2025.03.28
名曲解説100
30秒でわかるラヴェル:《ボレロ》
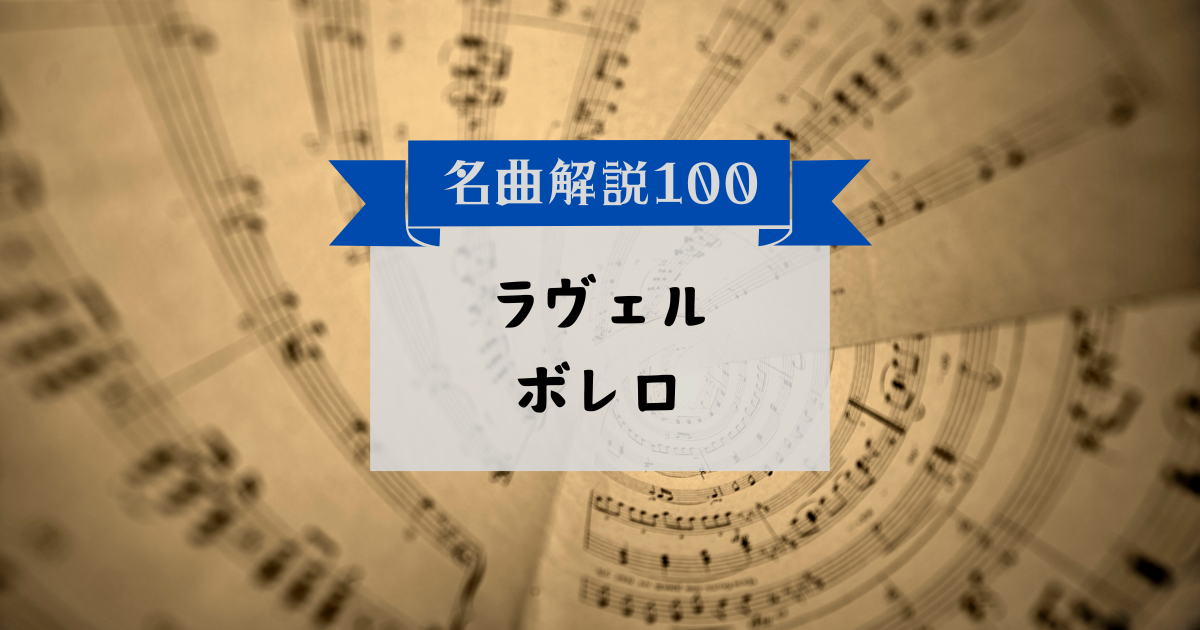
ラヴェル:《ボレロ》について30秒で丸わかり♪
研ぎ澄まされた知性と鋭敏な感性で新しい響きの世界を追求したフランスの作曲家モーリス・ラヴェル(1875~1937)の作品の中でも、舞踏家イダ・ルビンシテインの依頼によって書かれた《ボレロ》は、きわめて異色の作といえるものです。
延々と繰り返される小太鼓のボレロ(スペインの舞踏の一種)の執拗なリズムの上で、対となったたった2つの対照的な主題が、旋律自体は何の変化も施されることなくただ反復されていくのですが、そのたびごとに、オーケストレーションを巧みに変化させ、しかも全体にわたって大きなクレッシェンドを築いていくことで、響きの色彩と雰囲気を次々と変えていくというユニークな構成になっています。いっけん単調な繰り返しが鮮やかな色調の変転を生み出していくところに、ラヴェルの魔術的な手法があるといえるでしょう。
そしてクライマックスで、それまでのパターンを崩し、思いがけない転調とともにここに至るまでに膨れ上がってきたエネルギーを一挙に解放して閉じられます。
ラヴェル:《ボレロ》
作曲年: 1928年
演奏時間: 約15分
編成: ピッコロ、フルート2(第2はピッコロ持替)、オーボエ2(第2はオーボエダモーレ持替)、イングリッシュホルン1、クラリネット2、小クラリネット1、バスクラリネット1、ファゴット2、コントラファゴット1、サクソフォーン3(ソプラニーノ、ソプラノ、テノール)、ホルン4、トランペット3、小トランペット1、トロンボーン3、テューバ1、ハープ1、ティンパニ、大太鼓、小太鼓2、シンバル、タムタム、チェレスタ、弦5部
関連記事

バレエダンサー上野水香が語る《ボレロ》の魅力「自分が“音楽の化身”になる」
名曲解説100
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest

イベント
2026.02.05
石田泰尚さんが横浜みなとみらいホールプロデューサー“ラストイヤー”への意気込みを...

読みもの
2026.02.05
スカラ座より熱い!? ミラノ五輪はサン・シーロから始まる

インタビュー
2026.02.05
ケヴィン・ケナーが語るショパン演奏「音楽はアイデアではなく、体験である」

読みもの
2026.02.04
ピアニストの久末航が日本製鉄音楽賞「フレッシュアーティスト賞」を受賞!

レポート
2026.02.04
京都コンサートホール2026年度ラインナップ発表
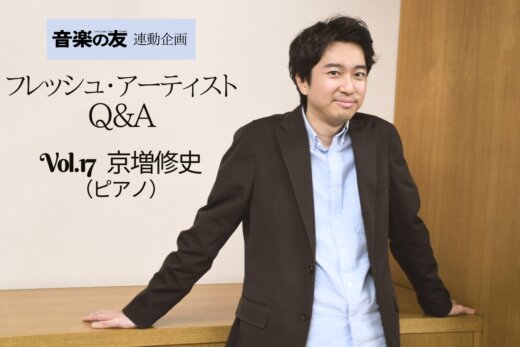
連載
2026.02.03
京増修史さん(ピアノ)、「もう一度聴きたい」と思われるような演奏家でありたい

インタビュー
2026.02.03
ネルソン・ゲルナーが語るショパン演奏と審査で大切なこと「音楽そのものに集中して理...

読みもの
2026.02.01
2026年2月の運勢&ラッキーミュージック☆青石ひかりのマンスリー星座占い