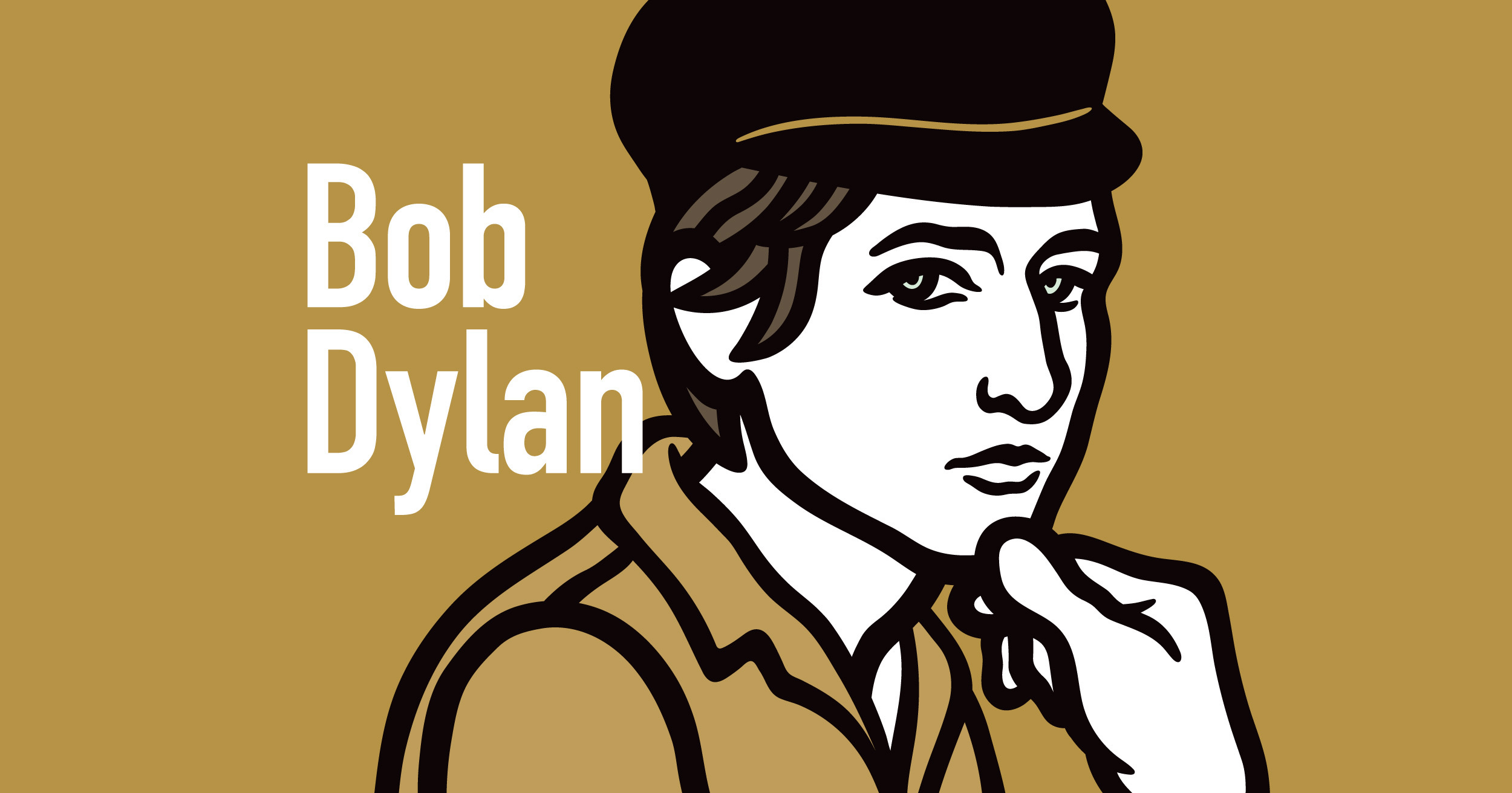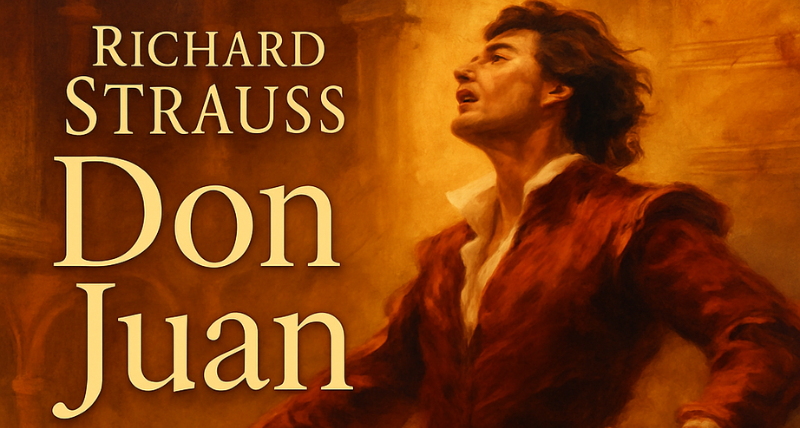演出としての「手話」がチェーホフ劇に新たな音を宿す――レッドトーチ・シアター×クリャービン『三人姉妹』

アントン・チェーホフによる名作『三人姉妹』。演劇の世界ではプロ・アマを問わず繰り返し上演されてきた古典中の古典に、手話によって新たな命を吹き込んだ話題の公演が来日します。役者たちが台詞を発しない舞台だからこそ、音や音楽が大切になる? 高橋彩子さんが見どころを紹介してくれました。

早稲田大学大学院文学研究科(演劇学 舞踊)修士課程修了。現代劇、伝統芸能、バレエ、ダンス、ミュージカル、オペラなどを中心に執筆。『The Japan Times』『E...
「手話」と言われて、シアターゴアー(劇場の常連)の皆さんはどんなことを思い浮かべるだろうか? 手話言語を用いた“手話劇”には海外でも日本でも一定の歴史があるほか、劇が上演される傍らで行なわれる手話通訳も近年認知され始めている。
個人的には、ドイツの振付家ピナ・バウシュ率いるヴッパタール舞踊団『カーネーション』でダンサーがガーシュウィンの〈The Man I Love〉を手話で踊る名シーンや、アメリカの劇団デフ・ウエスト・シアター『ビッグ・リバー』での出演者全員による手話だけでのクライマックスが忘れ難い。
声・言葉の視覚化である手話がもつ表現の可能性は、まだまだ開拓され尽くしてはいないだろう。今週末、そんな舞台手話史(?)に新たな1ページを開いた作品が来日する。ロシア人演出家ティモフェイ・クリャービンが手がけたレッドトーチ・シアター(シベリアの中心都市ノヴォシビルスクを拠点とする劇団)の『三人姉妹』だ。
冴えわたる音・音楽へのアプローチ
ロシアの文豪チェーホフが1900年に執筆した『三人姉妹』。亡き父の赴任先である田舎で暮らしつつ、生まれ育ったモスクワへ帰る日を夢見るプローゾロフ家の三人姉妹オリガ、マーシャ、イリーナとその周囲の人間模様を描いた群像劇だ。2015年に初演されたレッドトーチ・シアター版では、出演者のほぼ全員が手話でもって演じる。
注目すべきは、レッドトーチ・シアターが聴覚障害者の集団でもなければ、普段から手話劇を上演する集団でもない点。あくまで本作の表現手段として、手話が用いられているのだ。観客はロシア語手話に通じている人を除いて、俳優たちの仕草や表情と字幕で物語を追うことになる。
ちなみに舞台上には幾つもの部屋があるという設定だが、壁を表すのは床に引かれた白線のみで、どの部屋の様子も観客には丸見えだ。これらの状況から、他の『三人姉妹』にはない効果が生まれていく。

まず観客は、舞台上のさまざまな音に、かつてないほど意識を向けるだろう。衣擦れや靴音、食器がぶつかる音、猫の鳴き声、手拍子、登場人物たちが決して耳にすることのない音楽……。音楽に関しては、大音響で鳴っても台詞の進行が妨げられないため、通常の台詞劇とは異なる用い方が可能になっている点も指摘しておきたい。
一方、戯曲に書かれている音は決してカットされることなく、アイデア豊かな変換が施される。マーシャが口笛を吹いてオリガに止めるよう言われる場面は口笛ではなく笛になっているし、「驚くような音を出す」と台詞にある独楽を回す場面では人々はテーブルに耳をつけてその振動を“聴く”し、密かに心を通わせるマーシャとヴェルシーニン中佐が歌を歌い合う場面はショートメッセージのやりとりに。耳が遠い老人のはずのフェラポントは、ここでは登場人物の中で唯一、手話を解さないがゆえに相手の言うことがわからないという設定に変わっている。


見えている/聴こえているのは、誰?
また、台詞が独白というより、かなり明確な意思を持って相手に向かって話すケースが多くなるのも一つの特徴だろう。声を出しての会話と違い、背を向けている人物には、たとえ近くでも相手に届かないからだ(ただし、厳密には相手に見えていないはずの手話で会話が進行する場面もある)。
ドラマティックなのは、町で火事が起きたあとの3幕だ。火事の影響から舞台上では時折、停電が起きるのだが、こうなると、観客にすべての部屋を見渡すことができていたそれまでの状況が一転するのが面白い。我々の頼りは、登場人物たちがつけるスマートフォンの灯り。いわばスポットライトのように、その灯りがフォーカスを絞る。人々が心の内を明かす場面とリンクする形でこの停電が起きるのも巧い。

そう、私たちはこの舞台を通して、見るということ、聴くということに、これまでになく意識を向けさせられるのだ。数えきれないほど上演されてきた古典に、このような形で新鮮な感覚を注ぎ込んだクリャービンの手腕には驚かされる。
35歳の鬼才ティモフェイ・クリャービンに注目!
クリャービンは84年生まれの35歳。ロシア国立舞台芸術大学GITISを07年に卒業後、1920年創設という歴史あるレッドトーチ・シアターに所属し、国内外で数々の話題作を演出。これまで手がけた演劇に『エウゲニ・オネーギン』『マクベス』『エレクトラ』『ヘッダ・ガブラー』『ノラあるいは人形の家』など。09年からはオペラにも携わっており、《イーゴリ公》《タンホイザー》《リゴレット》などを演出している。

15年からはレッドトーチ・シアターの芸術監督に就任してカンパニーを率いているクリャービン。16年には《ドン・パスクワーレ》でボリショイ・オペラデビューも果たすなど、まさにロシアの舞台芸術界の今後を担うであろう逸材だ。その貴重な来日公演、できれば事前にあらすじを確認のうえ(知らない物語を字幕で追うのは疲れるはずなので)、目も耳も研ぎ澄ませて臨みたい。

日時:
2019年10月18日(金)13時開演
2019年10月19日(土)13時開演
2019年10月20日(日)13時開演
会場: 東京芸術劇場プレイハウス
作:アントン・チェーホフ
演出:ティモフェイ・クリャービン
出演:
イリーナ・クリヴォノス
ダリア・イェメリャノワ
リンダ・アフメジャノワ
ほか
関連する記事
-
読みものプロコフィエフの名曲と素顔に迫る12のエピソード
-
読みものホルスト《惑星》~人間の運命を司る星々が、時代の不安を映し出す
-
インタビューロシア音楽研究サイモン・モリソンへプロコフィエフとロシア音楽に関する10の質問!
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest