
日本演劇の魅力を集め、“声”の力で描く源平の物語——『子午線の祀り』

演劇・舞踊ライターの高橋彩子さんが、「音」から舞台作品を紹介する連載。今回は『平家物語』の世界を“群読”のスタイルで独自の劇にした、木下順二の名作『子午線の祀り』。野村萬斎、成河、若村麻由美らが出演する再演を前に、その魅力を解説してくれました。

早稲田大学大学院文学研究科(演劇学 舞踊)修士課程修了。現代劇、伝統芸能、バレエ、ダンス、ミュージカル、オペラなどを中心に執筆。『The Japan Times』『E...
“群読”という言葉をご存知だろうか? 簡単に言えば、一つのテクストを集団で声を出して読むこと。学校の授業などに取り入れられており、愛媛県では「ことばのちから実行委員会」が主催する「群読コンクール」も開かれているようだ。この「群読」を取り入れた名戯曲が存在する。劇作家・木下順二の『子午線の祀り』だ。
『平家物語』の世界を描いた現代劇
『子午線の祀り』の物語は、古典『平家物語』を下敷きにしている。
平知盛が指揮する平家軍は、源義経率いる源氏軍との一の谷の合戦に臨み、奇襲を受けて敗北する。知盛は和平を結ぶため、巫女である影身の内侍を後白河院のいる京へ遣わそうとするが、阿波民部重能の妨害に遭って頓挫。やがて後白河院から、知盛の弟であり源氏の人質になっている平重衡の身柄と引き換えに三種の神器を渡せという、非情な院宣が下り、知盛は戦いの続行を覚悟する。一方、源義経は、兄・頼朝の命を受けて同行する梶原景時の横槍に神経を尖らせながらも、潮の流れを見極めて勝機をつかもうとする。それぞれの思いを抱えながら、平家と源氏は壇ノ浦の決戦の日を迎え——。
平家の滅亡を見届け、「見るべきほどのことは見つ」と言って海に飛び込んだ平知盛。『子午線の祀り』は、その知盛の苦悩に焦点を当てて進んでいく。没落する定めの知盛に対置されるのが、日の出の勢いの義経だ。だが、その義経も平家に勝利したのちに悲しい運命を辿ることは誰もが知るところであり、劇中にもその予兆が感じられる。
『平家物語』の表現を随所に散りばめながら、源平両軍の戦いを、重厚かつ臨場感を持って描く本作だが、特筆すべきは、現代的な装いと言葉で各幕冒頭に登場する“読み手”の存在。劇の最初と最後(こちらは影身役の俳優が担う)には、「あなた」という言葉を用いながら天体の話をし、現代の私たちに繋げる。
筆者がこの作品を初めて生で観たのは、1999年の新国立劇場の公演だったが、知盛役の野村萬斎の瑞々しい美しさと共に、広大な世界観の中で800年前と現代が交差する瞬間の感動が、今も鮮明に記憶に残っている。いわばこの作品は、歴史劇の側面を持ちつつも現代劇として開かれ続けているのだ。
木下順二が日本演劇の魅力を集め、聴く醍醐味が詰まった“群読”
この戯曲が書かれたのは1978年。既に『彦市ばなし』『夕鶴』などを発表し、劇壇・文壇で名を成していた木下の、60代の充実期の作品にあたる。
木下は、自身のミューズであり(『夕鶴』は彼女のために書かれた)同志・パートナー的存在であった山本安英が主宰する「山本安英の会」内の“ことばの研究会”で生まれたテーマのもと、68年、『平家物語による群読―知盛』という実験作を書いて試演を重ねる。そのテーマとは、「日本古典の原文による朗読はどこまで可能か」(『子午線の祀り』河出文庫あとがきより)。古典を現代語訳せず原文のエネルギーを聴き手に届けることを目指して、出演者一人から全員までさまざまなバリエーションで朗読させたり、伝統芸能と新劇の演者を組み合わせ、伝統芸能の演者に現代語を読ませたりしたという。この試みが、『子午線の祀り』へと結実する。
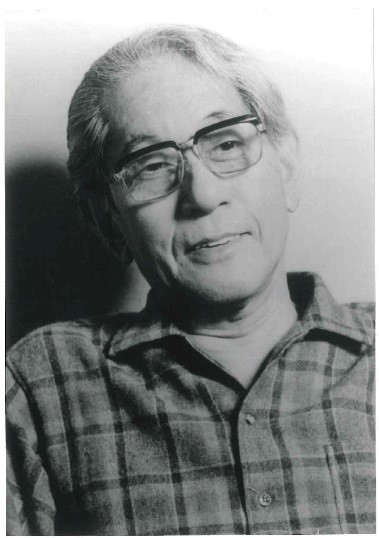
『子午線の祀り』には、その名も「群読の人々」という役名の人々が登場する。彼らが担うのは、「新中納言知盛の卿は、一の谷、大手生田の大将軍にておわしけるが、その勢みな逃げ討たれて、今はおん子武蔵の守知章おん年十六歳、お供には監物太郎頼方、ただ主従三騎になって、助け舟に乗らんと汀のかたへ落ち給う」といった『平家物語』の一節から、平家の武将らの会話の裏で強弱をつけながら繰り返される「いるかだいるかだいるかだいるかだ」といった声まで。どこかコロス(ギリシャ悲劇で、劇の背景などを説明する合唱隊)のような雰囲気もある。

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演『子午線の祀り』 撮影:細野 晋司

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演『子午線の祀り』 撮影:細野 晋司
中でも必聴なのが、クライマックスの壇ノ浦の合戦での、語りの迫力。平家はもちろん、源氏にとっても容易な戦いではなかったその様子が克明に語られるさまは圧巻だ。聴くものとしての演劇の醍醐味が、そこには詰まっている。それもそのはず、『平家物語』自体、琵琶法師が琵琶の演奏と共に語って伝えたもの。「語りもの」の系譜は、能狂言や浄瑠璃に受け継がれている。木下は『子午線の祀り』で日本のさまざまな演劇の魅力を集め、新たな表現を模索したのだ。

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演『子午線の祀り』 撮影:細野 晋司
継承され、更新され続ける舞台
日本の多様な演劇の力を集結させるという木下の試みを実現するには、新劇だけではなく、伝統芸能の演者の力が必要だった。初演では、新劇から山本安英(影身・読み手B)や滝沢修(重能)、能から観世榮夫(宗盛)、狂言から野村万作(義経)、歌舞伎から嵐圭史(知盛)など、各界の錚々たる顔ぶれが集結。演出は、新劇の宇野重吉のほか、能の側面から観世榮夫、群読の側面から酒井誠、歌舞伎の側面から高瀬精一郎、そして木下。主要なキャストは初演のまま、再演と呼ばず「第●次」と名づけて続ける公演は、92年の第五次まで数えた。
81年の第二次公演の模様はNHKで放映され、09年にも再放送されている。その後、既述の99年の新国立劇場公演では、野村萬斎(知盛)、市川右近(義経)、三田和代(影身)、観世榮夫(読み手Aほか)、鈴木瑞穂(重能)、木場勝己(景時)らが出演。04年の世田谷パブリックシアター公演では、野村萬斎(知盛)、嵐広也(義経)、高橋惠子(影身)、観世榮夫(宗盛ほか)、木場勝己(重能)らが出演している。
そして、2017年、野村萬斎が知盛を演じると共に演出を担当。萬斎はタイトルの「祀り」、すなわちレクイエムとしての側面に着目し、夜の海辺に黒衣の現代人たちが集まる形で劇を開始した。影身と読み手を演じる若村麻由美が、ろうそくを手に劇の最初と最後に現れるのも象徴的。
また、それまで伝統芸能の演者が務めてきた義経役を、初めて現代劇の俳優である成河が演じたのも画期的で、その突き抜けるような高い声と炎のような激しさでもって、義経の勢いと哀愁が鮮やかに表現され、憂愁の貴公子・知盛とのコントラストをなしていた。



さて、この舞台の2021年版が、間もなく幕を開ける。2017年の舞台を踏襲しつつ細部を見直し、美術も一新したバージョンとなるようだ。コロナ禍で傷を追った現代に、この祈りと鎮魂の劇は何を見せてくれるのだろうか。

神奈川公演
KAAT神奈川芸術劇場
2021年2月21日(日)~27日(土) 6回公演(全14:00開演)
名古屋公演
日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
2021年3月3日(水)18:30、4日(木)12:00
久留米公演
久留米シティプラザ ザ・グランドホール
2021年3月7日(日)16:00、8日(月)13:00
兵庫公演
兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール
2021年3月13日(土)11:00/17:00、14日(日)13:00
東京公演
世田谷パブリックシアター
2021年3月19日(金)〜30日(火)11公演(19日16:30開演、以降全日程14:00開演)
関連する記事
-
イベント真に多様な創作を続ける太陽劇団による“夢の日本”
-
イベント声・言葉と身体のマッチングの妙で描くパイト流ゴーゴリの世界
-
読みもの戯曲から聞こえてくる「時代の声」〜20世紀の名作『エンジェルス・イン・アメリカ』...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest


















