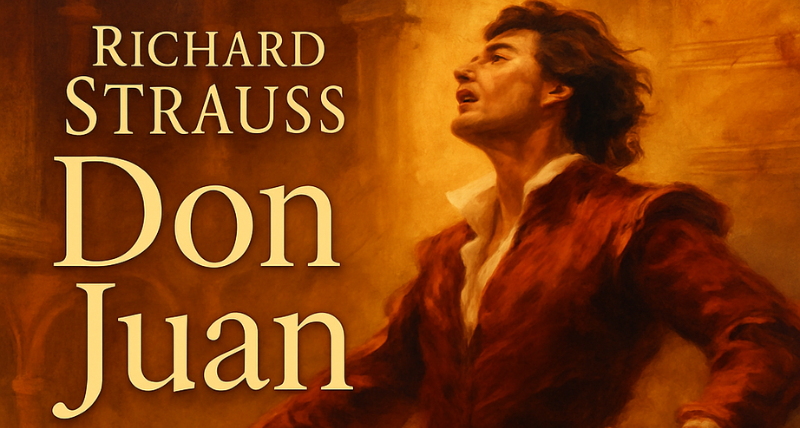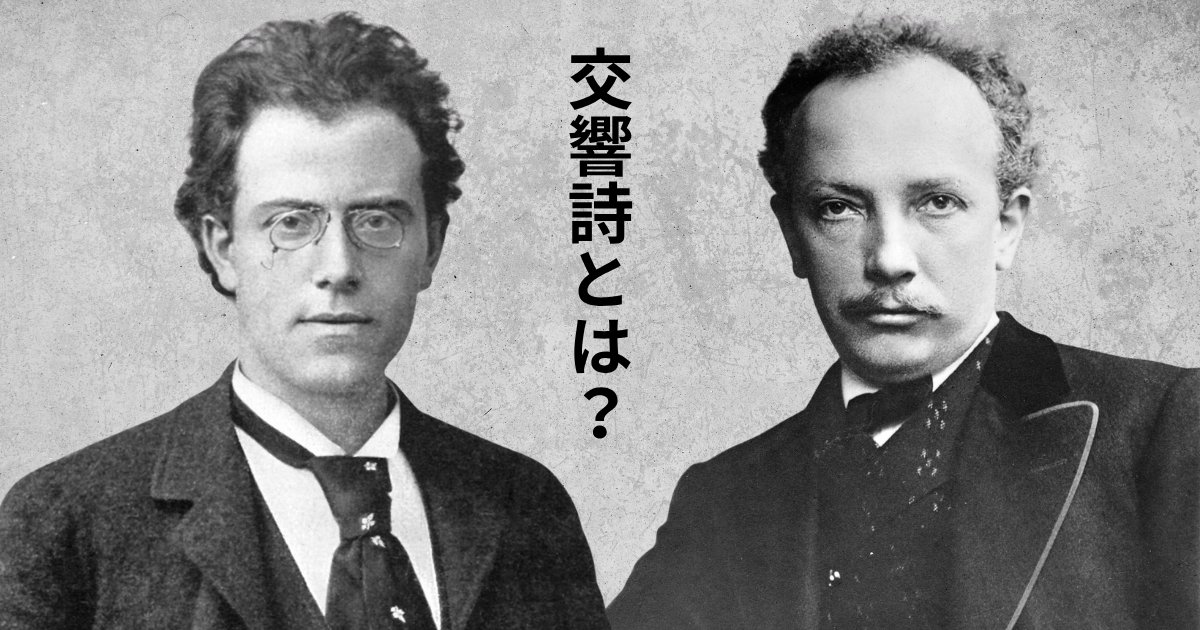プロコフィエフの「ピアノ協奏曲第3番」は和風? 作曲の過程からひも解く“東方的”の由来

プロコフィエフの「ピアノ協奏曲第3番」は、日本の長唄「越後獅子」に似ている?
そんな“和風”説について、この名曲の東方的な響きのルーツを音楽学者・菊間史織氏が徹底解説。ロシア、カフカース、日本、そしてフランス……各地で進められた作曲のプロセスをたどると、“異国情緒”の正体が見えてきます。
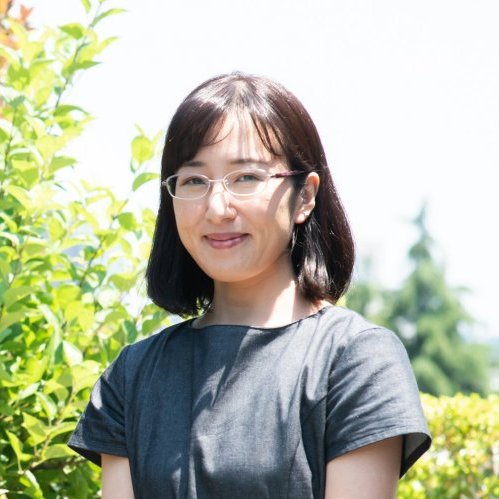
1980年東京都生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科、同大学院修了(音楽学博士)。音楽教育に携わりながらプロコフィエフ研究を続ける。著書に『「ピーターと狼」の点と線~プ...
プロコフィエフの「ピアノ協奏曲第3番」は、映画化された『蜜蜂と遠雷』にも出てくるようにピアノ・コンクールの定番曲で、たいへん明るく楽観的な調子の曲なので、世界中で親しまれている。
日本では、この作品の第3楽章に、長唄の「越後獅子」の影響が見られるのではないかと長らく言われてきた。この説は、プロコフィエフと友情を築いた音楽評論家の大田黒元雄を囲むサークルのメンバー、野村光一氏の回想が出処になっているようだ。
この説を裏付ける、あるいは否定するための決定的な資料はなかなか見つからない。本当にあの第3楽章の音楽は日本的なのだろうか? プロコフィエフはなにを意図していたのだろうか?
ロシアでの作曲〜プロコフィエフ「ピアノ協奏曲第3番」の出発点
日本では“和”、ロシアでは“ロシア的”と言われる第1楽章
作曲順に追いかけてみると、まず1917年の秋から翌年春までの時期に、第1楽章の輪郭と、第2楽章のふたつの変奏部分が書かれている。この頃プロコフィエフは、ロシア革命で混乱する都市部から逃れ、暖かいカフカース地方に滞在し、国外脱出を考えていた。
第1楽章の音楽も、日本では、“和”を感じると言われがちだ。しかし実際のところ、ロシアではこの楽章はきわめてロシア的と考えられてきた。クラリネットのソロではじまる冒頭主題では、4度下行がロシア民謡の色合いを出している。どちらと判断することはできないが、ひとつ指摘するならば、この音楽が書かれたカフカース(コーカサス)地方はロシアの中でもひときわ東方的な雰囲気を帯びた場所なのである。(ちなみに本記事では中東、極東を合わせた非西欧的地域を東方と呼ぶ)。
そこに滞在しながら、自ずとそのような雰囲気をともなう音楽が生まれてきた可能性はある。プロコフィエフは1908年にこの地方でリムスキー=コルサコフの「ピアノ協奏曲」を熱心に練習していたことがあるが、ロシア民謡を扱った主題ではじまるそんな曲の記憶も、1917~18年によぎったかもしれない。
リムスキー=コルサコフ「ピアノ協奏曲」
日本と、アメリカ行きの船の中での作曲〜「越後獅子」説と 第3楽章
プロコフィエフは日本で何を聴いた?
「越後獅子」に似ていると言われてきた第3楽章の第1主題と、それに続くやや荒々しい第2主題は、プロコフィエフの自伝と日記によれば、1918年夏に2か月滞在した日本と、日本からアメリカに向かう船の中で書かれた。
第1主題は、いくつも半音を含む旋律が日本人の耳には和風に聞こえ、とくにミファラシドという都節音階を使ったような部分もある。プロコフィエフが日本で「越後獅子」を聴いたかどうかはわからないが、大田黒元雄の回想が正しければ、彼が大田黒と行った料亭では日本舞踊の「松島」が流れていた。「松島」にも第1主題中の「
「越後獅子」、日本舞踊 常磐津 「松島」
白鍵のみの音を使って書くという試み
しかし、この第1主題はいつも和風に聞こえるわけではない。「協奏曲」の中では、三和音の半音階進行に乗せられていたり、九の和音に組み込まれていたりもする。そうした場合は、プロコフィエフのピアノ曲《束の間の幻影》や、ドビュッシーの音楽のような洒落た響きがする。というのは、このときにプロコフィエフが意図していたのは、ピアノの白鍵のみの音を使って書くという、西欧の伝統的な和声理論に挑戦する試みだったからだ。
これらの主題は、この時点では「ピアノ協奏曲第3番」ではなく、《白い四重奏》という弦楽四重奏曲のために書かれたのだ。《白い四重奏》は1914年に、その白鍵のコンセプトとともに着想され、最終的には放棄されるのだが、1918年にはまだ構想が生きていた。七の和音をフィーチャーして作曲されたその第1楽章は、《炎の天使》第5場の修道院の場面などに転用されているので、彷徨うような幻想的な響きを音源で確かめることができる。
プロコフィエフ:《束の間の幻影》、《炎の天使》第5場
フランスでの仕上げ〜「ピアノ協奏曲第3番」はどう完成した?
《スキタイ組曲》でパリデビュー
作曲環境的には日本との関連が強いこれらふたつの主題を「協奏曲」に使い、全体をどことなく“東方的”に仕上げることにしたのが、1921年である。なぜそのように仕上げられたのか?
プロコフィエフが「ピアノ協奏曲第3番」を真剣に完成させようとしたのは、アメリカのシカゴ交響楽団のフレデリック・ストックによる初演と、懇意の指揮者クーセヴィツキーによるパリ初演が約束されたからだった。それで彼は、母や恋人と過ごす夏の作曲地として、フランスのロシュレ海岸沿いの村を選び、1921年3月に引っ越した。
クーセヴィツキーはその5月、プロコフィエフの《スキタイ組曲》をパリ初演して、古代の強く自由な遊牧民族、スキタイ人と重ね合わせられた東の“野蛮人”といった鮮烈なイメージで、彼をパリデビューさせた。本当はバレエ・リュスのディアギレフがバレエ《道化師》の初演で、プロコフィエフをパリデビューさせたかったのだが、クーセヴィツキーが数週間先駆けた形だ。
クーセヴィツキーは出版社も経営しているので、作品を売り込むことが必要なのだ(《スキタイ組曲》も「ピアノ協奏曲第3番」も彼の傘下のグートハイルから出版)。プロコフィエフ自身、このイメージに沿って、“東方”の風合いで「協奏曲」を仕上げようとしたようだ。
プロコフィエフ《スキタイ組曲》
日本人との文通とラヴェルからの影響
5月末、彼はロシュレで「ピアノ協奏曲第3番」第2楽章の変奏の続きを書きはじめた。“東方”に幻想を抱く象徴主義詩人のバリモントや友人のバシキーロフがロシアから亡命してきて、彼の周りにいた。
また1921年前半には、大田黒元雄、徳川頼貞、日本から一緒に船に乗って当時マニラにいたピアニストのアレクサンドル・スクリャレフスキーとの文通もあった。夏には、アメリカでのマネージャー、フィッツヒュー・ヘンゼルがエルネスティーネ・シューマン=ハインク夫人の日本公演に帯同する様子を知らされていた。このような環境で、いつしか、《白い四重奏》の素材が「協奏曲」に使われることになった。
さらに、プロコフィエフは以前から尊敬していたラヴェルの《スペイン狂詩曲》のいくつかの書法を真似て取り込んだようだ。「協奏曲」第3楽章には、《スペイン狂詩曲》の〈マラゲーニャ〉冒頭のピツィカートで刻むコントラバス、〈祭り〉終わり近くの2度の不協和音の連続と舞踊的リズムが聞こえる。
ラヴェル《スペイン狂詩曲》より〈マラゲーニャ〉〈祭り〉
このようにして、さまざまな色合いを取り込んで、意図的に西欧のクラシックとは異なる味わいに仕立てられたこの作品。ぜひ聴いて確かめてみていただきたい。
関連する記事
-
読みもの映画『ブーニン 天才ピアニストの沈黙と再⽣』が2026年2⽉20⽇に公開!
-
レポート【取材の裏側】音楽家・阪田知樹の脳内を覗く! 『音楽の友』9月号表紙&特...
-
プレイリストピアニスト、アレクサンダー・ガジェヴ~”再生”を必要としているあなたに送るプレイ...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest