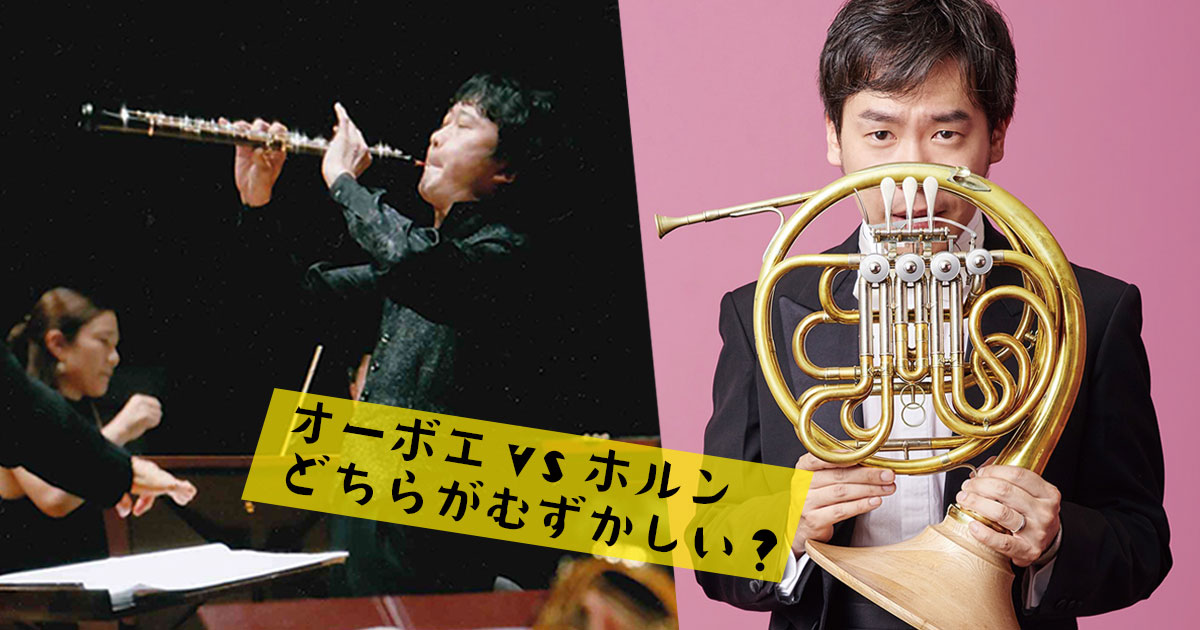サックス裏口入門! 現代ジャズシーンを知るならこの3人

本当は花形のトランペットやサクソフォンをプレイしたかった、吹奏楽出身の弦バスプレイヤー・小美濃悠太氏による、オススメのサクソフォン・プレイヤー3選。音色だけで即座にプレイヤーの名前が当てられる人もいるほど、個性が色濃く出る楽器、サクソフォン。それだけに好みも千差万別なのかもしれません。
往年のサクソフォン・プレイヤーもいいけれど、現代ジャズシーンを知るならこの3人! 現役ベーシストならではの視点でご紹介いただきました。

1985年生まれ。千葉大学文学部卒業、一橋大学社会学研究科修士課程修了。 大学在学中より演奏活動を開始し、臼庭潤、南博、津上研太、音川英二など日本を代表する数々のジャ...
前回の記事では、トランペッターおよびサクソフォニストというポジションへの憧れ、そして嫉妬について告白させていただいた。吹奏楽部に入部し、この花形楽器のどちらかを手にすることで、私の人生は変わる。高校入学直後の15歳の私は、そう信じていたのである。
それから18年が経ち、予定よりかなり音の低い楽器を手にして、毎日ステージの後ろのほうに立っている。愛憎入り交じった感情を抱きつつ、録音作品やライブで数え切れないほどのサクソフォニストの吹奏を耳にするうちに、サックスについてはかなり偏った好みができてしまった。
今回は、そんなごく私的なサクソフォニスト観の開陳にお付き合いいただきたい。ジャズファンでない方にジャズサックスを楽しんでもらうための、「正面入り口」ではない、ある種の「裏口」として楽しんでいただければ幸いである。
現代のテナー・ジャイアント ジョー・ロヴァ―ノ(Joe Lovano)
まずは王道中の王道。アメリカのサックス奏者、ジョー・ロヴァ―ノ。まさに現代ジャズサックスの最高峰の一人である。アメリカでの高い評価に対して日本ではあまり話題に上らないようだ。私が紹介するまでもない巨人だが、それでも触れずには通れない魅力がある。
とにかくプレイリストをご紹介しよう。数多くの作品を残しているが、カルテットでのライブ録音から。
CD2枚組で発売されているのだが、オススメは2枚目。ジャズのカッコイイところを凝縮したような演奏が収められている。
1曲目から、ロヴァ―ノの咆哮をリズムセクションが絶え間なくプッシュし続ける熱演。ジャズがいかにエネルギーに溢れた音楽であるかをよく示す名盤だ。伝統的なイディオムを踏襲しながらも、徐々にアブストラクトになり、熱を帯びていくサックスソロ。いきなりライブのクライマックスさえ感じさせる強力なピアノソロを経て、再び始まるサックスソロはさらに壮絶である。決して秋の夜長をリラックスして楽しむタイプのジャズではないので、注意して聴いていただきたい。

意外と知られていない(吹奏楽部員しか知らないという説も)ことだが、サックスは木管楽器である。ロヴァ―ノの音色は、サックスが木管楽器だということを改めて思い出させてくれる太くて温かいもの。迫力だけでなく、包容力ももっている。できれば大音量で聴き、肌で感じたい音楽だ。
天使のささやき ヘイデン・チザム(Hayden Chisholm)
サックスの音色は、それだけで即座にプレイヤーの名前を当てられるほど個性の幅が広い。一方で個性的な音色のフォロワーも多いため、影響を受けたサックス奏者が比較的わかりやすいという側面もある。しばしば「あの人は○○系だね」という言われ方もする。
余談だが、サックス奏者に「キミ、ジョン・コルトレーン好きでしょ?」と自信満々に話しかけているリスナーを見かけることがある。そういう人は、たいていジャズと名のつくものをすべてマイルス・デイヴィスとジョン・コルトレーンに収斂させて、遠い昔のジャズ薀蓄を語りだす。それは、例えるなら「どんな料理を出しても中濃ソースをだばだばかけて食べる自称グルメ」のようなもので、あまり信用しないほうがいい。

話が脱線したが、次に紹介したいのはヘイデン・チザム。ニュージーランド出身のサックス奏者で、ドイツに拠点を置いて活動している。
マット・ペンマン(Matt Penman)というベーシストを追いかけているうちに、共演していたチザムの演奏に出会った。温度の低い澄んだ音色で、8分音符をクールに連ねていく演奏。強いて言うならポール・デズモンドの系統にある気もするが、それとも違う音色の特徴があって、天上から降ってきたささやき声のようである。いったい何が違うのか。
答えは彼の経歴の中にあった。彼の音楽キャリアのスタートは、ディキシーランドジャズのバンドでクラリネットを吹くところからスタートしている。なるほど、クラリネットのテイストが含まれているのだ。特に高音域にそれが顕著で、クラリネットの素朴でまっすぐな音色と、サックスの艶っぽい成分を併せ持っていると言えばいいだろうか。
一方でサックスのザラッとした成分がやや強調されている録音もあったりして、その全貌がつかめないプレイヤーでもある。現地に住む方からの情報によれば、ドイツ語圏の民謡に関するドキュメンタリー映像のプロデュース・主演を務めたりもしていて、なかなか尻尾がつかめない、不思議な魅力に溢れた音楽家だ。
幅広い(広すぎる)彼の活動の中からアルバムを一枚紹介するとすれば、ピアノ、ベースとのトリオのこちら。
1曲目から現代音楽のような雰囲気で、若干ひるんでしまうかもしれない。しかしそこをグッと堪えて、彼特有の音色を味わってほしい。2曲目、抑制の効いた音色でのピアノとの丁々発止のインプロヴィゼーションは静かなスリルに満ち溢れている。
サックスの極北 ヤン・ガルバレク(Jan Garbarek)
北欧代表として、紹介しないわけにいかないのがノルウェーの国宝級サクソフォニスト、ヤン・ガルバレク。
ジョー・ロヴァ―ノが偉大なサックス奏者ジョン・コルトレーンにルーツをもつのと同じように、ガルバレクもコルトレーンの影響下にあり、「北欧のコルトレーン」と呼ばれることもある。しかし実際にはその呼び名は適切ではなく、ガルバレクはガルバレクでしかない。後続するノルウェーのサクソフォニストは、彼の影響を受けずにサックスを吹くことができないのではないかと思うほど、強い影響力をもつに至っている。
キース・ジャレット(ピアノ)が率いた伝説的なカルテットでその名を知られるようになったガルバレクは、ヨーロッパの先鋭的なミュージシャンたちとの共演を重ねるだけでなく、パーカッション奏者トリロク・グルトゥ(Trilok Gurtu)やタブラ奏者ザキール・フセイン(Zakir Hussain)などのインドの音楽家、ブラジルの偉大なギタリスト・ピアニストであるエグベルト・ジスモンチ(Egberto Gismonti)など、ジャズという言葉ではまったく括りきれないところまで自身の音楽を拡張している。
細かい経歴はウィキペディア等をご参照していただくとして、彼の音色を楽しんでいただきたい。聴くものの内面から何かを抉り出すような鋭さは、やはりノルウェーという土地の氷点下の風景を想起させるものだ。その魅力を紹介し尽くすにはアルバムを何枚紹介出しても足りないのだが、ここでは2枚だけご紹介しよう。

1曲目である。名盤とされる作品は、1曲目から凄まじいエネルギーをもっている。このアルバムはとにかく1曲目だけでお腹いっぱいになってしまうので、2曲目以降の再生回数が圧倒的に少ない(実は曲名すら覚えていなかった)。
只事ではないピアノイントロに導かれてリズムセクションが加わり、0:37あたりからガルバレクのテナーが聴こえてきた時点で、こちらが気圧されるほどのエネルギーが放出されている。再生から1分もしないうちに、その神々しさのあまりスピーカーに向かって頭を下げてしまうこと必至。
短いテーマを終えて、キースの唸り声混じりのピアノソロがあり、4:00ジャストあたりからテナーソロが始まる。高揚しきっているリズムセクションを踏み台にして、スケールの大きな演奏で高みへと上っていくガルバレク。いつの間にかキースもピアノを弾くのを放棄して、パーカッションを叩き始める。バンドはトランス状態に到達し、凄まじいテンションで演奏していたことは想像に難くない。聴いていると意識がどんどん引き込まれていってしまうので、ひとりで車を運転しているときには聴けない。
ちなみに、これは先日解体が表明された中野サンプラザでの79年4月の公演を収録したもの。日本での他の公演に比べるとこの日の演奏はイマイチだったらしく、リリースは10年後まで遅れた。これでイマイチだったとしたら、ほかの日は一体……と想像するだけで恐ろしい。
同じメンバーでのアルバム《My Song》もオススメ。タイトルチューンである《My Song》は感涙間違いなし。
ブラジルの国宝エグベルト・ジスモンチ(Egberto Gismonti)、世界で一番ディープなサウンドのベーシスト、チャーリー・ヘイデン(Charlie Haden)とのトリオの、こちらもコンサートを収録したもの。《Palhaço》はけだし名曲。
ブラジルの哀愁を感じさせるジスモンチのナンバーが中心で、物悲しくも美しいアルバム。空いている長距離列車(新幹線以外が望ましい)に独りで乗り、秋の車窓をぼんやり眺めながら聴けば、一人旅の旅情がグッと増すはずだ(実践済み)。
関連する記事
-
インタビューフルート奏者で龍角散社長の藤井隆太が語る演奏家の「健康経営」
-
インタビュー福川伸陽が語るR.シュトラウスと父、その愛憎を超えて作り出されたホルン曲の数々
-
読みものオーボエ vs ホルン、世界一難しい楽器はどっち? 大島弥州夫と福川伸陽が対決!
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest