
クロード・モネ没後100年——夢のような風景画に入り込み、光と風と雪の中に身をゆだねよう!

現在開催中の「モネ没後100年 クロード・モネ —風景への問いかけ」は、印象派の巨匠モネが描いた風景画の中に入り込んだかのような没入体験をもたらす展覧会。日傘の女性が立つ野原の光と風、雪景色が見せる蜃気楼のような幻想、そして晩年に到達した仙境のような睡蓮の世界。西洋絵画の伝統を覆し、日本趣味を取り入れたモネの創造の軌跡を辿ります。
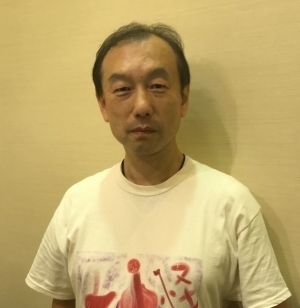
1959年北九州市生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業。日経BP社の音楽・美術分野の記者、「日経アート」誌編集長、日本経済新聞美術担当記者等を経て、2012年から多摩...
アーティゾン美術館で開かれている企画展「モネ没後100年 クロード・モネ — 風景への問いかけ」を訪れた。印象派の画風を切り開いたクロード・モネ(1840〜1926)の画風は実に清々しく、室内にいても気持ちいい風をあびる感覚を与えてくれた。風景画はモネの神髄だ。その風景への問いかけをテーマにしたこの展覧会は、はたしてどんな答えを出してくれるのだろうか。

印象派の画風を開拓していた時代にルノワールが描いたモネの肖像画
まばゆい光と心地よく揺らぐ風
白い服を着た一人の女性が、野原の中で日傘をさしている。なんとさわやかな絵だろうと思う。足元にたくさんの花が咲き乱れる一方で、画面上部の日傘が日の光の強さを演出している。マフラーが風になびいている部分を見ている筆者の頬を、一陣の風が吹き抜ける。この女性と一緒に野原を歩けば、なんと気持ちいい時間を過ごせるだろう。そんなことを思いながら、この絵の中に入り込みたくなった。

明るい陽光の中の情景を描くのは、モネとルノワールが1870年代に協働で開拓した印象派の技法の特質をフルに生かした技だ。絵具を混ぜずにカンヴァスの上に細かく小さな塊として置いていくことで混色による濁りを防ぎ、絵具が本来持っている明るさを保つ。鑑賞者は少し離れたところから見て、目を通した脳内で混色させる。小さな網点の集合体で表現した現代のカラー印刷のような原理に基づく技法である。
さて、モネのこの展覧会が「風景」をテーマとしていることはタイトルに書かれているわけだが、人物をメインのモチーフとして大きく描いたこの絵を風景画として見るのは、なかなか面白い試みだと思う。その気になって見ると、この絵には風景画としての決定的な要因があることに思い至る。見ている人々を風景の中にいざなう力をもっているのである。描かれている女性の名は、シュザンヌ・オシュデ。モネの2番目のパートナーの先夫との娘という。
歴史や宗教の場面を描くことが主流だったそれまでの西洋絵画の伝統の中で、モネが特に風景画を好んで描き始めたのは19世紀後半に入ってからだったが、その前からフランスでは風景画を描く画家が現れていた。
たとえば、カミーユ・コロー。花鳥風月、すなわち自然の風景を愛する日本人にとっても、なかなか心地よく映る画風だ。筆者もコローの絵を見ると、ものすごく心が落ち着く。
モネは、亡くした先妻のカミーユの絵などでは顔をリアルに表した人物画も描いたが、こちらの絵では顔の描写が略されている。そこにも、この絵が風景画たるゆえんがある。モネにとってシュザンヌはすでにかけがえのない娘になっていたと想像するが、絵を通してこの風景の中を一緒に歩いていたのではあるまいか。

19世紀半ば頃にチューブ入りの油絵具が発明されてから、欧州の画家たちは屋外で絵を描くことができるようになった。アトリエの中で描くのとはまるっきり違うシチュエーションが現れたわけである。進取の気性に富んだ印象派の画家たちが屋外の風景を見たままに描き始めたのは、もはや必然だったと言ってもいいだろう。そのフレッシュな感覚が、モネの明るい画風を育んだのだ。
雪を愛した印象派の画家たち
そうした屋外の風景で特に筆者が注目したのは、雪景色である。再び日本の話を出して恐縮だが、清少納言は「枕草子」で雪の風情を綴り、歌川広重は浮世絵でたくさんの雪景を描いた。日本人にとって雪景色は奈良・平安の昔から文学や絵画の極めて身近なテーマであり続けてきたのだ。
一方、西洋では伝統的には雪はさほどメジャーな画題ではなかったのだが、モネの時代になって大きく変わった。

モネの《かささぎ》は、第1回印象派展が開かれる1874年よりも少し前の時期の作品だが、実に美しい雪の情景が描き出されている。陰の部分に青の絵具などを使ってリアリズムを追究しているのも興味深い。モネはかなりたくさん雪を絵に描いたが、ルノワールやシスレーなど他の印象派の画家たちも、雪景色を描いている。
たとえば、ルノワールの《雪景色》は、絵具を点々と置いていく印象派技法の実験作の一つ。その柔らかな表現には、画家のやさしさが感じられた。

筆者がさらに興味を引かれたのは、モネの《氷塊》という作品だ。

解けつつある氷が浮かぶ池の様子を描いたのだろうか。冬の屋外を描いたなかに、暖色で表された多くの樹木が立っている。日が当たったからなのか、樹木や葉の色なのかは、遠景だからわからないのだが、まるで夢のような風景だ。本展カタログの解説によると、この絵を見た小説家のマルセル・プルーストは「解氷のせいですべてが揺らめき、すべてがまるで蜃気楼のようです。それが氷なのか太陽なのか、見分けがつかず、あらゆる氷の塊が砕けて空を映し出し、木々は輝きに満ち……」といった文章を残しているという。
この頃のモネは、光をカンヴァスに焼き付けることを旨とした画家だったゆえ、実際に日の光が当たるなどして、こうした風景が立ち現れた一瞬をカンヴァスに描きとめたのだろうと想像する。
日本趣味からランドアートへ
「睡蓮」は、後半生のモネが熱心に取り組んだ画題として有名だが、描かれた場がこの展覧会で「ランドアートの走り」と位置づけられていたことに少々意表を突かれ、新たな視点で作品群を見る僥倖(ぎょうこう)を得た。

モネは当時、日本から輸入された多くの浮世絵に影響を受けたジャポニスム(日本趣味)の画家である。この展覧会でも「ジャポニスム」に一つの章を割いており、葛飾北斎や歌川広重の浮世絵が多数展示されていた。さらに、後半生に住んだパリ近郊のジヴェルニーという土地に日本風の庭園を造り、柳の木や藤、牡丹、蓮を育て、さらには太鼓橋を架けて「日本」を演出する。そこで数多く描いた「睡蓮」は、モネの代名詞として知られる画題になった。
では、「ランドアート」とはどうつながるのか? 「ランドアート」は文字通り、大地を造作することによって作り上げる美術作品を指す。湖に渦巻き状の突堤を築いた米国の美術家、ロバート・スミッソンの《スパイラル・ジェッティ》(1970年)などの作品が知られている。もう説明しなくてもわかるのではないか、モネのジヴェルニーの庭園がランドアートの走りとされた理由が。
もともと、日本の寺に多く見られる庭園にもランドアートとしての側面があったことを考えれば、モネが日本風の庭園を築いたことは自然な流れの上に生まれたと言える。モネは当時欧州で開かれていた万国博覧会で日本文化に接する機会を得ていたと聞く。断片的な文物への接触から、本格的な日本風の庭園を造ることができたのは、やはりモネの想像力がなせるわざだったのだろう。
ランドアートとともに暮らすなかで、モネは睡蓮を描き続けた。その数は250点におよんだという。
そして仙境へ
筆者は、モネが仙境、西洋流の言い方ではユートピアに入ったのではないかと思い至った。いくら描き続けても、真の境地にはなかなか到達しない。だからこそ描き続ける。ジヴェルニーの庭はまさに仙境であり、睡蓮は追究するのにふさわしい画題だったのだ。さらに晩年視力が衰え、心の目で描くようになっても描き続けたのは、仙境に入ったゆえのことだったのではあるまいか。没する4年前に描いた《しだれ柳》を見てほしい。表現は抽象的になったが、以前にはなかった深みがある。そこには、風景の奥にある何かが見えてくるのである。

ラクガキスト小川敦生のラクガキ

「富士山に傘がかかると雨が降る」と言いますが、日傘ならカンカン照り間違いなしですね。モネにも、日本に来てぜひ赤富士を見せてあげたかったと思う今日このごろです。
関連する記事
-
イベントガウディ没後100年記念! サグラダ・ファミリアを全身で体感できる展覧会
-
レポートユジャ・ワンのプロコフィエフ、アルゲリッチのシューマン、パリで二つの協奏曲が競演
-
読みもの【音楽を奏でる絵】カンディンスキー「色彩の音楽」とシェーンベルク、同時代の作曲家
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest


















