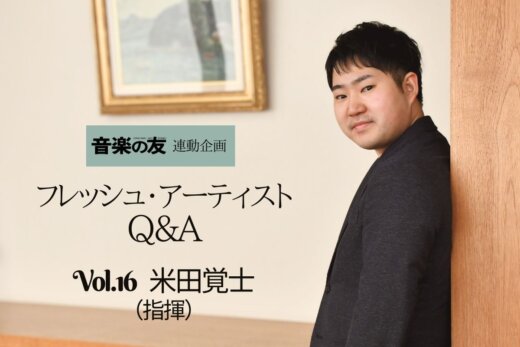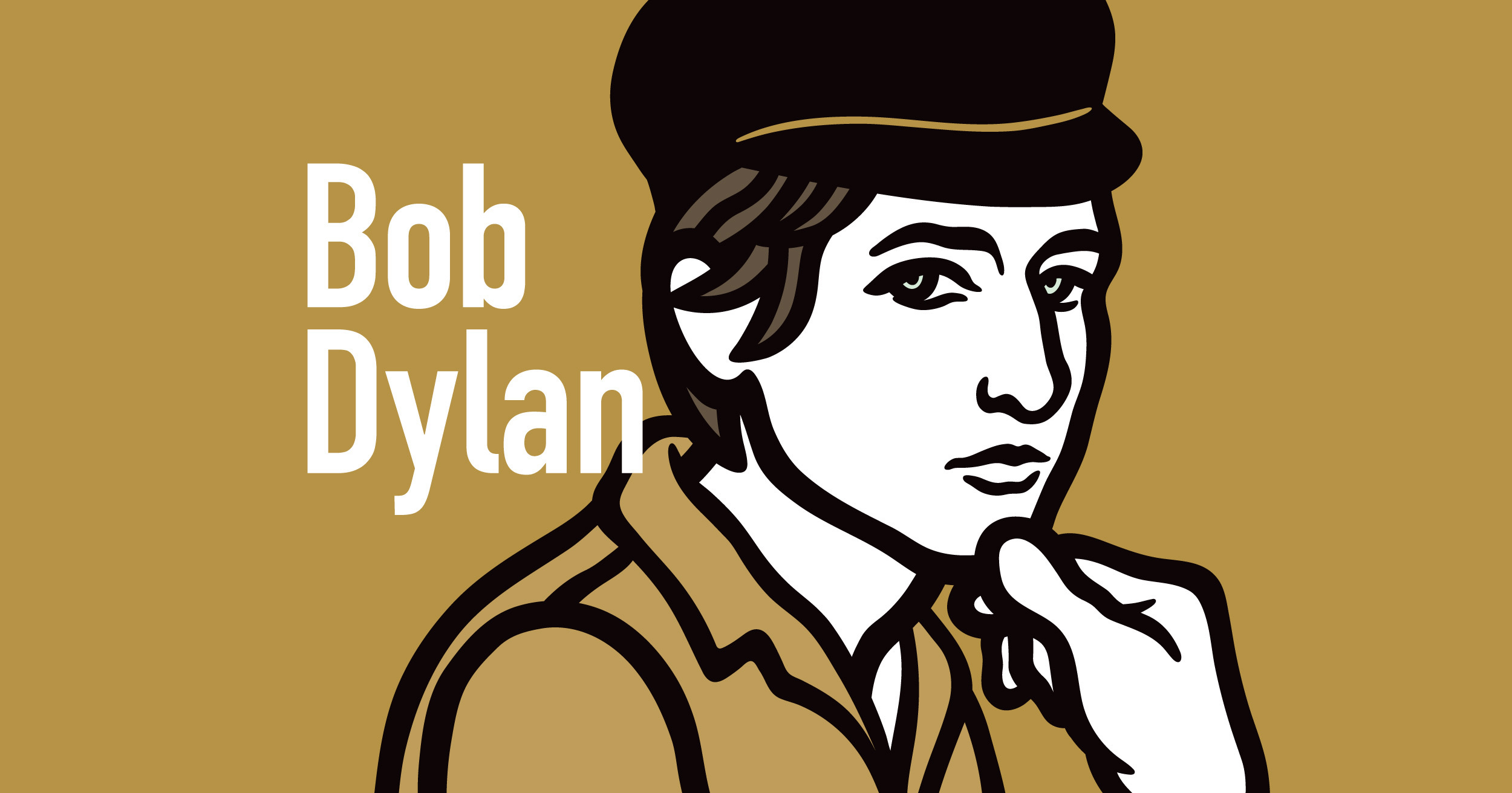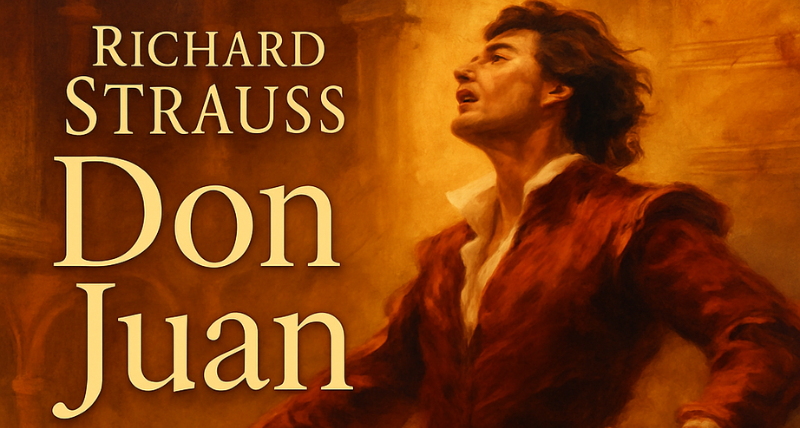審査員の海老彰子、児玉桃が語る第19回ショパンコンクールの傾向

第19回ショパン国際ピアノコンクールの審査員として日本から参加した海老彰子、児玉桃のお二人に、今回のコンクールの傾向や、日本人コンテスタントの活躍について伺いました。

2019年夏、息子が10歳を過ぎたのを機に海外へ行くのを再開。 1969年東京都大田区に生まれ、自然豊かな広島県の世羅高原で育つ。子どもの頃、ひよこ(のちにニワトリ)...
海老彰子「ショパン自身のピアノの弾き方に注意を払うことも大切」
――多くの国際コンクールでの審査を通して
海老 若いピアニストの演奏技術は、昔とは比較にならないぐらい向上しています。今回のコンクールのようなハイ・レヴェルが、いまやスタンダートになってきています。
――今回のショパン・コンクールの参加者の多くがアジア系ピアニストであることについて
海老 もしかしたら、戦争の関係も出ているのかもしれませんが、はっきりとしたことはわかりません。その点では、もう少しさまざまな地域の人たちが参加されてもよかったのではないかと思います。
――日本人コンテスタントの傾向
海老 以前と比べ、大きく変わってきています。自分の主張をはっきりと表現しており、たいへんよい傾向だと思います。
日本のピアニストのみなさんは、ショパンに対しての思いに自信をもって取り組んでいけばよいのではないかと思います。
――中国人コンテスタントの演奏水準の向上について
海老 音楽に限らず、華僑の方々は外国に根を張られると、とても強いのです。私たち日本人は、人々も文化も概して繊細です。華僑の方々は、よい意味で本当に太い! その文化的な土壌が彼らを育んでいるのではないかと思います。
――ショパン演奏について
海老 ショパンの音楽をどのように解釈するかということと同時に、天才ショパンのピアノの弾き方はどうだったのだろう……そこにも注意を払うことは大切だと思いますし、そのように指導していくことも重要です。そのような点では、ストラータさん(Gabriele Strata)の弾き方はとってもよかったです。無理のない弾き方が一番! 良い音が響きますから。
コンクールでは、優勝者は一人だけ決定されますよね。でも、誰が優勝かということは、とくに音楽では、もしかしたら意味がないことなのかもしれません。そのようなシステムから漏れた人たちのなかで、ほんとうによいものを持っているピアニストを育む仕組みを作っていくことも大切だと思います。
(2025年10月20日)

関連する記事
-
インタビューワルシャワ・フィルのオーボエ奏者がショパンコンクールを振り返る
-
インタビューワルシャワ・フィルのファゴット奏者がショパンコンクールを振り返る
-
インタビューワルシャワ・フィルのチェロ奏者がショパンコンクールを振り返る
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest