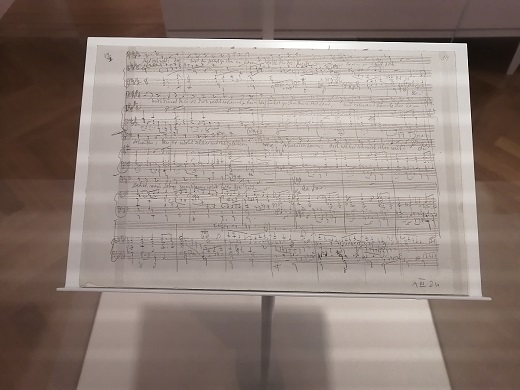舞台の上は、ファンタジーではなく、すべてが真実であるべきだ――演出家フランコ・ゼッフィレッリ

現代最高のオペラ演出家であり、映画監督・脚本家のフランコ・ゼッフィレッリ氏が2019年6月15日、ローマの自宅で逝去されました。
ONTOMOでは追悼として「音楽の友」1998年3月号に掲載された独占インタビューを再掲載いたします。インタビュア―は当時「音楽の友」の編集部に籍を置いていた、ONTOMOエディトリアル・アドバイザーの林田直樹さん。
前編では、1998年新国立劇場のこけら落としとして上演されたオペラ《アイーダ》について、ゼッフィレッリが語っています。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

Franco ZEFFIRELLI(1923-2019)
イタリア・フィレンツェ生まれの映画監督・脚本家・オペラ演出家・政治家。
新国立劇場開場記念公演「アイーダ」カーテンコールより 撮影:三枝近志

聴衆がエジプト的なフィーリングを得られるかが大事
――今回の《アイーダ》は、スカラ座で演出なさって以来35年ぶりの演出ということですが、35年前と今回の違いについてお話しいただきたいと思います。
Z: 私が思うに、あの《アイーダ》は、今世紀を代表する最高のものだったと思います。
デザインは私ではありませんでしたが、当時の最高のデザイナーでしたし、とにかく、あの当時としては、我々のアプローチはかなりショッキングなものでした。でも私たち自身は、特別に斬新なもの、近代的なものにしようと意図したわけではなかったのです。
当時はローマとレニングラードで公演が行われました。あれ以来、私自身《アイーダ》の演出をしませんでした。そして3年前に日本の東京の新国立劇場からの演出依頼を受けて、やってもいい頃じゃないか、と思ったのです。
私の基本的なコンセプトはあのころと変わっていません。しかし、私自身に多少の変化があったのと同様に、周りの人々、時代そのものが変わりました。でも、音楽はいつでも、常に演技、キャラクター、動きまでをも写し出します。
私自身はほとんど変わっていません。そして始めのころからその方向性も変わっていません。でも、今回の方がずっと現代的である、ということはできますし、その人物描写により重きが置かれていますし、ずっとスペクタクルに富んでいます。またこの人物描写にしても今回のようにすばらしいキャスティングに恵まれたからこそ可能だった、ということができます。つまり、前ならドミンゴしか思い浮かびませんでしたが、歌うだけではなくて、ルックスもよければ、演技もできるような知性を兼ね備えたクーラのようなテノールはまれでしたからね。そしてグレギーナにしてもそうですし、ベーカーもそうです。このようにすばらしい声楽家であり、演技者である人々に囲まれて、今回の公演が、以前には不可能であったもの、ドラマが、実現できたのです。

新国立劇場開場記念公演「アイーダ」 撮影:三枝近志

新国立劇場開場記念公演「アイーダ」 撮影:三枝近志
――実際にエジプトにいらしたり、かなり綿密に下調べなどをなさったのですか。
Z: もちろんですよ。私の書斎には、エジプトの本や資料が山ほどあります。そしてとても入念にいろいろなことを調べました。しかし、演出をする上では、そのエッセンスともいうべきものが必要となります。何もかも全てというわけにはいきませんから、それだけにポイント、ポイントを押さえる必要があるのです。聴衆が見て、エジプト的なフィーリングを得ることができるかどうか、それが大切なのです。ここでは強大な神殿、つまり建築物と、そこに生きる人々の描写が大切であると考えました。人間と比べて、エジプトの建物はおそろしいほど巨大なものです。そしてそれこそがエジプトだ、と、私は実際にその地を訪ねてみて、一層強く確信しました。人間と建物との割合の差、それがとても大きいこと、それがエジプトなのです。人々にとって、巨大な建築物、と言うよりもあの高い柱は、まさに天、神につながるものであり、人々の祈りが具現化したものなのです。私は舞台の上では、巨大な円柱を12本、効果的に使うことにしました。表裏を違えて使うことで効果を上げることもできました。でも、これが果たして忠実に再現したかというと、そうでもないのです。ある意味では創造の産物であり、エジプトのイメージ、想像の世界の中のエジプトなのです。
そして忘れてはいけないのが音楽です。本当にすばらしい音楽です! ピアニッシモのヴァイオリンで始まり、ピアニッシモのヴァイオリンで終わるすばらしい音楽。そしてさらにはその物語性、ヴェルディはこの物語の中の人物描写にとても力を注いでいました。中でもアイーダは見事に描かれています。そしてグランドオペラのもつ壮大さ、豪華さも、そのファラオの絢爛豪華な世界とぴったりです。もう一方で、このオペラの細かなディテールの質にもこだわりました。これは、細かなもの、小さなものにおいて、かなり質の高いものを誇っている日本文化の伝統があるからこそ可能なことでした。細かなディテールにこだわりながら、巨大な建造物を再現し、物語を展開させたのです。

ストーリーを明確に、聴衆が理解し楽しめる表現を
――ゼッフィレッリさんの演出を語るとき、その徹底したリアリズムと絢爛豪華さが話題となるのですが、ご自身にとってのリアリズムとはどんなものなのでしょうか。
Z: 私が思うには、ステージにおけるリアリティというものは……そうですね、昔は、ステージの上はあくまでファンタジーの世界であり、太った歌い手が歌っていれば、目をつむって想像すればかまわない、と言った風潮がありました。私は昔からそれは違うと考えてきました。舞台の上もファンタジーではなく、全てが真実であるべきなのです。私の描くキャラクターは、演技を含めて、全てにリアリティがなくてはいけません。そしてこのオペラの場合は、スペクタクル、絢爛豪華な要素も欠くことはできません。そして何よりもヴェルディ自身がこのオペラには豪華さを求めたのです。
――それにしても、そのリアリズムはまるでマジックのようですね。こうしてお話を伺っているとすごく細かいところを積み重ねて、その上でその世界を作り上げていらっしゃるようですが、そのマジックの秘密を少し教えていただけませんでしょうか。
Z: 作曲者の意図を大切にする、その伝えんとすることに忠実であることですね。この《アイーダ》の場合は、ヴェルディは、あくまでこのストーリー(芝居)を皆さんに見てもらいたかったのです。ここで展開される物語の面白さを聴衆に味わってもらいたかったのです。そして私はその作曲者の意図をそのままに聴衆に伝えるお手伝いをしているのです。このオペラの一番最初のところを思い浮かべて下さい。舞台の上には3人の人物しかいません。音楽が始まり、さらにはその音楽がめまぐるしく変わりこの後の運命を暗示します。(ここでメロディーを口ずさむ)アイーダは後から入ってきますが、私はここではこの3人以外の人物を出さないことによって、聴衆の目がこの3人だけに集中できるようにしました。今舞台で何が起こっているか聴衆のためにわかりやすくする、ということは私にとって大切な務めです。あの時代のオペラを、今日、このような形で舞台に上げるということは、良いことであり、とても意味のあることだと思います。つまり偏見ではなく、歴史的な事実、スタイルにもっと敬意を払うことができましたし、さらには、伝えたいこと、ストーリーを明確にしながら、聴衆が理解でき、楽しむことのできる表現、言語を用いることができたからです。
――オペラの舞台における制作上のテクニックについても少しお話し願えますか。
Z: 一応、私はそれが職業ですし、プロですから。自分で言うのも何ですが、私は今、世界でトップレベルのデザイナーだと自負しています。私は、かなり若い頃から本当に良いもの、すばらしいもの、いろいろなものをたくさん見てきました。そして、それらをただ漫然と見るのではなく、細かく観察をしてきました。こうして多くのものを吸収して、自らのものとしてきたのです。例えば、過去50年の間に、《アイーダ》―つをとってみても100以上のものを見てきました。そしてそれらの中から本当の最高のものだけを抽出し、私の個性をそこに足して、私の世界を作り出したのです。まねではなく、過去のすばらしいものを継承することも大切なことなのです。
――記者会見の時にミケランジェロの名前が出てきましたが、やはり、そういった伝統的な技術に強く惹かれるのでしょうか。
Z: ええ、何よりも、私はフィレンツェに生まれました。そしてそこで子供時代を過ごし、ルネッサンスは私の周りに溢れていました。後に芸術大学に進み、建築学を学びましたが、常に芸術に心を惹かれていました。そしてその後音楽と出会いました。こういったものの集大成とも言えるのが、今の仕事です。でも、私にとって、地上の神とも言える存在は、変わることなく、ミケランジェロであり、レオナルド(・ダ・ヴィンチ)です。
ミケランジェロは、力(パワー)であり、ダ・ヴィンチは神秘です。その神秘とは、幻想であり、夢であり、空想です。ご存じでしたか。レオナルドの描いている女性は皆、同じ顔だってこと。彼の母親の顔なんです。ミケランジェロは、また違います。そこには動きがあり、力がみなぎっています。
「音楽の友」1998年3月号より転載
関連する記事
-
インタビュー阪 哲朗が紡ぐ、喪失感を浄化するコルンゴルトの歌劇『死の都』の音楽世界
-
レポート井上道義が現役最後に取り組むオペラ《ラ・ボエーム》が秋に全国7都市で公演
-
読みもの続々 ワグネリアンのバイロイト案内 祝祭劇場で《パルジファル》がどう響くか疑似体...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest