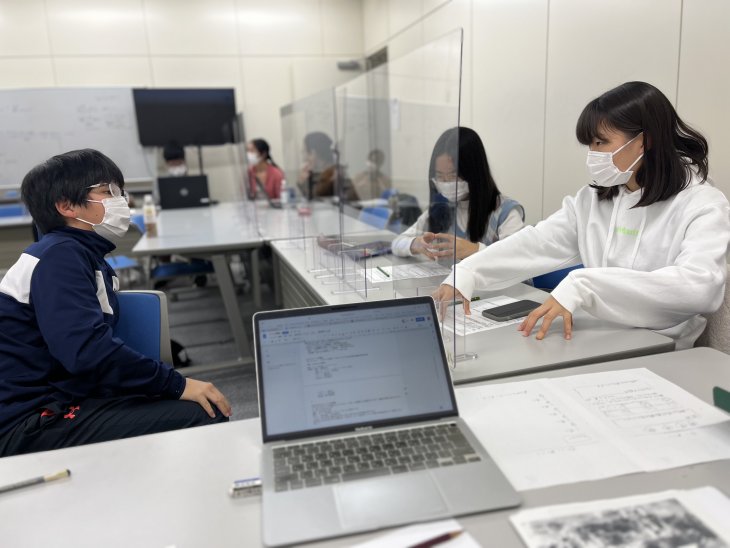仏文学者・水林章~語学で「自由」へと向かう作家。その音楽を経由した言語表現とは 後編

フランス語で小説を執筆するフランス文学者・水林章さんとの対話。後編では、フランス語で小説を執筆するようになった経緯や、日本とフランスにおける言葉の文化の違い、理想とするコンサートのことなどが語られた。

岡山市出身。京都市立堀川音楽高校卒業後渡仏。リヨン国立高等音楽院卒。長年日本とヨーロッパで演奏活動を行ない、現在は「音楽の友」「ムジカノーヴァ」等に定期的に寄稿。多く...
「語学を単なるコミュニケーションツールとせず、その襞の中に入っていく努力をすると、別の世界が開けていく」というフランス文学者の水林章さん。
後編では言語と音楽、日本語とフランス語、2つの世界を行き来する豊かさについて、さらにお話を伺った。
フランス語で小説を書くことになったのは偶然の賜物
船越 水林さんがフランス語で執筆された小説は広く愛読されていますが、母国語でない言語で書かれた作品が、これほどにフランス人の心を掴むのは、やはり驚異的だと思うのです。なぜフランス語で執筆を始められたのですか?
水林 偶然の連続です。まず、小説家ダニエル・ペナックの『学校の悲しみ』を翻訳したということがあります。彼とは仕事の過程でとても親しくなりました。翻訳完成間近の頃、ペナックさんの自宅を訪ねると、彼の一番の親友だという作家・精神分析学者のJ.B.ポンタリス(のちに、僕はポンタリスさんを〈J.B(ジーベー)〉と呼ぶようになりました)を紹介されたのです。
ペナックさんの家で夕食をともにしたとき、ジーベーは「どうして日本という遠い国で、フランス語に興味を持ったのか」などと無数の質問を投げかけ、僕は一つずつ律儀に答えました。すると、「今日の君の話は、優に1冊の本に値する。書いてみないか」と、誘われたのです。ジーベーは亡くなるまで、仏ガリマール出版のエディターとして知る人ぞ知る存在でした。こうして生まれたのが、フランス語と僕の関わりについて綴った『他処から来た言語 Une langue venue d’ailleurs』(未邦訳)なのです。

3.11によってフランス語を徹底的に生きてみるという選択が生まれた
船越 この『他処から来た言語』には、19歳からフランス語を学び始めた水林さんがフランス語を極めていく道のりが記され、湧き上がるようなエネルギーに満ちています。人の生き様というものは、経験をどう自分の糧とするかに表れるのだと感じました。この書で日本語を〈母語〉、フランス語を〈父語〉と表現されていますが、これはどういうことですか?
水林 日本語は、知らない間に身についた言葉、フランス語は勉強を重ねて自分のものになった言葉です。両方とも自分の一部だと思うのですけれど、日本語を話す自分とフランス語を生きる自分は、同じ人間ではないように感じます。言えることと言えないことの境界が異なるのです。
フランス語を勉強し続けるうちに、母語であるはずの日本語に対しても「エトランジェ(異邦人)」になった自分を感じます。フランス語を「父語」と呼ぶのは、自由の経験に向かう姿勢を父から学んだと思うからです。
船越 私の語学力は通常の生活に困らないという程度ですが、長年フランスで仕事をしているので、ピアノのレッスンに関してはフランス語の方が表現しやすいと感じます。日本語だと適切な表現がすぐに出てこないときがあり、そういう場合はやはり音で伝えることの素晴らしさ、音楽の雄弁さを感じるのです。その後、水林さんは音楽を中軸とした小説を次々と執筆されますね。

水林 僕は東京で暮らす人間ですから、フランス語での執筆はこの1冊で終わりにするのが自然な成り行きでしたが、書き続けることになったのには理由があります。
2011年の1月に上梓された『他処から来た言語』のプロモーションのために、僕はパリに向かったのですが、その日が実はあの3月11日だったのです。ド・ゴール空港に着くと、恐ろしい震災の光景が大画面で放映されていました。
1カ月ほどの滞在中「フランス語を話すだけでなく、フランス語で執筆する日本人がいる」と、いろいろな番組に呼ばれ、日本の状況についてインタビューを受けました。本のプロモーションは二の次という感じでした。
その時の一般的な論調は「この極限的状況の中でも略奪や暴動に走ることなく、規律正しく行動する日本人の称賛すべき市民精神」といったものでした。僕はまさに「市民」が存在しないことが日本の問題だと考えていたので、「日本人の市民精神」という言い方に根本的な違和感を覚えたのです。フランス人は何も分かっていないと思いました。
日本に帰ってから、その後の政治的・社会的展開を前にして、いやがうえにも日本のことを改めて考えなおすことになりました。日本語を括弧に入れて、フランス語を徹底的に生きてみるという選択はこうして生まれたのです。

関連する記事
-
イベントリーズ国際ピアノコンクール2024 出場者と配信リンクまとめ
-
イベント「第18回難民映画祭」で指揮者グスターボ・ドゥダメルのドキュメンタリーが日本初上...
-
記事川崎市×ザルツブルク友好30周年! 記念公演や、子どもたちが企画したモーツァルト...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest