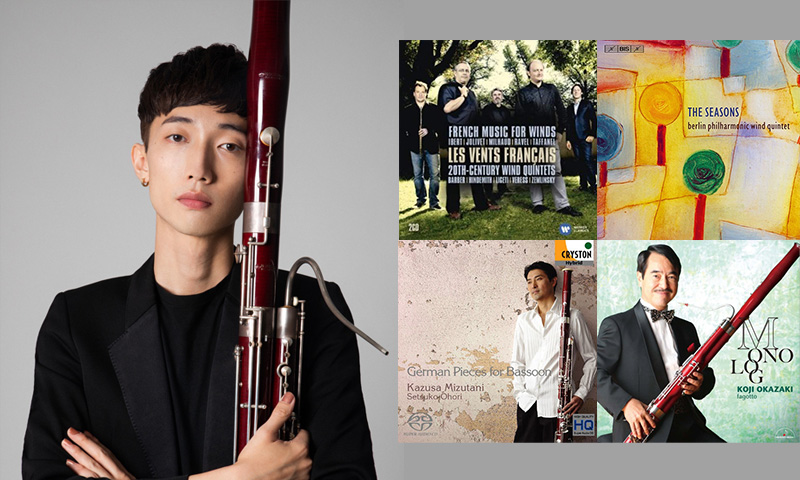博報堂が企業のコンサルティングに室内楽を導入! アンサンブル型の組織をつくるための音楽ワークショップ

働く人にとって、仕事場での人間関係は大切。組織にとってみても、コミュニケーションが活性化すれば、いい仕事につながり得るため、配置換えをしたり、席の固定をやめたりするなどは多々見受けられる。
だが、ここでは一風変わった室内楽を取り込んだワークショップを、企業のコンサルティングの一環として行なっている、博報堂の森泰規さんに迫った。
一般企業のコンサルに弦楽四重奏のワークショップを
日本を代表する広告会社のひとつ、博報堂。そこに弦楽四重奏や自身のクラリネットを加えた五重奏を使って、組織を活性化しようとする人がいる。ブランド・イノベーションデザイン局の森泰規さんだ。
初めて知ったときには、奇をてらった方法のようにも思えたが、そのワークショップを見学すると、編集部の想像を超えて参加者は湧いていた。

第1部はコンサート。1曲目は、桐朋学園音楽大学を卒業して数年のメンバーからなるアミクス弦楽四重奏団に森さんのクラリネットが加わり、モーツァルトのクラリネット五重奏曲K.581を演奏。
2曲目は森さんが抜けて、ヤナーチェクの弦楽四重奏曲 第1番「クロイツェル・ソナタ」を熱演した。
そして、第2部では、森さんがワークショップのファシリテーターとなり、以下の構成で進められた。
1.演奏を聴いた印象のもとで、自分を振り返る
休憩時間を挟み、考えを熟成させる。

2.画像投影法による言語化(ストーリーテリング)を行なう
さまざまな幾何学模様が描かれた多数のカードを並べておき、参加者は1枚目は「今の自分たち(仕事・会社)の姿」、2枚目は「これから、こうありたいと思った自分たち(仕事・会社)の姿」、3枚目は「ありたい姿に向かっていくために、捨てなければならないと感じたもの」というお題に合わせて、イメージに合うものを選んでいく。
なぜそのカードを選んだのか、その絵柄が仕事でのどういう状況を表しているのか、個々にチームで発表する。





3.皆で共有し、組織のこれからを考える
さらに全員の前でチームごとに発表をして、自社や自身の仕事の在り方の改善につなげていく。

ここでお伝えしておきたいのは、今回の森さんのクライアントは自動車物流という運送のプロたちだということ。大半はクラシック音楽をほとんど聴いたことがない、生演奏に触れたことがほぼないという方たちであった。通向けと言われることも多い室内楽の、若い演奏家たちの雄姿を見て、どう感じるのか。
編集部員2名で見学させてもらったが、みなさん、非常に前のめりで、観察といってもいいほど集中していた。
そして、幾何学模様のカードを使った発表では、目の前で室内楽を観て聴いて感じたことを織り交ぜて話す人が多く見られ、自身の考えがリフレッシュされたり、気づきが得られたりと、実り多き結果であったようだ。
Q.学んだこと、感じたことは?
- 業務に関係ない分野からも自分たちのおかれている状況を分析できるんだという驚きを感じた。また、日々の業務に埋もれているのではなく、仕事を早く切り上げてでも、いろいろな世界を見ることの重要性を学んだ。
- 5人の音がきれいに揃うのはなぜなんだろう。じゃ、仕事だと、2人でも何かをきれいに終われないってどうなんだろう。
Q.日々の仕事にどのように活かせると思いましたか?
- 仕事をしていくうえで、楽団のみなさんのように、相手の間合い、相手の行動をみてから自分のアクションを起こすことでチームとしてうまくいく。
- ひとつの考えに固執せずに意見を出し合いながら柔軟に対応する、意見を出し合える環境づくりをする。
Q.このワークショップをより良いものにするなら?
- 受けたいと思う人全員が受けられるようにしていただけたら、良いなぁと思います。なぜならどこにいる人でもどんな仕事をしている人でも、ワークショップを受けて何か感じることができると思うからです。

後日、なぜこのようなワークショップをするに至ったのか、実際のところ、室内楽を一般企業向けのコンサルティングに導入した成果はどれほどなのかなど、森さんにインタビューした。
博報堂の森さんにインタビュー!

——斬新なワークショップを見学させていただき、ありがとうございました! 森さんのクラリネットがプロ級で、びっくりしました。
それは大変に光栄なご感想です。演奏技量については、昔から吹いていたとはいえ、本格的なトレーニングに乗り出したのは5年くらい前です。
——30代後半に、もう一度クラリネットに目覚めたのですか?
中学校に入ったときに、NHKでモーツァルトの協奏曲を聴いて、おもしろい楽器だと思い、吹奏楽部で始めたんです。どうせならきちんとした先生に習いたいと思い、当時東京フィルの首席だった生方正好さんに楽器を習うことにしました。
高校では吹奏楽部には入らず、クラリネットの勉強は続けていたんですが、3年生のとき、生方先生が都知事選に出ている大前研一さんのポスターを指差して、「この人はクラリネットが上手だ、お前はこっちだ」と言うんです。楽器の技量を身につけることと職業は別だと。だから僕は音楽大学ではなく一般の大学に入りました。
2000年に博報堂に入社してからは、息も絶え絶えになってしまい、身の入った演奏はできなかったんですが、あるとき、どうやって自分の能力開発を見直すかを考えた時期がありました。当時非常にお世話になっていた音楽事務所に高橋知己先生を紹介していただいて、2004年くらいからレッスンを受けています。
作品を解析して、演奏で再現するということは、構想と実行力が両方必要なもので、その点で仕事と似ており、そのつながりが見えてからのほうが伸びています。
——なぜ博報堂に就職しようと思われたのでしょう?
すごく積極的に全世界のホールを回ったりしているアマチュアオーケストラに入っていました。そこは、大人数いてあまり出番が回ってこないから、下っ端は団内の広報誌を作ったり、演奏旅行の前の企画のまとめをしたりするんです。それで、だんだんこういう仕事が面白いと思ってきて、広告会社に入って働いてみようというドライバーの1つになりました。
卒業してしばらくは、オルフェウス室内管弦楽団(註:1972年からニューヨークを拠点に活動するオーケストラで、指揮者を置かずメンバーがリーダーを交代しながら運営)がまだ日本でもてはやされていたときに、指揮者を置かずに少人数でオーケストラ活動をしようと始まった団体にしばらく参加していたこともあります。
それぞれのプロフェッショナルがお互い協力し合う、室内楽の姿を示す
——今言われたオルフェウスなんですが、そこから今回の室内楽を使ったワークショップの着想を得たのかな、と思ったのですが。
そうです。オルフェウスの活動(註:企業や教育機関向けにコラボレーション・リーダーシップ開発をするプロジェクト)は、2000年前後に日本に導入されていて、今でも医療機関の方々にはそのメソッドが浸透しているところもあります。でも、ある段階以降から彼らに浸透しなくなって、どうして広まらなかったのかということをずっと考えていたんです。

日本でオルフェウスを広めようとしている人たちは、自分で楽器を演奏しないので、ライブ感や音楽の本当の魅力を伝えきれていないんだろうな、ということと、音楽の人が事業の人の立場で説明していないからイマイチピンときていないんだろうな、と。「これはやり方がかなり特殊だから、相当のところまでビジネスの文脈に翻訳できるスキルを持った人が出ない限り、広まらないだろう」と博報堂の先輩たちに言われました。
私が今ワークショップで実践しているのは、この2つの点を補うことで、彼らがやろうとしたものを前に進めようという性格があります。
それと、オルフェウス管弦楽団自体は、もちろん優れた芸術家のグループですが、アメリカ拠点の楽団の一つなので、なかなか日本で活動を把握するのが難しいのかもしれません。
——十分な成功例にならなかったのですね。それでも、博報堂のコンサルの一環に、同様のコンセプトで室内楽を使ったワークショップを取り入れようと思った。そのきっかけはなんだったのでしょうか。
私は、博報堂ではブランド・イノベーションデザイン局のディレクターとして、B2Bや家族経営のクライアントを中心に、組織開発やブランドマネジメントの業務を担当しています。
心を動かすメッセージや表現の開発は、もちろん博報堂の主力事業ですが、何かのサービスを提供して納品したらそこで終わり、という性格が少なからずある。でも、「メッセージを開発しました」、「ロゴを作りました」ということによって何がしたいかというと、その会社が良い方向に向かってほしいわけで、その組織が元気になったのかどうかが一番大事。
それらを理解した社員さんが実際に行動していくこと、その行動につながる戦略を考えること、これらはもっと重要なサービスです。どうすればこの会社が良くなるのか、と考えたときに、やはり一人ひとりのもつセンスや努力があったりするんですが、もっとお互いに協力し合えば良くなるのに、と思うことが増えてきました。
今は一段進んで、社会とのかかわりをもっと増やしていくという視点から、「オープンイノベーションの社会実装」というところへ業務を進めていこうとしています。
——お互いに協力し合う、という部分で、室内楽の例が当てはまるということ?
はい。一般に、個々のプロが経験・実績と専門性を高めれば高めるほど、お互いにわかり合うことが難しくなると感じています。
たとえば、ものすごく専門的な物流のお客様を担当するとき、個々の部署がエキスパートなんですが、そうなればなるほど、この道のコンテナのプロ、この道の倉庫にある備品を管理するソフトウェアのプロ、という同士は話が噛み合わなくなってくる。一人ひとりが優れたプロになればなるほど協力が難しくなる、という現実を見ていた。これは良い人を2人連れてきても、必ずしも良いデュオにはならない、ということと似ているなと思いました。
室内楽は、一人ひとりがきちんとしたプロだけど、4、5人の単位で、1つの有機体やシステムとして成果を上げるということを見せると、何かヒントがあるんじゃないかと思いついたんです。
——なぜ弦楽四重奏だけでなく、ご自身のクラリネットも取り入れたのでしょうか。
既存のシステムが完成されればされるほど、新しい人を加えて変化していくことが難しくなります。でも、新しいアイデアを持った人を入れ、成長を促していくことがイノベーションの源泉となる。そのことをお伝えしてみたかったからです。
「完成されたシステムに対し、バックグラウンドや傾向のまったく違う要素を重ねる面白さと難しさを表現できないか」と考えていった結果、一流の音楽大学で専門的教育を受けたプロ演奏家のチームに対して、自分が入って実演すればいい、という結論にいたりました。
実際、クラリネットが発明されたとき、弦楽四重奏というシステムはすでに完成されていました。モーツァルトは後半の交響曲にしかクラリネットを用いておらず、ハイドンにおいては使いこなせたとはいいがたいながら、弦楽四重奏曲においては当時すでに名作が生まれています。
よって、モーツァルトの時代に設定すると、クラリネットは「新技術」のたとえです。当時の「新技術」だった道具を、作曲家はどうやって既存のシステムに組み入れて新しい形をつくろうとしたのか、そしてもとからスタイルを確立していた弦楽四重奏のメンバーはどのような工夫をして、この「新技術」を取り込んで発展していく必要があったのか、そうしたことも自分が加わることで実演できると考えたのです。

普段と違うネットワークを形成することで、クリエイティブな発想が生まれる
——クライアントの方たち向けのワークショップの3回目を見学して、弦楽四重奏の生演奏に触れることのなかった一般の人が、間近で室内楽の演奏家のやりとりを見聞きし、それを自身の仕事の状況に置き換え、新たな気付きを得て考えを深めていく様子は、とても興味深かったです。これには前段があったとのことですが、どのような流れで3回目に至ったのでしょうか。
第1回目はオフィス内の会議室を借りて、幅広い階層の皆さんにお集まりいただくものでした。第2回目は、弦楽四重奏の特徴を解説するため、配置の違いが成果に及ぼす影響、クラリネットが入るときにどこに入って吹くかなどをご説明していきました。ご出席者がより社長に近い経営層であっただけに、役員向けのリーダーシップ開発研修のようなものという特徴がありました。
取材された第3回目は多くの拠点、役職の方にご参加いただき、コンサートとしての性格が強くなっていたと思います。室内楽に触れていただいた皆さんの交流(社内の専門家同士のネットワーク形成)にアクセントを置いています。
——これは、会社での日常にまで変化を起こせるものなのでしょうか。
実際に変化があります。個々の事業の専門家同士が本気で話し合いをするようになりました。
たとえば、A地区のマネージャーはB地区のことにあまり関心がないというようなことはありますよね。でも横で見ていてこのやり方は違うとか、「前こうだったから」じゃなくて変えていかなきゃだめだ、などと話し合いの場をもつようになりました。ある会合に出させてもらったら、ベテランの幹部職の方が本気でぶつかっているんです。その様子をお聞きしていると、どちらも真剣に仕事の話をしていて、周りが止めに入っているようで、止めていないんです。
クライアントさんにとっては、「このレベルの人が本当のところの一番大事なことを意見交換するチャンネルがあったほうがいい」と思っているんですね。でもなかなかできるようで、できない。だから周りが止めに入らないんですね。このシーンを見ていて、部門間のネットワーク形成は定性的な姿ではありますが、「効果があったな」と思いました。
クリエイティブな発想をもつことのメリットは、普段と違う人間関係(ネットワーク)を形成するきっかけができることです。専門外のあるいは部門外の方と知り合いになる機会や、同僚の意外な一面を知ることを通じて成果を創出することが増える、ということは一定の検証結果を得ています。
たとえば、ボストン近郊にもシリコンバレーにも、人的資本・資金の地理的集積という条件だけでなら同様のものがありながら、シリコンバレーだけが成功した背景には、研究者同士の情報交流が盛んで人材交流が果たされていたという報告があります(サクセニアン『現代の二都物語』より)。
お金と賢い人、という条件だったらボストンにも同じものはあったけど、交流の形が違うからボストンにシリコンバレーはできなかった。
専門家は自身の専門性が高まるほど、自分と同じネットワーク内部での交流よりも、別分野の専門家との結びつきが強くなる、ということを示した報告もあります(グラノベッターやペリー・スミスの有名な論文です)。
この種の成長を創り出す関係性は、社会関係資本(ソーシャルキャピタル)と呼ばれています。実際このことは、日本で私が実施した調査の結果でも裏付けられています。「自分のアイデアやリソース、ナレッジを職場内に進んで共有している」という回答は、「今の仕事は、世の中や周囲から良い評判を受けている」との回答と有意な相関がありました。関係の質が高い方も仕事の評価が高いのです。
私もこの活動を続けていくうえで、クラリネットの先生のみならず、若手の演奏家のみなさんが協力してくださったことも大きいです。そうした『仕事外の専門家』『若手』というキーワードもまた、私自身の業務をより創造的にした「関係の質」であり、かけがえのない「ソーシャルキャピタル」だったと思います。
クリエイティブな活動をしている人のほうが、仕事でも成果を出しやすい
——「クリエイティブな活動をしている人がいるほうが、お互いに助け合い、成果を出せる会社になりやすい」という研究が示されたとあります。この研究では「クリエイティブな活動」とは何を指し、なぜ成果に結びついたのでしょうか。
すでに研究分野でも定義が難しくなっているようですが、「広範な感性・嗜好性・行動様式を指し、絵を描く、音楽を聴く(弾く)、住居の内装に工夫をするなどや、ユーモアのセンス、余暇時間の楽しみ方の工夫なども含めるもの」というようなものになります。
北米の研究では、クリエイティブな活動をしている人ほど、業務責任範囲を超えても自発的にお互いを助け合う行動を取ることがわかり、かつ業務上の成果も高いことを示されています。
なお、私が実施したアンケート調査でも、クリエイティブな活動をしている人のほうが仕事の評価が高い(という実感がある)ようです。
——森さんご自身も、いちばんの趣味であるクラリネットを利用して、クリエイティビティを高めている?
そうありたいとは思っています。
自分が好きで楽しいことは、成果が出なくても、周囲が止めても、人はやるものです。そういうことの中から、次第に革新的な事例が出てくるのではないか。
クライアント企業では「上司がなかなかいうことを聞いてくれない」「理解が得られない」というお話をよく伺います。イノベーションを起こそうとしても、即効性のある成果ばかりが求められて成功しないというのです。
私は逆で、評価されたいという気持ちが原因で、イノベーションが起こらないと思っています。本当に好きなことをやっていく中から自然にイノベーションが生まれるというメカニズムに、もっと気が付いていただきたいと考えています。
私からみたクラリネットと同じ存在のものを、どんな人でも必ず持っているはずです。それに気づいて実行していけば、そのうちにイノベーションが起こるのではないでしょうか。
——好きなことを究めて仕事とつなげようとすることが、結果的にクライアントや博報堂に貢献することにもなると。
博報堂は、もともとクリエイティビティを中核的な競争力にしている会社です。
私個人の理解なんですが、ブランド・イノベーションデザイン局は、簡単にいうと新規事業をやりなさい、というところ。いきおい、「自分の仕事は自分で作りなさい」ということになります。
そのために何をするのか、それぞれ自分で工夫して考える。どうやって売り上げを達成するか考え、持っているものは全部使おうと思い、今に至った。上司は「音楽はいいですね、クラリネットを吹きなさい」と言っていたわけではなくて、「成果を上げなさい」と言っていました。そのための手段は踊りでもファッションでもいいんです。よって同僚たちが私の活動の本質に気づいて、同じように自分の得意技を生かして活動してくれればいいなと思っています。
私自身は、ワークライフ・ブレンディングと呼ばれる、自分の大切にしているものはプロ活動にもどんどん導入していく、という働き方をもっと周囲に伝えていくことが、クライアント企業や博報堂への貢献につながる。「キャリアとは人生そのもの」だと思っています。

演奏以外の実業で音楽を活かすには
——音楽をクリエイティブな活動とするなら、ただ好きなだけではダメなのかなと思うんですが、音楽活動はどのようにあるべきだと思いますか。
自分なりの考え方でいうと、「作曲家はこう書いたはずだ」というアカデミックな考え方(学術校訂)と、「我々は長らくこう演奏してきたから、体系や蓄積を大事にするべきだ」という演奏習慣の2つの考え方があって、いずれかによって硬直化していくことは、健全な発展を遂げないと思います。
例えば「学術的には、古典派ではトリルが上からが正しいのです」と習うと常にそうする方もおられるけど、本当にそれだけが正しいのかは考えてみたほうがいいと思います。良いものを作るために学術的根拠を規範としたほうがいい場合もあれば、先輩たちが作ってきた演奏習慣や、その場その場の文脈を参考にするほうが良い場合もある。よって、モーツァルトの協奏曲K622を聴いていると熟達した演奏家のみなさんは、ひとりひとりそれぞれ違います。毎回違うという人さえいます。
いまクラリネットを師事している高橋知己先生は、長らくドイツの管弦楽団で演奏された方ですが、演奏するたびに毎回違うということをとても大事にされる方です。自由さや即興性を許容することで、積極的なコミュニケーションと創造性が生まれていきます。お互いの働きによってリアリティが常につくりかえられていくんですね。
ただ、先生が指導されているのは毎回違えばそれでいい、という意味ではなく、同じことをしていても少しずつ生まれてくるわずかな違いを感じ取れるか、またそれに対して自分自身が対処していけるか、ということだと思います。
——つまり、クリエイティビティとは「変えていくこと」?
変化を受容して次の行動を描いていく、ということでしょうか。博報堂が掲げている「正解より別解」という概念にならっていうと、高橋先生はコンサートのたびに「別解」をつくりだしなさい、と教えてくださったのかもしれませんね。もちろん明らかにおかしいことならばそこは指摘を受けます。それは事業も同じです。
また高橋先生は「クラリネットを吹くかどうかは手段の問題であって、その鍛錬は確かに求められるけれど、本質的には芸術表現をやっているのだ」ということもよくおっしゃっています。これも手法と本質意義を混同しがちな会社の事業に通じるご指導です。
ただ、公私の最適な「ブレンディング」とはなかなか難しく、滅私奉公みたいに自分を殺してしまうことも、利己的な姿だけがみえてしまうことも、やはりよくないことです。ある企業の経営者の方は「それはかなり難しいけど、できなくはないよね。だからブレンダーという職業が成り立つんだ。ニーズはあるんだよ」とおっしゃっていました。
——音楽業界でこの活動が生かすとしたら、どんなことができそうでしょうか。
第一に、演奏家の皆さんは純粋に芸術にかかわるということに誇りと自信を持っていただいていいと思います。
桐朋学園大学音楽部でピアノ科を出られた小野啓太さん、ヴィオラの山本周さんはそれぞれ名手であるだけでなく、企画・人選において多大な協力をしてくださっています。
よく弦楽四重奏のメンバーで入っていただくヴァイオリンの山縣郁音さんは、同じく桐朋学園大学音楽部を卒業されて優秀な演奏家でありますが「この種の企業ワークショップに参加して、お客様との対話を通じ、自分の人生に自信が持てた」とおっしゃってミラノに留学されました。最近ご帰国されてまたご一緒に演奏していただいています。演奏家の方にも啓発効果があったのなら、光栄なことです。
続いて、このワークショップは私が提供するサービスの中でも、高いリピート率を誇っています。博報堂の提供する「クリエイティブな組織作り」ということの延長線上に室内楽という例示がわかりやすい、という構造が成立しているから、という面はやはりあると思います。
ただ、ビジネスの場面でわかりやすく説明するには、かなりの翻訳がいるのも事実で、今後この活動を広げていくには、純粋な音楽家だけでなく、音楽の素養がある経営者の方や、このような活動に共感してくださる音楽家の方が一緒になっていく必要があるでしょう。
より長期的な将来像としては、専門に大学まで音楽教育を修めた方々が、その素養を活かして事業の世界に参入されるということはあるかもしれません。進路として演奏以外の実業を勧める流れも音楽大学には増えているように思います。
音大生の皆さんが実業界に参加するということの流れが出るとすれば、ひとつ意味を持ってくるかもしれません。機会があればそうした音大生の皆さんを対象にした常設講座をやるとどうなるだろう、と思うことはあります。
——このワークショップにタイトルをつけるとしたら、何になりますでしょう。森さんは、音楽を手段として組織に変化をもたらすことをされていると思いますが、一般の人が読んだときに個人で何か応用しようとすると、現実的には難しいのかなと思うんですが、どう思われますか。
そうですね。実は、数多くのコピーを手掛けてきた博報堂のコピーライターの木村透さんとまさに、「君の活動にキャッチコピーをつけるなら何だ」と議論していました。「クリエイティビティでアンサンブル型の組織を作ろう」というような話をしています。もう少し検討を要するでしょうね。ちなみに、オルフェウスのことを紹介したセイフターさんのご本の原題は Leadership Ensembleです。なかなかいいコンセプトだなと思っています。
ディレクターがいてその通りに動くような標準作業に向いた組織より、個々の個性を引き立たせながら、それでいて全体像としても成果が出るような。
——その言葉は、私たちにとってはわかりやすいです。同じ楽器でも人が変われば違う音楽になりますし、その人たちが集まってチームの個性が作られる、というのはイメージしやすい。組織の大小に関わらずできるものだとしたら、小さい組織、たとえば私たちの編集部でもできることがあるのか、一般的に落とし込んだときに森さんじゃないとできないものでなく、何か応用できることがあればお伝えできればと思っています。
まずは一人ひとりがちゃんとしていることが大事ですよね。協力以前に、個々人がちゃんとプロとして自立しているかが大前提。
それと『ビジョナリーカンパニー』を書いたジム・コリンズという人の本の中に、「ライトピープル・オン・ザ・バス」という有名な言葉があります。つまり、正しい人をバスに乗せなさい、行き先を決めるのはそれからです、ということ。
これはものすごいことですね。だって、「チームも何も、合わない人は最初に降りてください」と言っているんです。それくらい自分のパフォーマンスを出し切って、その先に協力というテーマがある。これはどんなチームにもあるんじゃないでしょうか。

——当然のことだけれど、そう簡単にはいかない……。先ほどおっしゃっていた組織の硬直化について、ミドルクラスの人が受け入れ難いのは、やはりそれまでのあり方を守ることで生命を保っているからで、難しいですよね。
クリエイティブの対義語は、リスク管理だと考えるとわかりやすいかもしれません。ミドルマネージャーというのは、リスク管理しているほうが自分の立場が保全されるから、そういうふうに動いている。そうすることで、実際には会社が良くなっているという面もあるのかもしれませんね。
ある仕事で、日本の企業をもっとクリエイティブにするにはどうすれば良いのか、という話で3人くらい前に立ってもらったんですね。いろんな経営者にインタビューしていたところ皆さんがおっしゃったのは、「森くん、それは簡単だ」と。
「アメリカがどうしてクリエイティブだかわかる? それはリスク管理をしないから。日本の会社はリスク管理をゆるくすれば、すぐにクリエイティブになるんだよ。リスク管理をしているほうが利益が上がるから、そうしているだけのことであって、それは戦略なんだ」と言っていました。
良くも悪くもそういうことなんだと思います。クリエイティブだから何でもいいということではないでしょう。だけど、リスク管理とクリエイティブの加減やそれぞれの良し悪しをわかっておられるなら、状況に応じて調節できれば変化に応じた成果が出せるでしょうし、それも戦略ですし、私たちの考える「別解」です。
——なるほど。今回、音楽に親しんでいる私たちだからこそ、クリエイティブな組織のあり方をイメージしやすい側面もあるかもしれないと、モチベーションが上がりました。ありがとうございました!
関連する記事
-
プレイリストオーボエ浅原由香さんがオススメ! 木管五重奏ほかアンサンブルの音源
-
プレイリストファゴット皆神陽太さんがオススメ! アンサンブル/ソロコンテスト向きの音源
-
読みもの名手たちによるブラス・アンサンブルの話題がつづく!
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest