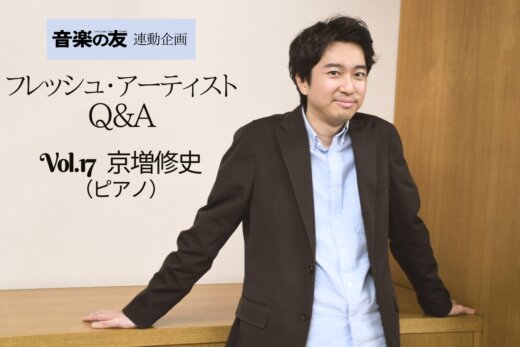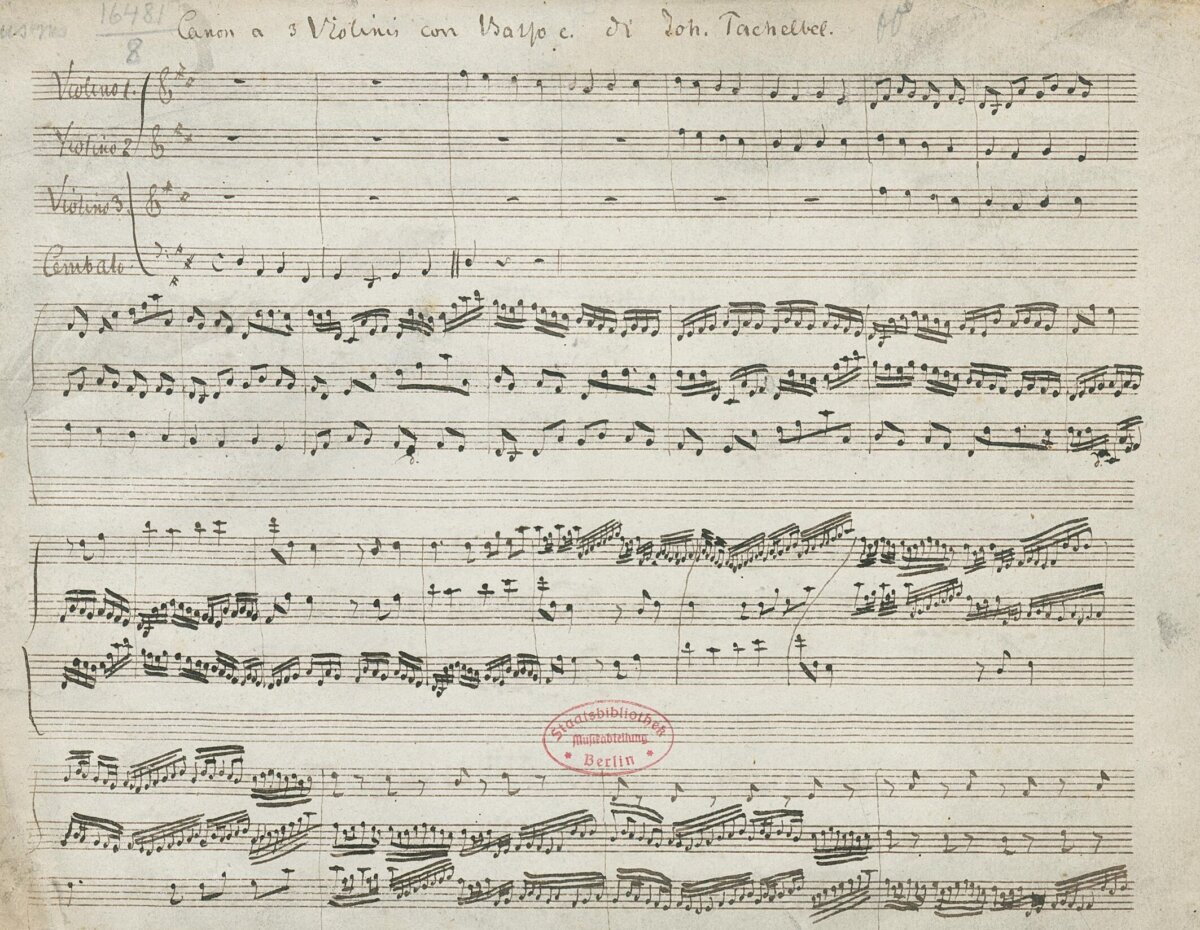世代を超えた議論と仲間意識が彩るベルギーのオーケストラ

世界各国のオーケストラで活躍する日本人奏者へのインタビュー連載。オーケストラの内側から、さまざまな国の文化をのぞいてみましょう!
第16回は、ベルギー国⽴管弦楽団でコンサートマスターを務める赤間美沙子さん。人と人との繋がりを大切にするベルギーでの活動や、ヨーロッパのオーケストラの演奏における特徴など、教えてもらいました。

東京・神楽坂にある音楽之友社を拠点に、Webマガジン「ONTOMO」の企画・取材・編集をしています。「音楽っていいなぁ、を毎日に。」を掲げ、やさしく・ふかく・おもしろ...
ベルギーの首都で活動する1936年創立のオーケストラ
——所属されているオーケストラについて教えてください。
赤間 ベルギー国立管弦楽団は、首都ブリュッセルを拠点にベルギー全土で活動しています。1936年に、コンクールを立ち上げたことでも有名なエリザベート王妃の後援のもとに創立されました。のちに初の音楽監督として就任したアンドレ・クリュイタンスのもとで、楽団のサウンドが作り上げられたそうです。
本拠地は、アール・ヌーヴォー建築の代表作に数えられるボザール(BOZAR)です。ボザールをはじめとするベルギー国内での演奏会のほか、定期的にヨーロッパ諸国でのツアーもあります。またエリザベート王妃国際コンクール創立当初からずっと本選会での伴奏を務めており、オーケストラにとっても伝統行事のようになっています。

2021 年よりベルギー国⽴管弦楽団コンサートマスター。これまでにゲスト・コンサートマスターとしてベルギー王⽴歌劇場オーケストラ、ブリュッセル・フィルハーモニック、ボルドー・アキテーヌ国⽴管弦楽団に招待される。2017 年より2年間、フランス国⽴⾳楽院オーケストラ(Orchestre des Lauréats du Conservatoire)でコンサート・ミストレスを務めた。2024〜25 年度、ブリュッセル王⽴⾳楽院にて講師を務める。
国内外の国際コンクールにおいて、 東京⾳楽コンクール第3位、 アンリ・マルトー国際コンクール第2位及びモーツァルト演奏特別賞、 ロン・ ティボー ・ クレスパン国際コンクールにてブーレーズ作品演奏特別賞、ヴァルナ国際コンクール第1位などの実績を収める。ソリストとして新⽇本フィルハーモニー管弦楽団、パリ⾳楽院オーケストラ、フランス国⽴⾳楽院オーケストラ、ベルギー国⽴管弦楽団と共演。
室内楽では、⽇本やヨーロッパ各地で意欲的に活動している。サロン・ド・プロヴァンス室内楽⾳楽祭(フランス)では、エリック・ルサージュ、ゴルダン・ニコリッチ、フランク・ブラレイ、ズヴィ・プレッサー、エマニュエル・パユらと共演。2022 年5⽉にはベルギー国⽴管弦楽団の⾸席奏者で結成した弦楽四重奏団として、ベルギー国王・⼥王陛下のギリシャ訪問に際して御前演奏を⾏なった。
3 歳よりヴァイオリンを始める。 桐朋⼥⼦⾼等学校⾳楽科、 桐朋学園⼤学⾳楽学部を経て、フランス・パリ国⽴⾼等⾳楽院(CNSMDP)第⼀および第⼆課程を審査員称賛付き満場⼀致の⾸席で卒業。同⾳楽院第三課程(アーティストディプロマ)を修了したのち、ケルン⾳楽⼤学 Konzertexamen 課程で研鑽、最優秀の成績で修了。
⽯井志都⼦、景⼭誠治、ジェラール・プーレ、ロラン・ドガレイユ、ミハエラ・マルティンに師事。またイタリア・クレモナ Accademia Walter Stauffer にてサルヴァトーレ・アッカルドの薫陶を受ける。
これまでにZilber Vatelot Rampal 財団から楽器貸与、Adami 財団から奨学援助を受ける。
©Jun Takumi
赤間 団員はベルギー人をはじめオランダ人、フランス人はもちろん、スペイン人や東欧出身者など多様で、日本人は私を入れて5人います。さまざまな文化の交差するベルギーという国、そしてブリュッセルという街を象徴するかのようです。
雰囲気は和気あいあいとしており、世代関係なく仲良く交流しています。団員それぞれがはっきりと意見を主張するため、時にはぶつかることも躊躇しない反面、仲間意識も強いように感じます。

——なぜこのオーケストラに入ろうと思ったのですか?
赤間 フランス・パリで長く勉強していたため、オーディションはフランス語または英語圏のオーケストラを中心に探して受けていました。どこかで環境を変えたいと思っていた当時の私にとって、就職は良いきっかけになったと思います。パリから近いフランス語圏ということもあってブリュッセルはとても魅力的に映りました。
ベルギー国立管のことはエリザベート王妃国際コンクールを通して知っていたため、コンサートマスターのポストに合格できたことは本当に光栄に思いました。
3公演目で披露した《シェエラザード》のソロ
——楽団員とのコミュニケーションは何語でされていますか?
赤間 私はフランス語と英語でコミュニケーションを取っており、指揮者とはフランス語圏の方でない限り、英語で話すことが多いです。第1ヴァイオリンの同僚はフランス語話者が多いので、セクションに発言するときは自然とフランス語になります。
入団当初はフラマン語(ベルギーで使われている、オランダ語の方言)の勉強も俄然やる気でいたのですが、フラマン地域出身の同僚たちは皆フランス語や英語が堪能なため練習する機会があまりなく、最低限の数字や単語を覚えたくらいで今まで過ごしてしまっています……。
——今のオーケストラでいちばん思い出に残っている演奏会や曲目を教えてください。
赤間 試用期間がはじまって3つ目のプロジェクトが、リムスキー=コルサコフの《シェエラザード》でした。美しいヴァイオリン・ソロで有名な曲ですが、このときは文字通りオーケストラでの演奏初披露というような緊張も相まって、特に思い入れを持って臨みました。幸せな思い出です。
同じく、初年度に作曲家のトマス・アデスが指揮したプロジェクトがあったのですが、彼の存在感とオーラに圧倒されながらも、そのおおらかで温かい人柄に強く感銘を受けたのを覚えています。
また年1回モネ劇場オーケストラとの合同企画があるのですが、そこで演奏したマーラーの「交響曲第6番」は、私にとって初めてのマーラーの交響曲だったこともあり、印象に残っています。

大きな流れに身を委ねて演奏する幸せ
——お国柄を感じたエピソードや日本とは違うなぁと感じる点を教えてください。
赤間 ベルギー人は家族や土地、内輪の繋がりをとても大切にするように見受けますが、日本との違いというよりも、むしろこうしたシンパシーの強さはどこか日本人に似た部分があると思います。
また、もちろん日本と比べてオーガナイズがゆるい、余計なおしゃべりが多いなど、やきもきすることには事欠きませんが、まともに取り合っていてはこちらの精神ももたないので、もし必要があれば大事なことはこちらから事前に聞いたり頼んだりしておくことで、冷静でいるようにしています。そして大概のことは何とかうまく収まるものです。
郷に入れば郷に従えで、在欧歴が長くなるにつれ、なるべくストレス対処をしながらトラブルをやり過ごすように努めています(笑)。
むしろ日本において求められる細やかさ、何事にも用意周到な姿勢の方が世界基準では珍しいのかもしれません。
どんなにこちらに慣れても、日本特有の丁寧さやきちんとした感覚は日本人として守っていきたいものです。ヨーロッパの人々の自由さ、ある意味での人間らしさに憧れつつ、日本人らしいこうした感覚を失わないようにと気をつけています。
一方で、時間を守ること、気遣いを喜ぶこと、相手の表情を見ながら話すことなど、対人関係におけるリスペクトの大切さは世界共通だなと思います。
——「この国に来てよかった!」と感じるのはどんなときですか?
赤間 音楽が立ち上がるときの立体感、またオーケストラ全体が音楽の大きな流れに身を委ねるときの香りや伸びやかさ、鮮やかさはヨーロッパ独特のものだと感じますし、その中で弾くときの幸せと刺激は格別です。
またこれはベルギーに限らないことだと思いますが、日本の文化や歴史について聞かれる場面が多いため、日本についてある程度しっかり知っておく必要があります。こうしたことから、少し角度を変えて日本という国と向き合うことの面白さを学ぶことができたのは、大きな収穫でした。


——おすすめのローカルフードがあれば教えてください。
赤間 ベルギーといえばチョコレート、ワッフル、ビール、フリット……というイメージだと思います。実際その通りで、あまりサプライズはありませんが(笑)どれも美味しいです!
ワッフルやフリットはたまに友人といただくくらいですが、チョコレートはカカオを味わえるビターでシンプルな板チョコが好きでよく食べます、というより、もはや中毒です。
郷土料理でいうと牛肉のビール煮込みや、ヴォル・オ・ヴァン(鶏肉のクリーム煮、パイ包み)、コロッケもおすすめ。またブリュッセルは美味しいコーヒーが飲めるカフェがたくさんあるので、カフェにふらっと入ってお茶をするのも楽しいです。






関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest