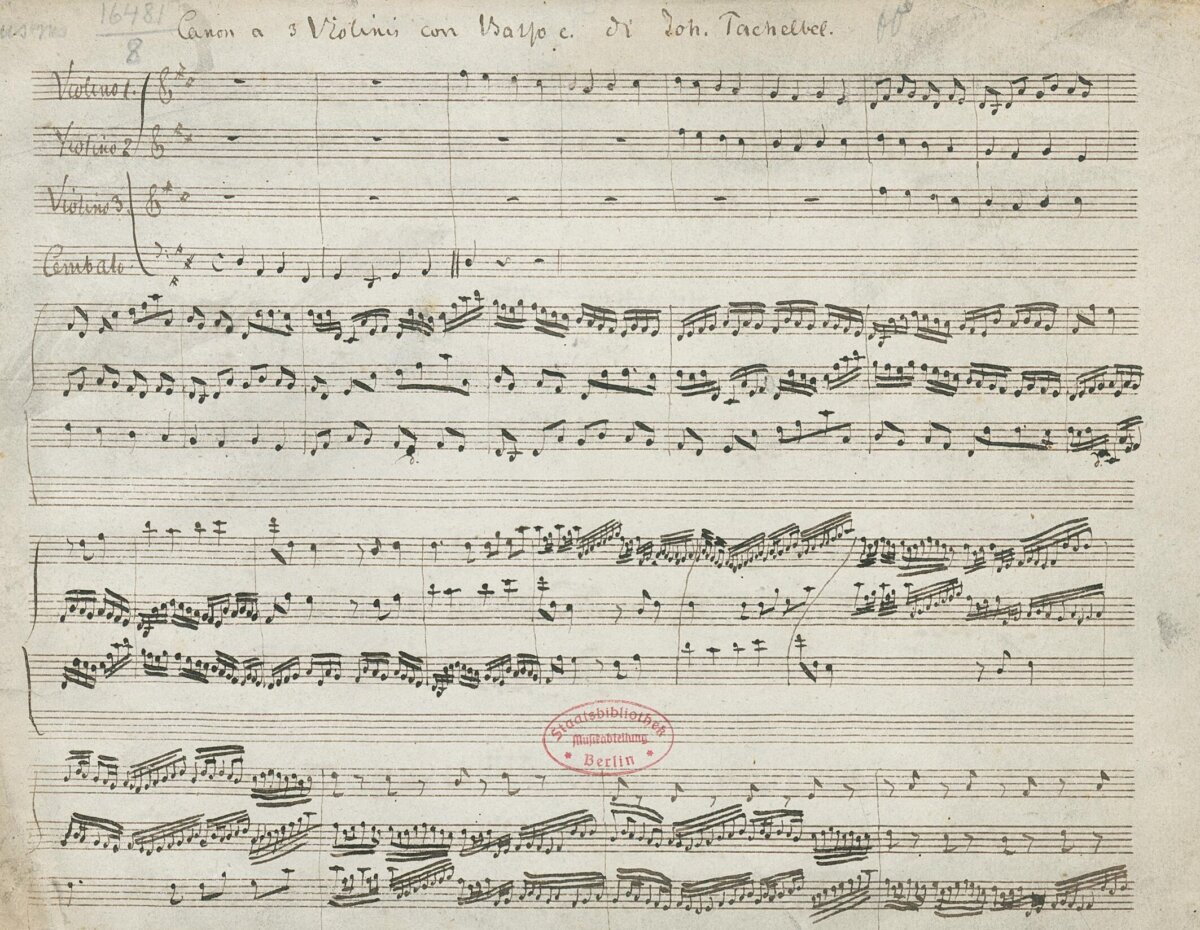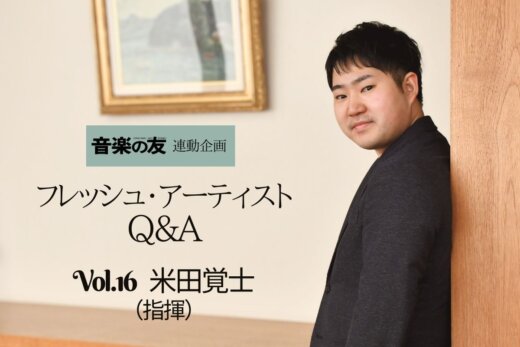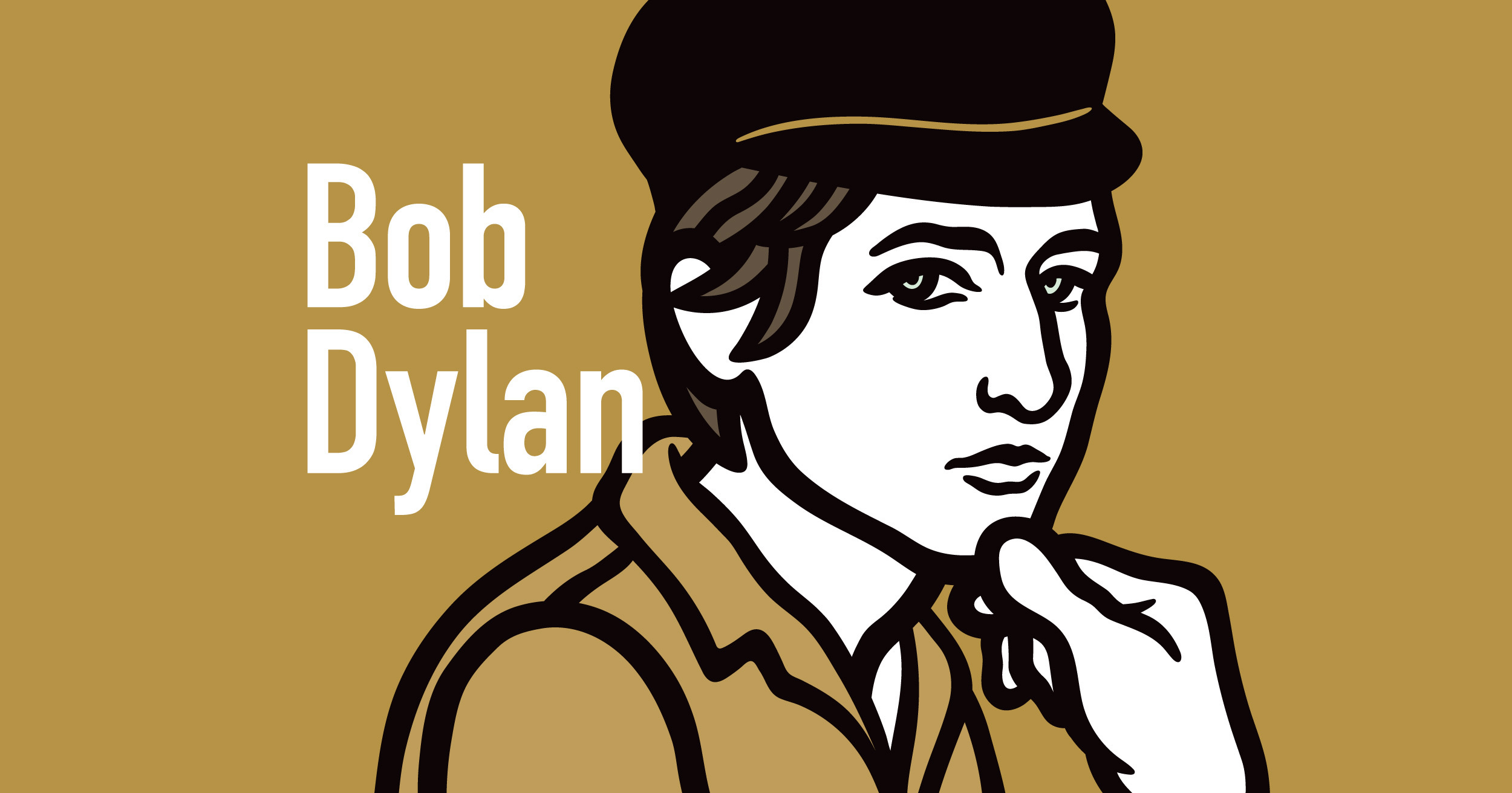アルヴォ・ペルト90歳の誕生日を祝う公演、チューリヒ歌劇場で2大スターの《マノン》

スイスの10月の音楽シーンから、注目のオーケストラ公演とオペラ公演を現地よりレポートします。

1941年12月創刊。音楽之友社の看板雑誌「音楽の友」を毎月刊行しています。“音楽の深層を知り、音楽家の本音を聞く”がモットー。今月号のコンテンツはこちらバックナンバ...
取材・文=中 東生
Text=Shinobu Naka
全曲アルヴォ・ペルトの公演にパーヴォ・ヤルヴィ、五嶋みどり
今年90歳になったアルヴォ・ペルトはエストニアを代表する作曲家である。今年の「オーパス・クラシック賞」でも、その生涯にわたる功績を讃え、「特別功労賞」が授与された。
10月19日チューリヒ・トーンハレではエストニア祝祭管弦楽団が全曲ペルト作品で記念碑的公演を行なった。指揮は当楽団を2011年に創立したパーヴォ・ヤルヴィで、ペルトとは父ネーメの代から家族ぐるみの付き合いだという近しい視点からの集大成であった。
まず1964年作曲の《B-A-C-Hのためのコラージュ》でJ.S.バッハをペルトの美しい手法と、現代のカオスを暗示する表現とで交互に問題定義する。次に50年飛んだ作品の《白鳥の歌》では、悠々とたゆたう姿のなかに、「ラクリモーザ」(涙の日)が聞こえるようだ。
また50年さかのぼった《常動曲》でペルト独特の幻想的世界が完成された。《トリノの聖骸布》では運命的悲哀が、エストニアにしんしんと降り続く雪のように積もる。途中で客席から携帯電話が弱音だが長く鳴って、現実に戻されてしまったが、まるでその怒りをぶつけるようにクライマックスに達した。
ここでヤルヴィが絶大な信頼を置くMIDORI(五嶋みどり、vn)とエストニアの若手ハンス=クリスティアン・アーヴィク(vn)を招き、《タブラ・ラサ》がものすごい集中力で演奏された。ピアノ側の席だったせいかピアノが邪魔なほど、高音なのに深い音がMIDORIの海色のドレスとあいまって、海からの祈りに聞こえる。アーヴィクは無垢な音で応える。彼らが創り出した30分弱の世界は、ティンティナブリ様式(小さな鐘、ペルトが作った、三和音が分散してつけられていく様式)が生き、自然への畏敬と回帰が感じられた。
アンコールには「(2本のヴァオリンのための)パッサカリア」で応えた。その後、弦楽オーケストラのみで《主よ、平和を与えたまえ》で締めくくり、アンコールには団員たちが弾きながら歌う《エストニアの子守歌》で微笑と共に終演となった。
バンジャマン・ベルナイム、リセット・オロペサが出演した《マノン》
今シーズンから新しく総裁に就任したマティアス・シュルツ氏の手腕か、今をときめくソプラノとテノールをキャストに獲得したマスネ作曲《マノン》再演は、2019年のニュープロダクション初演時よりもフロリス・ヴィッサーの演出が映えた。
その最適なキャストとは、まずデ・グリュー役のバンジャマン・ベルナイムだ。母国語のフランスものを歌わせたら、現代最高のテノールだろう。前述の「オーパス・クラシック賞」で「今年の男性歌手賞」受賞時に歌ったウェルテルも、当歌劇場で好演した記憶が新しい。柔らかい声で甘く、情熱的に歌う彼の発声はデ・グリュー役でも光り、アリアでは断ち切ったはずのマノンへの愛が蘇ってくる様を切なく表現し、幕切れでは別れへの恐れ、マノンを守りたいのに守れない辛さがひしひしと伝わって来た。

題名役を歌ったのはリセット・オロペサだ。この演出ではヴィッサーが「現代で言えば “ボーダーラインパーソナリティー症”」とマノンの性格を定義しているように、序曲の間に、きらびやかな社交界に憧れを抱く少女マノンが父親に冷たくあしらわれる様子を描いている。それによって病的な不安定さを持ったマノンを、2019年のキャストだったエルザ・ドライジクも上手に演じていたが、セクシャルな魔力は感じられず、地味な印象となった。その後ハンブルク州立歌劇場でドライジグが演じたマノンはハマり役だと思わせたので、演出との相性も重要だ。その点オロペサはこのマノン像を輝かせ、不幸な心の翳りも表現した。二人の声もよく合い、愛を確認する二重唱では夢のように寄り添い、抗うデ・グリューに赦しと愛を懇願する二重唱は最高のドラマとなった。
指揮のセスト・クワトリーニも、歌手の長所を花開かせていた。レスコー役のヤニック・デブスはがんばりすぎて空回り気味だったが、ギロ役のダニエル・ノーマンは存在感を見せ、デ・グリュー伯爵のニコラ・テステも威厳で脇を固めた。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest