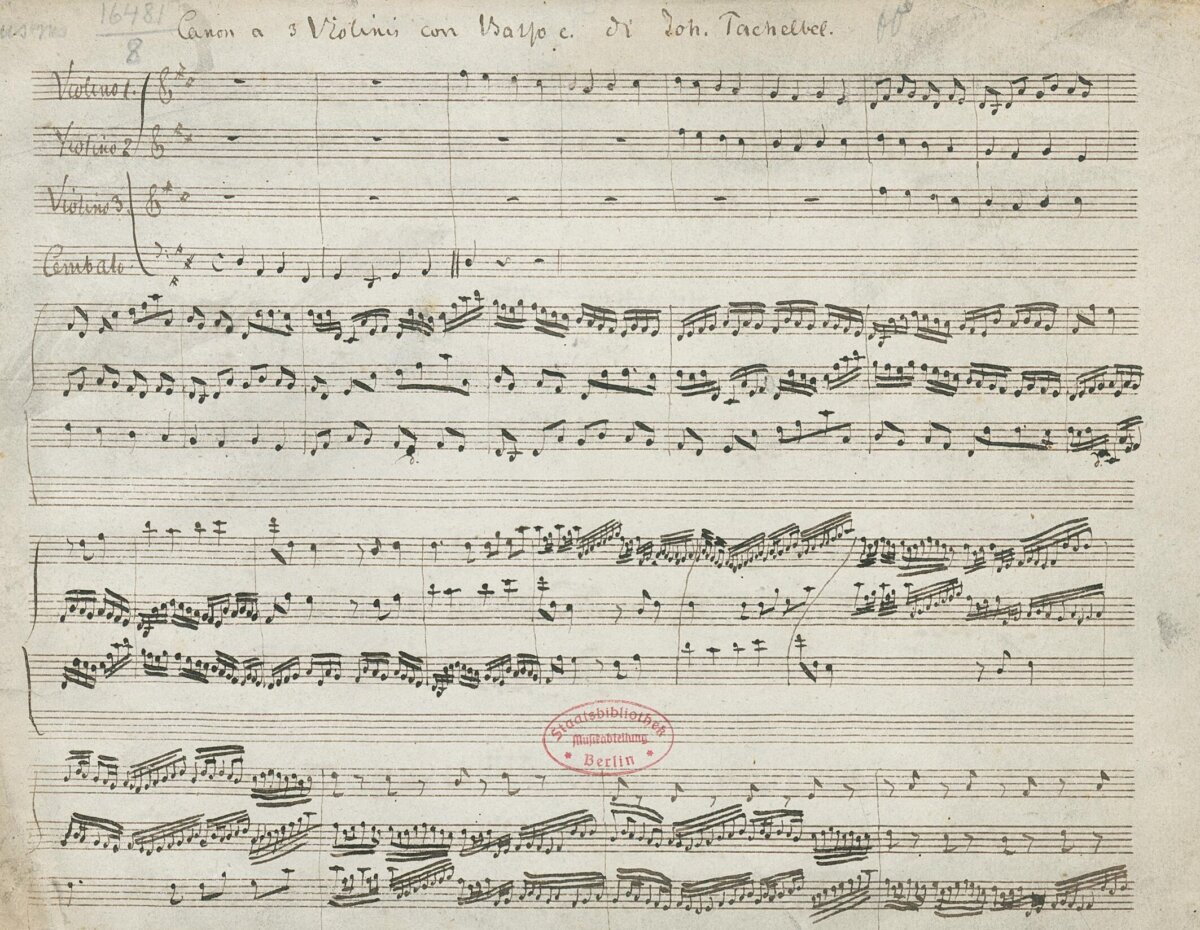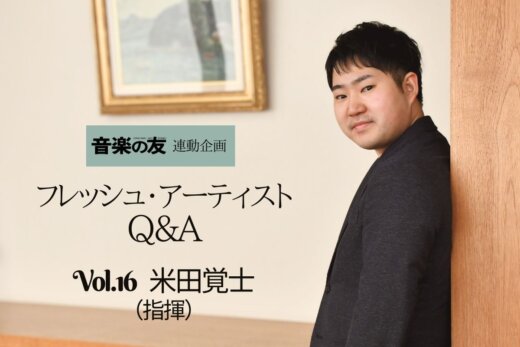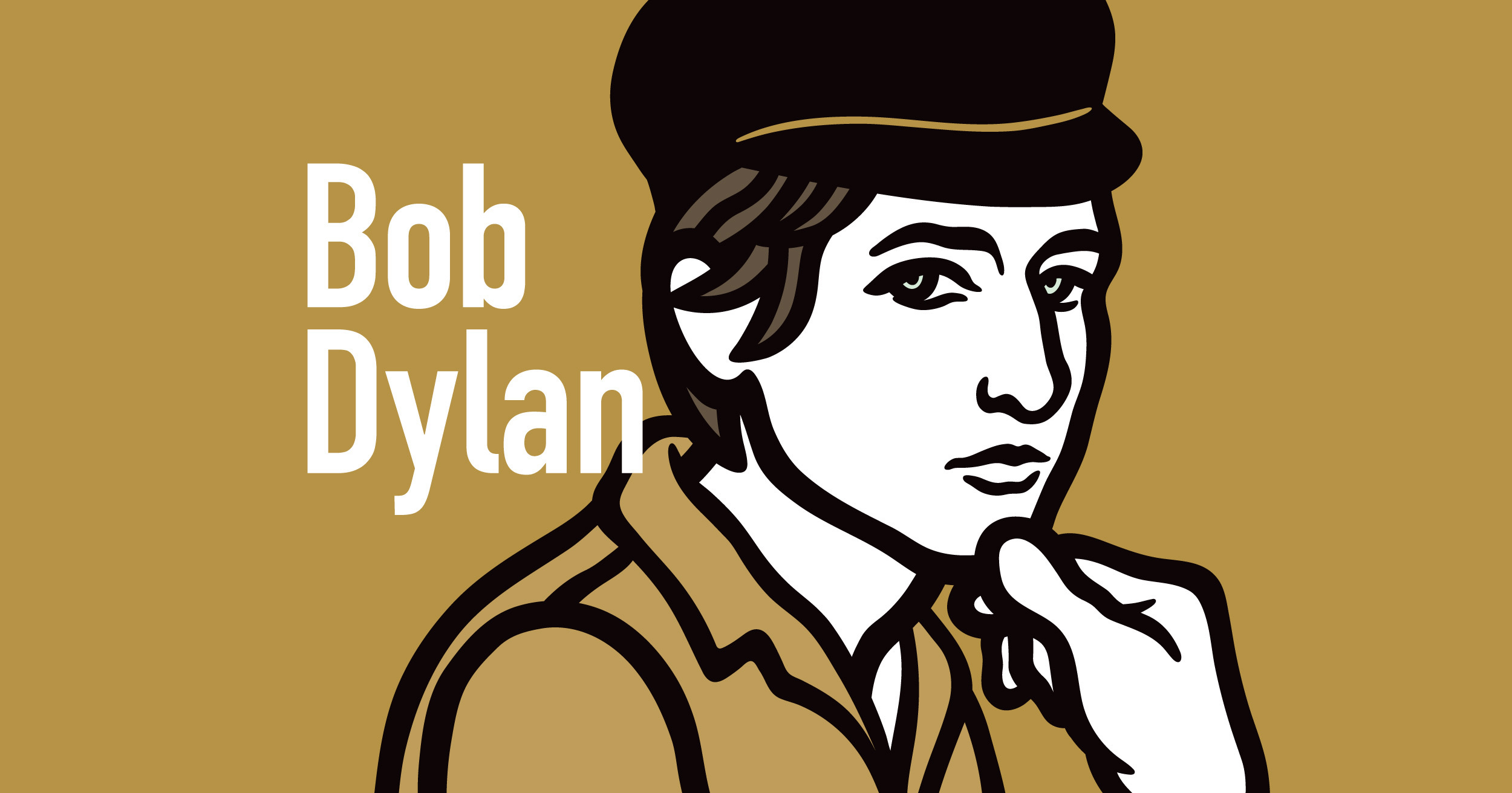メトロポリタン歌劇場が開幕、ニューヨーク・フィルがブーレーズ生誕100周年記念公演

アメリカの10月の音楽シーンから、注目のオーケストラ公演とオペラ公演を現地よりレポートします。

1941年12月創刊。音楽之友社の看板雑誌「音楽の友」を毎月刊行しています。“音楽の深層を知り、音楽家の本音を聞く”がモットー。今月号のコンテンツはこちらバックナンバ...
取材・文=小林伸太郎
Text=Shintaro Kobayashi
若い観客を集めたメトロポリタン歌劇場(MET)の開幕公演
メトロポリタン歌劇場はジーン・シェア台本の《The Amazing Adventures of Kavalier & Clay》(カヴァリエとクレイの驚くべき冒険)で9月21日に開幕したが、予想外の好評だったようで、最終公演となるはずだった10月11日の前日、4回にわたる追加公演を来年2月に行なうとともに、1月24日から予定されていなかった映画館での配信上映も行なうことを発表した。シーズン中に追加公演が発表されるのは異例中の異例である。
本作は、ピューリッツァー賞を受賞したマイケル・シェイボン作の同名小説《カヴァリエ&クレイの驚くべき冒険》を原作としており、インディアナ大学ジェイコブズ音楽学校との共同制作によって2024年に同大学で世界初演され、今回MET初演となった。
第二次世界大戦前後の米国と欧州を舞台に、プラハからナチスの手を逃れて米国に亡命したジョー・カヴァリエ(バリトン、アンドレイ・フィロンチク)と、ブルックリンに住むサム・クレイ(テノール、マイルズ・ミュッカネン)というユダヤ系の従兄弟同士が協力し、ナチスによって囚われた人々や迫害された人々を救うスーパーヒーローを主役としたコミック《The Escapist(脱出者、解放者)》をヒットさせ、米国に大戦参戦を促す。しかしジョーは、プラハから救出できずに家族を失ったことに絶望し、恋人に告げることなく軍隊に入隊、欧州で戦う。いっぽう、サムは自身のホモセクシュアリティと苦悩しながらも向き合い、ある俳優と愛を育むが、彼は戦場で帰らぬ人となる。二人は結局、彼らが創造したアートの世界だけでは世界を救えないという現実に直面するが、それぞれに再生の道を踏み出す。
長大な小説を2時間半あまり、あまりにも単純にまとめ過ぎたという評も少なくなかったが、ベイツの音楽はナチスの脅威を表すエレクトロニカのサウンドや、ジャズの影響が顕著な大戦前後のアメリカの描写など、豊かな表情で十分に魅力的に感じられた。
59 Studioによるビデオ・デザインを含むセットと照明を駆使したバートレット・シャーによる演出も、ブロードウェイでは見られないスケール感のある演出もMETにふさわしく、出演者の好演にも支えられ、見応えのあるものとなった。
METのプレス発表によると、観客の35パーセントがMETを初めて訪れ、5割以上が50歳以下、3割が40歳以下と、通常より若い観客を集めたという。今回も指揮を務めたヤニック・ネゼ=セガンの人気とともに、新作オペラに力を入れてきたMETの好調ぶりを示す数字であるかもしれない(10月2日所見)。

エサ=ペッカ・サロネンがブーレーズ生誕100周年を記念してみずからプログラム
グスターボ・ドゥダメル指揮による9月の演奏会の興奮が記憶に新しい10月初旬、ニューヨーク・フィルハーモニックにはエサ=ペッカ・サロネンが登場、ピエール・ブーレーズ生誕100周年を記念して自らプログラムした演奏会を指揮して人気を集めた。
サロネンの指揮は視覚的にもひじょうに滑らかであるが、2週間2種類のプログラムを通じて今回強く感じたことは、その精緻な滑らかさと、高い技術を誇るニューヨーク・フィルとの相性の良さである。
第1週、ブーレーズ「《ノタシオン》第4曲」、「同第7曲」、「同第2曲」のピアノ独奏版と管弦楽版に、ドビュッシー《管弦楽のための映像》からジーグと〈春のロンド〉をシームレスに連続して演奏したプログラムでは、ブーレーズのサウンドがドビュッシーの遺産があってこそのものであることが、精緻で磨かれたサウンドから、ごく当たり前のごとく聞こえてくる。ピエール=ロラン・エマールの知性あふれるピアノもぜいたくだ。後半は、ドビュッシー「ピアノと管弦楽のための幻想曲」(エマールp)と《海》が演奏された(10月3日)。
第2週は、ストラヴィンスキー「管楽八重奏曲」(ある意味、ニューヨーク・フィルの管楽メンバーのショーケースでもあった)、バルトーク「管弦楽のための協奏曲」をこのうえなくクリーンに聴かせ、そのどこか距離を置いたアプローチにも後年のブーレーズ到来を感じさせるものだった。
休憩後、ブーレーズ《リチュエル – ブルーノ・マデルナの追憶に》では、ホールのバルコニー各所にメンバーを配置し、録音のように精緻でありながら、録音では決して聴くことはできないであろう、立体的な音場で観客の集中度と興奮は最高潮に達した。
ロサンゼルスとのつながりが深いサロネンだからだろうか、《リチュエル》はベンジャミン・ミルピエがみずから率いるL.A.ダンス・プロジェクトの6人のメンバーに振り付けた舞踊との共演となった。ブーレーズの音場を聴くために舞踊は必要ないと考える向きもあるかもしれないが、サロネンの指揮の延長のような滑らかな身体表現は、逆に言うと身体表現の延長としての音楽を感じさせるものでもあり、興味深いものだった(10月10日、以上、デヴィッド・ゲフェン・ホール)。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest