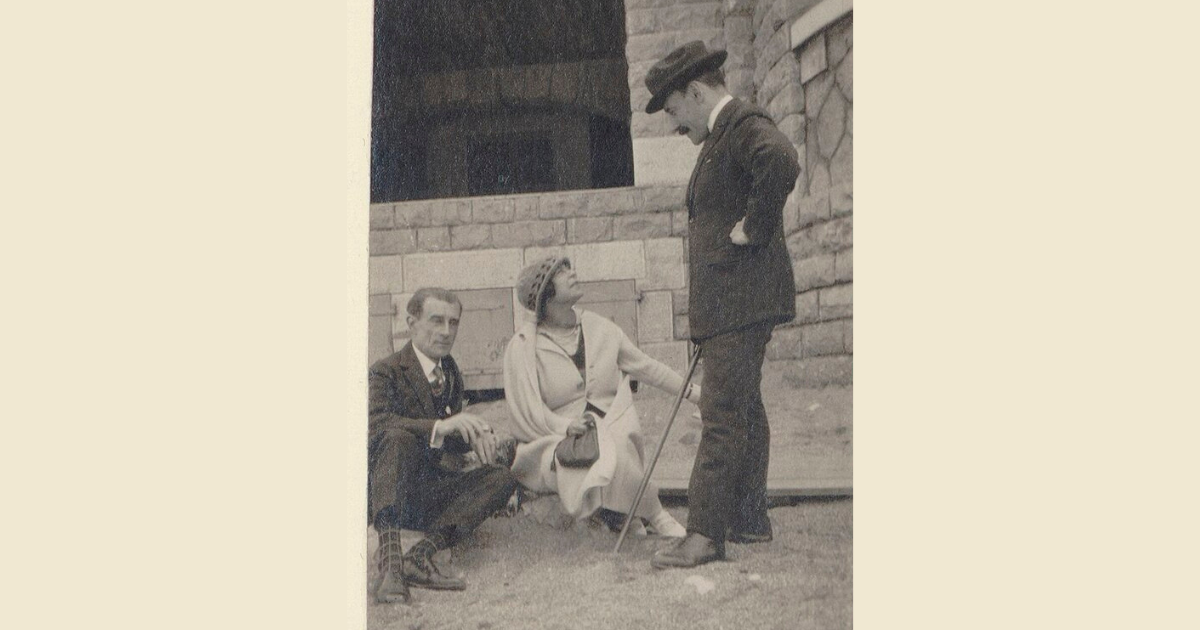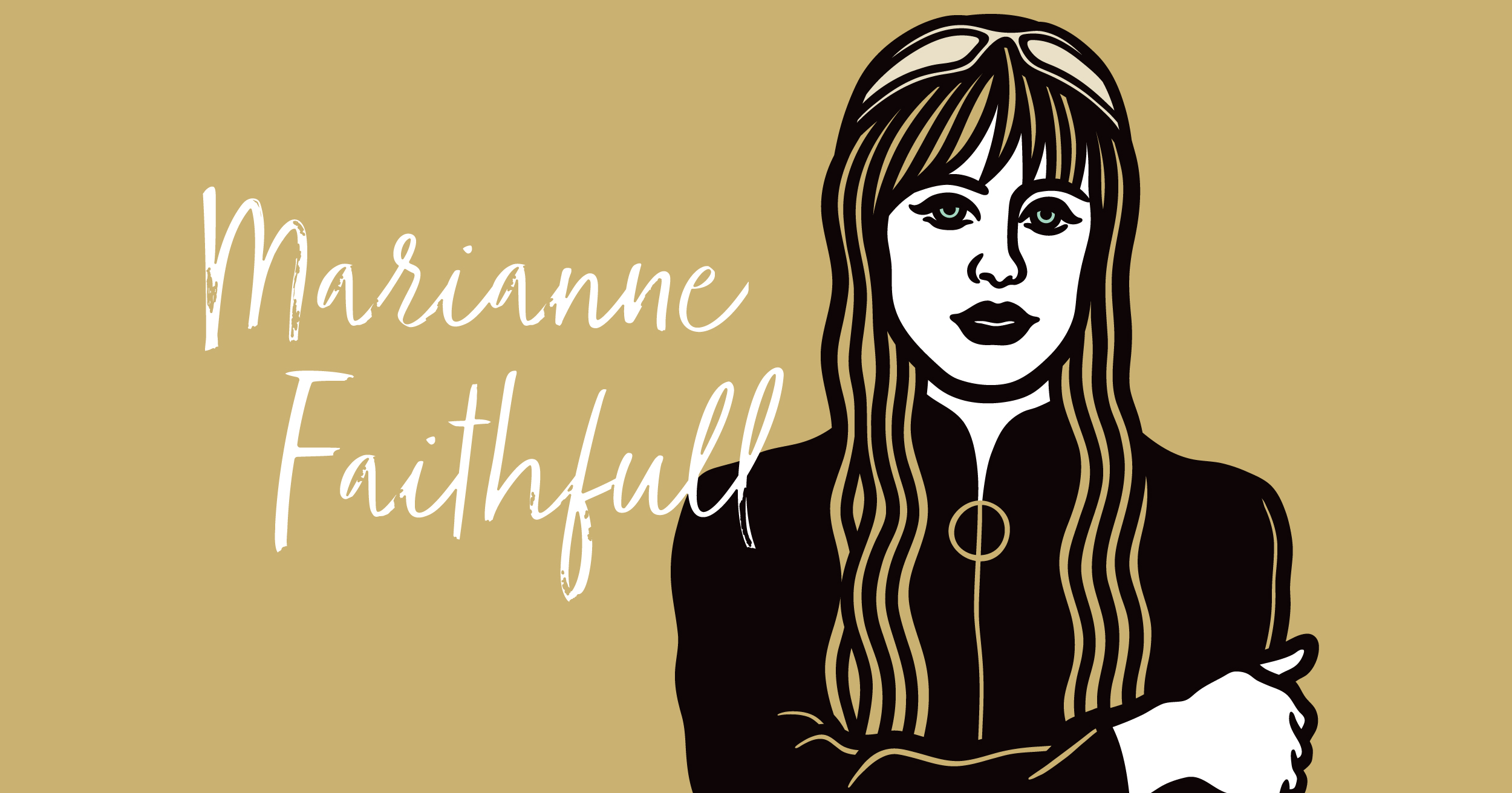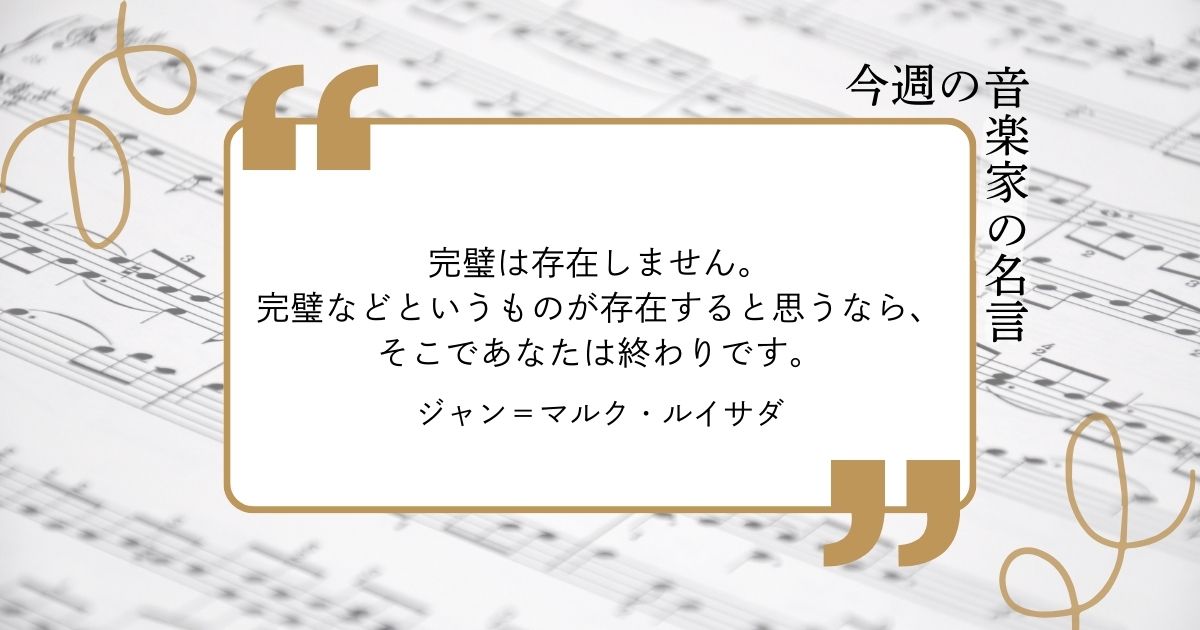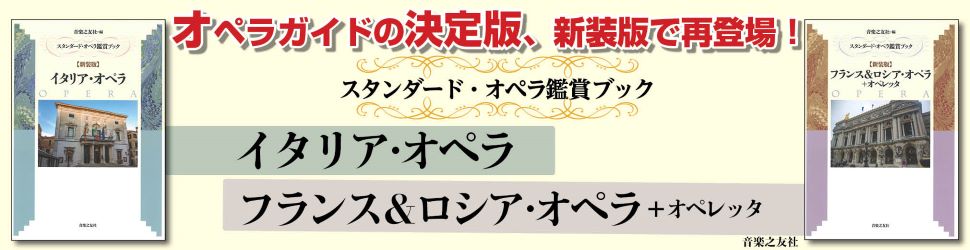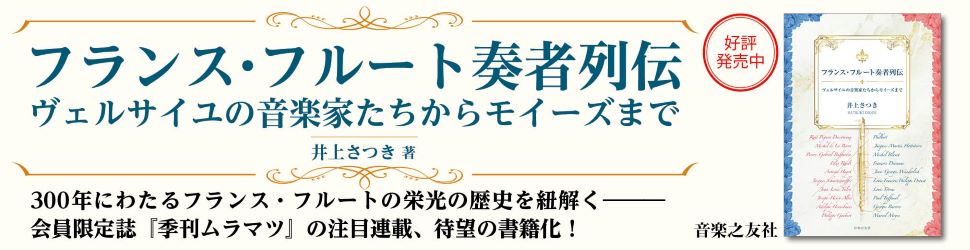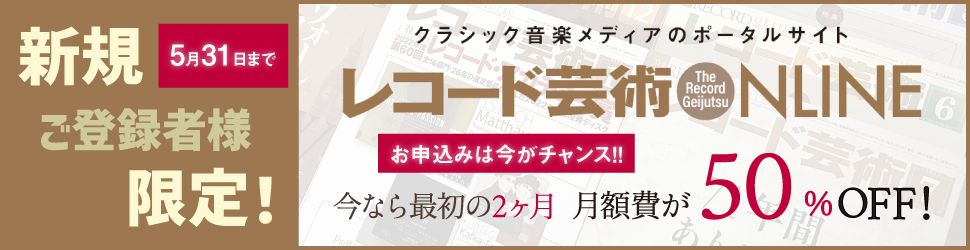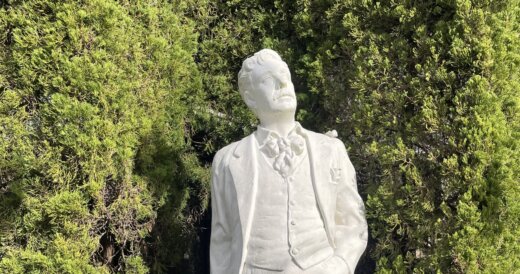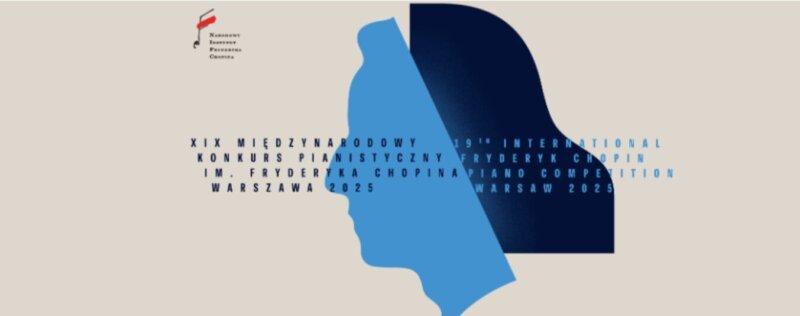【音楽が「起る」生活】今が聴き時~ダルベルト、パシフィックフィルハーモニア東京

音楽評論家の堀内修さんが、毎月「何かが起りそう」なオペラ・コンサートを予想し、翌月にそこで「何が起ったのか」を報告していく連載。5月は、ラ・フォル・ジュルネからハンソン四重奏団、ミシェル・ダルベルトの来日40周年記念リサイタル、パシフィックフィルハーモニア東京の第174回定期演奏会、シュレキーテを指揮に迎えるN響定期を予想。4月の結果報告は、ヤーコプス指揮ビー・ロック・オーケストラ、ムーティ指揮東京春祭オーケストラ、オロペサ(ソプラノ)のコンサートです。

東京生まれ。『音楽の友』誌『レコード芸術』誌にニュースや演奏会の評を書き始めたのは1975年だった。以後音楽評論家として活動し、新聞や雑誌に記事を書くほか、テレビやF...
何かが起りそう(5月のオペラ・コンサート予想)
1.ハンソン四重奏団 モーツァルト「狩」ベートーヴェン「ラズモフスキー」第3番(5/3・東京国際フォーラム)

さてどれを聴くか?「あれもこれも」ができるのが毎年恒例「ラ・フォル・ジュルネ」のいいところだが、1つだけなら弦楽四重奏2曲を聴くのはどうだろう。1時間のコンサートで2曲、それもモーツァルトとベートーヴェンの人気曲を聴くのは、気楽とまではいかないけれど、休日の愉しみとしては理想的ではないだろうか。演奏が、若手の、評判の高い四重奏団であるのもいい。ベートーヴェンの弦楽四重奏の現在の演奏はこうなのかと驚くかもしれない。
2.ミシェル・ダルベルト(ピアノ) ブラームス:パガニーニの主題による変奏曲、他(5/13・すみだトリフォニーホール)

プログラムが魅力的だ。コンクールで優勝して何年かの若いピアニストなら驚かないが、ダルベルトみたいなキャリアを積んだピアニストが弾くとなると、どういうことなのだろう?と興味をひかれる。わーっ、すごいテクニックだ!なんてびっくりするのとはまったく別の感興があるのではないだろうか。
何十年も前に聴いて、自分の関心の範囲からはずれていたダルベルトだけれど、「来日40周年記念」と銘打たれたコンサートに新たな関心を呼びさまされてしまった。リストの「《ノルマ》の回想」はどういう風に弾かれるのだろう?《夜のガスパール》との対比は?
3.パシフィックフィルハーモニア東京 第174回定期演奏会 飯森範親(指揮)ジャスミン・チェイ(フルート)(5/18・東京オペラシティ コンサートホール)


これが聴き時ではないか。指揮する音楽監督・飯森範親はコンサートでもオペラでも成功を重ねているし、演奏されるのはメンデルスゾーンの「ヴァイオリン協奏曲」のフルート版や、珍しいフェルディナント・リースの交響曲で、聴いてみたい気持ちをそそられる。オーケストラがいまの名称で再出発してから3年たつ。聴く頃合いというものだ。ジャスミン・チェイのフルートも、初めて聴くリースの「交響曲第3番」も、聴いてみる価値がありそう。
4.NHK交響楽団 第2038回定期公演 Cプログラム ギエドレ・シュレキーテ(指揮) 藤田真央(ピアノ) 《ばらの騎士》組曲、他(5/30・NHKホール)
藤田真央がドホナーニの「童謡(きらきら星)の主題による変奏曲」を弾くのも面白そうだが、やっぱりR・シュトラウスのオペラによる交響的幻想曲と組曲が聴きものだ。指揮するシュレキーテは東京でもう二期会の《魔笛》や読響のコンサートに登場していて、これならシュトラウスがいけるはず、と期待できる。N響とも合いそうだ。秋にウィーン国立歌劇場が《ばらの騎士》を上演することになっているが、その前に《ばらの騎士》組曲のモダンな演奏で気分を高めるのはどうだろう?
何が起ったのか(4月のオペラ・コンサートで)
1.ルネ・ヤーコプス(指揮)ビー・ロック・オーケストラ ヘンデル《時と悟りの勝利》(4/4・東京オペラシティ コンサートホール)⇒⇒⇒作曲当時の秘かな喜びが東京で実現された
絶対「快楽」の味方をしてやる。勇んで出かけたが道のりは困難だった。「美」を歌うスンへ・イムが魅力的なのは当然としても、「美」を正しい道に導こうとする「悟り」のポール・フィギエや「時」のトーマス・ウォーカーが説得力十分に歌う上、ヘンデルが少なくとも表向きは、正しい道に向ってこの立派なオラトリオをこしらえているからだ。
ウォーカーが説得力十分に歌ったからだけではない。
それでも初志貫徹できたのは「快楽」を歌ったソプラノ、カテリーナ・カスパーのおかげだ。第2部で敗色が濃くなった「快楽」のくり出す第23曲「棘がついたまま」(ヘンデルの絶望のテーマ・ソングというべき《リナルド》第2幕のアルミレーナのアリア「涙の流れるままに」と同じ歌だ)では涙にくれた人も少なからずいたのではないだろうか。声の艶も歌う技も申し分ない。敗者に優しいヘンデルが伝わった。
オペラがはばかられていた季節のローマで、それならこれだとこのオラトリオを作った音楽家や、存分に味わった聖職者たち、そしてその秘かな喜びを東京で実現させたヤーコプスとビー・ロック・オーケストラに感謝しよう。300年前にいたはずの、こっそり「快楽」の味方をした尊敬すべき枢機卿にも微笑みを送ろう。
2.リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ(4/11、12・東京文化会館 大ホール)⇒⇒⇒コンサート全体の威厳に頭を下げた夜
ムーティが振るだけで音楽の目鼻立ちがっくっきりしてしまうのは一体どうしてなのだろう? それがわかってやってきた満員の聴衆の前に《ナブッコ》の序曲がそそり立つ。前半の終りは《運命の力》の序曲だったが、おなじみの曲が聴衆の待ち望むとおりに現われ、会場の喜びが共鳴する。
コンサートが「ローマの松」の盛大な響きで幕を閉じると、曲にではなくコンサート全体の威厳に頭を下げるしかなくなる。「何が起るか」この夜は誰もがわかっていた。
3.リセット・オロペサ(ソプラノ)(4/10、13・サントリーホール)⇒⇒⇒オペラのヒロインを現出させた歌の力
底抜けに明るく、皆に好かれる連隊の娘マリーが引っ込んだと思ったら、恋に夢中の皇女マティルドになって現れた。しっかりした低音から柔らかな高音まで、なめらかに歌うソプラノは、歌の力によってオペラのヒロインになる。いまが盛りのソプラノの威力を、オロペサはまざまざと示した。
いくつもの歌が歌われるのでなく、《連隊の娘》や《後宮からの逃走》や《ルチア》など、オペラ全体を後ろに従えたヒロインの歌だ。定評ある《ルチア》は予想通りすばらしかったが、この夜の収穫はモーツァルトやグノーだった。
ただ、ムーティのコンサートでの序曲と同じように、オロペサの歌うアリアを聴くと、オペラの全曲を求めたくなる。


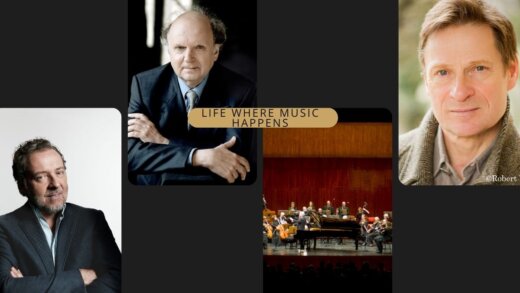
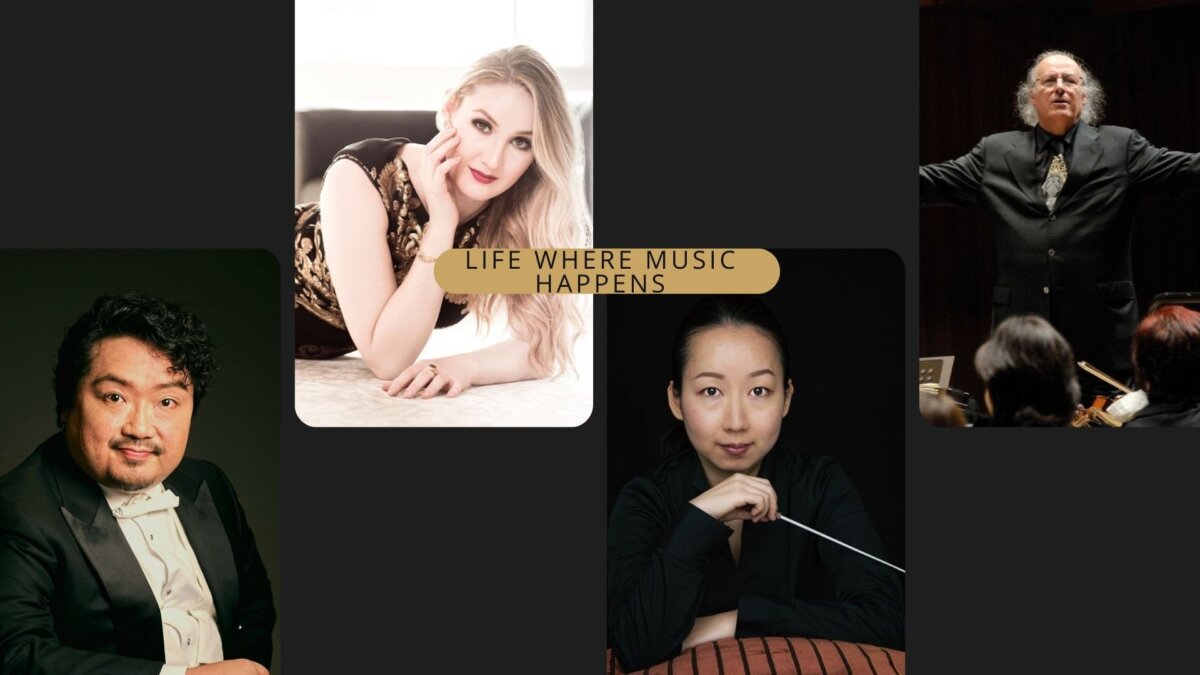
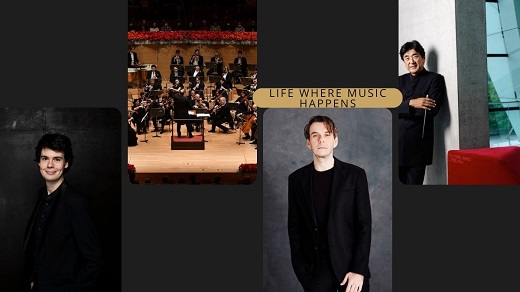
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest