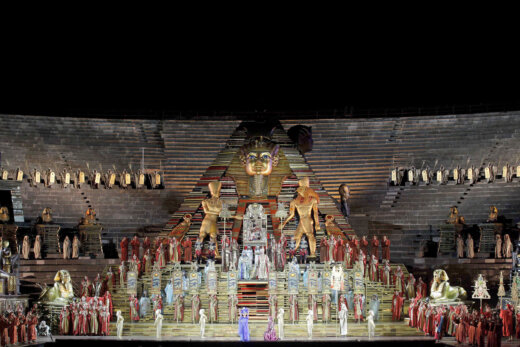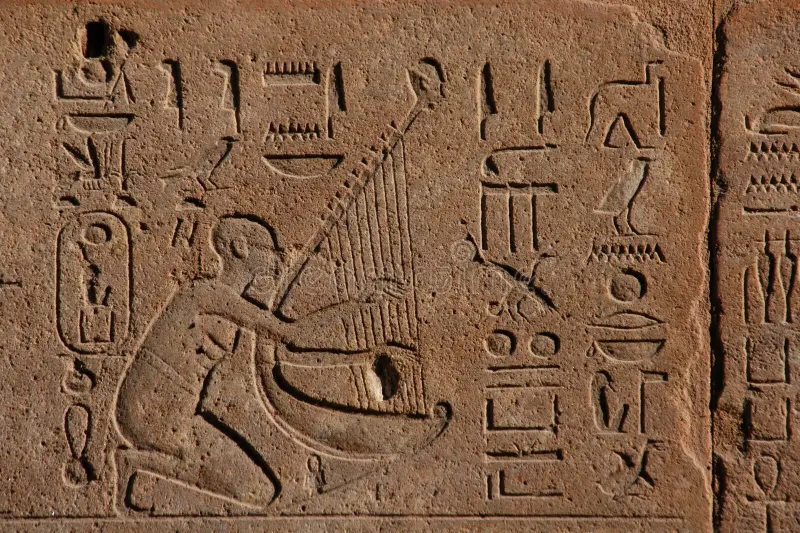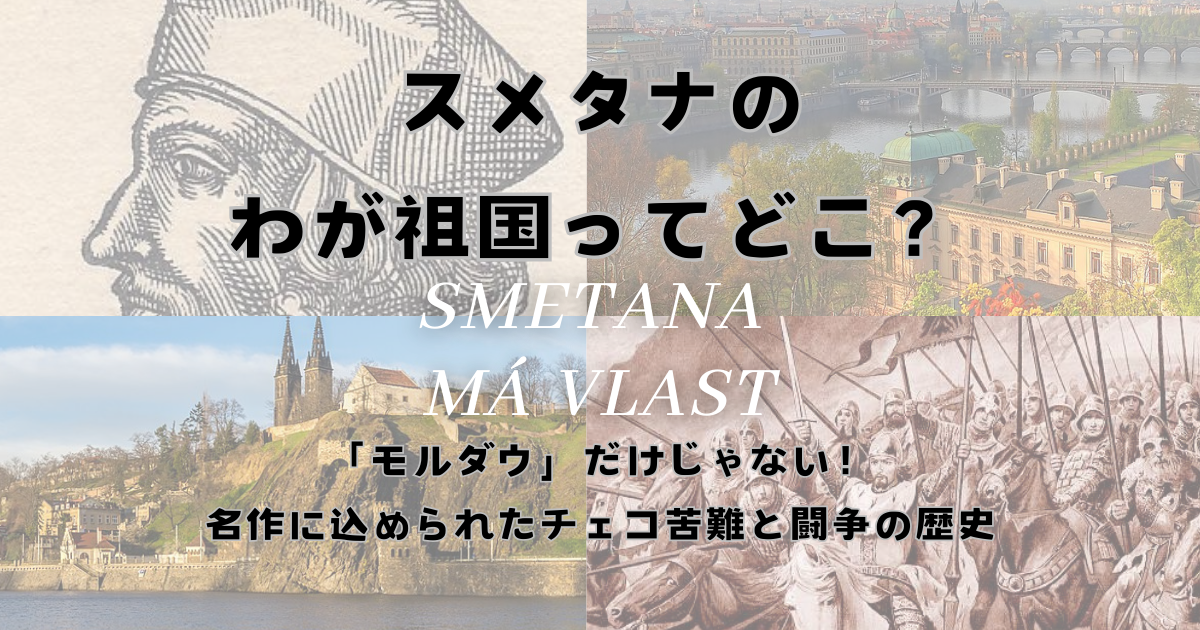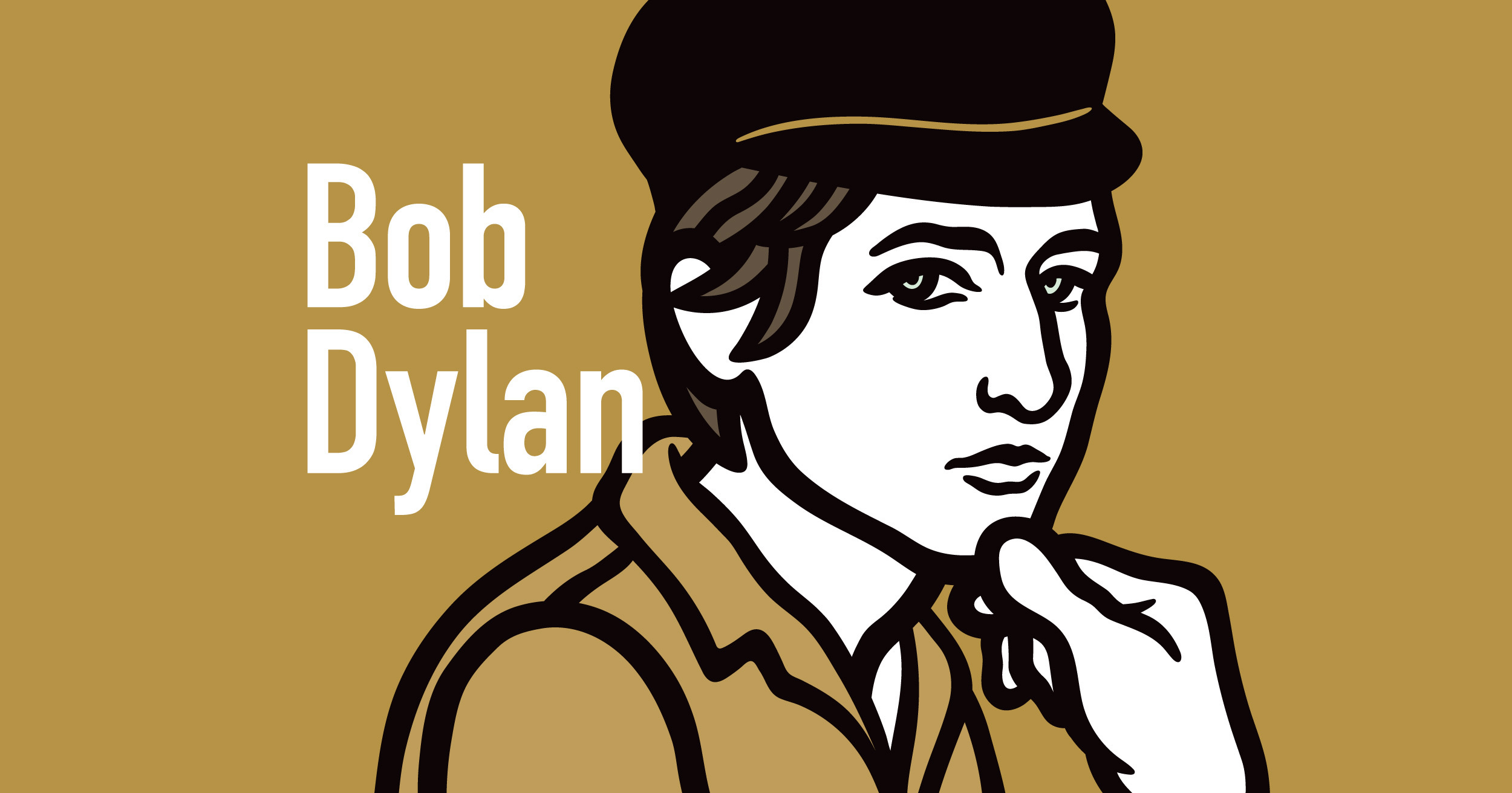
ブライアン・イーノの活動を生成AIで描いた映画『ENO』
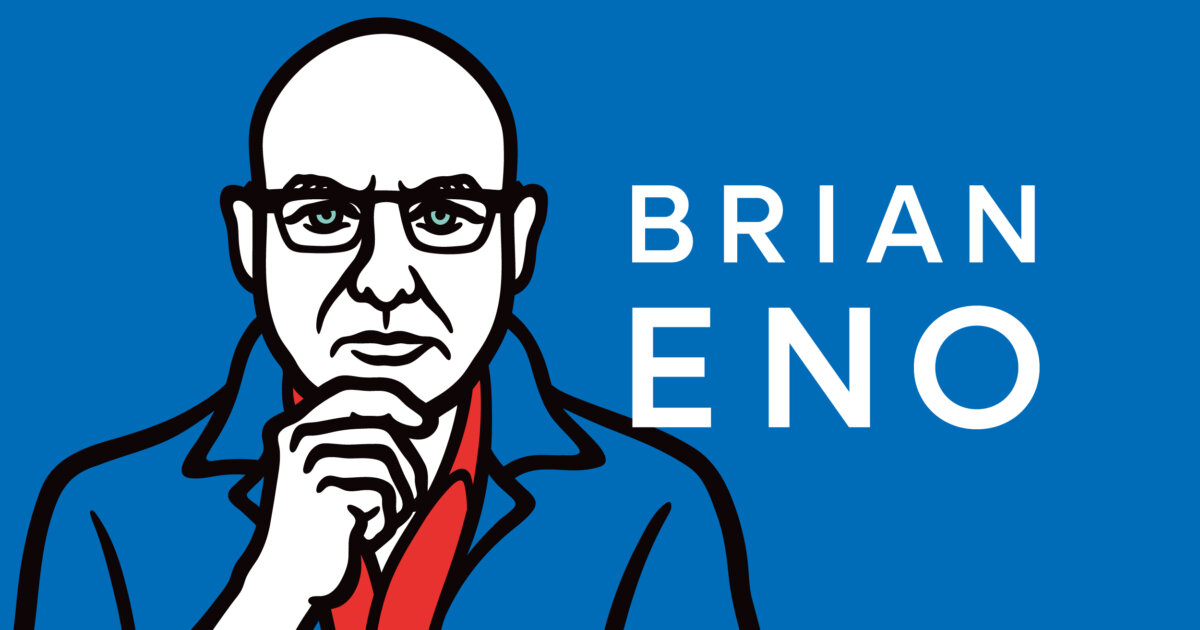
ラジオのように! 心に沁みる音楽、今聴くべき音楽を書き綴る。Stereo×WebマガジンONTOMO連携企画として、ピーター・バラカンさんの「自分の好きな音楽をみんなにも聴かせたい!」という情熱溢れる連載をアーカイブ掲載します。
●アーティスト名、地名などは筆者の発音通りに表記しています。
●本記事は『Stereo』2025年9月号に掲載されたものです。

ロン ドン大学卒業後来日、日本の音楽系出版社やYMOのマネッジメントを経て音楽系のキャスターとなる。以後テレビやFMで活躍中。また多くの書籍の執筆や、音楽イヘ...
頭のよさ、発想の面白さに衝撃を受けたイーノとの出会い
ブライアン・イーノが最初に注目されたのは、デビューした頃のロクシー・ミュージックのメンバーとしてでした。1972年のことです。あの頃のロクシー・ミュージックは全員奇抜な格好をしていましたが、その中でもかなり怪しい雰囲気を漂わせたのがイーノ。当時まだ何なのかよくわからない小型のシンセサイザーで何かをしているようでも、具体的にはよくわからない存在でした。しばらくするとロクシーを脱退し、いくつかのソロ・アルバムを出したり、キング・クリムゾンのロバート・フリップと共演したり、70年代後半にはデイヴィッド・ボウィの「ベルリン三部作」に関わったり、トーキング・ヘッズの一連のアルバムをプロデュースしたり、常に活発に活動していました。
デイヴィッド・ボウィ「ベルリン三部作」
元々美術学校で絵画の勉強をしていた彼は、時期が1960年代半ばということもあって美術よりもポピュラー音楽の世界の方がより面白く、そっちに魅力を感じていました。とはいえ、学生時代の彼が関わったのはどちらかといえば前衛や実験音楽で、偶然に駅のホームでロクシーのサックス奏者アンディ・マカイと出会っていなければ、おそらく美術の教師にでもなっていたのではないかと本人が語ったことがあります。
ぼくは一度だけイーノと仕事をしたことがあります。1984年、彼が東京でヴィデオ・インスタレイションを行なったときのお手伝いをしただけですが、彼の頭のよさ、そして発想の面白さに衝撃を受けました。そのときのインスタレイションではテレビを横に置いて、つまり縦長にして絵画に近いような感覚のゆったりとした映像を流していました。
当時話題になったアンビエント・ミュージック
ブライアン・イーノというと多くの人がすぐに連想するのはたぶんアンビエント・ミュージックでしょう。今やさまざまな解釈がある言葉ですが、元々イーノが1978年に発表した『ミュージック・フォー・エアポーツ』で提示した発想でした。その誕生の背景が興味深いです。ドイツでアーティなパンク・ロックのバンド、ディーヴォのアルバムをプロデュースしていたイーノはその仕事を終えた後、ケルンのできたばかりの空港で飛行機を待っていました。美しい建築物ですべてがピカピカのこの空港で1つだけそぐわないことがあったのです。それはカフェでがんがん鳴り響いていたディスコ・ミュージックだったそうです。空港という場所はただでさえ緊張感の伴うもので、もっとリラックスした気持ちになる音楽ができないかと考えたのが『ミュージック・フォー・エアポーツ』のきっかけとなったわけです。聴き入ることも、無視することもできるアンビエント・ミュージックの発想は当時そうとう話題になりました。
映画『Eno』は生成AIを使いその活動を描きだした
ケルン空港の話は映画『Eno』でも展開されます。厳密にいうと、展開されることがあります。日本では6月から上映されているこの映画はブライアン・イーノが50年以上の間にやってきた仕事に関するドキュメンタリーですが、その上映のしかたはこれまでになかった「ジェネラティヴ」な方法です。生成AIが使われていて、3時間ほどある素材の中から毎回90分前後の内容がAIによって選ばれ、何がどの順番で映るか分からないという前代未聞の作品です。
イーノは常に前に向かっていて、自分がやってきた夥しい数の過去の仕事を振り返ることに興味はないらしく、これまでドキュメンタリーの話を持ち込まれても断っていたそうです。その割には映像素材やその他諸々の資料が膨大にあり、それを整理するだけでも数年かかったと、アメリカ人の監督のギャリー・ハストウィットが言います。アート、建築などのクリエイティヴな分野のドキュメンタリーを得意とするハストウィット氏はデイヴィッド・ボウィのファンで、実はどの上映でもボウィとのセッションの映像は入れているそうです。全体の3割はコンスタントで、残りの7割はランダムで組み合わされるようにプログラムされているのです。この方法を編み出していなければブライアンの許諾をとることはできなかったというのですが、そうでなくても1つのドキュメンタリーでイーノのものすごく幅の広い活動を網羅することは無理な話だと思います。
どんな構成の回でも必ず伝わってくるイーノの基礎にある自然観
この映画の日本語字幕の監修を頼まれたので、用意されているすべての素材を見ていますが、それぞれの項目はだいたい5分ほどの長さで、時代もジャンルもさまざまなので物語性がなく、このジェネラティヴな方法で見ても十分見応えがあるものです。デイヴィッド・バーンのファンだったり、U2のファンだったりすれば当然その部分を優先的に見たいはずです。もしかしたら数回見ないと出てこないかも知れません。
しかし、どんな構成の回でも必ず伝わってくるのは、ブライアン・イーノというアーティストの基礎にある自然観、そしてそれに基づく抽象的なコンセプトをとても合理的で分かりやすく語ることができる彼の魅力です。知的であると同時にイギリス人特有の自嘲的なユーモアもあり、決してうぬぼれたことは言いません。人間はなぜアートを作るか、なぜ音楽を好むかという投げ掛けも極めて興味深いです。
特殊な上映スタイルの関係で頻繁にどこでもやるわけではありませんが、今後も上映の予定があるので、ぜひ注目してください。9月に開催されるぼくの音楽映画祭でも上映するつもりです。お待ちしています!
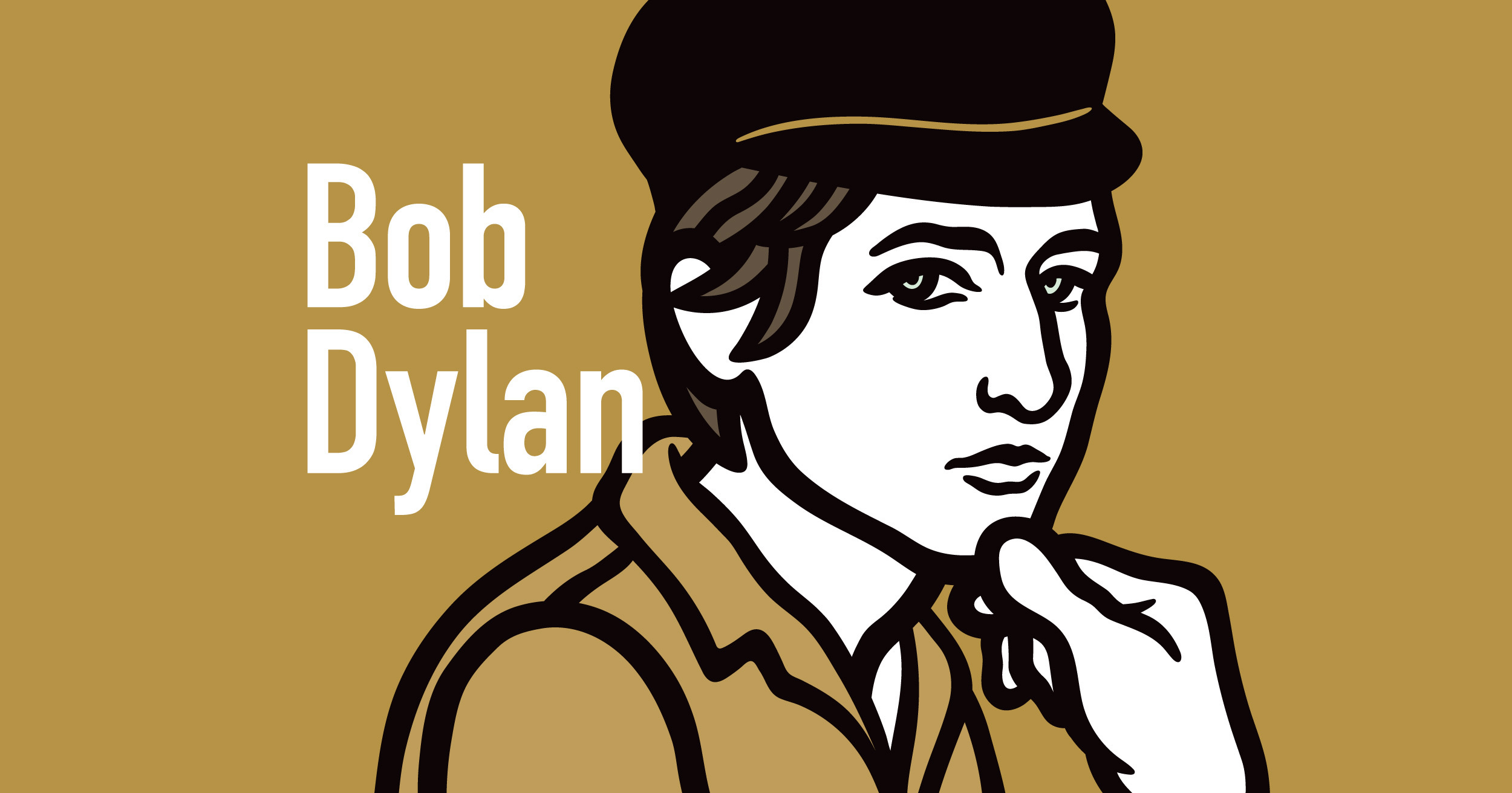



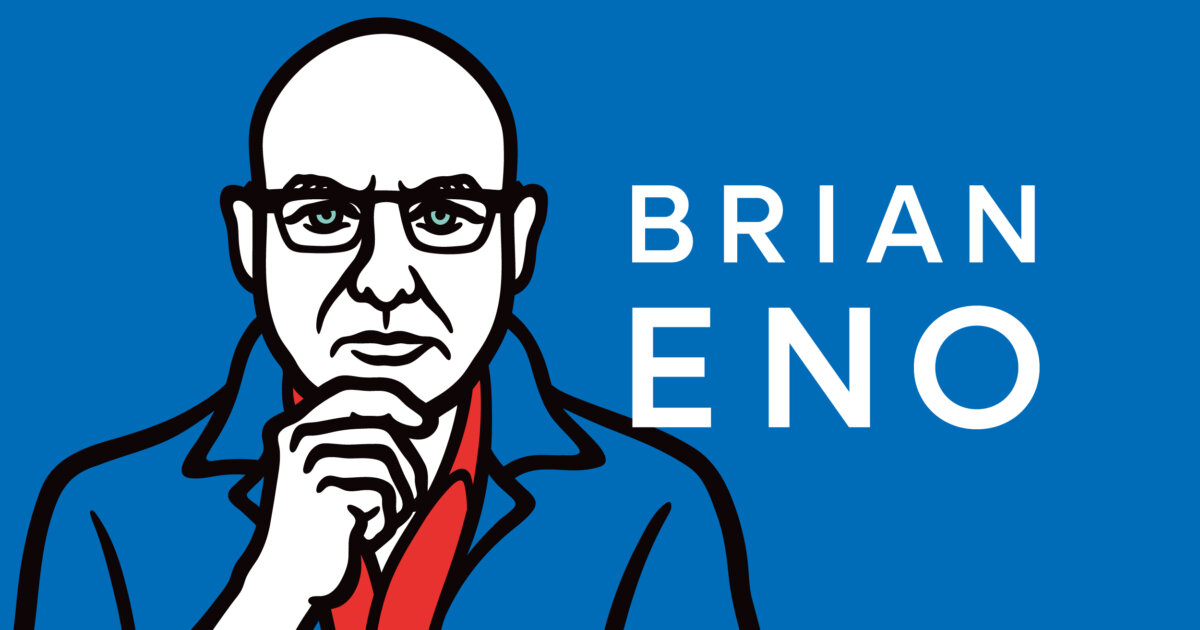
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest