
ホロヴィッツとチャイコフスキーが彩る不道徳な20世紀の芸術世界──川本直『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を音楽の観点から読む連載。第17回は川本直による、架空の作家の生涯を綴った回想録の形で書かれた小説『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』。実在の芸術家たちも多く登場するこの作品。ピアニストのホロヴィッツとチャイコフスキーに関する現代ではおよそ許されない記述から、20世紀とクィアな芸術文化の変遷をたどります。

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...
ホロヴィッツの弾くチャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番ほどオカマの美学を結晶化させた音楽は存在しない。それは二人のハラショーなホモ野郎、ホロヴィッツとチャイコフスキーの幸福な結婚だった。
──川本直『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』河出書房新社、2021年
通じなくなったジョークと失われた20世紀
ある伝聞によれば、ピアニストのウラディミール・ホロヴィッツは生前にこんなジョークを飛ばしたという。
「ピアニストには3種類しかいない。ユダヤ人、ホモセクシュアル、下手くそだ」──

ウクライナ生まれでアメリカに帰化した20世紀を代表するピアニスト。
2021年のいま、もし誰かがこんなジョークを口にすれば、たちまち非難にさらされるだろう。たとえ言った本人のうち「2種類」の当事者であったとしても。
セクシュアル・マイノリティをめぐる人権意識の高まりは近年とくに著しい。「ホモ」という侮蔑的な略称はもちろん、19世紀中盤に登場した「ホモセクシュアル」という歴史ある呼称も、ネガティブなイメージをもよおすとして今日では回避される傾向にある。
しかしホロヴィッツが君臨したのは、こんなジョークこそが一夜のパーティーで輝きを放った時代であった。20世紀。それはイギリスの詩人オスカー・ワイルドが同性間の性行為の罪で投獄された1895年から、世界初の同性婚がオランダで認められる2001年までを結ぶ流転の時代だ。
19世紀最後の年に死んだワイルドが残していったのは、性的少数者の人権問題だけではない。奇抜なファッション、放蕩、ハッタリ、阿片、セックス。それらの不道徳な遺産を礎に、20世紀のクィア・カルチャーは幕を開けた。
今日、wikipediaの人物記事に付された「LGBTの音楽家」「LGBTの著作家」などの配慮の行き届いたカテゴリー名は、そうした過ぎ去りし時代の匂いを一様に消し去ってしまう。ワイルドより7年前に没したチャイコフスキーにもやはり「ロシア出身のLGBTの音楽家」というカテゴリー名が付されているが、20世紀のクィアな文化人たちが、この前世紀の同士に寄せた親密なからかいの妙は、今日的な語彙では決して表現しえないだろう。
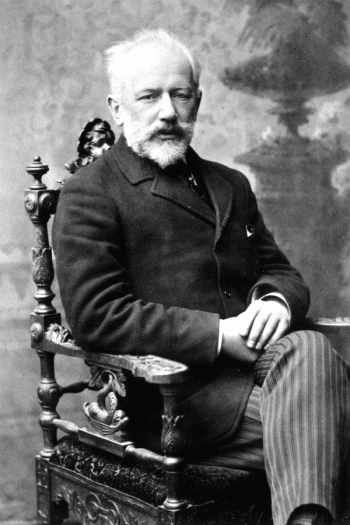
手紙や日記から、同性愛者であったことが現在では定説になっている。
かように脱臭されつつある過去の時代を、架空の主人公と語り手の挿入によって生き生きと現代に蘇らせた小説。それが本作『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』である。
ホロヴィッツとチャイコフスキーが幸福な結婚を遂げる時代
『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』は、アメリカの文芸評論家ジョージ・ジョンが、自身の人生の相棒であり作家ジュリアン・バトラーの生涯を綴った回想録(という体の小説)である。
1925年に民主党所属の上院議員の息子として生まれたジュリアンは、その美貌に似つかわしい女装を好み、男たちを誘惑し、奔放な小説を書き、ノーマン・メイラー、トルーマン・カポーティ、ゴア・ヴィダルといった同世代の作家たち(ジョージとジュリアンを除き、この小説に登場する文化人の多くは実在の人物である)と渡り合い、「20世紀のオスカー・ワイルド」と称される。
そんなジュリアンが1953年に発表し、発禁騒ぎを巻き起こした3番目の長編小説『ネオ・サテュリコン』は、こんな一文から幕を開ける。
ウラディミール・ホロヴィッツが弾くチャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番は、オカマのオカマによるオカマのための賛美歌だ。
この冒頭部にギョッとするのは、1950年代初頭の保守的な読者ばかりではないだろう。21世紀のわれわれの感覚からすると、どうしたって「オカマ」という言葉に引いてしまう。しかも「オカマのオカマによるオカマのための」とは、いうまでもなくホロヴィッツとチャイコフスキー双方に対する強烈なイジりだ。
『ネオ・サテュリコン』の主人公である“私”こと女装者の「ジュリー」は、カーネギー・ホールのボックス席で、ホロヴィッツの弾くチャイコフスキーを聴きながら恋人の「クリス」と猥褻行為に耽り、最後にはトイレに駆け込んで事に及ぶ。ほかの客に行為をとがめられてホールから逃げ出したふたりは、タクシーに乗り込みながらこらえきれずに笑い出す。
ホロヴィッツの弾くチャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番ほどオカマの美学を結晶化させた音楽は存在しない。それは二人のハラショーなホモ野郎、ホロヴィッツとチャイコフスキーの幸福な結婚だった。
不道徳なのは小説内のエピソードばかりではない。回想録の語り手ジョージ・ジョンはこう明かす。ジュリーのモデルはジュリアン本人、恋人のクリスはジョージであり、このカーネギー・ホールでの一幕も(脚色されてはいるが)彼ら自身の実体験がベースなのだと。
しかもこの小説『ネオ・サテュリコン』は、大半をジョージが執筆しており、ジュリアンは口頭で直しを入れたに過ぎない。他の長編小説も程度の差はあれジョージの手が大きく入っている。つまり美貌のお騒がせ作家ジュリアン・バトラーの正体は、ジュリアンとジョージのコンビだったのだ。
ふたりの出会いはアメリカの名門寄宿学校、フィリップス・エクセター・アカデミーだった。ジョージは「最後の清教徒」というニックネームにふさわしい堅物で、趣味は読書と、祖父から影響を受けたクラシック音楽鑑賞。対するジュリアンはすでに性に対する自意識を強く持った少年で、女物の服を着こなし、両性具有的なダンサーとして知られるイダ・ルビンシュタインの写真を部屋に飾る。クラシック音楽は好まないが、音楽聖歌隊で鍛えられたファルセットを得意とし、ジュディ・ガーランドの「虹の彼方に」やノエル・カワードの「マッド・アバウト・ザ・ボーイ」などのクィアな文脈の曲を好んで歌う(前者はレインボー・フラッグの由来となった曲、後者は同性愛の示唆を含んだ曲として知られる)。
彼らはワイルド作の演劇『サロメ』の学内上演をきっかけに距離を縮め、リヒャルト・シュトラウスの「七つのヴェールの踊り」が序曲として流れる本番の舞台で、はじめてキスを交わす。……
往年の少女漫画の「ギムナジウムもの」を想起させる、この少年期の睦み合いは、ただの青春の1ページとしては終わらない。ふたりの仲はその後30年以上にわたって続き、彼らはアメリカ文壇でともにキャリアを積み、ともに人生をサバイバルし、ともに老いていく。ふたりの長年にわたる関係は、同性愛を青年期の一時的な現象であり、異性愛への過程とみなす同性愛観へのアンチテーゼでもあるだろう。
長い人生においては、滑稽な悲劇にも遭遇する。彼らの政敵である作家リチャード・アルバーンは、公衆の面前でジュリアンを「今に見ていろ。オカマ野郎!」と罵倒するが、実は彼自身が「オカマ野郎」の当事者であり、自宅でチュチュを着てチャイコフスキーの「くるみ割り人形」をBGMに踊るのが趣味だったことが発覚する。
カーネギー・ホールでの大胆な公然猥褻ではなく、家のなかでの秘密裏(クローゼット)な戯れ。このグロテスクな事実もまた20世紀的だ。登場人物の誰かが「作家には3種類しかいない。ユダヤ人、ホモセクシュアル、下手くそだ」と言い出しても不思議ではない際どさが、この小説には満ち満ちている。
フィクションの力が過去を引き寄せる
20世紀に生まれ20世紀に死んだ架空の作家ジュリアン・バトラーの生涯と作品は、21世紀の人権感覚とは大きな断絶がある。今日においてはホロヴィッツもチャイコフスキーも「LGBTの音楽家」であり、「ホモ野郎」でも「オカマ野郎」でもない。ホロヴィッツが奏でるチャイコフスキーの協奏曲を「オカマの美学を結晶化させた音楽」と評することは、20世紀とは異なる理由で許されなくなった。
しかしこの作品は──川本直氏の著作であるところの『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』は、物語構造上のさまざまな仕掛けによってジュリアンの生を2021年にまで延命させている。
『ネオ・サテュリコン』の主人公ジュリーがカーネギー・ホールで「オカマのオカマによるオカマのための賛美歌」を聴くとき、その演奏にはモデルのジュリアンが、そして影の作者たるジョージが、さらにはそのジョージが名を変えて紡ぐ語りが、そして彼の正体を追う作中人物≠本作の著者としての川本直氏の声が、倍音のように響いている。逆説的ではあるが、非実在と実在が交錯する、この分厚いメタの構造こそが、近くて遠い20世紀の世界を読者の眼前に引き寄せ、ワイルドの遺産を使い倒して豪遊する作家たちの姿を輝かせる。
この記事の筆者は残念ながらアメリカ文学史に疎く、本作に埋め込まれた数々の元ネタを発見してニヤけるほどの知見を持っていない。しかし、フェイクを仕掛けて過去を手繰り寄せる、この小説の企みの痛快さは、前提知識がなくとも充分に感じられる。
本書を読む喜びは、音楽にたとえるならば、原曲のエッセンスと当世流のレトリックが合体した優れたトランスクリプション(編曲)を聴いたときの高揚感に似ている。編曲は、原曲への愛なしには成立し得ない。著者・川本氏にとっての原曲とは、20世紀の実在のクィアな作家たち、とりわけ自身が面会したこともあるゴア・ヴィダルであるにちがいない。巻末に付された「本書はフィクションです」というありふれた注に、ここまで深い余韻をおぼえる小説はまれだろう。

アメリカの小説家、劇作家、評論家、政治活動家。自身も両性愛者であり、アメリカ文学史上初めて同性愛を肯定的に描いた小説『都市と柱』を著した。
著者・川本直による本書に登場する音楽のSpotifyプレイリスト





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest
















