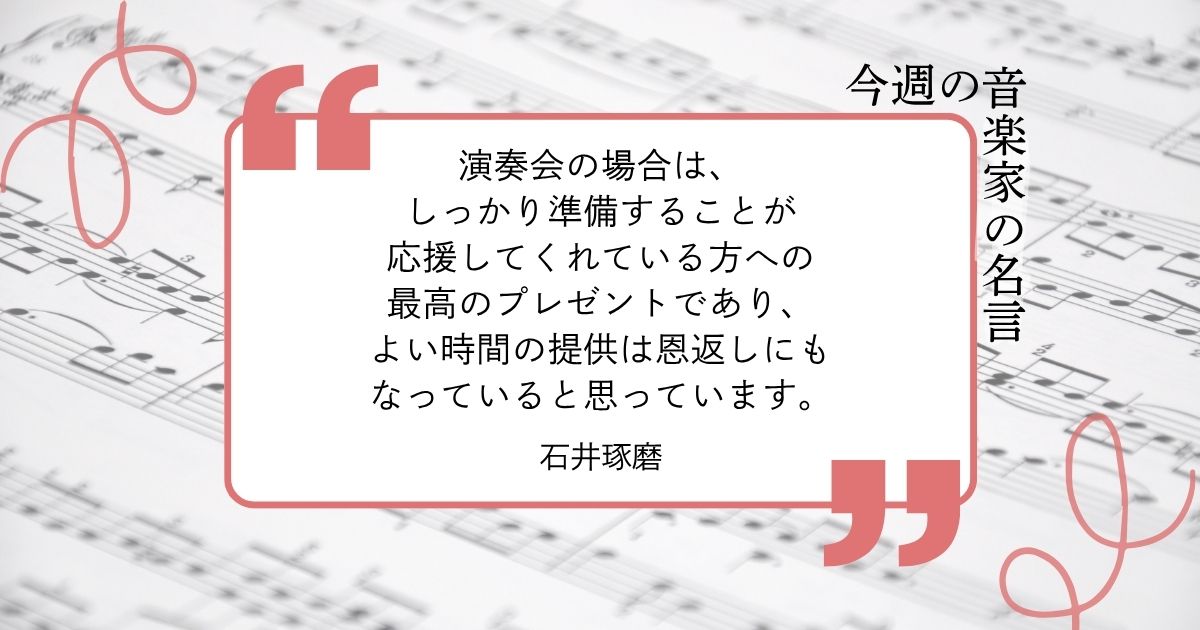芸術家が反語法と二枚舌を使うとき──米原万里『オリガ・モリソヴナの反語法』

かげはら史帆さんが「非音楽小説」を音楽の観点から読む連載。第21回は、社会主義時代のチェコ・プラハで幼少期を過ごし、ロシア語通訳の第一人者、エッセイストとしても活躍した米原万里の長編小説『オリガ・モリソヴナの反語法』。
ダンサーである主人公は、恩師オリガ・モリソヴナの激動の人生を追い、その「二枚舌」な存在と、反語に込められた意味を感じとっていきます。2022年を生きる我々にも、無関係ではないお話です。

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...
さらに度し難く恥ずかしく思われたのは、その体操服を着せられてフォーク・ダンスを踊ることだった。メキシコの輪舞もブルガリアの舞曲も全て同じ曲に聞こえるような演奏でレコード盤に吹き込まれている。土臭さ、あるいは血の滾るような勢い、あるいは憂鬱、あるいは悲しみなどの、どの民族の音楽にも漂うその民族独特の雰囲気はきれいさっぱりとぬぐい取られて、一様にただただ楽しいだけの、陰のないのっぺらぼうな音楽になっている。
──米原万里『オリガ・モリソヴナの反語法』(集英社、2002年)
ショスタコーヴィチの「二枚舌」とスターリン時代
20世紀の政治弾圧は、多くの芸術家を苦境に追いやった。旧ソビエト連邦の最高権力者であったヨシフ・スターリンによる1930年代の大粛清はその最たるものである。多くの文化人が命を落とし、あるいは強制収容所に送られ、それまでの仕事を奪われた。
当局から擁護された側であったゆえに、より複雑な状態に置かれた文化人もいた。ドミートリイ・ショスタコーヴィチの作品に散りばめられた、当局への反逆や皮肉ともとれる多数の暗号めいた引用やイニシャルをめぐる謎は、今日でも議論の的になっている。ショスタコーヴィチをスターリンに屈さなかった英雄とする声もあるが、実際の彼の心情や音楽活動は、もっとアンビバレントであったという見方もある。
亀山郁夫氏は彼の作品を「二枚舌」と呼ぶ。
かりに、そうしたイニシャル(筆者注: 交響曲第12番に現れるスターリンのイニシャルを模した音形)の使用による「二枚舌」を、書法上の「前進」と認めるにしても、それとうらはらに、ショスタコーヴィチが生涯をとおして、純然たるプロ・ソビエト的な音楽に躊躇うことなく没頭していた事実も指摘しておかねばならない。
──亀山郁夫『磔のロシア──スターリンと芸術家たち』岩波書店、2010年
ショスタコーヴィチ:交響曲第12番《1917年》。作品は1917年の十月革命を題材としており、作曲直後に作曲者は「レーニンを偲ぶ作品」と発言している。
今日の私たちが知っているのは、結果的に彼も彼の作品も死なずに済んだという事実のみである。二枚舌を使った芸術家は彼ひとりに限らない。ある者は祖国にとどまりたいがために二枚舌を使い、ある者は遠くに逃げのびて生きるために二枚舌を使った。名前を変え、過去を変え、パスポートを偽造し、さまざまな嘘を駆使して追っ手を煙に巻いた。
そんなスターリン時代を生きたダンサーであるオリガ・モリソヴナの芸術の精神が、第二次世界大戦後に日本からやってきた少女の心身に投げかけられたとき。彼女が人生をかけて守り抜いた芸術は、新しい世代へとバトンを繋いだ。
奇妙な老舞踊教師の秘められた過去
小説『オリガ・モリソヴナの反語法』の冒頭の舞台は、1960年代のプラハ。ソビエト大使館付属八年制普通学校でのコミカルなワンシーンである。
ああ神様! これぞ神様が与えて下さった天分でなくてなんだろう。長生きはしてみるもんだ。こんな才能はじめてお目にかかるよ! あたしゃ嬉しくて嬉しくて狂い死にしそうだね!
──米原万里『オリガ・モリソヴナの反語法』※以下、引用はすべて同書
声の主は、この学校の舞踊教師であるチェコスロヴァキア出身のロシア人、オリガ・モリソヴナ。自称「50歳」であるが見た目は明らかに70代。1920年代風の浮世離れしたファッション。奇妙な訛り、そして歯に衣を着せない独特な「反語」。下手な生徒がいれば「驚くべき天才少年」「カバの日向ぼっこ」と罵り、ウジウジ悩んでいると「結局スープの出汁になってしまった七面鳥」とまた罵る。
しかしダンスへの知見は驚くほど深く、「舞踊と名のつくものなら、一切差別をしない」と明言。自ら編曲までこなし、マズルカ、フェルガナ、レスギンカ、チャルダシュ(それぞれポーランド、ウズベキスタン、コーカサス、ハンガリーの民族舞踊)といった、多種多様なダンスを情熱的に指導する。
父親の海外勤務の都合で編入してきた日本人の少女・弘瀬志摩は、この風変わりな教師に惹かれ、やがてダンスを志すようになる。
そして月日は流れて1992年。すでに引退した42歳の志摩は、あの個性的な旧師の人物像に迫るために、ソビエト連邦が崩壊したばかりのモスクワを訪ねる。再会した旧友カーチャとともに史料や証言者を探し当るなか、彼女はオリガの驚くべき真実を知る。実は彼女は戦後にチェコに来た生粋のロシア人で、名前も偽名であり、1930年代のスターリン政権下の大粛清によって、悪名高いラーゲリ収容所に送られた過去を持っていたのだ。
主人公・志摩と同じくプラハのソビエト学校で少女期を過ごした作者・米原万里による、実話要素を含むこの小説は、ソ連崩壊後の90年代、学校時代の60年代、そしてオリガが生きたスターリン時代を行き来しながら展開される。
中盤以降はひたすら史料を読み、証言者の話を聞いて推理するという動きの少ないストーリーでありながら、読む人の心を騒がせてやまないのは、芸術と社会との関係性という問題を複数の時代や視点で浮き彫りにしているからだろう。有事であっても平時であっても、芸術は社会から軽視されがちである。
ラーゲリ収容所からの生還者である女性ガリーナ・エヴゲニエヴナは、収容所の様子をこう綴る。
「人文系や芸術系など、収容所には必要とされない教育を受けた女たちはずいぶん辛い目にあった。多くの者は、日干し煉瓦作りに動員された。」
一方の志摩は、プラハから帰国したあと通いはじめた日本の公立学校で強いショックを受ける。日本でのダンスの授業は、自らグランド・ピアノを奏で、舞踊のスピリットを叩き込んでくれたオリガのそれとはまるでかけ離れていた。
「メキシコの輪舞もブルガリアの舞曲も全て同じ曲に聞こえるような演奏でレコード盤に吹き込まれている。土臭さ、あるいは血の滾るような勢い、あるいは憂鬱、あるいは悲しみなどの、どの民族の音楽にも漂うその民族独特の雰囲気はきれいさっぱりとぬぐい取られて、一様にただただ楽しいだけの、陰のないのっぺらぼうな音楽になっている。」
しかし一介の舞踊教師たるオリガはなぜ、あれほどに傑出した音楽やダンスへの見識を持っていたのだろう? 42歳の志摩は、その答えをモスクワのミュージック・ホールのポスターのなかに発見した。オリガは収容所に送られる前の若い頃、ミュージック・ホールのダンサーとして活躍していたのだ。
20世紀のヨーロッパやロシアの大都市圏のミュージック・ホールには、バレエとはまた異なる独自のカルチャーがあった。奇術、映画、黒人バンド、風刺喜劇、それから民族舞踊まで、なんでもありのびっくり箱のような演目が繰り広げられ、観客を沸かせる。ロシア革命に伴う内戦が落ち着き、スターリンが台頭する直前のわずかな平和の時代に、モスクワに隆盛した文化。若きオリガはちょうどその頃、「ディアナ」という芸名で一世を風靡した。
自分がもっとも輝いていた時代のファッションに、老いてなお身を包み続ける。それは彼女なりのプライドゆえだったのだろう。ダンスを守り、ファッションを守る彼女は、生き延びるためにそれ以外のほとんどすべてを捨てた。偽の名前を使い、偽の人生を演じ、そしてジーナという実の娘ではない少女を育てる彼女は、あらゆる場で悪罵のような反語を使い続ける。その反語が、ショスタコーヴィチの二枚舌さながらの暗号として聞こえだしたとき、志摩は、オリガの壮絶な人生を我が事として追体験するのだ。
まだ終わっていない「反語」の役割
オリガの過去を知ったあと、志摩は旧友のカーチャにこう打ち明ける。
「あたしが踊りを捨てたのはね、日本ではダンサーの社会的地位も収入も低くて苦しかったこともある。舞台舞踊に対する需要が限られているのだから、そんなことはもともと覚悟の上だったけれど、実際に飛び込んでみると、本当に苦しかった。」「くだらないでしょ。オリガ・モリソヴナの苦労に較べたら恥ずかしくなるよ」
一方で志摩は、ダンスや芸術に対する情熱と、それを与えてくれた旧師を決して忘れることがなかった。そうでなければ彼女は、ソビエトが崩壊したばかりのモスクワを訪ねはしなかっただろう。本作は、職業ダンサーの理想と現実に身を裂かれ、大きな挫折を味わった彼女が、旧師の波乱の生涯をたどりながら静かに癒されていく小説でもある。
収容所からの生還者ガリーナは、志摩にこう言う。収容所内の労働において無用の長物とされていた芸術は、夜になるとラーゲリの収容者たちを救った。俳優は一人芝居を演じ、ダンサーは踊り、音楽家は楽器なしに人の声で交響曲を演奏し、それがみなに生きる気力を与えた、と。
「もう、毎日が学芸会。どんなに身体がヨレヨレに疲れていても、歌を聴き踊りを見ていると、不思議と元気になるんですもの」
2つの顔を持ちながら生きる。オリガもまたそうした時代の芸術家のひとりであった。
芸術家が政治弾圧にさらされ、二枚舌や反語で生き延びたのは過去の話ではない。そうせざるを得ない危機的状況は2022年において、すぐ目の前にある。
著者の米原万里氏は2006年に癌のため惜しくも逝去した。もし存命で、いまなお健筆をふるい、オリガ・モリソヴナに匹敵する名キャラクターを創造したとしたら、その人物にどんな二枚舌をあてがい、どんな反語を語らせただろうか。米原氏は1950年生まれ。ソ連崩壊後のロシアで長年にわたり政権を握ってきた現大統領とほぼ同世代である。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest