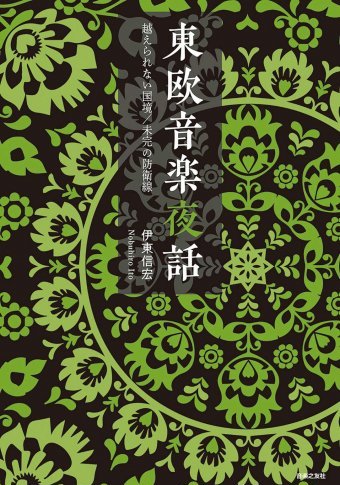ピエロが見た月は狂気の源泉〜コパチンスカヤが創る新時代の『月に憑かれたピエロ』

文学や映画に登場する狂気のピエロ、その源泉は「月」だった......?
シェーンベルクが、歌うように語られる声(シュプレヒシュティンメ)、フルート、クラリネット、ヴァイオリン、チェロとピアノのために作曲し、今や現代音楽の古典に位置付けられる『月に憑かれたピエロ』。近年、この声のパートに取り組んでいるモルドヴァ出身のヴァイオリニスト、パトリツィア・コパチンスカヤの新盤が話題となっています。コパチンスカヤと親交がある伊東信宏さんに、狂気のピエロの歴史を交えて、彼女の斬新かつ正統的なアプローチを紹介していただきました。
文学や映画で定番となった「狂気のピエロ」
『月に憑かれたピエロ』の「月に憑かれた」は「狂気に取り憑かれた」というほどの意味である。月は「夜」や「死」の象徴であるとともに、「狂気」の源泉でもある。
シェーンベルクの『月に憑かれたピエロ』(1912年初演)で用いた歌詞(原作はA.ジローだが、1892年のハルトレーベンによる独語訳が用いられている)で、月は例えば次のように描かれる。
研ぎ澄まされたサーベルのような月が、/黒い絹のクッションの上に横たわり、/亡霊のように大きく、彼を上から脅かす/苦しみに黒々とした夜を貫いて。
(第13曲「斬首」第1連)
つまり月はここでは彼(=ピエロ)の首を切り落とそうとしている巨大な「サーベル」である。いやピエロは月を見て、それが自分の首に落ちてくる刃物なのだという妄想に取り憑かれている。
このほかにも月は、「ひどく病んで」熱っぽく目を見開いており(第7曲)、「蒼ざめた洗濯女」であり(第4曲)、「人の悪い皮肉屋」(第17曲)でもある。
本来人を笑わせるのが仕事であるはずの道化が、不吉な「月」に取り憑かれる、つまり禍々(まがまが)しいものと結び付けられる、というのは現代の我々にとってはそれほど新奇なものではない。『ジョーカー』(2019年)でも、『IT』(1990/2017リメイク)でも、殺人鬼的道化が描かれるが、これは一種の映画的クリシェ(常套句)だ。
歴史的にも遡ることができる。レオンカヴァッロによるオペラ《道化師》(1892年)は殺人を犯す道化師の話である。
あるいは、道化師でありながら殺人を依頼する《リゴレット》(ヴェルディのオペラは1851年初演だが、原型のヴィクトル・ユゴーの『王は愉しむ』は1832年の作品)も忘れることはできない。
同じ頃に書かれたアンデルセンの童話(『絵のない絵本』1839年)では、醜い道化のアルレッキーノはコロンビーナに恋をしていたが彼女は亡くなり、月が見守るなか、彼女の墓を訪れる。
初演から100年を経てもなお斬新なシェーンベルクの名作『月に憑かれたピエロ』
シェーンベルクによる『月に憑かれたピエロ』は1912年の作品で、音楽的には、「歌うように語られる(シュプレヒシュティンメ)」独特の語法、少ない楽器が無調で対峙しあう音構成の点で、今もとても「新しい」作品に聞こえる。

だが、道化と月(禍々しいもの)という発想自体は現代のものというよりも、むしろロマン主義のものなのだ。
ヴァイオリニスト、パトリシア・コパチンスカヤがここ数年取り組んでいて、ついにCD化された新譜は、そのエキセントリックな演奏に注目が集まっているが、ある意味ではこれは極めてオーセンティック(正統的)なものでもあることを強調しておきたい。

2. ヨハン・シュトラウス2世/シェーンベルク編:皇帝円舞曲 Op.437
3. シェーンベルク:ヴァイオリンとピアノのための幻想曲 Op.47
4. ヴェーベルン:ヴァイオリンとピアノのための4つの小品 Op.7
5. クライスラー:ウィーン小行進曲(ヴァイオリン、クラリネット、チェロ、ピアノ)
6. シェーンベルク:6つの小さなピアノ曲
パトリツィア・コパチンスカヤ(声:1、ヴァイオリンI:2、ヴァイオリン:3-5)
ミーサン・ホン(ヴァイオリン&ヴィオラ:1、ヴァイオリンII:2)
ジュリア・ガレゴ(フルート:1,2)
レト・ビエリ(クラリネット:1,2,5)
マルコ・ミレンコヴィチ(ヴィオラ:2)
トーマス・カウフマン(チェロ:1,2,5)
ヨーナス・アホネン(ピアノ)
ここに寄せられた解説は、コパチンスカヤのパートナーでもあるルーカス・フィエルズ氏によるものだ。彼はピエロのような白塗り道化の起源を説き起こし、コメディア・デラルテ(イタリア発祥の仮面即興劇)の伝統がフランスに飛び火してドビュローという傑出したピエロ役者が現れたこと、さらに彼が実際に(犯罪とはならなかったが)人を殺めてしまったという事件があったこと、そして19世紀末パリの芸術キャバレーの伝統の中で「黒いピエロ」というイメージがもてはやされたことなどを、豊富な図版とともに解説している。

ジャン=ギャスパール・ドビュロー(1796〜1846)はフランスのパントマイマー。白塗り・白い衣装のピエロを考案し、熱狂的な人気を誇った。
ヴァイオリニスト・コパチンスカヤがアイデアと技術を詰め込んだ渾身の「ピエロ」の声
フィエルズ氏の考えはもちろんコパチンスカヤの朗唱にも大きな影響を及ぼしている。もともと彼女は、腕を痛めてしばらくヴァイオリンの演奏をセーブせねばならなかった6年ほど前から、この「ピエロ」に取り組んできた。
2017年10月、コパチンスカヤがミネソタ州のセントポール室内管弦楽団と「ピエロ」役で共演した『月に憑かれたピエロ』
以前からヴァイオリン・パートでは、この曲の演奏に参加したことがあったが、その頃から実は声のパートをやりたくて仕方なかったらしい。
彼女は普段から、早口で、辛辣で、とても移り気で、でもシャイな話し方をするが(つまり、そもそもの語り口が『月に憑かれたピエロ』的なのだが)、そういう彼女からすれば、自分なら声のパートをこんな風に語るのに、というアイディアが一杯あったのだろう。
その上で老練な声楽教師であるエステル・デ・ブロが彼女を導いた。その訓練によって、これはヴァイオリニストの気まぐれな余技といった域をはるかに超えるものとなり、それまでに温められていたアイデアはきちんとした技術的基礎を持つようになった。
実際、シェーンベルクが楽譜のそこここに書き込んだ詳細な指示——「音を出さずに囁くように」「ここは歌う(シュプレヒシュティンメの朗唱法ではなく通常の声楽の方法で歌う)」「嘆くように」などを、これほど正確に音としている演奏はこれまでにもほとんどなかったように思える。

©️Lukas Fierz
その上で、ヴァイオリン奏者として世界を驚かせてきた透徹した譜読みと大胆な表現は、そのままに活かされる。脇を固める奏者たちも曲者ばかりだ。非常に敏感なヨーナス・アホネンのピアノ。もともとは羊飼いを目指していたというクラリネット奏者、レト・ピエリ。それらを総合すればこの「ピエロ」は21世紀の新しいスタンダードだ、としても言い過ぎではない。これは月をめぐる芸術表現の新しい里程標である。

©️Lukas Fierz
コパチンスカヤの話題も豊富な伊東信宏さんの著書
関連する記事
-
インタビュー郷古 廉に50の質問!〈前編〉舞台に上がる時の気持ちは?これまでで最大の試練は?
-
インタビューHIMARIが語るカーティス音楽院生活~1日の練習時間は? どんな授業がある?
-
インタビュー石田泰尚と﨑谷直人のヴァイオリン・デュオ「DOS DEL FIDDLES」が抱く...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest