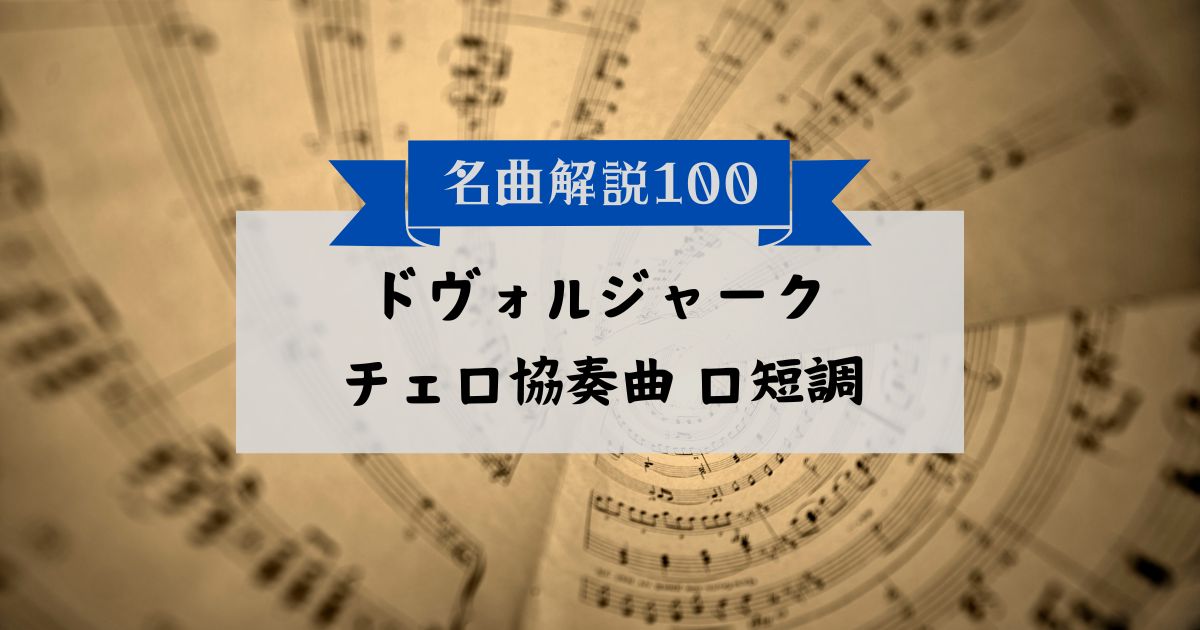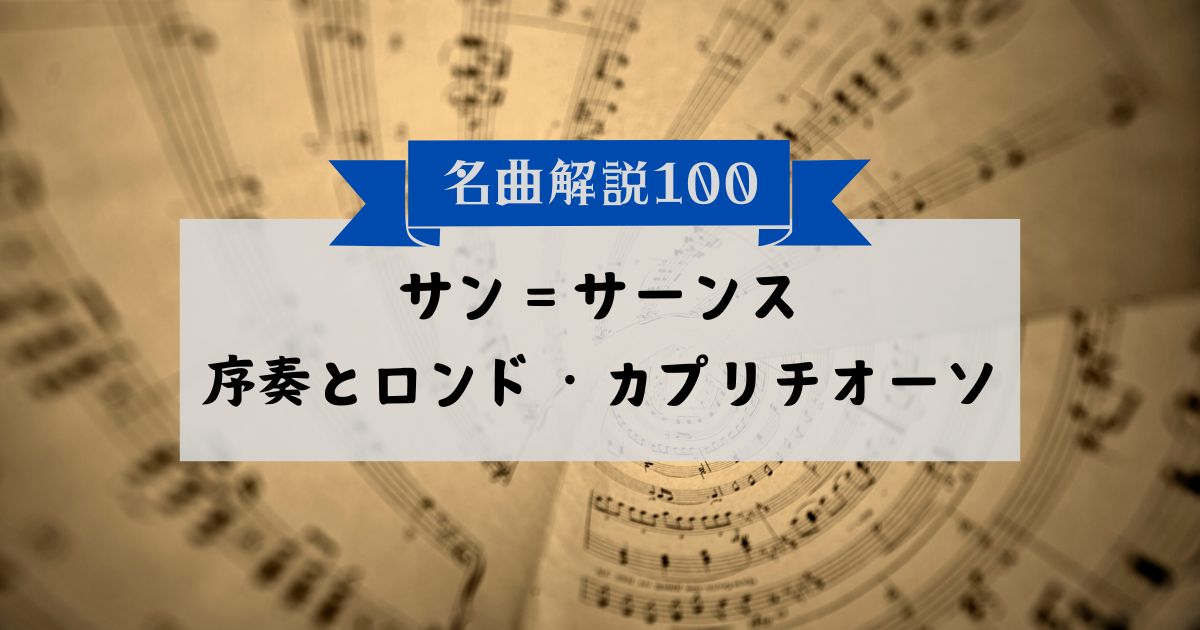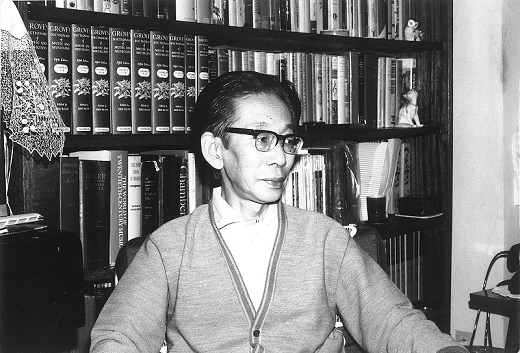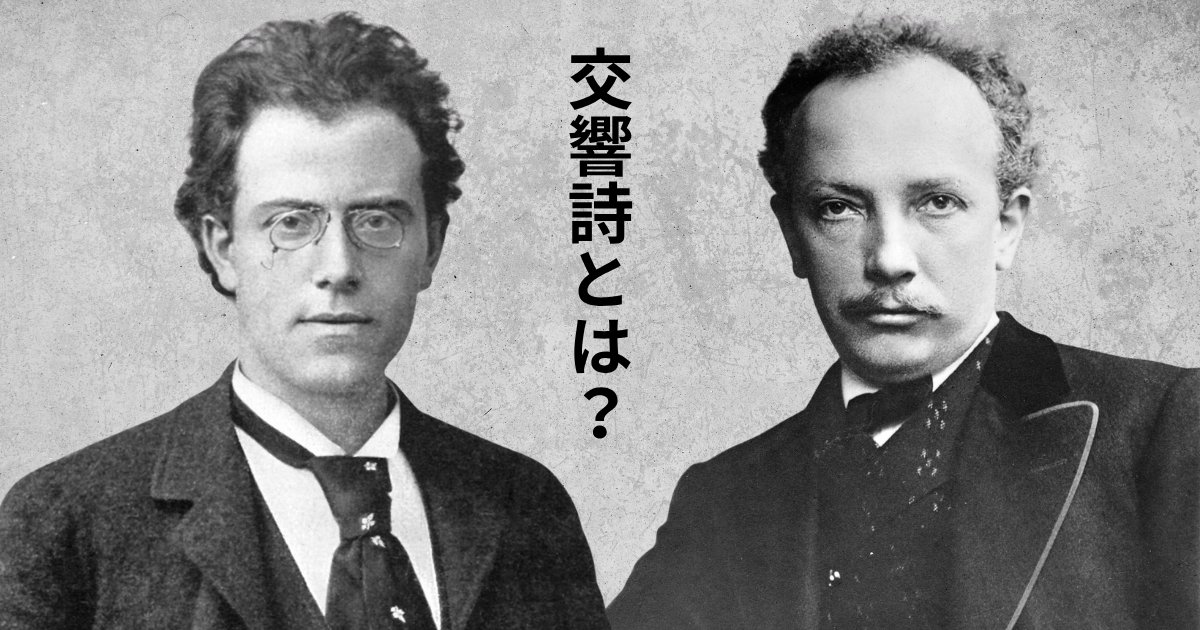エルガー《威風堂々》の原題に隠された『オセロ』の皮肉な意味

卒業式や式典の定番曲でもあるエルガーの《威風堂々》。威厳と華やかさを表すこの邦題は、誰もが知る日本語訳となりましたが、その原題 Pomp and Circumstance の出典は意外にも、シェイクスピア悲劇『オセロ』の暗く皮肉な場面。輝かしい勝利の象徴が、実は喪失と絶望の中で放たれた言葉だった……そんな背景をイギリス歴史文化の専門家・齊藤貴子さんがひも解きます。

上智大学大学院文学研究科講師。早稲田大学および同大学エクステンションセンター講師。専門領域は近代イギリスの詩と絵画。著作にシェイクスピアのソネット(十四行詩)を取り上...
「威風堂々」は『オセロ』第3幕第3場からの引用
物事はあまり額面通りに受けとらないほうがいい。少なくとも、給与の額を初めから手取りで開示する人はほとんどいないし、歯の浮くようなセリフを吐く男は大抵、誰にでも同じようなことを言ってまわっている。
悲しいけれど本当のことで、物事は文字通り真に受けていいほど、必ずしも単純明快ではない。威厳があり立派な様子を表す四字熟語、イギリスの作曲家エドワード・エルガーの行進曲のタイトルとしても有名な「威風堂々」というフレーズが、元をたどればたどるほど、何とも皮肉めいて聞こえるように。
1901年に作曲され、卒業式をはじめ20世紀のあらゆるセレモニーの定番楽曲となった《威風堂々》の原題Pomp and Circumstanceが、シェイクピアの悲劇『オセロ』第3幕第3場からの引用であることは、比較的よく知られている。
Farewell the neighing steed and the shrill trump,
The spirit-stirring drum, th’ear-piercing fife,
The royal banner, and all quality,
Pride, pomp, and circumstance of glorious war!
さらば、いななく軍馬に鋭い喇叭
魂を揺さぶる太鼓と耳をつんざく笛の音よ
君主の旗にすべての荘厳
誇り、華やかさ、輝かしい戦のものものしさよ!
エルガーがこの部分からタイトルを引用したこと自体は、誰の目から見ても実に理にかなっている。彼が作ったのは「喇叭」に「太鼓」に「笛の音」から成る管弦楽のための行進曲。時の国王エドワード7世がいたく気に入り、王たっての希望でのちに歌詞をつけて《戴冠式頌歌》ともなった行進曲の第1番中間部、もはやイギリスの「第二の国歌」レベルで広く知られている旋律にいたっては、主旋律を担う管楽器や弦楽器以上に、ティンパニという「太鼓」によって「魂を揺さぶる」高揚感が確かにもたらされている。
引用元は主人公が嫉妬に飲み込まれるドス黒い場面!?
ただ、だからといって、楽曲の内容とタイトルの間にも完全な整合性があるというわけではない。愛国主義のマーチにふさわしい曲名をシェイクスピアという国民文学に求めたにせよ、金管・打楽器への言及があり、おあつらえ向きだったにせよ、輝かしい栄光に満ちた勝利のスローガンを『オセロ』という「悲劇」から、それもよりによって第3幕第3場から引用するのは、正直いかがなものかと思わないでもない。
というのも、第3幕第3場は主人公の将軍オセロが「嫉妬」というドス黒い感情に飲み込まれ、破滅に向かってまっしぐらに狂い出す部分。どこまでも人間がねじけた部下イアーゴーの奸計(かんけい)により、妻デズデモーナの不貞というありもしない嘘を信じ込まされ、これでもう心満ち足りた幸福な生活も終わりだ、自分の人生を懸けた愛が終わりを告げたのだ!と、ひとしきり絶望の叫びを上げながら語られるのが先の引用部分なのである。
すなわち、原典の文脈からいえば「華やかさ(pomp)」と「ものものしさ(circumstance)」とは今や失われてしまったもの。貞淑な妻、真実の愛という己が人生の支柱を失った(と思い込んだ)がゆえに、数々の輝かしい勝利に彩られてきた将軍オセロの栄光と幸福の日々もまた色褪せ、たちまち意味を失くしていくという喪失の嘆きが、Pomp and Circumstanceの本当の意味。舞台の上で放たれる絶望の叫びの、本来の苦く切ない残響にほかならない。

喧嘩が元で解任された副官キャシオを庇うオセロの妻デズデモーナは、そのせいで夫オセロからキャシオとの仲を疑われる(冒頭のシャセリオーの版画参照)。しかしすべてはイアーゴーの奸計で、彼はデズデモーナの侍女である自らの妻エミリアを使って彼女のハンカチ(オセロからの大事な贈り物)を手に入れ、浮気の証拠を捏造してオセロの嫉妬をさらに煽ってゆく。
エルガーの行進曲のタイトルとしては名訳だけど……
翻って考えると「威風堂々」とは、けだし名訳。シェイクスピアがオセロという登場人物に背負わせたこれら複雑な事情と心情を、整然たる四字熟語の字面と語感で見事にかき消し、エルガー自身の目指した「栄光の行進」という楽曲コンセプトのみを明快に伝えることに成功している。いかなる意味においても、エルガーの行進曲タイトルの邦題として、これ以上のものはないだろう。
しかしながら、舞台の上で確固たる意志をもって語られる生々しい戯曲の台詞は、本来決して直前直後の文脈を無視して引用されるべきではない。なぜなら、前後の文脈を無視してピンポイントで切り離された引用語句は、いつしか独り歩きを始めるものだから。そして今日Pomp and Circumstanceといえば、一種のイディオムすなわち慣用句として、文字通りの意味とはやや異なる趣で用いられるのが普通になってしまったから……。
めぐりめぐって本来の意味に近づいている?
エルガーの《威風堂々》が演奏される盛大な儀式や大規模な国家的行事は、少なからぬ人びとが近代イギリス帝国主義の過去のあやまちを知る21世紀の今、必ずしも額面通りには賛美されない。過剰な儀礼的行為を冷ややかなまなざしで見つめ、時代遅れの愛国心の表明として批判し、嫌悪さえする人びとが一定数存在するのは、もはや否定できない事実といっていい。
この苦い事実を傍証するかのように、威風堂々の原題であるPomp and Circumstanceというフレーズもまた、華やかでものものしいという文字通りの意味とは別に、物事の表面上の華美にたいする多少の侮蔑を孕んだ比喩として用いられる。もっとも簡単な例を挙げると、No pomp and circumstance! といえばすなわち「派手な演出や形式ばったことはやめて!」という意味になるのだ。
でも、これはこれでいいのかもしれない。そもそもpompはともかく、circumstanceという単語は、今と昔とではかなり意味が異なる。語彙の歴史的変遷を知るうえで欠かせない『オックスフォード英語辞典』(OED)によれば、シェイクスピアの生きていた時代においてcircumstanceは「あらゆることに関する騒ぎ(ado)」という意味だった。「形式、儀式、あらゆる重大な出来事ないし行為に関する騒ぎ」とも定義しており、むしろ今日の批判的かつ比喩的用法のほうが元来の語義に近い。
あるいは『オセロ』第3幕第3場で、妻の不貞という本来ありもしない「重大な出来事ないし行為」のせいで大騒ぎして取り乱し、自暴自棄になった将軍オセロが語る自虐の弁のニュアンスに限りなく近いというべきか。
ことほどさように物事は単純ではない。けれど、前後の文脈を無視した引用が、めぐりめぐって原典の文脈、本来の意味に近づいていくこともあるのだから、それはそれでいいのかもしれない。そんなふうに作者本人の意図を超えて、さまざまな物思いを誘う名曲があるに越したことはない。
チャールズ3世の戴冠式では《威風堂々》第4番が使用された
関連する記事
-
読みもの【林田直樹の今月のおすすめアルバム】ピアノデュオの既成概念をくつがえす、坂本姉妹...
-
読みもの【林田直樹の今月のおすすめアルバム】何度見ても新鮮なベルリン・フィルの子ども向け...
-
記事「イギリス音楽」の普及に尽力した昭和の音楽評論家 三浦淳史を知っていますか?
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest