
いにしえの絵画に満ちた音楽と恋〜「メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年」より5作品

日曜ヴァイオリニストで、多摩美術大学教授を務めるラクガキストの小川敦生さんが、美術と音楽について思いを巡らし、“ラクガキ”に帰結する連載。
第32回は、「メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年」で出会った音楽に満ちた絵画たち。今は聴くことができない、その瞬間に響いていた音楽を想像し、音楽と不可分な「恋愛」にも思いを馳せます。
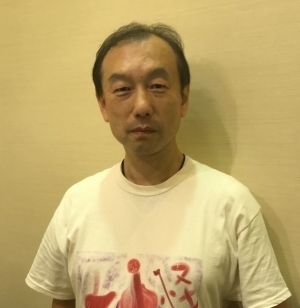
1959年北九州市生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業。日経BP社の音楽・美術分野の記者、「日経アート」誌編集長、日本経済新聞美術担当記者等を経て、2012年から多摩...
絵画が残した、今は聴けない音楽の響き
物質でできている絵画や彫刻と違って、音楽の演奏はその場で消失してしまう。それゆえ、録音技術が生まれる前の演奏を、現代人が自分の耳で確かめるのは不可能だ。
しかし、である。いにしえの世界にも絶対に、素晴らしい音楽があったはず。歴史上の名作が多数出品されている国立新美術館(東京・六本木)の「メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年」に出かけると、その証しともいえる絵画作品がいくつも展示されていた。今日は、音楽の素晴らしさをしのばせる絵画作品を見ながら、いにしえの音楽世界へ旅立ってみたい。

音楽家たちの中に紛れこむキューピッドと作者カラヴァッジョ
最初に紹介したいのは、16世紀から17世紀にかけてイタリアで活動した巨匠画家カラヴァッジョの油彩画『音楽家たち』である。画面でもっとも目立っているのは、真ん中でリュートを調弦している男だ。画面最下部のヴァイオリンは、背を向けて楽譜らしきものを手にしている男性がこれから弾くのだろう。
すなわち、この絵は、音楽家たちがこれからまさに合奏を始めようとしている様子を描いているとみられる。奥の右側でこちらに目線を向けているのはカラヴァッジョ本人と言われる。角笛を持っているのだが、本当に演奏したのだろうか。あるいは、自身も深く音楽を愛し、その中に没入したかったのかもしれない。

画面をよく見ていてはっとするのは、左端奥に翼が生えたキューピッドが描かれていることだ。音楽と愛は近しいということだ。どちらも切なく心をふるわせる。筆者も同感である。古代風の衣装の人物が描かれたこの絵は、当時のイタリアでも音楽が盛んだったことを表している。

同展の図録によれば、カラヴァッジョはこの絵を、最初のパトロンとなったデル・モンテ枢機卿のために描いたという。貴族は音楽家を雇い、自邸でしばしば奏でさせていたのだろう。録音や放送がなかった当時は、音楽を聴くためには生演奏の場を設けるしかなかった。折りに触れ、奏でられ、場を幸福な音楽で満たしていたのではないだろうか。
音楽と愛は切り離せない? カラヴァッジョに続いて「音楽を描いた」画家たち
次に目を向けたのは、シモン・ヴーエの『ギターを弾く女性』という作品だ。こちらの登場人物は一人である。カラヴァッジョが描いていた音楽家はすべて男性だったが、こちらは女性である。ギターの形は現在のものよりもずんどうで小さめだ。

ヴーエはフランスの画家だが、明暗をくっきり描いているところからはカラヴァッジョの影響を大きく受けていることがわかる。同展の図録によれば、そもそも、この画題自体が、ローマに滞在したときに見たカラヴァッジョの絵から着想したものだという。当時のローマはヨーロッパの多くの画家が憧れる最高の芸術都市だった。ヴーエが描いたのは、演奏者の姿を借りたローマ文化への憧れだったのかもしれない。

オランダの画家、ハブリエル・メツーが描いた『音楽の集い』では、リュートに左手をかけている女性が、右手では手紙を受け取っている。恋文だろうか。やはり音楽と愛は近しいのだ。リュートのすぐ下には楽譜らしきものが置かれている。右側の男性は、ヴィオラ・ダ・ガンバという楽器を調弦している。
オランダの17世紀は、市民の富裕層が経済力で芸術を盛り上げた時代でもあった。この絵も、富裕層の邸宅の一室で、住人がこれから趣味の合奏を始めようとしているといった内容なのだろう。音楽をたしなむ良家の女性の楽器演奏の腕のほどはわからないが、アマチュアだからこそ、喜びに満ちて音楽を奏でていたのではないだろうか。日曜ヴァイオリニストを自称する筆者の実感を反映した想像でもある。

オランダの画家、ヤン・ステーンが描いた『テラスの陽気な集い』は、描かれた人物がとにかく楽しそうだ。右側で若者が奏でているのはシターンという楽器らしい。後ろのやや左には、横笛を吹いている男性もいる。主人公とおぼしき中央の女性は、なかなか開放的な雰囲気を醸し出しており、性欲を象徴することもあるという画面上部の空の鳥かごの存在といい、全体に浮かれ騒いでいる様子といい、どうやら教訓めいたものが表現されているようだ。
想像をふくらませると、こうした場では音楽に乗って、浮かれ騒ぐことが日常的にあったということにもなろうか。音楽と恋は人の心を惑わせる? なんてこともあるだろうか。

最後は、フランスの画家、アントワーヌ・ヴァトーの『メズタン』。主人公の男は、ヴーエの『ギターを弾く女性』に描かれたものと同じタイプのギターを弾いている。同展の図録の解説によると、メズタンは当時の演劇の登場人物で、「おどけ者の使用人か従者」「ギターを奏で、報われない恋をむなしく追い求めている」という。
ああ、ここでも恋が! 演劇の一場面ゆえ、現実の生活をそのまま描いたとは思えないが、その演劇を鑑賞した当時の人々が、音楽を背景に「恋」への想像をふくらませるなどして日常を楽しんでいたことが想像できるのである。

音楽は愛。世界を救うのも愛。世界に音楽と愛が満ちるとき、人々はみんな幸福になれるのです! 平和よ恋(来い)!(Gyoemonは筆者の雅号です)
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest



















