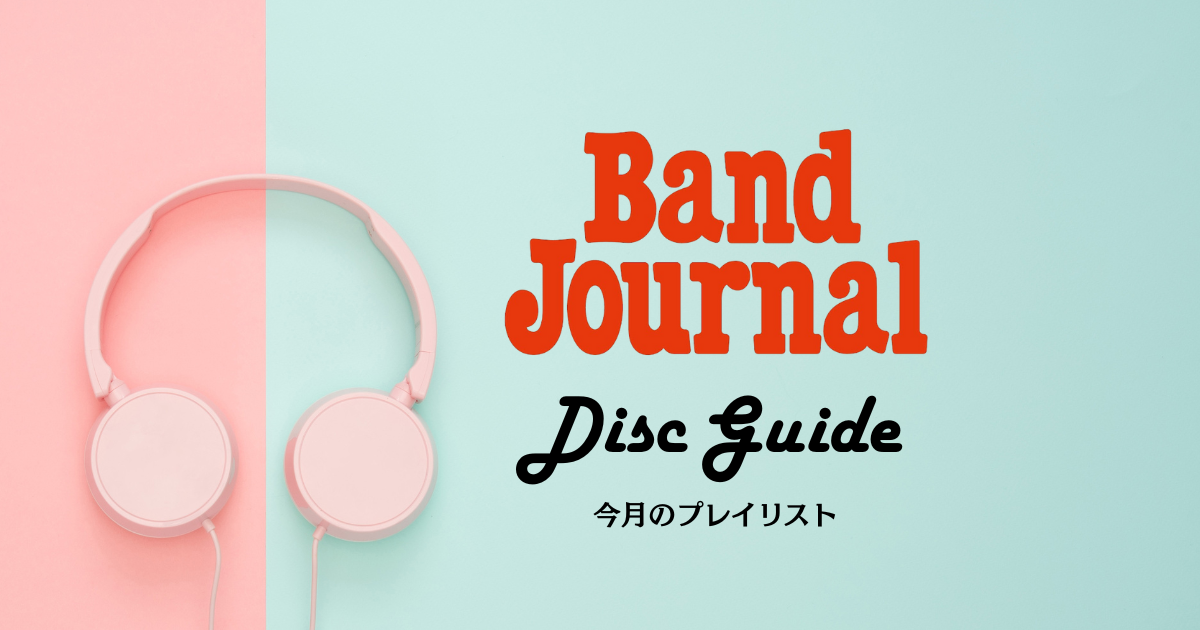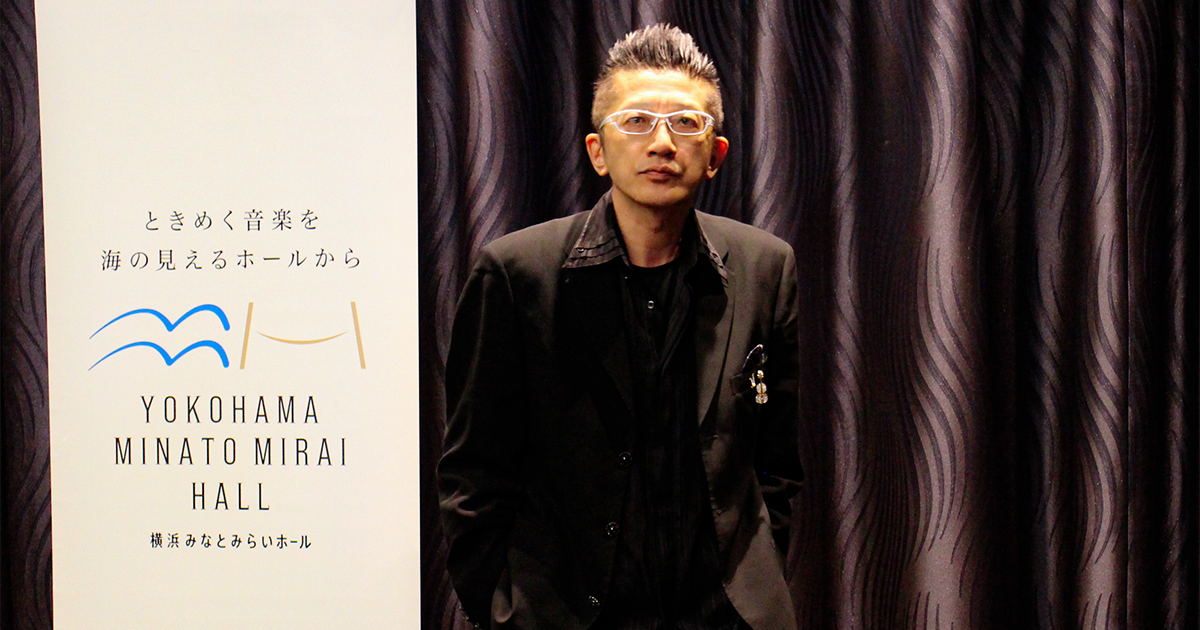ショパンコンクール第1ステージ~コンテスタントたちは「ワルツ」にどう取り組んだ?

第19回ショパン国際ピアノコンクールの第1ステージが、10月7日に終わりました。今回、第1ステージの課題曲にワルツが加わり、Op.18 とOp.34-1、そして Op.42の3曲の中から1曲を選んで演奏することに。第1ステージで演奏したショパンのワルツについて、コンテスタント6名のコメントを紹介します。

2019年夏、息子が10歳を過ぎたのを機に海外へ行くのを再開。 1969年東京都大田区に生まれ、自然豊かな広島県の世羅高原で育つ。子どもの頃、ひよこ(のちにニワトリ)...
桑原志織「クラシック・バレエの経験から、踊っているイメージを思い描いた」

ワルツの課題曲3曲の中で、第1番のグランドワルツ(Op.18)だけが私のレパートリーでして、あとの2曲を弾いたことはありませんでした。選曲にあたり、3曲すべて弾いてみました。準備時間があまり長くなかったので、もっとも自分の手に合う第2番のワルツ(Op.34-1)を選びました。
私は、小さい頃にクラシック・バレエを習っていたので、ワルツの振り付けを考えたり、YouTubeをいろいろ見たりして、ワルツのステップについていろいろ試行錯誤を重ねました。クラシック・バレエは、民族的な踊りやワルツなどのダンスとは違いますよね。でも、私の中では、クラシック・バレエが一番しっくりきます。頭の中で踊っているイメージを思い描いてみました。
少し迷宮に迷い込んでしまいましたが、徐々にリズムや曲の雰囲気に馴染んできて、最終的には作品の持ち味を自然に表現できるようになり、とても楽しく演奏できました。
進藤実優「朗らかに演奏できるように、リラックスして臨めた」

今回のコンクールでは、ワルツの課題曲としては3曲しか候補がありませんでした。まず、前回のコンクールで演奏したOp.42を避けたいと思いました。残り2曲のなかで自分の手に馴染みが良いのは、Op.34-1でした。
コンクール前に、このワルツをコンサートで何回か演奏する機会がありました。でも、真剣になりすぎたり、緊張のせいか、あまり楽しく朗らかに聞こえなかったりということもありました。できるだけ普段通りに、朗らかに演奏できるように心を落ち着けてから演奏したつもりです。ですから、リラックスして臨めたのではないかなと思っています。
関連する記事
-
インタビューワルシャワ・フィルのオーボエ奏者がショパンコンクールを振り返る
-
インタビューワルシャワ・フィルのファゴット奏者がショパンコンクールを振り返る
-
インタビューワルシャワ・フィルのチェロ奏者がショパンコンクールを振り返る
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest