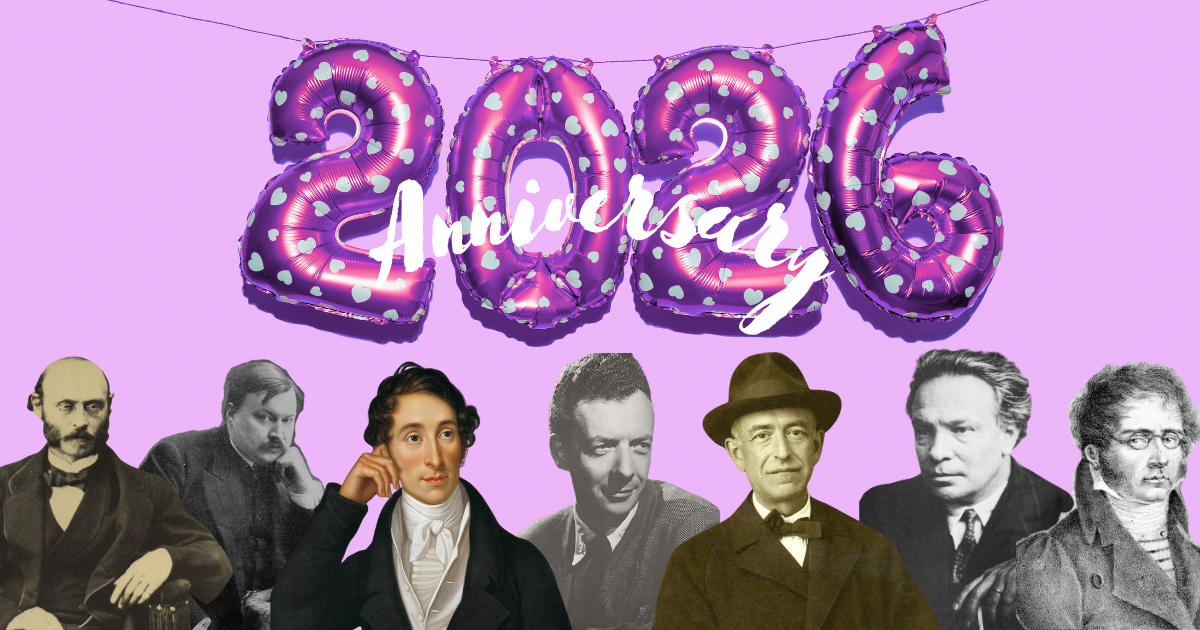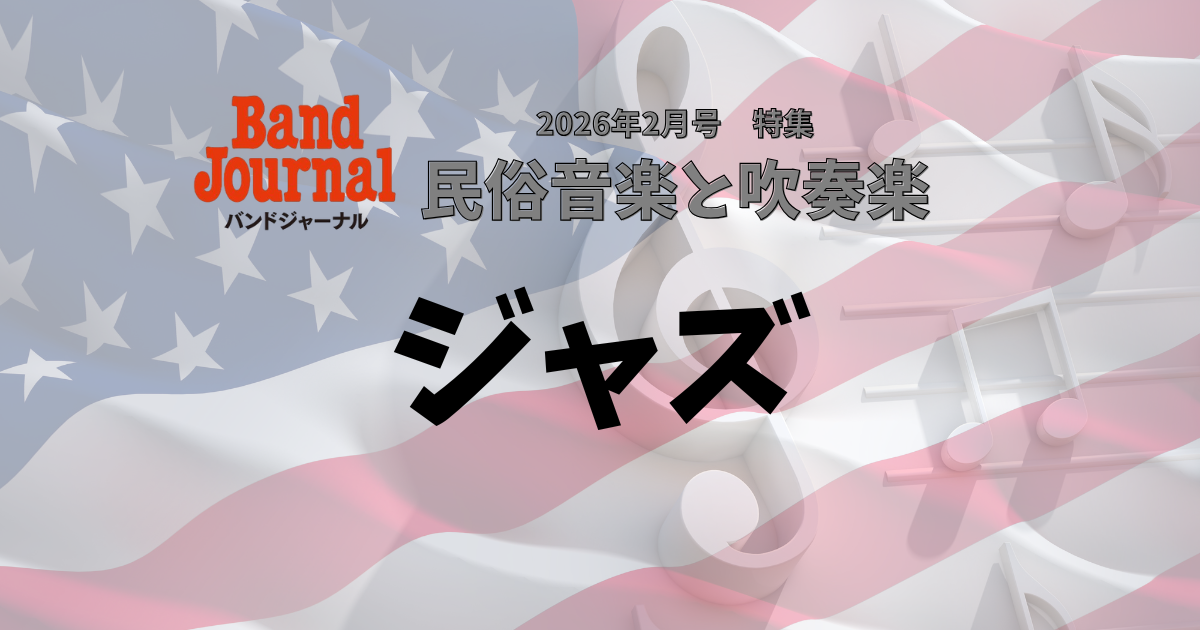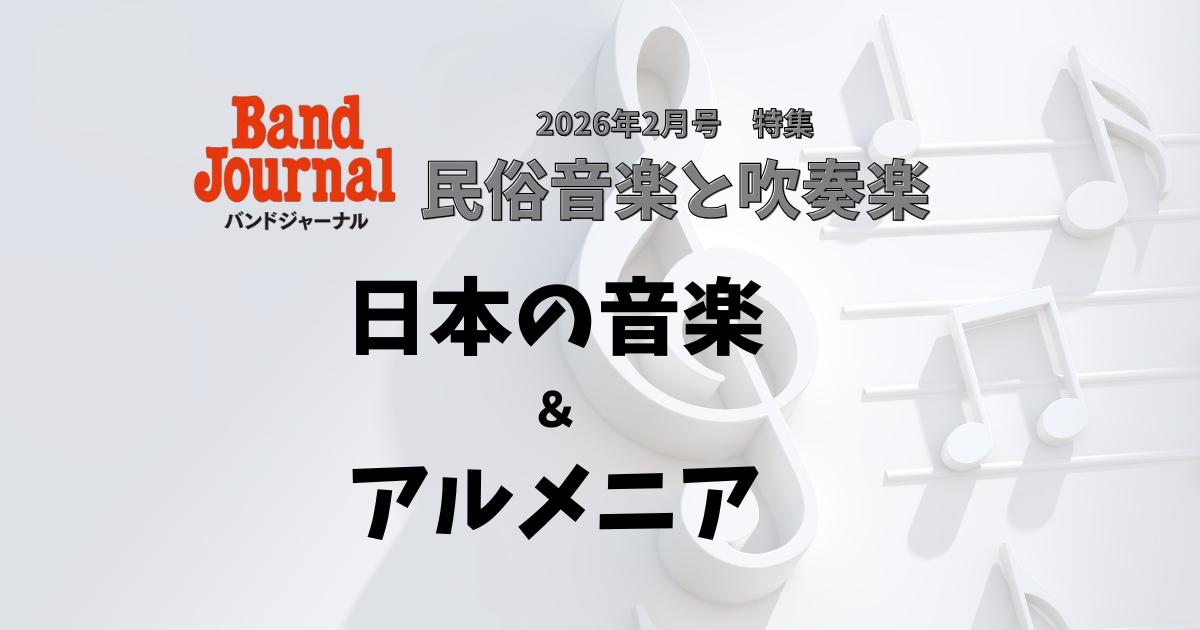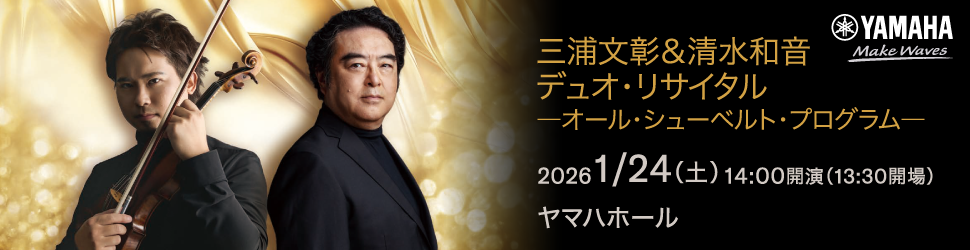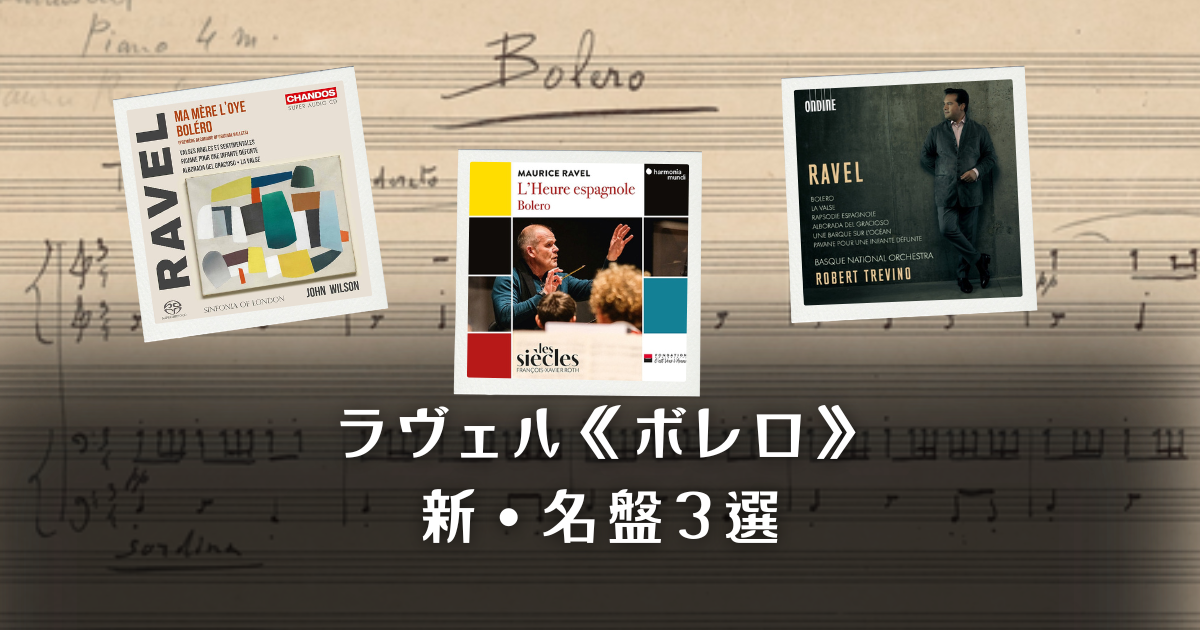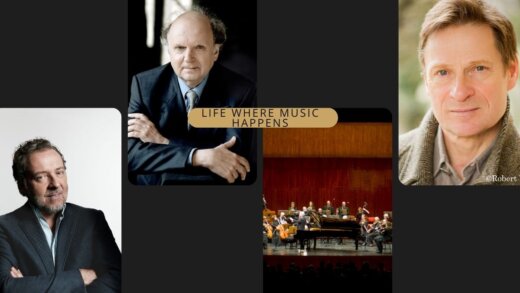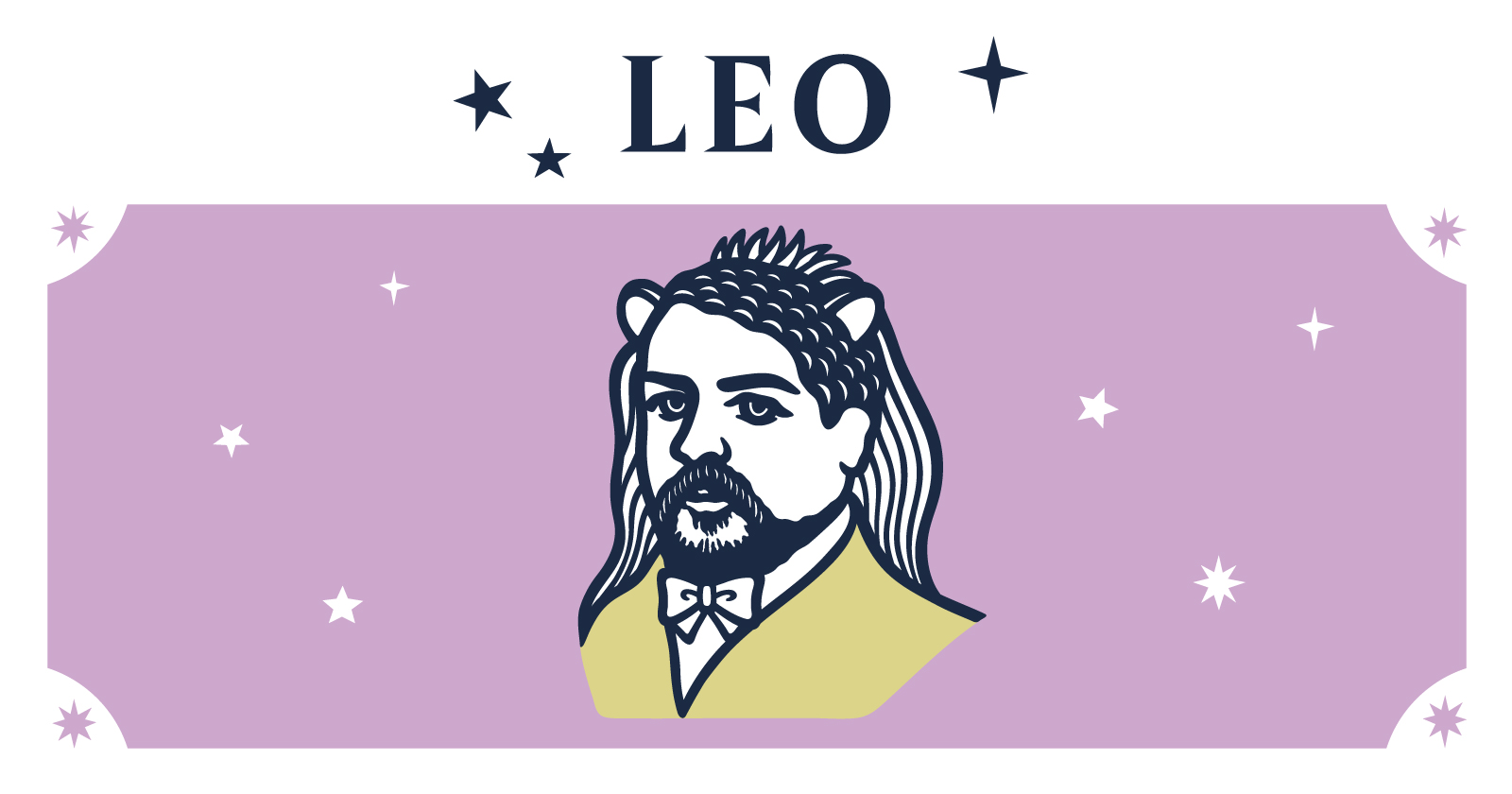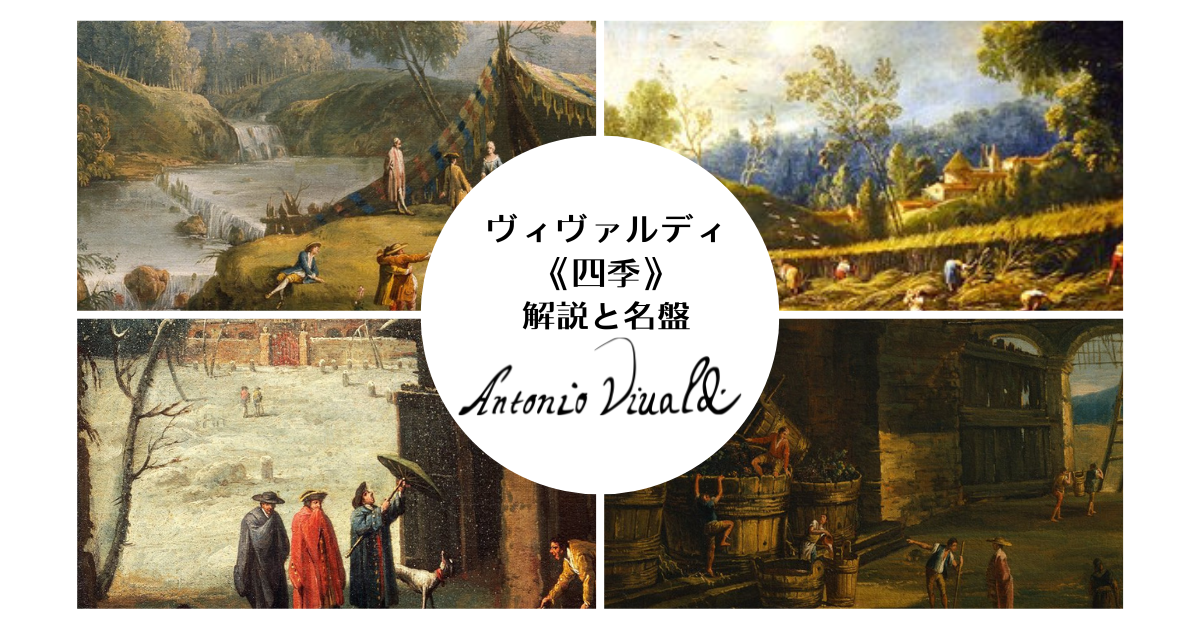日本センチュリー交響楽団副首席ホルン奏者・鎌田渓志さん「ホルンはパイプ役であり、オーケストラにおける要の存在です」

日本センチュリー交響楽団副首席ホルン奏者・鎌田渓志さんがホルンを始めたのは、中学校の吹奏楽部への入部がきっかけ。当初はトランペットが吹きたかったそうで、ホルンは希望をしていなかったとか。しかし、音のコントロールを身につけるうちに、音の多彩性に惹かれて楽器と音楽にのめり込んでいったそうです。ホルン奏者としての日常や、オーケストラにおける役割、そして音楽以外のインプットなどを伺いました。
「オーケストラの舞台裏」は、オーケストラで活躍する演奏家たちに、楽器の魅力や演奏への想いを聞く連載です。普段なかなか知ることのできない舞台裏を通じて、演奏家たちのリアルな日常をお届けします。

1997年大阪生まれの編集者/ライター。 夕陽丘高校音楽科ピアノ専攻、京都市立芸術大学音楽学専攻を卒業。在学中にクラシック音楽ジャンルで取材・執筆を開始。現在は企業オ...
吹奏楽部で始めたホルン
——ホルンを始めたきっかけを教えてください。
鎌田渓志さん(以下、鎌田) 中学生のとき、吹奏楽部に入部したことで始めました。実は、ホルンはまったく希望していなくて、本当はトランペットのように目立つ楽器を希望していたんですよ。たまたま楽器を決める期間に家族旅行に行っていて、次に部活に行くとホルンしか残っていなかった(笑)。
——当初、希望した楽器は何だったのでしょう?
鎌田 トランペットが第一希望でした。派手な楽器が吹きたくて。
そもそも、吹奏楽部に入ったきっかけは、もともと映画が好きだったからなんです。家族にデザイナーが多くて、映画にあるデザインやデッサンなどに興味を持って、その一環で音楽にも関心があって。
ホルンは希望していた楽器ですらなかったので、最初はジョン・ウィリアムズの音楽で自分の吹いているホルンが活躍している、なんて気づきもしませんでした。徐々に「ホルンって実はおいしい役割なんだな」と気づき始めて、のめり込みましたね。

関連する記事
-
インタビュー東京都交響楽団ヴァイオリン奏者・塩田脩さん「都響と石田組の両方で成長できる」
-
読みものラヴェル《ボレロ》の「新」名盤3選〜楽譜や楽器のこだわり、ラヴェルの故郷のオーケ...
-
連載【音楽が「起る」生活】読響とN響の演奏会形式オペラ、シフの親密な室内楽、他
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest