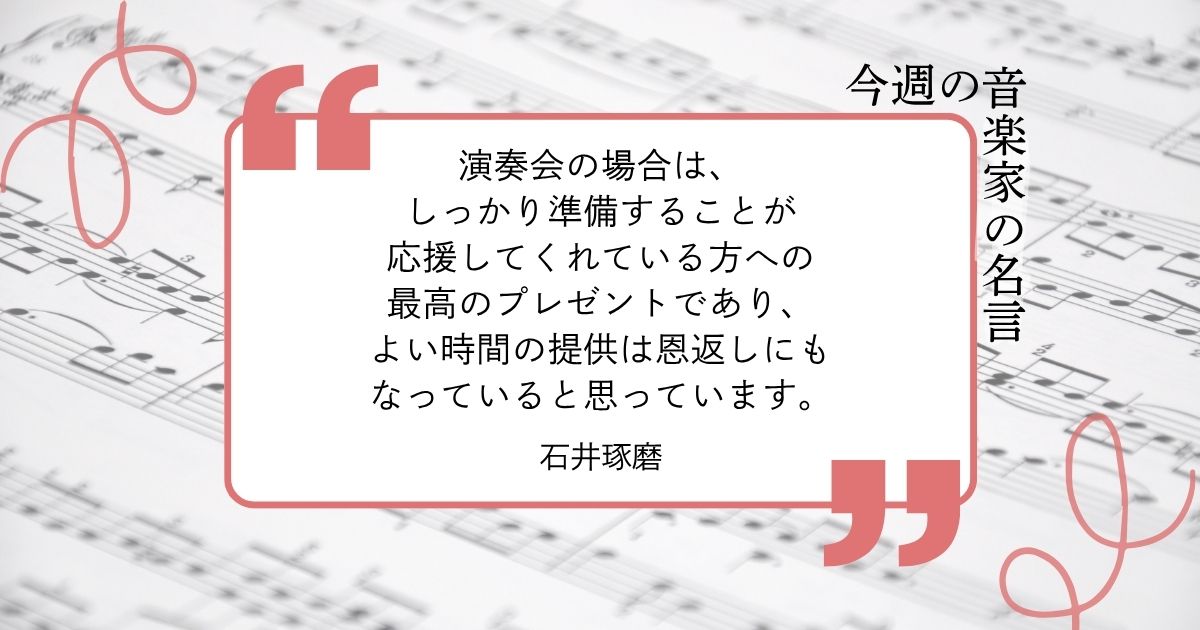挾間美帆のシンフォニック・ジャズが、オーケストラ×ジャズの新境地を切り拓く!

2016年、創刊80年を超えるアメリカのジャズ雑誌「ダウンビート」で、錚々たるミュージシャンの顔ぶれが並ぶなか「未来を担う25人のジャズ・アーティスト」に選出された日本人がいる。ジャズ作曲家、挾間美帆。越境する音楽家の原点を、「クラシックとジャズの融合」という切り口から探る。
いまだにジャズを、好事家の頑固親父が顔をしかめて聴くものだとか、お洒落なバーやカフェのバック・グラウンド・ミュージックだとか、思ってはいないだろうか? もし、そうした昔ながらのイメージにとらわれているのだとしたら実にもったいない。
21世紀に入ってからというもの、ジャズ・ミュージシャンは最先端のエンターテイメントとして音楽フェスの会場でロックを超えるほどの熱狂を引き起こし、他方ではクラシック音楽や現代音楽の分野でも芸術性を認められるジャズ作曲家が現れはじめているのだから。

国立音楽大学でクラシック音楽の作曲を学んでいた挾間は、2007年に突如として日本が世界に誇るジャズ・ピアニスト山下洋輔のコンサートに抜擢。山下と共作した《ピアノ協奏曲第3番「エクスプローラー」》は、2008年1月に佐渡裕の指揮により初演されて一躍話題となり、新鋭作曲家として注目を集めた。
その後、2010年にマンハッタン音楽院へ留学。ジャズの本場でジャズの作曲を学びだすのだが、わずか4年後の2016年には前述した通り「未来を担う25人のジャズ・アーティスト」に選出されてしまうのだから、その破竹の勢いには驚かされるばかりだ。
現在、ニューヨークを拠点に、日本やヨーロッパでも第一線で活躍する世界的な音楽家である。
クラシックとジャズを学校で学んだ挾間は自ら「ジャズ作曲家」という肩書を標榜しているが、実は手がけてきたジャンルはクラシックとジャズだけに留まらない。編曲やオーケストレーション〔※オーケストラ用のスコアを書くこと、並びにオーケストラ用の編曲〕の仕事としては坂本龍一、山下達郎、八代亜紀、五木ひろし、平原綾香、セーラームーン、ヱヴァンゲリヲンなど……とジャンルも年代もバラバラなのだ。なぜ、これほどさまざまなジャンルの音楽を仕事としてこなせるのか? 越境する音楽家、挾間美帆のヒミツに迫るべく、お話をうかがった。
挾間美帆の原点
――編曲家(アレンジャー)としての挾間さんが、どんなジャンルの音楽でも対応できてしまうのは何故なのでしょう?
挾間: それはひとえに、いろんな種類の音楽を小さいときから聴いてきたとしか言いようがないですね。父親は大のビートルズファンで、母親はアース・ウィンド・アンド・ファイアーや山下達郎やエリック・クラプトンの大ファン。そして、父方の祖父はベートーヴェン狂と言いますか、N響(NHK交響楽団)が大好きなおじいちゃんで、母方の祖母はコーラス大好きみたいな感じだったんです。プロのミュージシャンは一人もいないんですけど、この通り音楽好きの一家に育ちました。
あとは母が趣味で弾いていた電子オルガンで、ジャズのスタンダードナンバーとかをちっちゃい頃からずっと聴いていたんですけれど、実はJ-POPが完全に抜けてる。本当だったら小室ファミリー(小室哲哉)とか、完全に世代ど真ん中じゃないですか。でも私にとっては、「スキー場で聴く音楽」でしかなくて(笑)。
――もう少し上の世代だと広瀬香美さんみたいな感じでしょうか。
挾間: そう、それ! 本当なら世代ど真ん中だったはずのSPEEDとか、あの辺を全部私はすっ飛ばしていて。自分のお小遣いで最初に買ったアルバムは、アース・ウィンド・アンド・ファイアーのベスト盤だったんです。
――完全にお母様の影響ですね(笑)。
挾間: だからJ-POPは、小学校6年生になるまで全然わかんなくて。でも宇多田ヒカルの《Movin’ on without you》(1999)っていう曲が出たときに、「これは衝撃だ!」と思って。それまでJ-POPのCDなんて買ったことなかったから、すごい罪悪感だったんですよ。なぜか、J-POPなんか買っちゃいけない……みたいな暗黙の了解があると勝手に信じ込んでいて、ミスチルなんて買おうものなら……
――(笑)。
挾間: 決死の覚悟で宇多田ヒカルのCDを買ったのを覚えています。それぐらい色んなものを小さい頃からまんべんなく聴いてきたんですけど、唯一抜けてるのは演歌だったんです。NHKの歌謡チャリティコンサートをやらせていただいたときは、別の編曲家の方のスコアを見せていただいたりとかして勉強しました。やっぱり全然書き方が違うので。
あと、この前はじめてゲーム音楽のアレンジをしたんですが、ゲームも全然していないのでわからないんです。ゲーム音楽がループ(繰り返し)するものなんだって知らなかった。
――ゲームは映像の尺(時間の長さ)が決まっていないので、ほとんどの楽曲がループになっていますよね。
挾間: それを知らなくて「これどうやってアレンジすればいいんだろう……」って途方にくれました(笑)。
ダンスや視覚的なものと音楽のコラボレーションもすごく魅力的だと思うんです。だからPerfumeにハマったんだと思う。音も良いし、すごく独特。特徴があると思うから、そういう意味でも大好きです。K-POPなども、ちゃんとミキシングやマスタリングにお金をかけて、すごくいい人たちを使って、イギリスの最先端ポップス顔負けの布陣で曲を出したりとかしていますよね。もしかしたら、そういうことに興味があるというだけかもしれないな。
――現在は「ジャズ作曲家」という肩書で活動されているわけですけれど、こうしたさまざまな音楽への興味が下地としてあるんですね。意外な面もあって、とても興味深いです。

《ラプソディー・イン・ブルー》になってしまう
――さて、挾間さんはジャズのなかでも(昔でいうところのビッグ・バンドを含む)「ラージ・アンサンブル」と呼ばれる分野で主にご活躍されています。ジャズにおける作曲というとJ-POPや歌謡曲などと一緒で、作曲家はメロディとコード(和音)を書き、どの楽器にどのように割り振るかという作業はアレンジャー(編曲家)の仕事……と分担するケースが多かったかと思います。でもラージ・アンサンブルの作曲家は違いますよね。クラシックの作曲家と同じで、何段もある楽譜に音符を書いていきます。
挾間: もともとラージ・アンサンブルはダンスの音楽だったわけです……要は今で言うところのクラブ・ミュージックですよ。あそこまで奏者に合わせた曲を作った(デューク・)エリントンは凄かったと思いますけども、彼もやっぱりダンスホールの音楽だったという定義は変わらない。
でも、そこから(小編成の観賞用音楽へと変化した)ビバップの時代へ来たあとに、ガンサー・シュラーとか、ギル・エヴァンスとかがラージ・アンサンブルを、今度は芸術として段々復活させてきた辺りからの流れは、今でも変わっていないと思います。
奏者に即興できる人がいる限りは、即興のセクションを作るのはやっぱり醍醐味だし、ラージ・アンサンブルの醍醐味でもあると思う。だから書かれている必然の部分と、偶然性のある部分とのバランスみたいなのも含めて考えるのが、ジャズ作曲家の面白いところというか、腕の見せ所なんじゃないかと思いますね。
――歴史的にはラージ・アンサンブルとクラシック音楽の関係はどのようなものであったか、挾間さんはどのように考えていらっしゃいますか?
挾間: もうちょっと絡んでくれればよかったのにって思っています(笑)。ちょっとタイミングが悪かったなと思うのは、ガーシュウィン(1898–1937)のあとにダンスホールの音楽が流行ったわけですけど、その楽器編成がビッグ・バンドだけだったってところが勿体なかったと、私は思うんですよ。
(ガーシュウィンにラプソディー・イン・ブルーを委嘱した)ポール・ホワイトマンみたいな管“弦”楽団みたいなのを作って、それがダンスホールでやっててくれたら、今でもシンフォニック・ジャズ(=オーケストラによるジャズ)ってあったかもしれないじゃないですか。でも、あの当時のバンドは(コントラバスを除いて)弦楽器をゼロにしてしまったので。
――それがジャズのラージ・アンサンブルとクラシック音楽が、充分にクロスオーヴァーしなかった原因じゃないかって考え方なんですね。
挾間: そう! そこが、もっと絡んでいてくれていたら……いまのシンフォニック・ジャズのあり方って、全然変わってたかもしれないなと、実は思っています。
――では、挾間さんの認識では弦楽器を含んだシンフォニック・ジャズはどの辺りから出てくるのでしょうか。
挾間: ほとんどないんじゃないでしょうか。ガーシュウィンで止まっているから、今でもオーケストラと一緒にジャズを演奏しましょうっていうと《ラプソディー・イン・ブルー》(1924年初演)になってしまうんですよ。
ラテン系のジャズ・ピアニスト、ミシェル・カミロとフランクフルト放送響の演奏するラプソディー・イン・ブルー
挾間: あとはバーンスタイン。《オン・ザ・タウン》(1944)とか《ウェストサイドストーリー》(1957)は確かにそれっぽいんだけど、そこで止まってるのが非常にもったいない。それ以降もものすごく良い作曲家、それこそギル・エヴァンス(1912–88)とかいるのに、その人たちが書いていたインストゥルメンテーション(編成)がオーケストラじゃくてビッグ・バンドだ、というところで、気軽に演奏できる状況じゃなくなってしまっている。
――つまり当時のオーケストラがギル・エヴァンスに委嘱してたら、ちょっと現在の状況とは違ったんじゃないか? ということですね。
挾間: そうです。今やっと、チック・コリアがピアノ・コンチェルト書いたり、マリア・シュナイダーが、チェンバー(室内オーケストラ)と一緒にコンサートやったり、少しずつ出てきていますね……ビッグバンドのアルバムの量に比べたら少な過ぎますけど。
――しかもそういった作品は、ジャズファンには聴かれなかったり、評価されなかったりするのも、難しいですよね。
挾間: ジャンル分けが結構難しいんじゃないですかと思うんです。それこそチック・コリアのピアノ協奏曲をジャズのコーナーに置いてもジャズの人は違和感を感じて買わないし、クラシックの人は知らないから買わない。だから(ジャズのサウンドを取り入れた楽曲が人気を博している作曲家)カプースチンは「オイシかった」と思うんですよね。クラシックのところに思いっきり置いてあって、すべて書き譜のピアノ音楽だけど、ああいう感じの音楽をやりたい人っていっぱいいるから。だから、あれだけヒットしたじゃないですか。そういうことに、もっとなると良いんですけどね。
カプースチン Impromptu Op.66 No.2
――オーケストラを使ってシンフォニック・ジャズをできる人ってのが結局のところ、あまりいないわけですよね。そうすると、挾間さんの立ち位置が際立ってくるというか。
挾間: 自分はそれをしたくてしょうがないんです(笑)。いろんなところに「そういう活動がしたい」と言い回っています。
――それはやっぱりクラシックの作曲を勉強してきたっていうより、もともとオーケストラがとにかく好きっていうところがあるんですよね。
挾間: そうですね、それが私の音楽家としての原点でもあるので。
関連する記事
-
インタビュー東京都交響楽団ヴァイオリン奏者・塩田脩さん「都響と石田組の両方で成長できる」
-
読みものラヴェル《ボレロ》の「新」名盤3選〜楽譜や楽器のこだわり、ラヴェルの故郷のオーケ...
-
連載【音楽が「起る」生活】読響とN響の演奏会形式オペラ、シフの親密な室内楽、他
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest