
聴覚障がい者とつくる音楽がアートに! イノベーションを起こす新井鷗子の思考

音楽とは聴くもの、とだけ考えていると思い至らない、聴覚障がいをもつ方たちの音楽の楽しみ方。
障がい者とともに新しい音楽表現の在り方を探ってきた、東京藝術大学特任教授で、クラシックコンサート構成作家の新井鷗子さんにインタビュー!
クラシックコンサート構成作家の新井鷗子さんは、東京藝術大学の特任教授として、COI拠点の「インクルーシブアーツ」研究室で、障がいのある人との芸術活動「インクルーシブアーツ」の研究に取り組んでいます。
また、文章でひとりの音楽家の姿に迫る、子どものための伝記シリーズ「音楽家ものがたり」(音楽之友社)は、新井さんがわかりやすく、リアルな音楽家の姿を描いています。
今回の伝記シリーズで登場するベートーヴェンは、聴覚障がいがあったことで知られていますが、それをどのように捉え描いたのか、これまでの研究やプロジェクトの経験とともにうかがいました。
聴覚障がいの子どもたちとオペラを作る
——東京藝術大学COIのホームページを見ると、新井さんの研究分野「インクルーシブアーツ研究」の説明として、「感動と脳機能の関連性を探索しながら、芸術に触れる感動を障がい者から学ぶことにより、すべての人たちに夢をもたらす共生社会の実現を目指します」とあります。これまでの活動で“障がい者から学んだこと”とは、どのようなことでしょうか。
新井 藝大では、障がいのある人の芸術表現の研究を進めるにあたり、最初は障がいのある音楽家を招き、客席にも障がいのある方を招待した鑑賞型のプロジェクトを実施していました。2015年からは障がいのある人が表現者として舞台に立つ機会を提供する方向へと転換していきます。
聴覚障がいのある人とのかかわりとして、2018年に「からだできくオペラ」を企画・実施しました。ワーグナーの《ニーベルングの指輪》より「ジークフリート」を題材にとり、その一場面をプロの演奏家と聴覚障がいのある小学生・中高生がともに創り上げるプロジェクトです。


活動は、3回のワークショップ形式でおこないました。耳以外のすべての感覚を作って、オペラを創り上げるのです。
風船を楽器に近づけて振動を感じる体験や、登場人物に合わせた字幕フォントをつくる活動をしました。物語から想像して作った粘土造形を使いクレイアニメ―ションを製作したり、登場人物に合わせたオリジナルの香りをつくるなど、多彩な試みをしました。
オペラの歌詞づくりもしたんです。決まった数の音符に、日本語の歌詞を当てはめる方法をとりました。小鳥やヘビの歌うアリアの音符を数え、それが7つの音だったら7文字の言葉で、登場人物の雰囲気を表す歌詞を考えました。例えば、小鳥のアリアの歌詞を考えるとき、歌詞「あぁ私は小鳥。○○○○○○○の声で歌うわ」を、小鳥はどんな声だと思う? と考えさせて、「かわゆい涙(7文字)」の声で歌うわ、という歌詞を聴覚障がいの子どもたちが考えました。
ワークショップの3回目は、音楽ホールでの上演会です。でき上がった歌詞をプロのオペラ歌手が歌い、舞台の背景にはクレイアニメ映像を流し、会場には香りのボックスや風船、振動スピーカーを設置するなど、耳以外の感覚を刺激する作品ができ上がり、全員でオペラを楽しみました。
オペラは音楽や演劇、美術、文学といった、さまざまな要素が合わさってできる総合芸術です。耳が聞こえなくても楽しめるのではないか、と考え、オペラに含まれる要素を洗い出し、再構築したら、このようなワークショップになったというわけです。
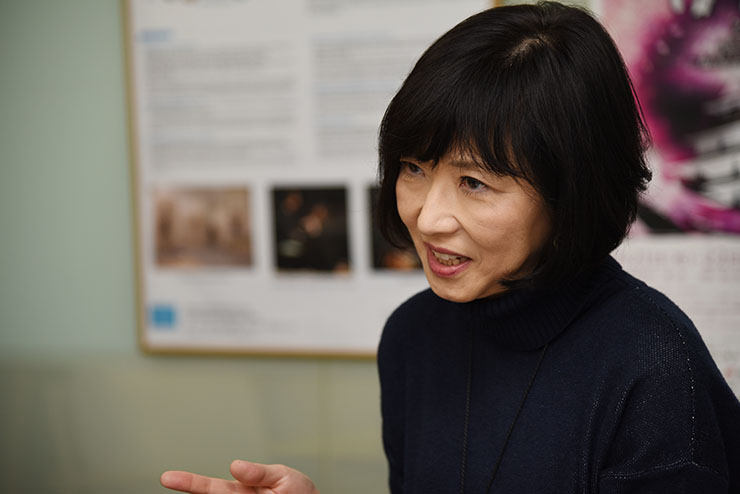
発想の転換が共生社会を創る
——「からだできくオペラ」をはじめ、聴覚障がいをもつ方への音楽の活動から、どのような発見があったのでしょうか。
新井 舞台を作り上げるプロセスを通して、さまざまな気付きがあり、考えの転換を促されました。
たとえば、私たちは「高い音」と言うときに、自分の手を目線より上にかかげて表そうとしますよね。でも、音の「高さ」とは本来、地面からの距離という意味での「高さ」とは違う性質のものです。だから「高い音」を聴覚障がいの子どもたちに感じてもらうには、それでは伝わらないと思いました。
そこから、音の高低をさまざまな素材の布で表現し、子どもたちにその手触りを感じてもらう試みが生まれました。こうした発想の転換から音楽の可能性を発見することが「障がいから学ぶ」ことだと思っています。
ワークショップのあいだ、子どもたちはわくわく、真剣に取り組んでいて、ビビッドな反応を返してくれました。聞こえない・聞こえにくいのに、どうやってプロのオペラ歌手や奏者のすごさを感じるのかといえば、それは表情や動きを見て、そして「オーラ」を感じとっているのです。私たちはワークショップの終わりには「この子どもたちは音が聞こえない、聞こえにくいだけなんだけれど、それが何か?」という心境に至りました。
近年、障がいのある人とともに活動をしたいと考える企業が増えています。一流の演奏家たちも参画するようになってきました。これは2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、障がい者の芸術文化振興に関する機運が高まっていることが大きく影響していると感じます。
ぜひ、大会後もこうした試みが特別なことではなく、公共ホールにはヒアリングループ(※)が設置されて、盲導犬が来ても誰も驚かない、といった、ごく普通のことになっていくのが理想的です。全国各地のホールが小規模でもいいから、障がいのある人を対象にした事業を自主的に企画制作できるようになればと思います。藝大COIのコンテンツも今後、積極的に地方に貸し出していこうと思っています。
(※)ヒアリングループ:マイクなどの音声信号を電気信号に変えて、補聴器や人工内耳で聞き取れるようにする設備。磁気誘導ループともいう

ベートーヴェンは何に困っていたのか
——ベートーヴェンも聴覚障がいを抱えていました。ご著書の伝記にもその葛藤を描かれています。音楽家が聞くことができない、というのはやはり大変なことではないかと想像しますが、ベートーヴェンは、どんな気持ちだったと思われますか。
新井 私がこれまでの活動を通して感じているのは、聴覚障がいの人たちの中には音楽が大好きな人がたくさんいるということです。楽器を演奏したり、アンサンブルをしたり、歌ったりして音楽を楽しんでいます。
だから、ベートーヴェンのことを「聴覚障がいがあっても作曲ができたからすごい」という視点で捉えないでほしいのです。私はベートーヴェンは普通とは違う聞こえ方で作曲をしていたのであり、私たちが想像するほど困ることはなかっただろうと思っています。では、何が困ったかといえば、人とコミュニケーションを取ること、会話をして何かを伝えることだったのです。
伝記では、おいのカールが、ベートーヴェンと筆談でなければ会話ができないことにいらだったエピソードや、 指揮者としてオーケストラの前に立ったとき「耳が聞こえなくなったのでは」と言われたことにおろおろする、といった場面を入れました。付録には「聴覚障がいと音楽」のコラムも加えていますので、合わせて読むとより理解が深まると思います。
——インクルーシブアーツの活動が、今回の伝記に活かされているのですね。新井さんの「音楽家ものがたり」シリーズを読むと、ベートーヴェンやモーツァルトといった偉大な音楽家の“人となり”もわかるような気がして、とても身近な存在に思えてきます。音楽の、また音楽家の素晴らしさを読み手の心に届ける文章は、どのように書いているのでしょう?
新井 時や空間を越えて、過去の人と交流ができるのが音楽の素晴らしさだと私は考えています。メロディや音そのものの素晴らしさはもちろんですが、ベートーヴェンの想いに私たちが共感できるのは、ベートーヴェンの音楽があるからなのです。この伝記を通して、時代や空間を越えて、リアルに人とつながることができるのが音楽の魅力なんだと、その部分が伝わればいいなと願っています。

関連する記事
-
読みもの《第九》が年末に演奏される理由とは?《第九》トリビアを紹介!
-
読みものベートーヴェン《月光》の献呈相手ジュリエッタのことを友人に綴った手紙
-
読みものベートーヴェンの生涯と主要作品
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest




















