
第2回:全日本ピアノ指導者協会 事務局長 加藤哲礼さん

若き音楽家たちが才能を競い、熾烈な闘いを繰り広げるコンクール。舞台の表でも裏でも、さまざまなドラマが展開しているであろうことは想像にかたくありません。コンクールにもさまざまなレベルや種類がありますが、全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)が運営する「ピティナ・ピアノコンペティション」は多くの参加者が集い、世界でも最大規模のコンクールです。その全体をマネジメントするのが、ピティナ本部事務局長の加藤哲礼さんです。巨大コンクールの裏の裏(!?)を知る加藤さんは、はたしてどんな思いで運営にあたっているのでしょうか。
30年計画で考えるコンクールの「評価」
巨大コンクール運営の面白さ
――ピティナのコンペティションは、参加者数がすごく多いですよね。

加藤 そうですね。今年も参加人数は予選だけで3万2千組ほどです。下は3歳から、上は70代の趣味の方までいらっしゃいます。
――参加カテゴリーがいろいろありますね。「A級」から「F級」、そして大学・大学院生を中心にプロを目指す人たちが受ける「特級」、アマチュアの大人向けの「グランミューズ部門」等々。事務局長である加藤さんのお仕事は、その運営のマネジメントということになりますか。
加藤 ピティナは「ピアノ指導者協会」としてさまざまなプロジェクトを抱えており、コンクールの運営はそのうちの一つです。私は全体の業務内容やスタッフの配置を考えたり、若手職員の育成をしています。コンクールも含めてそうした日常的な業務が8割とすれば、2割は若いピアニストたちの育成サポートにも力を注いでいます。コンクールで「特級グランプリ」を受賞した若いピアニストたちを、その後どうプロモーションしていくかも考えていますから。
――コンクール運営の仕事は、どんなところが大変ですか? 面白いところは?
加藤 全国規模の巨大プロジェクトを、滞りなく動かしていく面白さはありますね。鉄道会社の路線って同時にたくさんの電車を動かしているじゃないですか。あれに近い快感というか。
6月末から7月の頭は、全国的に予選の数が多くて、同じ週末に45箇所で開催していることもあります。審査員は各地区に5、6人が必要です。先生方に審査依頼をし、宿泊や交通の手配を整えて派遣し、そこにたくさんの参加者たちがわーっと集まるのを受け付けて……。ときには、台風のために開催を中止するかどうか迷ったり、そういうことも含めて、滞りなく運営させていく面白さ。もっと言うと、審査に対して親御さんからクレームだって寄せられますから、そういうこともスタッフみんなで考えて乗り切っています。

――コンクールというと、演奏に点数をつけて競い合うというイメージもあって、一般的には賛否両論が寄せられる世界ですよね。
加藤 「競争」というと悪い印象をもたれるけれど、特に小さい子たちは、ある程度人と比べて自分の立ち位置を知ることで、もう少し前にいきたいなと思うこともありますよね。「お友だちが持ってるから私もほしい」というのは子どもにとって日常的に起こること。同世代の人に刺激されて、「レベルアップしていきたい」と思うのは人間の根源的な欲求だし、社会動物としての自然な欲求です。その欲求に対する力の付け方、磨き方を、ピアノを使って知っていくことは、一つの方法としてアリだと考えています。
私自身コンクールに思い入れがあるわけではないですし、いろいろな意味で弊害が起こりうるのは百も承知です。
ただ、小さな子どもたちにとっては、練習嫌いとか、緊張だとかを乗り越えてステージに立ち、評価をもらって帰ってくる。そういう環境を作れているというのはいいんじゃないかと思っています。

演奏家たちの「成長」への興味
――「コンクールに思い入れはない」とのことですが、加藤さんは国内外のコンクール事情に大変お詳しいのだとか。その調査もやはり仕事の一環なのでしょうか。
加藤 私は2003年に入社して、まずは事務局のあらゆる業務をやりました。会員担当、チラシ作り、ウェブマスターなどなど。
2010年からはピティナのトップで現・専務理事の福田成康から引き継ぐ形で事務局長に着任しましたが、その少し前から、コンクールそのものというより、コンクールを受ける若い奏者たちの成長に関心が強くなっていました。彼らが今後、どう研鑽を積んで、どう育っていくのか。そこに非常に興味が湧いたのです。あくまで個人的な興味関心、趣味みたいなものですから、仕事とは別に自腹で新幹線をとったり代休を使ったりしながら、いろんなコンクールを聴きに出かけるようになりました。
とにかくあらゆるコンクールをチェックして、どんな参加者がどんな演奏をして、どんなふうに評価されているかを知りたかった。会社からも少しずつ理解をもらえるようになって、国内のコンクールだけでなく、ショパン国際コンクールや、エリザベート王妃国際コンクール、ロン=ティボー国際コンクールにも出かけていきました。
――すごい! 熱心ですねぇ。

加藤 趣味ですから!(笑) そうこうしながらたくさん聴いているうちに、コンクールの結果からいろんなことを感じるようになりました。いい演奏をした人が落ちて驚いたり、コンクールは水物だなぁと感じたり……。
――それは……コンクールを運営する団体の事務局長としてはある意味過激な発言ですねぇ。あ、でもここは「趣味」でしたね(汗)。

加藤 いや、でもその中で気づいたんですよ。演奏家の成長にとっては「誰に聴いてもらうか」がとても大切だということに。たとえば、演奏とは、作品を解釈し、全体を構築していく行為です。その中で「やれる」ことばかりをアピールするのではなく、「何をやらないか」を決めた上での設計もされています。ただし、その意図的な設計を聴き取れる耳を持った人に聴いてもらわなければ、単に「やれていない」と評価されてしまうだけ。「できてないから、やってください」と言われてしまう。
審査員の中には、審査する側に回ったとたんに、「できていなかったこと」を上から目線で羅列してしまう人がいる。「音色がありません」とか。正直、その方の演奏にも感じられるようなことだったりするんですよ! 驚くほどそうです。

「評価する」を変えるには、30年かかる
――となると、評価する側、審査する方の耳、姿勢が非常に重要になりますね。
加藤 ピティナとしては、どうやって審査のクオリティを担保するかを絶えず考え、審査員の依頼にはとても慎重になります。特に、セミファイナリスト7名を絞り込む「特級二次予選」の審査員にはこだわります。そのクラスの若い弾き手の演奏に「あなたがやっていること、やらないと決めたことに、ちゃんと気づいていますよ」と伝えることができて、その上で評価という形で成長を促してあげられる方。多面的な聴き方をなさり、教育的な視点から奏者をリスペクトしてくれるような方に審査していただきたい。ただし、それができる先生は非常に限られています。
――審査依頼は大変な仕事になりそうですね。
加藤 参加者に「この人に演奏を聴いてもらえるなんて幸せでしょ?」と自信をもって言える方を審査員にお迎えしたい。「あなたに聴いてほしいのです!」とラブコールを送り続けて引き受けてもらっています。一人30〜50分の演奏に真剣に対峙してくれる先生方は、ご自身の音楽にも真摯に向き合っている方ばかり。今年は若手の審査員として松本和将さんや田村響さんをお迎えしました。


現場の空気を体感。
――そういう審査員が揃えば、参加者は結果を出すことだけにとらわれるのでなく、聴いてもらうことで成長の糧にできる、という捉え方ができますね。
加藤 日本の音楽教育においては、上手くなればなるほど、学習が進めば進むほど、自分を「評価する人」ばかりに向かって演奏するようになり、自分の音楽を「喜んでくれる人」のためには弾かなくなる構造になっています。
小さい頃はおじいちゃん・おばあちゃんに喜んでもらうために弾いていたピアノですが、次第に「才能があるんじゃないの?」とか周囲に言われて、地元の偉い先生のもとに通うようになる。音高・音大の入学試験で演奏し、学内の期末試験などで演奏する。気がつけば、みんなが喜んでくれる発表会やちょっとしたコンサートではなく、自分を評価する人の前でしか弾かなくなる。
評価される場でばかり弾いていると、評価を得るために、わかりやすい部分を整えようとする。端的な例で言えば、ミスタッチを少なくしようとしますよね。「喜んでくれる人」「涙を流してくれる人」の前ではなくて「点数をつける人」の前で弾くと、そうならざるを得ない。「○×をつけます」「点数つけます」という人の前でミスを多くしたい弾き手はいませんから。

「日本の子たちはそういうことばかり気にして、音楽がつまらない」と一面的な批判をする人がいます。業界の評論家だったり、無責任な人たちが言うんですよ。そういう仕組みを作ったのは誰ですか? 大人たちなんじゃないですか? だったら、評価しようとするのではなく感動を求めて聴いてくれる人のために弾ける演奏の場を、大人たちが作ってあげなさいよ、と思います。それをやる覚悟もないなら、外野からくだらない批判をしないでほしい。
――日本のクラシックの土壌には、なぜか「評価してやろう」という聴き手側の「上から目線」が、いつまでもはびこっているような気がします。

加藤 その状況を変えていくには、「評価する人」や「教育する人」が考え方を変えていくしかなくて、それには世代が変わるしかないと思いますね。ジェネレーションをひと回りさせるには30年かかる。私が審査について考え始めたころ、30年計画で物事を捉えようと思いました。その頃から10年が経ち、その頃に海外に留学に出て、日本に戻ってきた世代が、審査し始めています。30年計画の10年が過ぎました。
音楽に感動を求めて聴いてくれる聴衆層をきちんと育てるにも、やはり30年は必要ですね。ピティナのコンクールを小さい頃に受けた人たちは、みんながみんなプロの演奏家を目指すわけではなく、受験などを前にピアノを辞めてしまう人がほとんどですが、音楽を聴いて感動できる聴き手には育ってほしいと期待しています。聴衆育成プロジェクトとしても、コンクールを機能させたいです。


ピアノと世界とをつなぐ視点
変わりゆく海外コンクールの「結果」
――「評価」する審査員を慎重に選ぶことで、参加者の成長を促すコンクールを目指している加藤さん。特級グランプリを選ぶ審査員は、海外からも呼んでいますね。
加藤 演奏活動はもちろん、国際コンクールで入賞する素晴らしい生徒を指導していたり、審査やアカデミーなどで真剣に教育活動に従事している先生にお願いしています。今年はカナダとフィンランドとフランスから来ていただきます。
――ということは、やはり海外のコンクールの動向をいつも見ていないといけませんね。ここ最近の海外の潮流はどうなっているのでしょうか。
加藤 大きな国際コンクールには、揺り戻しが起こっています。
――揺り戻し?

加藤 中国・韓国・日本の若いコンテスタントが、パワフルでテクニカルな演奏でガーッと出てきた時代から、「やっぱり音楽性重視」みたいな傾向に戻ったのです。それが、2010年のショパン・コンクールあたりで明らかになりました。
2005年には中村紘子先生や(アンジェイ・)ヤシンスキ先生や(ピョートル・)パレチニ先生など、国際コンクールの審査を知り尽くした先生方が審査員でした。1位のブレハッチはダントツの優勝でしたが、2位はいなくて、3位が韓国の二人、4位が日本の関本昌平さんと山本貴志さんの二人でした。
2010年は審査員にアルゲリッチ、ダン・タイ・ソン、ネルソン・フレイレといった、演奏活動で世界の最前線にいるアーティスト勢が審査に加わりました。結果は、優勝者のアヴデーエワのように、すでにプロのアーティストのように演奏ができて、インタビューなどでも自分の言葉ではっきりと音楽を語ることができるような人たちが入賞しました。そうなると日本勢はまったく通用しません。二次予選の段階で誰も通りませんでした。
そして2015年は、1位のチョ・ソンジンは磨き抜かれた別格として、前回の傾向を引き継ぐように、アートな感性を持ったリシャール=アムランが2位となった。そして新しい動向としては、エリック・ルー、トニー・ヤンらのような、アジア人の姿形をしたアメリカやカナダの10代の子たちが入ってきました。彼らはジュリアード音楽院やカーティス音楽院で教育を受けたアジア系なのです。彼らのように十代の早熟な才能が、確信をもって自分の音楽を語れるようになってきています。
ショパン・コンクールは5年に1回なだけに、傾向がはっきりと現れますね。

――なるほど。2015年までに裕福なアジア系アメリカ人が音楽教育を受け、優れた若者たちが育成されているという流れなのですね。
加藤 なぜアメリカが強くなったかといえば、ヨーロッパから高い教養と指導法をもった一流の先生たちが、こぞってアメリカの音楽院に着任したからなのです。
一方で、ジュニア向けのコンクールの流れとしては、どんなにテクニカルにミスなく難しい曲を弾きこなせても、叙情的に音楽を作ることができなければ即落ちるというコンクールも出てきました。今年3月にデンマークで行われたコンクールなのですが、日本からも一人「チャレンジしてみたら?」と僕から声をかけ、受けてきてもらいました。可能なら若いうちから海外に出て、成功体験を積んでもらいたいと思って。
そのコンクールでは、韓国の子が完璧にメフィスト・ワルツを弾いても、中国系の子が鮮やかにラヴェルのスカルボを弾いても、落ちるんです。それよりも、シューマンの「子供の情景」やショパンの「ノクターン」を繊細なタッチやペダリングで音色の操作をし、叙情的に弾ける子が通りましたね。
――いろいろな流れが巻き起こっているのですね。世界では「評価」のあり方が、とても動的であることがわかりました。

加藤 ヨーロッパにいれば、そういう情報が地続きで入ってくるのでしょうね。ネットでもなかなかわからないこともありますから、こちらは常時しらみつぶしに情報をかき集めている感じです。
そういう流れの中のキーパーソンを見定めて、ピティナの特級ファイナルの審査にお呼びしています。たとえば、前回お呼びしたのはスタニスラフ・ユデニッチ先生。ウズベキスタン出身ですが、2001年のヴァン・クライバーン国際コンクールの優勝者であり、コモ湖ピアノアカデミーの教授でもあります。まだ40代半ばですが、今年のクライバーンでも彼の生徒が銀メダルに輝きました。
海外から審査にいらした先生たちには、マスタークラスもやってもらいます。公募で書類審査の通った9名に、3人の先生が総当たりで2日間教えるのです。レッスン後はオーディションをして、ピティナの創始者の名を冠した「福田靖子賞」受賞者を決め、奨学金でさらに磨きをかけてもらうことが狙いです。
かつてジャック・ルビエ先生が「レッスンすれば、その子のポテンシャルがわかる」とおっしゃっていました。コンクールの1回きりの本番では、若い人はまだ変動要素が大きいですからね。レッスンを通じて若い人たちを「聴いてもらう」場も設けているのです。

ピアノで世界を平和にしたい!
――それにしても、どうして加藤さんはそんなに若い人の「成長」に関心があり、音楽家に育ってほしいと願うようになったのでしょうか。もともと、教育関係に興味があったのですか?
加藤 いえ、僕は外交官になるのが小学生からの夢でした。ピアノは楽譜が読める程度には習っていましたが、将来は外務省に入ることを考えていたんです。

――それで入学されたのは、東大の法学部(!)ですよね。大学生までは外交官を目指していたのでしょうか。
加藤 大学でいろいろ勉強してもう少し現場のことを知ったとき、なんというか、国際交流の方法としては政治や外交調整は古典的な気がしたんです。
外交にはさまざまな問題解決をはかってきた歴史があるけれど、それでも解決できない問題はたくさんある。「国」という枠組みでナントカ協定に加入したり離脱したりで揉めているうちに、環境問題のように待ったなしの地球レベルの問題は深刻化していく。100年単位、200年単位で考えたときに、もしかすると別の方法に頼れば、より早い問題解決ができるかもしれない。
たとえば、「音楽」のような手段に頼るほうが、政治に委ねるよりも早く国際的な問題を解決できるのかもしれない。在学中からそんなふうに考えはじめました。
――そこで音楽を思いつかれたところがユニークですね。
加藤 大学2年のとき、たまたまレンタルCDでホロヴィッツの弾くショパンを聴いたのをきっかけにクラシック音楽にハマり、塾講師のアルバイト代を中古CDにどんどんつぎ込んで、400〜500枚くらいのCDをコレクションしていた時期でもあったんです。
そんなあるとき、ピティナの関連企業、東音企画のウェブサイトでコンサート情報を調べていたら、横に「採用募集」と出ていて、社会科見学に行ってみようと思ったら、ピティナがくっついていた。それがピティナとの出会いです。面接を受けて先ほどのような話をしたら、ピティナのトップである福田が「音楽でもできるよ」と、面接なのに持論を語り出し(笑)、「はい通過です、来てくださいね」ということになりました。

――では、加藤さんの最終目標は、音楽で世界を平和にするということなのですね。30年計画どころか、100年単位、200年単位で考えておられたとは!
加藤 「スポーツで世界を平和に」みたいな言葉は、普通にCMでも流れるし、オリンピックも開かれて「スポーツで仲良くなれるといいね」と普通に考えられている。でも「音楽で、ピアノで、世界を平和にしたい」と発言すると、「あら随分スケールの大きな話ね」みたいな反応をされてしまう。けれど、それは音楽業界にいるわれわれの努力が足りないのだと思います。
これまでとは違った切り口で、音楽の魅力を掘り下げたり、言語化したりしないと、状況は変わっていきません。若い音楽家や聴衆を育てながら、どんな切り口があるのかを模索したいと思っています。まだその答えはわからないので、見つけていく過程が面白いと思っています。
■コンクール特級二次予選に密着!(2017年8月2日・3日)



平和をつくるツールとしての音楽
音楽とは、つないでいくもの
――100年、200年のスパンで「ピアノと世界平和」を考えているお話には一瞬驚きますけど、でも、クラシック音楽の長い歴史を考えると、そんなに驚くことではないのかも。
加藤 そうなんです。クラシックは何百年も受け継がれてきた伝統芸術です。だからこそ、次の世代へと受け渡していくことこそが、もっとも重要なことなんです。ですから、有名ピアニストの中には自分のリサイタル活動ばかりに専念していて、まったく教育活動していない人がいますけど、私はそんなのあり得ないと思っています。

クラシック音楽とは、つないでいくもの。日本の子たちは欧米から地理的に離れてしまっているので、自分につながっているものや、自分に注がれてきた流れがどういうものなのかを知らなすぎます。「私の師匠は○○先生です」とは言えても、その先生の先生が誰なのかは知らない。
たとえば、伊藤恵先生の師匠はハンス・ライグラフ先生ですが、そこからもう何代か遡れば、ツェルニーやベートーヴェンにつながっているわけですよ。そこにロマンを感じられないで「ベートーヴェンの気持ちを表現しよう」なんていうのはナンセンス! ベートーヴェンの作品がどう書かれた作品なのかを考えるのと同じように、自分が教えてもらった音の出し方や音楽の捉え方に興味をもつことだって大事でしょう。
で、教えてもらってきた流れに興味をもてれば、今度はそれを自分がどう未来につなげていくか、と考えるのは必然的ではないでしょうか。そうならない人は、クラシック音楽をやる知性が足りないと思います。ピアノを上手に操作できて、みんなが褒めてくれるからやっている、というだけでは残念な話です。

――よく「演奏活動ができなくなったから教える側にまわる」みたいな、教育活動をまるで第一線から後退するかのように捉えるイメージがありますが、まるで違いますね。第一線の人ほど、自らの演奏活動も教育活動も同時にやっていますね、年齢に関わらず。
加藤 さきほども話題に出たショパン・コンクールで第4位に入賞した関本昌平さんなんて、「育てること」に今ものすごく夢中になっています。
彼自身、音楽の内容に対して本当に関心をもち、自分が取り組んでいる作品の自筆譜を調べたり周辺の作品にも関心を広げたのが、コンクール入賞後にアメリカに渡り、素晴らしいクラリネット奏者チャールズ・ナイディックと出会ってからだったそうです。「気付くのがあまりにも遅かった」といつもおっしゃっていて、だからこそ、早いうちから子どもたちにそれを伝えようと、今必死になっています。
最初は音大生など大きな生徒を教えていたんですが、その年齢では遅い、もっと早い段階から……とやっていくうちに、小学校3〜4年生くらいからの教育が大事だとわかったそうですよ。
演奏は「サーカスの曲芸」ではない
――小学校3年生、というのが絶妙な年齢かもしれないですね。それより小さいと、「教えてもらったことだけを上手にやって褒められる」だけで十分かもしれない。
加藤 これは完全に個人的な意見なのですが、私はいわゆる「天才児」には興味がありません。小さい子がどんなに見事に難しい曲を弾きこなしたり、感情たっぷりに演奏できても、身体も心も急に変化していきます。軽やかに動かしていた身体は急に大きく重たくなるし、心もピアノじゃないものに興味が出たりする。自分はこのままピアノで突き進んでいいのかと悩んだりもする。
そうして大人になっていく中で、それでも音楽を選びとるかどうかが大事なんです。難曲を見事に弾きこなす運動性のアビリティはリスペクトしますが、自分の意思で選びとっていないのであれば、サーカスの曲芸と一緒。自分で選んだときこそ、本当の勉強が始まる瞬間でしょうね。

――子どもが「自分で選びとる」時間を、大人たちは作ってあげたり、見守ったりしなくてはいけないですね。
加藤 最初はある程度、先生が丁寧に導いてあげなくてはなりませんが、子どもたちが成長しはじめて、少し専門的な段階になっても手取り足取りやりすぎると、その反動が出てしまったり、弊害となって現れるケースをいくつも知っています。
ピアノを辞めないように「面白いでしょ、面白いでしょ」とたくさん用意してしまうケースも、自分で考える力を奪ってしまいますね。コンクールの課題曲だけは完璧に弾けるし、E級やF級で入賞もする。しかし実際のところ、その子がほとんど楽譜を読めず、ベテランの先生のもとに預けられたときにビックリ!……というような例も。
――私は日頃ピアノ教室をよく取材させてもらいますが、ピアノの先生たち、優しくなりました。私たちが子どもだった昭和のピアノの先生のイメージって、たいてい「怖い」でしたよね? 弾き終わって、冷た〜い沈黙のあと、「一週間何してきたの? 今日はもうレッスンしません。帰りなさい」と叱られるみたいなエピソード、今はとんと聞かなくなりました。
加藤 正解はないことかもしれないけれど、昭和のそういう教え方だって、「なんで先生、あんなに今日怒ってたんだろう?」と子どもなりに考えるきっかけになったかもしれない。
――それは確かにそうですね。何も教えてくれないのは困るけれど(笑)。

加藤 やっぱり基礎なんでしょうね、先生がしっかり教えてあげるべきことって。まず何より、クラシック音楽は緊張と弛緩の組み合わせでできているという大原則。難しい理論までわかっていなくても、緊張と弛緩を長いスパンと短いスパンで組み合わせながら、感動を届けるというのがベースじゃないですか。それすら知らずに弾いている人がいる。
幼稚園の年長さんに与えるのと同じようなことを、小5になっても与え続けてはいけないですね。音楽づくりの仕組みを与えてあげてほしい。そこさえ共有できたら、自分の頭で考えて音楽づくりができる人になると思います。
――与えられたことを真面目にこなすだけでは、本当の音楽は生まれない。でも案外、ピアノを習っている人が陥りやすい点かもしれませんね。教わることだけでも、すごく多いですから。
加藤 教えてもらったことを使って、自分に何ができるか。音楽ってそれを考えながら一生かけてやっていくもので、きっとそこが面白いのだと思いますよ。
アルゲリッチやらポリーニやら、すごい演奏家は山ほどいるのに、なぜあなたはピアノ弾くの? という問いに、サラリと答えられる人が音楽家として幸せな人だと思います。

フランスでテロが起こったときに、ピアニストのフランソワ・デュモンと食事をしていたのですが、彼はテロリストたちに対して、「彼らには、クラシック音楽が足りていないんだよ」と言いました。彼はいつでも音楽とともにある人、生きてることが音楽みたいな人です。そういう人は、自分の人生と音楽との間に隔たりがない。
学生たちを見ていると、音楽との距離が遠い人がいます。ステージでの演奏が緊張するのはわかりますが、舞台袖にいて膝の上で練習してみたり、弾く前に鍵盤を長々と拭きまくったり、天を見上げて祈ってみたり、いろいろな人がいます。舞台への取り組み方はさまざまなのでしょうが、そんなふうにしてわざわざスイッチを入れようとしている時点で、あなたと音楽との近さはその程度なんですか? と思います。
自己の存在意義自体が音楽とダイレクトに結びついている人は、ピアノの前に出てきたら、自然にすっと弾き始めます。いちいち祈ったり、スイッチ入れたりなんてしない。だって、音楽したくて仕方がないんだから。
クラシック音楽で、成熟した社会の想像力を磨く
――音楽と自分とが、どうしても近付いていってしまう人、そういう人がきっと、一生かけて音楽と面白く付き合っていけるんでしょうねぇ。
加藤 他の分野の人に言ったら怒られるかもしれないけど(笑)、私は音楽は最高に知的な総合芸術だと思っています。教養をもって立ち向かわなければならない究極の総合芸術です。練習室だけでやってる場合じゃないですよ。

――教養とは、単なる知識量というのとも違いますね?
加藤 教養とは、知識と知識をつなげる力だと思います。音楽をやるには、文学や建築や絵画の知識が必要になるし、ピアノの機構をうまく操作しようとしたり、感動の源泉を論理的に考察したりしようと思ったら、物理学の知識や数学的なものの考え方にも興味が湧くはず。音楽は、そういうさまざまなアングルから知識を有機的に結びつけて、知性を総動員して向き合えるものだと思います。
――先ほどのお話にあった「基礎」がしっかりあれば、さまざまな「知識」をつなげて「教養」に変えられるのかもしれないですね。
加藤 「ここさえ押さえておけば、全部つなげられる」というポイントがあるんですよね。たとえば、東大入試は本当によくできていて、教科書に書いてあることをきちんと理解しておけば、全部解ける良問なのです。
僕は高校時代を理数科で過ごしたのですが、同級生に数学オリンピックに挑戦したり、トップクラスの医学部や理学部に行ったり、数学が大好きな友人がたくさんいました。マニアックな数学雑誌に投稿して「エレガントな回答」を求めるような人たちです(笑)。
彼らにとって大事なのは、公式や定理を覚えて問題を解くことではなく、たとえば「2回掛けてマイナスになる数があるとしたら……」と仮定をひとつ立てて、そこから論理的な必然として理論体系や定理を構築すること。正しいか正しくないかではなく、あるひとつの約束事を立てることで、そこから広がる世界を考えていくこと。きっと人類がロケットを宇宙に飛ばせたのは、そういうものの考え方をする人たちがいるからでしょうね。

音楽活動も、それに通ずる人間ならではの知的な作業です。音楽業界にいる私たちは、そういう世界の入り口にあるという自覚をもっていたいですね。音楽に興味がない人たちに、そういう面からも真顔で伝えていきたいです。「わかる人にはわかる、わからない人にはわからない」などと言わずに。
――音楽にアプローチする切り口は無限にありますね。「世界を平和にする」もその一つですね。
加藤 音楽は国際交流ツールである、平和を作るツールである、ということを私は真顔で言い続けるつもりです。

――よく「音楽は世界の共通言語」という夢見がちなフレーズを耳にします。私は音楽って、そんなに生やさしいものじゃないと思うんです。方言よりも、外国語よりも伝わりにくいのが音楽かもしれない。ただ、加藤さんが今おっしゃった「ツール」というのはストンと納得できます。ツール=道具を便利に使えるのが、知性をもった私たち人間ですから。
加藤 たしかに音楽は、文化や時代の固有性を色濃く映し出すものですから、そう簡単に通じない面もあります。ただ本当に、音楽への切り口は無限にありますね。作品には無限の解釈があり、多様な表現スタイルが成り立つということ一つをとってみても。
――世界的にも今の社会では「多様性=ダイバーシティを認める」ことが重視されています。それによって、一つの居心地のいい場所に居続けられないために不安になった人たちが、揺れ戻しのように、超保守的な考え方の政治家にリーダーシップを感じる向きもあります。多様性を考えるあまり、拠り所を失うような感覚なのかもしれません。コンクールの結果というのは、ある種そういった拠り所として機能するのかもしれませんが、それを運営する加藤さんが、いろいろな考えを抱えながら奮闘しているのが面白いです。
加藤 コンクールでは、多様な考えをもった審査員が多様な視点から点数やコメントを書きます。しかし一人一人の立ち位置には一貫性がある。そもそもダイバーシティとは、一人一人の立ち位置が曖昧だと成立しない概念です。それぞれに明確な立脚点があってこそ必要となる概念なので、もう少し成熟した社会に適した用語なのかもしれないですね。

でも、これからの世の中においては、みんなが必要なことだと共有している。多様性、つまり相手のことを思いやれる想像力を鍛えるには、クラシック音楽ほど最適な素材はありません。
100年も200年も前に外国の人が書いた、喜びも悲しみもぐちゃぐちゃに混ざった曲なんかを真顔で弾くわけでしょう? その時代に生きた人の感情を、自分の中に引き受けられるのだとすれば、同じ時代の隣りにいる人に思いやりをもったり、多様性を認めるなんて簡単なことですよ。そういうツールとして、クラシック音楽を再定義しなくてはいけませんね。日本にいる私たちは、本場ヨーロッパと遠いところでそれをやっているのだから、その〈遠さ〉を強み、アドヴァンテージとして捉えて良いのだと思います。
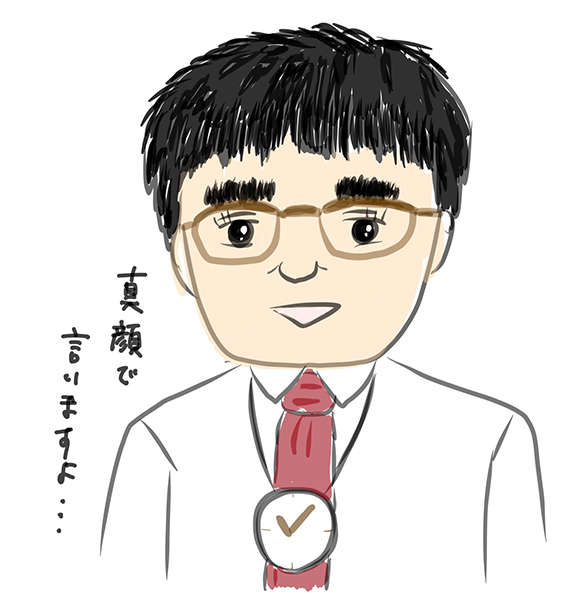





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest




















