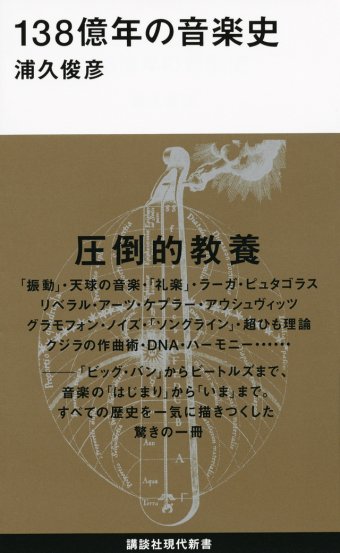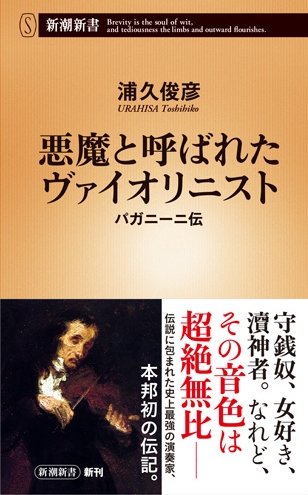文化芸術プロデューサー浦久俊彦——クリエイティヴィティを発揮できる文化的な社会を

クラシック音楽ファシリテーターの飯田有抄さんが、クラシック音楽の世界で働く仕事人にインタビューし、その根底にある思いやこだわりを探る連載。
第16回は、文化芸術プロデューサー、文筆家などの肩書きをもつ浦久俊彦さん。音楽と文学、音楽と建築、音楽と食など、音楽とさまざまな文化を掛け合わせた企画で、コンサートやイベントの企画・制作、国際交流事業の開催、芸術家たちとの対談や講演、執筆などの多岐にわたる活動を行なっている。指揮者の山田和樹さんとの対談シリーズも話題だ。その仕事と人となりに迫る。

1974年生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学院修士課程修了。Maqcuqrie University(シドニー)通訳翻訳修士課程修了。2008年よりクラシ...
演奏はせずとも音楽家である
——文化芸術プロューサーとしてコンサートや音楽祭の企画制作や執筆など、活動は多岐にわたっています。欧州日本芸術財団の代表理事であり、サラマンカホールの音楽監督も務めておられます。
浦久 肩書きはだいたい6つくらいあるんですよ(笑)。これは自慢でも何でもなくて、ぼくは組織に属さない生き方を選んだので、いろんな仕事をして自分の価値を高めていくしかない。自由業とはいえ、生活設計もできないし、安定もしにくいので、リスクを分散させる。例えば、コロナ禍で演奏会は全部だめになっても、なんとか書いて食いつなぐ……みたいな。そういうことが少しずつ身についてきたんですね。
「文筆家」とか「プロデューサー」という肩書を用いることが多いのですが、ぼく自身は「音楽家」だと思っています。音楽をよりよい社会のために活かすことや、音楽をいかに社会をよくするために役立てるか? を考えるのも立派な音楽家の仕事ではないかと思います。
ただ、ぼくみたいな人間が「音楽家です」というと、じゃあ何を演奏するんですか、何を作曲するんですか、とか、すぐそういう話になる。でも、音楽家=演奏家とイメージされるようになったのは、そもそも近代からです。かつては「音楽とは何か」を考える人、音楽と宇宙を結びつけて捉える人がムジクス(音楽家)と呼ばれていた。演奏家が、宮廷楽士や旅芸人のように呼ばれていた時代です。
日本では、音楽を社会に役立てるという視点で仕事をやっている人はまだ少ない。そういう人材や環境が整ってくると、日本の音楽文化は豊かになっていくと思います。
(指揮者の)山田和樹くんが、幸い私の本『138億年の音楽史』(講談社現代新書)を読んでくれて、面白がってくれたんです。彼はとても謙虚な人ですから、「それまで『音楽とは何か』なんて考えたこともなかった」と驚きを示してくれました。
音楽家=演奏家と狭い視点で捉えるだけでは、音楽が文化として根付かないような気がします。音楽は本来、世界や宇宙と結びつくほど、はてしない広がりのある世界です。クラシックとかジャズとかジャンルで分けられるようなものでもない。この点は、音楽界の中にいる人間が一番考えなければいけないと思う。
今のコロナ禍において、人と人とを結びつける音楽はどうあるべきか? インナーサークル化してしまっている現代の音楽業界は、内から変わっていなかなければならない。自分たちに音楽が必要だから生き残らなければならないではなくて、自分たちは、本当に社会から必要とされているのかということを、内部にいるわれわれがきちんと謙虚に批判し、外から見る目も失わずにやっていくことが求められていると思います。

日本人が西洋音楽をやることの意味
浦久 フランスで学生だったころ、どうしても拭い去れない問いがありました。ある日、音楽学校で友人から「おまえ、日本人のくせに、なんで西洋音楽やってるの?」と訊かれて、答えられなかった。すごく小さいころから西洋に憧れてきたのに……。あれから、ずっとその問いに向き合ってきて、40年近く経った今も、正直にいってまだ答えは見つかっていません。なぜ日本人である自分が西洋音楽をやるのか。
——日本人がなぜ西洋音楽をやるのか。答えのない問いなのかもしれませんが、考え続けたいテーマです。外国に出て、初めて気付かされることかもしれませんね。
浦久 そうですね。若い人は、一度は海外に出たほうがいいと思います。少なくとも20代のうちに、ふたつの異なる国の文化を知るべきです。複眼的な視点があれば、文化の地図が描けます。『138億年の音楽史』は、そのような想いで書いた本です。モグラのように物事を掘り進むだけだと、視界がどうしても狭くなる。ときには鳥になって幅広い視点で文化を眺めてみる。そうすると、音楽があらゆるものとつながっているのがわかる。そんな俯瞰的な視点から音楽を捉えてみようというメッセージを込めたつもりです。
——浦久さんが、対談イベントなどで音楽について語る際に、心がけていることはありますか?
浦久 観客にいかに参加してもらうかを意識して、一緒に考えていこうという空気感は作りたいですね。演奏家も無言の空気感を受けて演奏しています。コンサートは、観客があってはじめて成立します。観客のいない演奏は、ただのリハーサル。観客とともに作っていくことは、いつも心がけています。
このコロナ時代には、オンラインの形で演奏が発信されることが多くなりました。いい部分もありますが、人と人とのリアルなコミュニケーションの貴重さを、演奏家は訴える立場でもあってほしい。何よりも、観客とのコミュニケーションのかけがえのなさを誰よりも知っているのは、演奏家自身であるからです。
いまや日本中が、自粛ではなく萎縮しているように感じています。危機管理上、仕方がない部分もあるかもしれませんが、みんなが手探りで再開しはじめるしかない。何よりも怖いのは、国民の間に流れる「空気」の波です。「空気」には逆らえない。客席の空気に励まされるのが音楽家ですから、空気の怖さをよく知っているのも音楽家のはずです。

音楽が劇場の外に飛び出す時代へ!?
——コンサートホールがこれまでどおり運営できる日は来ると思いますか?
浦久 ぼくは、フランスや日本で、何十年という時間を劇場にかかわってきましたが、歴史的にみて、いまは劇場の役割が変わる過渡期にあるのかもしれない。劇場文化にも時代の役割があります。18世紀のイタリアの劇場は、あらゆる階層の人たちが一堂に会することができる唯一の広場でもありました。桟敷席からボックス席まであり、貴族はボックス席を買い取り、自分たちの好きなように壁紙やら額やら内装を施していた。そこに社会の縮図があり、それがひとつの文化を形成していた。そこから、19世紀革命期で貴族制度が崩壊して、市民文化の時代が到来すると、大衆向けの、みんなが平等に楽しもうという劇場文化に変わっていきました。
これからの劇場文化はどうあるべきかという問題は、コロナ騒動の前から、ずっと考えてきました。正直にいって、まだ劇場関係者としてベストな答えは見つけられていませんが、もしかすると、われわれは、そろそろ劇場から外に出ることを考えるべきときなのかもしれません。日本では昔ながらの盆踊りみたいに、広場でみんなで踊ったり音を出したりする時代に、再びコミュニケーションのあり方が変わっていくかもしれない。
そもそも、じっと「聴く」だけの文化って、日本にはなかったんですよ。音楽はただ聴くだけでなく、参加するものでもあった。演者も観客もみんなで叩いたり、踊ったり、うたったり。みんな座って、ただ大人しく聴きなさいよ、これが音楽文化ですよ、と植え付けられたのは、西欧音楽が入ってきた明治時代以降です。であれば、そろそろその文化が役割を終えるというのもあるのもしれない。もし、社会がもはやそれを必要としなければ、の話ですが。
ハコモノ行政と批判されながらも、いま日本には、2000ものコンサートホールがあります。それを、これからの地域の文化のためにどう活用するのか。これを町づくりや文化の拠点とするには、どうすればいいのか。おそらく答えは、一つひとつのホールが地域に根を下ろしていくしかない。
では、そのホールを生かすための人材を育ててきたかというとそうではない。日本の音楽教育は、演奏家教育にあまりにも偏って、多くの演奏家を送り出してはきたものの、その演奏家たちを受け入れ、育ててくれる土壌や有効に活かせる劇場がない。それがいまの現状です。
公共事業とアート、文化としてのアート
——行政の話が出ましたが、音楽に税金のサポートは必要だと思いますか?

浦久 ぼく持論があって「アートとしての芸術」に税金は投入されるべきではないと考えます。「文化としての芸術」であれば、国は全面的に支援するべきだと思います。
あいちトリエンナーレの問題がありましたが、あの芸術祭の運営が、もし税金によってではなくて私的な資金であれば、何の問題もなかったはずです。「表現の自由」は確かに尊重されるべきです。でも「アートなんだから、口は出さずに金は出せ」という、ある種傲慢ともいえるアーティスティックな考えが、国民の税金を蝕む社会にはなって欲しくない。もしアートに価値があって、ビジネスとして成り立つならば、資本経済のなかで成立させればいい。実際に現代アートの世界では、そうやって経済的に成功している人もいます。でも、税金を使うということは、それによって公共の福祉に役立つからこそです。
クラシック音楽界でも同じことがいえます。「ぼくたちは芸術を、素晴らしいことをやっているんだ」と音楽家がいくら主張しても、それが社会全体のためではなくて、一部の音楽ファンを喜ばせるためだけならば、多くの国民はそっぽを向くでしょう。クラシック音楽は自分の生活になくてもいいと思っている人がほとんどのなかでは、東京にオーケストラが9つも必要な理由を見つけるのは難しい。オーケストラはこれこれの理由で社会にとって必要なものなんだと、日本ではたしてどれだけ説得力をもって説明できるでしょうか。それは、クラシック音楽が、西洋からの借り物の文化に過ぎなかったということなのかもしれない。
社会をよりよいものにするという意味で、文化は必要です。国民が文化としての芸術を通じて、さまざまな視点を身につけ、価値観の多様性や、ものの見方の多様性を持った社会は、利他的で、寛容な社会になっていくはずです。日本はそもそも文化の豊かな国で、未来の文化という新たな道を世界に示せるポテンシャルがある。それは、20年以上、日本を外から見てきたから、ぼくにはよくわかります。
——このコロナの状況下においては、説得力のある活動はなかなか難しくとも、公金を使わなければ成り立たない面もありますね。
浦久 確かにそうですね。でも、税金によって助けられているということは、音楽事業も公共活動そのものということです。であれば、音楽をいかによりよい社会づくりに活かせるかという視点は忘れてはいけない。音楽が目的ではなくて、よいよい社会の実現が目的だからです。それから、これからは、組織にしがみついて、己を殺すような生き方よりも、もっと自立して生きる個人が増えて欲しい。そうすれば、より社会とのつながりが必要だということがわかると思います。
コロナの影響で、いま、多くの演奏家や劇場関係者が仕事を奪われて苦労していますが、大丈夫。ぼくも、振り返ってみると人生の半分くらいは仕事がなくて(笑)、いったい何を食べてたんだろうという感じでしたが、それでも死ななかった。人間はそう簡単には死にませんよ(笑)。
——浦久さんがおっしゃると、妙に説得力が……(苦笑) 浦久さんにはやはり生き抜けるだけのクリエイティヴィティがあったのだと思いますが。
浦久 そんなことはありません。いつもギリギリなだけで(笑)。ぼくは、まったく組織に向かない人間で、組織では人間関係の中で気を使って、息を殺して過ごしてしまうような人間でしたから。だから、ホール運営という危機管理の現場では、自由な発想は何ひとつ生まれなかった。企業での働き方を知っている人からすると、ぼくのようなのは、なっちゃいないと思いますね(笑)。
——リスク管理とクリエイティヴィティは真逆の発想、と言われますからね。
浦久 クリエイティヴィティにとっては、いかに精神をヒマな状態にしておくか、がすごく大事だと思います。危機管理だけでなく、日々の業務に追われて、ルーティンみたいに朝から晩まで忙しくする生活のなかでは、ぼくの経験では、クリエイティヴィティを育むのは難しいと思います。

日本を離れようと決意した、独学好きの「落ちこぼれ」時代
——浦久さんと初めてお会いしたのは確か、『フランツ・リストはなぜ女たちを失神させたのか』を出版されてすぐの頃でした。2014年くらい。とある講座でお話を伺ったら、もう本当に面白くて! 長年に渡りフランスで暮らしていた浦久さんだからこそ、ヨーロッパに息づく生々しい歴史観のようなものを、わかりやすく伝えてくださったのだと思います。
浦久 ありがとうございます。そんなふうに聞いてもらえてうれしいです。でもぼく自身は、極端な「アカデミズムの落ちこぼれ」で、失敗と挫折だらけで、若い頃はコンプレックスの塊でした。
——え、そうなんですか?
浦久 小学時代から落ちこぼれでしたね(笑)。小学1年生のときに、1足す1が、なぜ2になるのがわからなかった。リンゴならわかるけれど、水滴だったら大きな固まりの1になる。たぶん、窓についた雨の粒なんかを眺めていて、そんなことを考えたんでしょうね。だから、「1足す1が、2にならないこともあるんじゃないですか?」って、先生に訊いたんですよ。そしたらメチャクチャ怒られた。「屁理屈」と言われた。「ろくな大人になれないぞ」と。まぁ、結果的にロクな大人にはなれなかったけど(笑)。でも、ものすごいショックでしたね。
——それはちょっと先生ヒドいですね。大人のひと言が大きく影響することはありますよね。
浦久 いま思えば、ぼくもちょっと理屈っぽい子どもでしたね。でも、もし先生が「君が言っているのは、数と量の問題の違いだね」とか何とか話してくれたら、なるほどと納得できたかもしれない。
ともかくぼくはそこで、日本の教育はダメだと思ってしまった(笑)。「そんなことも教えてくれないなら、学校なんていらない」って。それからは、授業を聞くのをやめて、毎日、学校に本を1冊持っていって、それを授業中にずっと読んでました。だから成績はひどいものでした。落第こそしなかったけれど。そして、日本を離れることばかりを考えるようになった(笑)。
——え、まだ小学生ですよね?
浦久 そうですね。子どもの頃、親が買ってきたレコードでクラシックを聴くのが好きで、自然にヨーロッパに憧れた。それで、独学で音楽の勉強をはじめたんですが、ヨーロッパに行きたいというと、親からは猛反対されました。音楽を作曲したいなら、ギター持って、古賀政男みたいにやればいいじゃないか、と。
——ご両親はどんな方だったんですか?
浦久 父親は船乗り、母親は専業主婦。父は大正生まれで、学歴がなく、すごく苦労して勉強して一等航海士の免許を取って捕鯨船に乗っていました。大学も出ていない。今もよく覚えているのは、息子のぼくに「日本の人脈というのは、大学で築かれるのだから、お前は日本の大学を出ないなら、もし帰ってきても日本にお前の居場所はないと思え」と。それ正解ですよね。
でも、猛反対を押し切って行くことにしました。どうしても師事したい尊敬する作曲家がいたんです。アンリ・デュティユーです。それでフランスを選びました。19歳の頃でした。

フランスで待ち受けていた挫折と、永遠の問い
——なんと! あのアンリ・デュティユー!?(※1916-2013/ドビュッシー、ラヴェルらの跡を継ぐ、きわめてフランス的な作曲家と称される)
浦久 はい。でも、あっさり断られました。そのとき「音楽とは教えられるものじゃない」と言われたんです。苦労してフランスまでやってきたのに、いきなり扉が閉じた。小学校以来、数え切れないほど挫折はありましたが、最大の挫折のひとつです。では、音楽とはいったい何だ? という問いで頭の中がいっぱいになってしまった。
でも、もちろん日本に帰るに帰れない。それで、パリの音楽院で作曲の勉強をはじめたけど、これがまたぜんぜん身につかない(苦笑)。和声学や対位法のアカデミックな授業って、パズルみたいなもので、その日々の中で「音楽とは何か」という問いが、ますます大きくなっていって、学校も中途半端にやめてしまった。完全に袋小路ですよね。それからも、ほんとうにいろいろな挫折があって、フランスでの青春時代は暗黒の日々でしたね。
でも、デュティユー先生の後日談があるんです。何年も経ってから、先生にお会いできる機会があって、そのときに言ったんです。「先生に『音楽とは教えられるものではない』と言われたあの日から、私はずっと『音楽とは何か』と考え続けています」と。そしたら先生が、「ちがう、私はそんなこと言ってない」と言うんですよ(笑)。「『もう音楽は教えてない』と言ったんだ」と。「自分は今はもうクラスも受け持っていないし、個人的に弟子をとってない。そういうつもりで言ったのに、お前はなにを勘違いしたんだ??」と。……バカ丸出しですよね(苦笑)。つまり当時、ぼくはまだフランス語のニュアンスを聴き取る力がなくて、勝手に言葉の意味を取り違えてしまった。
——わかりやすく、言葉が壁になってしまったんですね。
浦久 でも、ひょっとすると、自分の中にずっとあった問いを、先生の言葉と結びつけていたのかもしれない。

フランスで国宝級の職人たちをプロデュース
——それでもフランスで、音楽で日々の生計を立てておられたんですよね。
浦久 はい。でも、本当にいろいろなことがあって、ずっとフランスにいたまま日本に帰ってこなかったわけではないんです。夢破れて一時帰国した期間もあったり、日本でコマーシャルの音楽を作っていた時期もあったりしました。その頃、フランスのある財団が、音楽、建築、美術、いろいろな分野でプロデュースできる人を探している、ということで、再びフランスに舞い戻りました。
そこからは、フランスの音楽ホールや音楽祭のプロデュースの仕事をはじめましたが、その財団は、芸術振興だけでなく、フランスの優秀な職人たちをサポートする活動もしていました。
フランスにはM.O.F.(Meilleur Ouvrier de France)という最優秀職人制度があって、料理や宝飾や家具や鞄などの職人が取得するもので、日本でいう人間国宝のような称号ですが、その職人たちをプロデュース、サポートする仕事が印象に残っていますね。フランスのバッグ職人たちの営業をしていたときは、パリの一等地にショールームを作ってディレクターをやったり、日本のフランス大使館の経済部と連絡をとって、日本の百貨店の外商部と仕事をしたり、まったく畑違いのこともやったりしました。その財団のオーナーがご高齢となり財団は閉じることになり、その後3、4年して日本に完全帰国することになります。
電気もガスもない、ブルゴーニュでの仙人暮らし
——財団のプロデュース業を終えられて帰国するまでの3、4年は何をなさっていたのですか?
浦久 電気もガスもなにもない田舎での生活です。子どもの頃から憧れた、ほぼ仙人の生活(笑)。
——え?
浦久 バッグ職人だった友人が、パリのアトリエを引き払い、パートナーとブルゴーニュ地方にアトリエを構えたんです。ぼくはパリからよく車で遊びに行っていたんですが、時間の流れがゆったりしたいいところでしたね。まわりは葡萄畑、人もいない。夏のバカンスの時期は1ヶ月くらい滞在させてもらったりしていたんですが、近くに小屋があって、そこでしばらく暮らすことになったんです。電気もガスもない、小さな小屋。
そのときはじめて、19世紀の音楽家たちがどういう音世界に生きていたかが、実感としてわかったような気がしたんです。機械の音、電気のノイズがない状態で生きていると、すごく耳が洗われていく。どんどん聴覚が研ぎ澄まされていくんです。そのなかで生活していると、ピアノの音が聴こえてきただけで、涙が溢れてくる。
とにかく、静寂の世界、電気のない世界はこういうことなんだ、と。クラシック音楽に登場する音楽家たちは、みんなそういう世界に生きていたわけですよね。世紀末から20世紀になって、都市の音を作曲に取り入れる作曲家も現れてきますが、マーラーにしても、現代の電気ノイズの世界とは次元が違う。彼らの耳の感覚は現代人と全然違うんです。
その頃も、たまにパリに戻れば、都会の騒音でクラクラして倒れそうになる。スマホなんかやっている現代のぼくたちの耳は、そもそも音楽を鑑賞できる耳なのか? という疑問をその生活の中で痛感しました。

日本での活動スタート、そして闘病
——帰国はいつでしたか?
浦久 2003年です。縁あって、仲道郁代さんの企画を手掛けたのが、最初の仕事でした。そののち、名古屋の三井住友海上しらかわホールにエグゼクティブ・ディレクターとして就任して、7年間ほど、名古屋で暮らしました。
——日本での活動開始は順風満帆ですね。
浦久 ところが、その頃、癌が見つかりました。中咽頭癌でした。すでにリンパに転移しており、ステージ4。医者からは「5年生存率も危ない」と言われました。闘病生活は、かれこれ約1年に及びました。痛みがあまりにひどくなると鎮痛剤も効かなくなるのでモルヒネを使う。麻薬ですよね。半分もう夢の世界にいるような、ものすごく嫌な気分になる。治療の最終段階では1日に1キロ体重が落ちて。何もしなくても、10日で10キロ。体力がどんどん奪われて、痛みが一番激しかったときに、ふと何かのスイッチが入ったんでしょうね。
そういえばぼくは20歳のころに、自分が50歳になったら本を出そうと決めていたと思い出したんです。そしたら、まるでシャンパンの蓋を開けたときみたいに、パーーッと書きたいことが次々と浮かんできたのです。ああ、これで自分は死ぬまで本が書けるな、と(笑)。
——今はすっかりご病気は完治されたのですよね?
浦久 はい。おかげさまで完治しました。そして、そのときに自分の命があと5年しかないとすれば、自分に、何ができるか。そう真剣に考えるようになりました。
自分のために仕事するのは、もうどうでもよくなる。蓄財しても仕方がない。それで、本を書こうと決めたんです。何か、世の中のためになれることはこれしかない、と。というのも、ぼくが日本に帰ってきたときに、自分がヨーロッパで学んできた西洋音楽史も含めた西洋の歴史と、日本の教科書に書いてあるような西洋の歴史が、まったく別物だということに強い違和感を感じていたのです。ぼくは、日本の大学も出ていないので、アカデミズムのしがらみもない。そのような視点で描かれた書物もあっていいはずだし、それを書いてみよう、と。
そして、2週間くらいで書いたのが『フランツ・リストはなぜ女たちを失神させたのか』でした。
——新書という形で、普段クラシック畑にいない人たちにも手に取りやすく、読み物としても面白い。新しい形のリストの評伝として、大変話題になりましたよね。
浦久 ありがとうございます。変なタイトルだと散々言われましたが、これまでの音楽の本とは違うんだと伝えたくて必死でした。音楽家が生きた時代や、当時の空気感を伝えたいと思うあまりに、エレガンスとシックの精神の違いにふれてみたり。そんなことを書いてあるような音楽の本って、ありませんよね(笑)。
本が好きすぎて、私は本になりたい
——その後は、非常に俯瞰的に音楽の歴史を捉えた『138億年の音楽史』や、意外にもこれまで日本で1冊も伝記が書かれていなかったパガニーニ伝を出版される一方、人気作家さんとピアニストの共演するコンサートプロデュースなど、常にありそうでなかった取り組みを実現されています。
浦久 どれも、どうすれば文化としての音楽を伝えられるかという視点ではじめた企画です。でも、それを気づかせてくれたのが、本でした。本の仕事は、もしかしたらぼくが書いたもので、一人でも二人でも、何か気づきを得てくれるかもしれないと思えると、誰かのためになれる気がしてうれしいですね。ぼく自身が、いろんな本に救われ、道筋をたててもらったわけだし、本にとても感謝してる。生まれ変わったら本になりたいくらい(笑)。
——こちらの浦久さんのお部屋にも、ものすごい数の蔵書が綺麗にならんでいますね。
浦久 ここにあるのは、日本に帰国してから買い集めた一部です。いま、建築家の伊東豊雄さんといっしょに、軽井沢に「みんなでつくる森と本の家」というプロジェクトを立ち上げました。若い人たちとともに、本に囲まれた空間でともに文化を語り合えるような小さな図書館を作りたい。コロナの影響で、少し延期になっているので、いろいろとアイディアを膨らませているところです。


文化的な生き方とは
——今あらためて、私たちはどう音楽やさまざまな芸術に向き合い、文化というもの捉えていくべきかをお尋ねしたいです。
浦久 文化は、ある意味では「どうでもいいもの」で「寄り道」でもあるといえるかもしれない。現代は何でも効率化が重視され、無駄を省こうとする。どういうやり方をすれば最短かが考えられる。
ぼくはまるでその逆の生き方をしてきてしまって、無駄しかない人生。だけど考えてみたら、それが文化的な生き方といえるのかもしれない。寄り道をして生きるということ。
——名言出ました!
浦久 もちろん日々生計を立てていくのは大変です。合理的に考えなければいけないときもある。でも、「生きるために食べるのか」それとも「食べるために生きるのか」といえば、ぼくは後者の人生はしたくない。挫折や劣等感まみれの人生でしたが、どこかで守ろうとしていたのはそういうことかも。そういうところでしか、自分を保てなかったのかもしれませんね。
——浦久さんの、今後の夢を教えてください。
浦久 やはり、未来へ文化のバトンを手渡していきたいです。音楽と社会を結ぶ文化的な人材をサポートすることをやっていきたい。クリエイティヴィティを育てる文化教育にも興味があります。
今の若い人たちには、ぼくたちの頃よりも生き方の選択肢があると思いますよ。みんな「安定」というのをすごく守りたがるけれど、 嘘をつかないとか、人を騙さないとか、誠実に生きるとか、人間としてのルールみたいなものを最低限身につけていれば、日本ではそう簡単に飢え死にはしない。若い人たちがのびのびとクリエイティヴィティを発揮できるような、文化的な社会を作っていきたいですね。





関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest