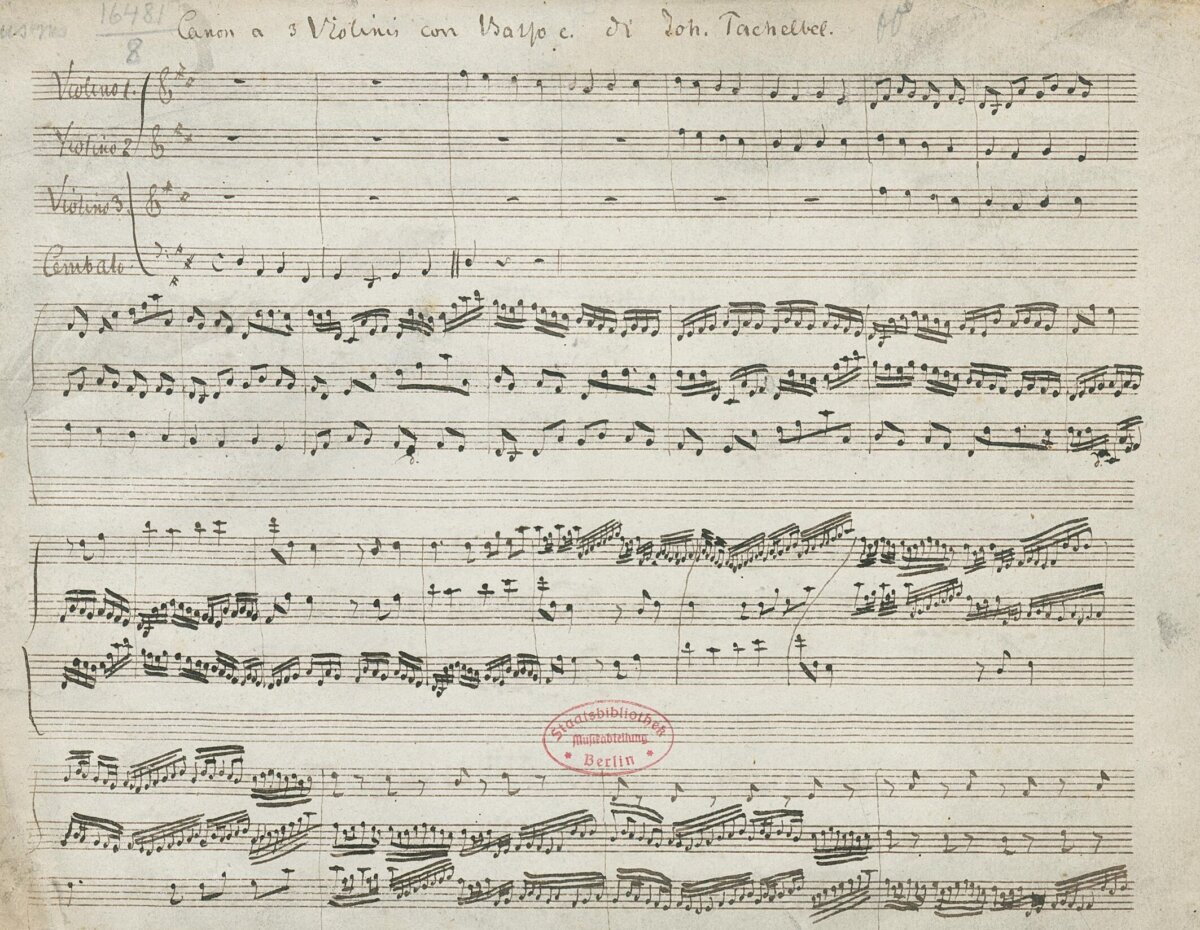チェリスト長谷川陽子——自慢の練習室でデビュー35周年のベートーヴェンを準備中!

2022年にデビュー35周年を迎えたチェリストの長谷川陽子さん。リサイタルに向けて目下準備中とのことですが、普段はどんなお部屋で練習しているのでしょう。今回は特別に自慢の練習室を大公開! デビュー当時から長谷川さんをよく知る伊熊よし子さんが、今改めて取り組むベートーヴェンへの情熱と、歴史とこだわりが詰まった練習室のお話を訊きました。

東京音楽大学卒業。レコード会社勤務、ピアノ専門誌「ショパン」編集長を経てフリーに。クラシック音楽をより幅広い人々に聴いてほしいとの考えから、音楽専門誌に限らず、新聞、...
若いときには理解できなかったベートーヴェンの「新約聖書」に今向き合う
日本を代表するチェリストのひとり、長谷川陽子が今年デビュー35周年を迎える。これを記念して、5月19日に東京文化会館小ホールでベートーヴェンのチェロ・ソナタ全曲演奏会を開くことになった。J.S.バッハの「無伴奏チェロ組曲」が「チェロの旧約聖書」と呼ばれるのに対し、全5曲のチェロ・ソナタは「チェロの新約聖書」とも称される。
「20代でベートーヴェンのチェロ・ソナタ全曲を演奏したことはあるのですが、本当に理解して弾いていたのかどうかわかりません。特に第5番は難しかったですね。初めて第5番を弾いたのは10代後半でしたが、特に第2楽章が理解できませんでした。以来、全曲演奏をすることはありませんでした」

色彩豊かな音色と音楽性を持ち合わせた、日本を代表するチェロ奏者の一人。2022年デビュー35周年。
フィンランドのシベリウス・アカデミーを首席で卒業。国内外の主要オーケストラとの共演、全国各地でのリサイタル、室内楽、朗読との共演など活動は多岐にわたる。ロストロポーヴィチ国際チェロ・コンクール特別賞、新日鉄フレッシュ・アーティスト賞、第9 回齋藤秀雄メモリアル基金賞等、受賞多数。桐朋学園大学音楽学部准教授。
当時、全曲録音の話も持ちかけられたが、時期尚早だと考え、実現しなかった。その後、しばらくベートーヴェンとは距離を置く形となっていたが、コロナ禍で再びベートーヴェンの作品と向き合うことになった。
「みなさん同じだと思いますが、コロナ禍ですべてが変化し、演奏する機会もまったくなく、しばらく楽器のケースを開けることすらできない状況に陥りました。そんなとき、たまたまベートーヴェンの楽譜と対峙する機会があり、ベートーヴェンが私を音楽へと引き戻してくれたのです。
ベートーヴェンは苦しみ、悩み、もがき、革命を起こした人、生涯に渡って戦っていました。いつも新しい世界を創造し、そのエネルギーの大きさは計りしれません。そのベートーヴェンの音楽が、“私には音楽しかない”と思い知らせてくれたのです。“楽器から離れ、音楽から離れ、いったい何をやっているんだ”と怒られた感じです。そこからベートーヴェンのチェロ・ソナタに向き合うようになり、これまでのさまざまな経験やいろんな人との共演を重ねてきたことなどが積み重なり、自分なりのアイデアでベートーヴェンの人間としてのエネルギーを表現したいと思うようになったのです。今回の全曲演奏会では、その思いをステージで存分に発揮したいと思っています」
その偉大な5曲を、今回は実力派ピアニスト、松本和将とともに演奏するが、それに先駆け、5月25日にはふたりによるベートーヴェンのチェロ・ソナタ(全曲)録音もリリースされる予定だ。

『ベートーヴェン:チェロ・ソナタ全曲|長谷川陽子』
♬ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第1番~第5番、《魔笛》の「愛を感じる男の人たちは」の主題による7つの変奏曲、《魔笛》の「恋人か女房か」の主題による12の変奏曲 、《マカベウスのユダ》の「見よ、勝利の英雄の来るのを」の主題による12の変奏曲
演奏:長谷川陽子(チェロ)、松本和将(ピアノ)
NARD-5079/80 4,400円[税込 2枚組]
「録音は4日間でしたが、松本さんはとても正統的な演奏で、最初はかなり感情を抑制していました。でも、耐えて耐えて、最後に爆発するというスタイル。そのコントロールのすごさに感服しました。私は最初から花火を打ち上げたい方ですので、異なるアプローチがよい方向に作用し、充実したレコーディングとなりました。
今回はヘンレ版の新しくなった版を使用し、ふたりでこまかく変更箇所などをチェックして話し合いながら進めました。でも、私はもっとよく弾ける、もっとよくなると思っています。ですから、10年後、20年後に再録音に挑戦したいと考えています」

大きな窓の部屋で研鑽を積んだフィンランド時代
長谷川陽子は9歳から井上頼豊に師事し、桐朋学園大学に進学後、1989年よりフィンランドのシベリウス・アカデミーに留学してアルト・ノラスに師事することになった。
「井上先生がノラスに演奏を聴いてもらえるように心配りをしてくださり、フィンランドで研鑽を積むことができました。ノラスは常に弾きながら教える教授法で、弟子はみんなそれを見ながら、聴きながら、自分で奏法を探していくという教え方です」

もっとも印象的だったのは、ベートーヴェンのチェロ・ソナタ第3番の第1楽章の最初の8小節の教え。長谷川陽子は半年間、この8小節だけを弾くというレッスンを受けた。
「8小節だけを半年間ただ弾くだけ。音の出し方、ビブラート、フレージング、音を出す前の呼吸、ポジション移動などをこまかく学んでいく。来る日も来る日も8小節だけ。もう一種のアレルギーのようになってしまい、ベートーヴェンのチェロ・ソナタは二度と弾きたくないとまで思ってしまいました。でも、いま考えると、ノラスの教えから得ることはものすごく大きく、その後に学んださまざまなことも含めて私の大きな財産となっています」

このフィンランド時代の話で印象的なのは、彼女の部屋の様子。フィンランドの冬は長く寒い。家は陽光を少しでも取り入れるよう工夫され、窓が大きくとられている。長谷川陽子は部屋で練習しているとき、窓の向こうに森が見え、その先に少しだけ海がのぞく。そこに夕日がゆっくり沈んでいく様子を感動しながら見続けた。まるで映画のワンシーンを見ているような光景である。
「フィンランド人は思慮深い人が多く、雪のなかで静謐な時間を過ごすからでしょうか。私はその雰囲気が大好きでした。シベリウスが“静寂が語る”ということばを残していますが、まさにその感覚がピッタリですよね。いまはずいぶんおしゃれな国になり、教育も福祉も経済も世界的に注目を集めるようになりましたが、私がいたころは、じゃがいもとニシンくらいしかないような(笑)、とても素朴な国でした。それがまたなつかしいんです」

父から譲り受け、自分流にカスタマイズしたこだわりの練習室
そんな彼女がいま、自身の響きをひたすら追求し、新たな奏法や解釈、表現を探求しているのが、ご自宅の練習室である。
ここは天井がとても高く、20帖ほどの空間には広々とのびやかな空気が漂っている。ウォーターサーバーやコーヒーメーカーが設置され、練習に訪れた共演者たちが自由に飲める雰囲気だ。

「私が小学校1年生のときにこの家に引っ越し、アマチュアですがヴァイオリンを演奏していた父が練習やクァルテットのメンバーとの音合わせに使っていました。母もピアノを演奏していました。
この部屋は昭和の建物ですから、当時は音響がとてもデッド(ほとんど残響がない)で、それがふつうだったんです。デッドな響きの部屋で練習していれば、どんなデッドな音響のホールでも対応できると考えられていたのです。でも、現在は各地のホールがとてもすばらしい音響を備えていますから、そうした考えではなく、練習もいい響きのところで行なうべきだというように変わりました」

父親の長谷川武久氏は著名な音楽評論家で、当時はさまざまな名手たちがこの部屋を訪れたという。
「父のヴァイオリンは道楽のようなものでしたが、クァルテットの練習のときには部屋に近づけない感じでした。いろんな音楽家が訪れ、ダニール・シャフラン(ロシアのユダヤ系チェリスト、1923~1997)、アンナー・ビルスマ(オランダのバロックチェロ奏者、1934~2019)、アマデウス弦楽四重奏団(イギリス、活動期間1948~1987)はよく覚えています。
ビルスマはフィンガリングのことをこまかく教えてくれ、1本1本の指が独立して動く方法などを伝授してくれました。父は(ヴァイオリン指導者の)鷲見三郎さんの本も手掛けたため、ヴァイオリンの重鎮たちもこの部屋で打ち合わせをしていました。当時、父が作ってもらったピアノは、杵淵ピアノで、いまでも健在です」
まさにこの部屋は伝説の音楽家が集う場所であり、その空気をいまだ纏っている感じだ。杵淵ピアノは、カリスマ調律師といわれた杵淵直知(1925~1979)の製作によるもので、とても貴重なピアノ。この部屋を訪れたアーティストがみな驚き、感嘆する。

「父が亡くなってからは私の練習室となり、数年前に大規模なリフォームを行ないました。音響を工夫し、楽譜が見やすいように照明にもこだわりました。ここは上から見ると、グランドピアノの形をしているんですよ」

「デッドな響きのときは次から次へと弾かなくてはなりませんでしたが、いまは響きを追うことが可能になり、私には合っています。ここでベートーヴェンもじっくり練習し続け、さらに次のステップを目指したい」
使用楽器は1700年製マッテオ・ゴフリラーと1850年製ヴィヨーム。ヴィヨームは井上先生、ゴフリラーはノラス先生の推薦による。その名器を携えてリサイタルのベートーヴェンに挑む。彼女の気概を音楽から受け取りたい。

関連する記事
-
インタビュー【Q&A】ヴァイオリニスト村田夏帆さん、世界が注目する17歳のオフ時間
-
インタビュー上野通明に50の質問!〈前編〉音楽家になると決めたのはいつ? 1日の練習時間は?...
-
記事チェリスト宮田 大にきく 多様なジャンルのプロ30人との“音楽の対話”から得たも...
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest