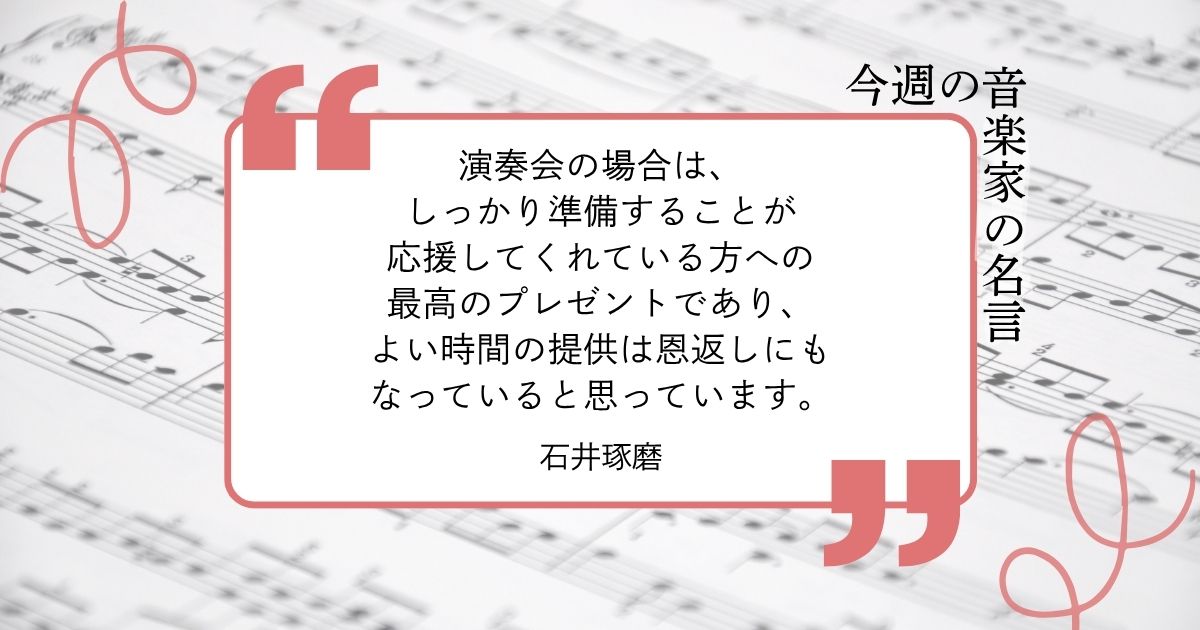ザ・ビートルズはクラシック音楽に影響を受けていた!? 聴き比べプレイリスト

2021年11月25日(木)~27日(土)に、未公開映像を含むオリジナル・ドキュメンタリー・シリーズとして、『The Beatles: Get Back』がDisney+で独占配信されるビートルズ。今なお注目を集める彼らの楽曲の魅力はどのようなところに隠されているのでしょうか? クラシック音楽の専門家でありながら、ビートルズ研究もされている、田村和紀夫先生にお聞きしました。

1952年、石川県七尾市生まれ。国立音楽大学楽理科卒業、同大学大学院修士課程修了。専攻は音楽学。尚美学園大学 芸術情報学部 音楽表現学科 名誉教授。クラシックからビー...
ビートルズが登場した時、聞いたこともないサウンドに世界が衝撃を受けた。当時はいわゆるポップスが全盛だった。アメリカで50年代からローティーン向けに商品化された音楽であり、遠いルーツはヨーロッパのクラシック音楽にあった。旋律美を武器とし、いわゆる古典和声にもとづき、歌い上げるサビをもつ構造で、少年・少女の心を鷲づかみにした。たとえば、これらの楽曲の大量生産の基盤ともいえるコード進行は、C→Am→F→Gといった和声法の根幹をなす終止形(カデンツ)そのものだった。
ビートルズの出現前夜はアメリカを中心に、フランスのシャンソンやイタリアのカンツォーネなども巻き込み、ポップスの黄金時代を迎えていた。「ヘイ・ポーラ」「悲しき雨音」「アイ・ウィル・フォロー・ヒム」「アイドルを探せ」といった音楽が醸し出す、淡い恋の気分にまどろんでいたティーンエイジャーに、ビートルズの音楽は冷水を浴びせたようだった。
「ヘイ・ポーラ」ポールとポーラが1962年に発表した楽曲。
他ジャンルを貪欲に吸収した初期
ビートルズの音楽の新しさは、ブラック・ミュージックへの接近にあったといわれることがある。だが黒人音楽に直接由来するロックンロールの波はすでに退いており、その再来というのでもなかった。初期のプレスリーに代表される音楽は、リズム・アンド・ブルースを素材として、そのまま白人風にパフォーマンスした例といえる。それに対して、ビートルズは黒人音楽の要素をとり込み、西洋音楽と融合させ、まったく新しい化合物を創り出した。
たとえば最初のアルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』の冒頭を飾る「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア」は、軽快なロックンロールでありながら、ポップス風のサビがある。このことはビートルズがやろうとしたことの革命を示唆している。歌詞や楽器を替えるだけで、1番、2番、3番……と反復を続けるロックンロールは、ダンス・ミュージックの形式(有節形式)だった。しかし、サビは歌のための形式である。つまり「サビつきロックンロール」とは、肉体を鼓舞する「踊り」と、旋律によって詩の内容を心に届ける「歌」の融合だった。これこそロックの土台である。
アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア
彼らは曲づくりで「ミドル・エイト(サビの8小節)」を常に意識していた。さらに、当時のロックンロールやポップスでは複雑すぎる、お洒落なコード(Ⅳm、♭Ⅵ)や6のコードを使ったりもした。ポップスのもとになった、ジャズのスタンダード・ナンバーからの借用だったと考えられる(ポール・マッカートニーの父親はアマチュアのジャズ・マンだった)。いずれにしても、新しさを目指すための意図的な借用だったことは間違いなく、ビートルズ・サウンドに新鮮な彩りを添えることになった。従来の音楽世界を拡大するための初期ビートルズの戦略の縮図がここにある。
クラシックのへの再接近──楽器の使用から、対位法まで
新しいサウンドへの模索は続いたが、第5アルバム『ラバー・ソウル』で大きな一歩を踏み出し、次の『リヴォルヴァー』で決定的な段階を迎えた。
特に後者ではクラシカルな楽器の導入が目立つ。「エリナー・リグビー」の弦楽八重奏(すでに「イエスタデイ」で弦楽四重奏が用いられていた)、「フォー・ノウ・ワン」ではチェンバロとホルン(ホルンは、当時、BBC交響楽団の首席ホルン奏者だったアラン・シヴィルが担当)、シングル「ペニー・レイン」ではピッコロ・トランペット(バッハの『ブランデンブルク協奏曲第2番』がヒントになった)が投入された。
弦楽八重奏が導入された「エリナー・リグビー」
チェンバロとホルンが導入された「フォー・ノウ・ワン」
「ペニー・レイン」と、そのヒントとなったバッハの『ブランデンブルク協奏曲第2番』
ほかにインド楽器のシタールやテープ操作による「アナログ電子音」が導入され、質実なバンド・サウンドから極彩色の音響世界へ変貌した。
しかし、楽器・音源もさることながら、スタイルの変化が重要である。ビートルズ中期の特徴的な様式としては、クラシック音楽的なスタイルの変化がみられる。「エリナー・リグビー」では、冒頭のフレーズとリフレインのフレーズが、最後に同時に重なって出る。複旋律的スタイルであり、クラシックでいう「対位法」である(別の旋律を同時に歌う「クオドリベット」といういい方もある)。これまでいわば表面下に隠れていた有機的な声部処理が、決定打として表舞台に立つ。「フォー・ノウ・ワン」でも間奏のホルンの旋律が、最後にヴァース(邦楽のAメロにあたる部分)の主旋律と同時に出て、絡み合う。似た趣向は「ペニー・レイン」でもあり、「愛こそはすべて」ではヴァースとコーラス(邦楽のサビにあたる部分)の旋律が重なる。
対位法はクラシックの粋ともいえる芸術的意匠であり、ビートルズの中期はそこに最接近した。こういうスタイルがクラシック出身のマネージャー、ジョージ・マーティンに負うところ大なのは想像に難くない。たとえばベートーヴェンの「第九」フィナーレでは「歓喜の主題」と「抱き合え」と歌う主題が順番に出て、最後に二重フーガで組み合わされる。「エリナー・リグビー」「フォー・ノウ・ワン」「ペニー・レイン」など、規模こそ違え、基本的にまったく同じである。そもそも音楽の進行とともに密度を高めていくという発想自体がクラシカルである。
「ラメント・バス」がビートルズを超えて名曲の源泉に
「ミッシェル」では特筆すべきことが起きた。半音階的に下行する低音が発見されたのである。これは西洋音楽におけるバロック期の「ラメント・バス(悲しみの低音)」にほかならない。下の例はバッハの「シンフォニア」ヘ短調であるが、ヘ短調という調性、Fから半音階でCまで下がる音まで「ミッシェル」と同一である。
バッハ「シンフォニア 9番」ヘ短調(再生ボタンを押すと音が流れます)
ラメント・バスは大きな可能性を秘めていた。半音階が醸し出す精妙な表現が可能となる。線的な動きが旋律と同時進行することで、疑似対位法的な面白さが生まれる。古典和声法にはないハーモニーの多様性も広がる。効果的なパターンとして、作曲上の拠りどころともなる。ラメント・バスはバロックの手法であるだけでなく、ジャズのクリシェ(常套句)でもあり、一部のポップスでも使われていた(「マイ・ウェイ」「マイ・フェイヴァリット・シングズ」など)。ビートルズはそれをロックに導入し、広く世に知らしめたことになる。
ラメント・バスを使った楽曲は『ラバー・ソウル』ではポールの「ミシェル」1曲だったが、次の『リヴォルヴァー』で4曲に広がり、続いてジョン、ジョージの作品に拡大する。そしてビートルズを超えて、ロック、あるいはポピュラー音楽全体に浸透し、数々の名曲の源泉となった。シカゴ「長い夜」、エルトン・ジョン「きみの歌はぼくの歌」、レッド・ツェッペリン「天国への階段」等々……その数は枚挙にいとまがない。
関連する記事
-
インタビュー新日本フィルハーモニー交響楽団コントラバス奏者・藤井将矢さん「一音でオーケストラ...
-
インタビューカーネギホール芸術監督が語るユースオーケストラの力~音楽の未来を育て人生を変える
-
インタビュー「体は“生きた楽器”そのもの」ソプラノ・森麻季に聞く、声のコンディションの整え方
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest