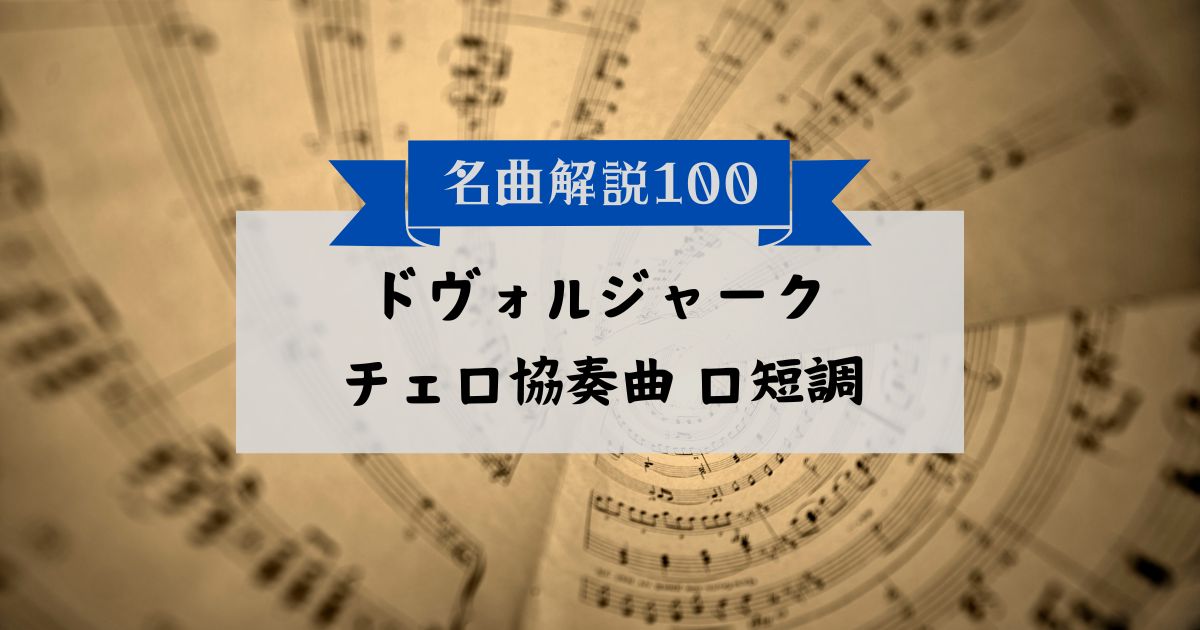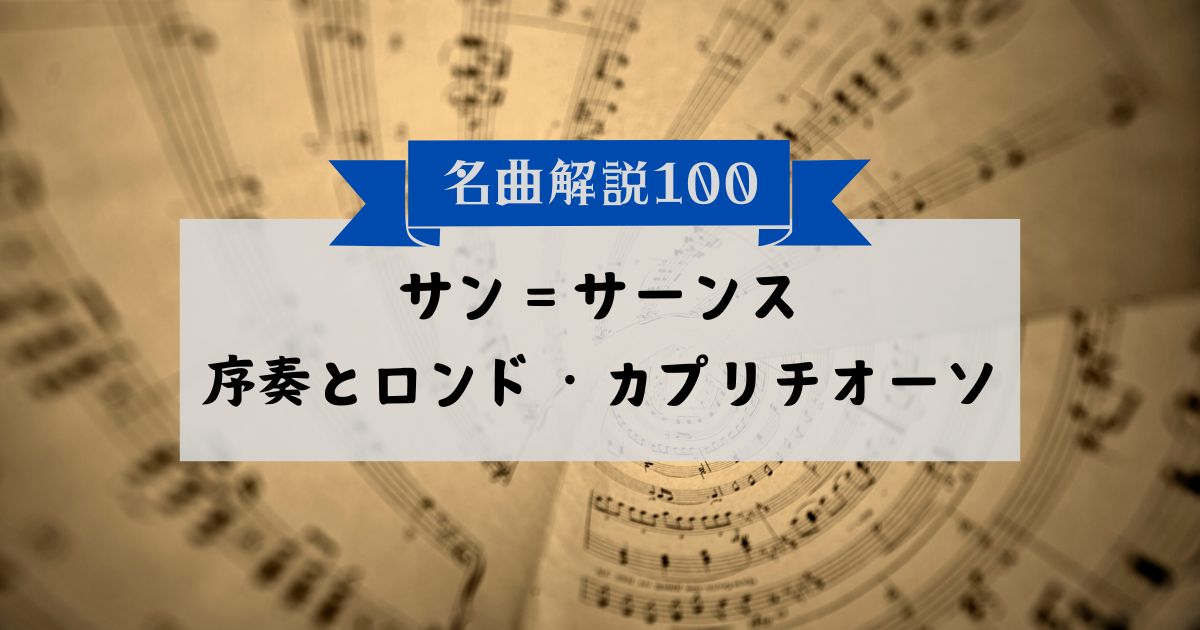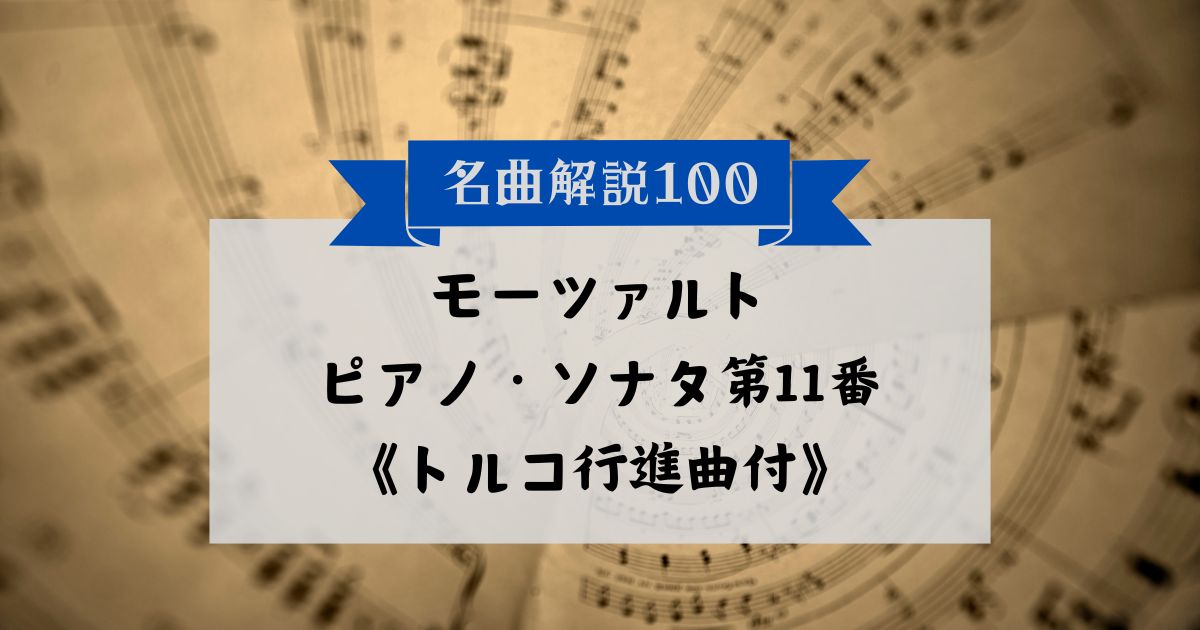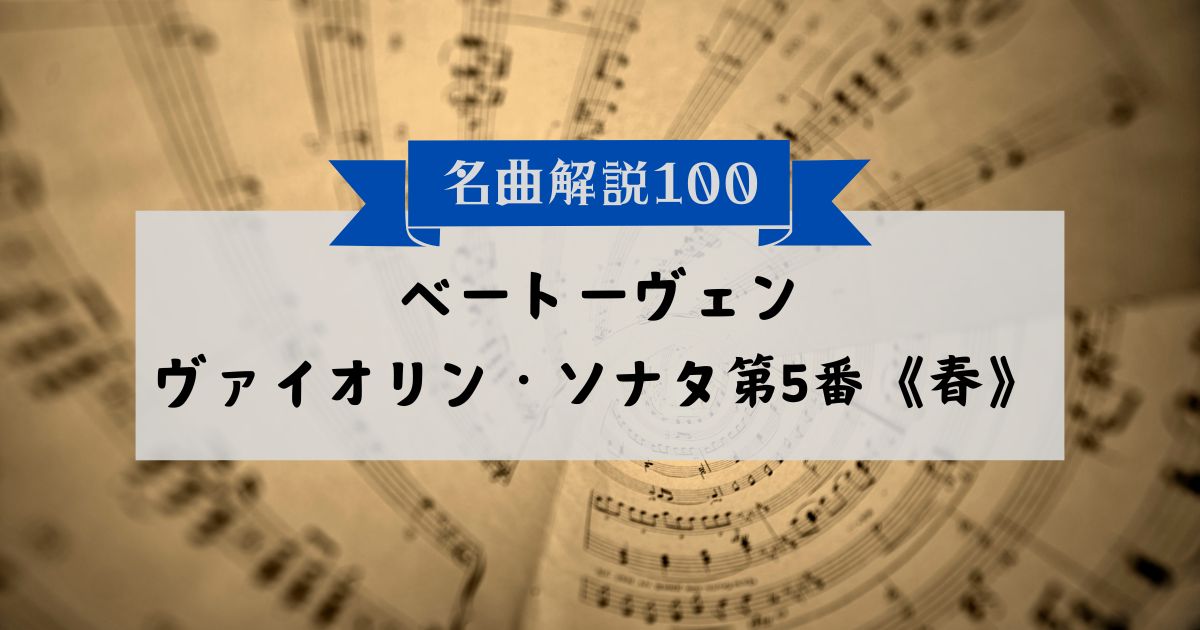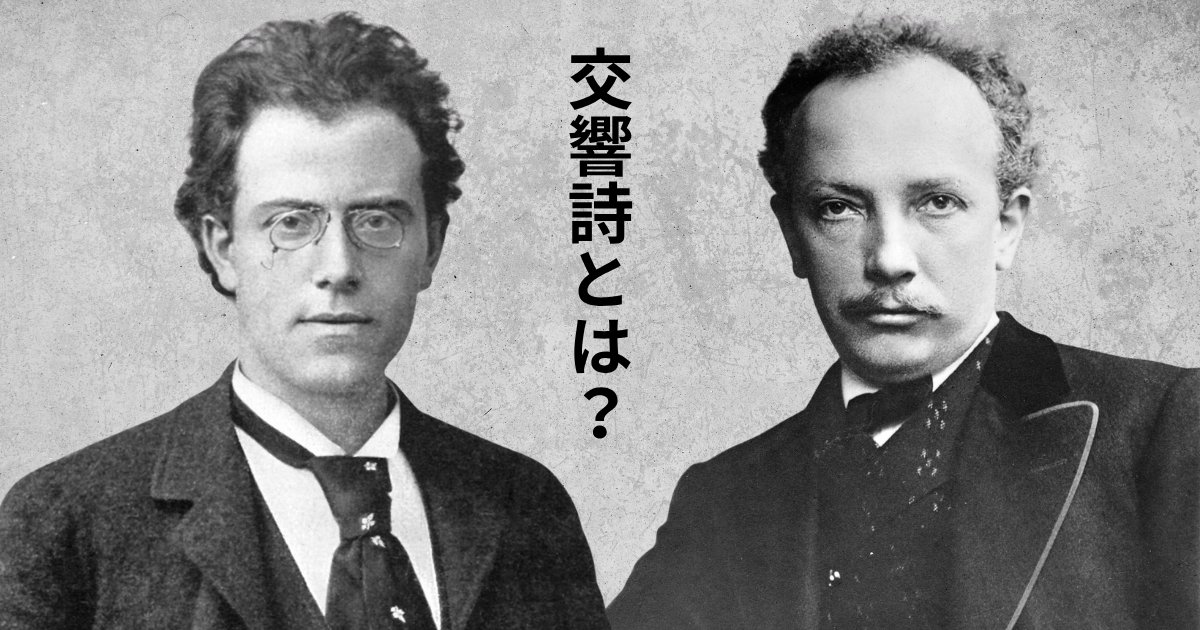ショパンコンクール第2ステージ~日本人5名と海外の通過者、印象的だったピアニスト

10月9日から12日まで、第19回ショパン国際ピアノコンクールの本選第2ステージが開催。日本からは5名が出場しました。現地取材を行なっている音楽評論家の道下京子さんが、日本人コンテスタントの演奏とともに、海外の第2ステージ通過者の中から注目されるピアニスト、そして惜しくも第3ステージ進出には至らなかったものの、印象に残ったピアニストの演奏をレポートします。

2019年夏、息子が10歳を過ぎたのを機に海外へ行くのを再開。 1969年東京都大田区に生まれ、自然豊かな広島県の世羅高原で育つ。子どもの頃、ひよこ(のちにニワトリ)...
詩情、繊細さ、奥行きの深さ……日本人5名が魅せた「前奏曲」
【桑原志織】日本人離れした豊かな音量とパワー
《舟歌》では、まろやかな音でメロディを美しく紡ぎあげていく。アリアのようにたっぷりと歌い上げ、とくに嬰ハ長調の箇所におけるポルタメントのような艶やかな表現は、この上なく美しい。また、ペダルを駆使して豊かな響きを生み出した。
「24の前奏曲」作品28(抜粋)においても、奥行きの深い音楽を築き上げた。「幻想曲」では、ほの暗い情熱をほとばしらせ、濃密なロマンティシズムを披瀝。日本人離れした豊かな音量とパワーも彼女の魅力。《英雄ポロネーズ》では、重厚な低音と右手による高音部の煌めくようなサウンドが相まって、精彩に富んだ音楽を聴かせくれた。
(10月10日午後・スタインウェイ)

【中川優芽花】ポーランドの栄華を感じさせるポロネーズ
プログラム冒頭は、「ポロネーズ第6番」。ポロネーズ・リズムが高らかに鳴り響き、そのフレーズには典雅な雰囲気も漂う。低音をしっかりと表わし、揺るぎないハーモニーを生み出し、音楽に豊かな彩りと立体感をもたらす。ポーランドの栄華を感じさせるポロネーズの演奏であった。
「24の前奏曲」では、24曲それぞれの性格を大胆に表わす。彼女の指から紡ぎ出される細やかな音の遠近や微細な緩急は、ショパンならではの詩情を生み出した。
(10月11日午後・カワイ)

【進藤実優】集中度のきわめて高い演奏
集中度のきわめて高い演奏であった。「24の前奏曲」の第1曲。フレーズを丁寧に重ね合わせ、感情を高揚させる。第2曲における淡くデリケートな響きは、よりいっそうメランコリーを醸し出した。心の襞をなぞるようなタッチで綴られた第13曲。メロディを言葉のように語り、一編の美しい詩のようにまとめ上げた。そして、第16曲では、進藤ワールド全開!
《英雄ポロネーズ》でも、士気を鼓舞するかのように高らかにポロネーズ・リズムを鳴り響かせる。
(10月12日午前・スタインウェイ)

【牛田智大】これほどまでに激しく感情を吐露する彼を見たことがない
《マズルカ風ロンド》では、初期の作品の清々しさをスタインウェイの煌びやかなサウンドで表現。変ロ長調のエピソードでは、メロディを語りかけるように奏でる。また、色彩の変化もひじょうに美しい。
「ピアノ・ソナタ第2番」の第1楽章において、これほどまでに激しく感情を吐露する彼を私は見たことがない。そして、「24の前奏曲」第19番から第24番。細密画を描くような繊細さと淡い詩情を湛えた優美なショパンであった。とくに、第20番。悲しみを静かに噛み締めるような表現は感動的であった。
(10月12日午後・スタインウェイ)

【山縣美希】作品が持つ魅力を自然な形で表現
プログラムを通して、作品が持つ魅力を自然な形で表現していた。プログラム冒頭は《英雄ポロネーズ》。たっぷりと楽器を鳴り響かせ、エネルギッシュにポロネーズ・リズムを刻んでいく。一方、中間部後段では、消えゆくように繰り返されるモティーフに儚さを感じた。
そして「24の前奏曲」全曲。24の音の詩を、透き通るような粒立ちの美しいサウンドで丁寧に綴り上げ、ひとつの物語にまとめ上げた。
(10月12日午後・カワイ)

海外の第2ステージ通過者から
Piotr Alexewicz(ポーランド)
2000年生まれのポーランドのピアニストで、前回のこのコンクールのセミ・ファイナリスト。それまでのショパン演奏とは趣を異にしたパフォーマンスであったと思う。鋭敏な打鍵によって音の動きを克明に刻み込み、クリアーなショパンを創出。生気に満ちたパフォーマンスであった。
(10月9日午前・カワイ)

Kevin Chen(カナダ)
ジュネーヴとA.ルービンシュタインの両国際コンクールの優勝者で、2005年生まれ。このラウンドでも、「エチュード」作品10全曲や「24の前奏曲」(抜粋)などで完成度の高い演奏を示した。切れ味鋭いタッチから、鮮明な音の情景が繰り広げられていく。とくに、テンポなどの作品へのアプローチでは、現代的なフィーリングが見られ、新しいショパンを感じた。
(10月9日午後・スタインウェイ)

エリック・グオ(カナダ)
2002年生まれで、第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクール優勝者。抜群の指先のコントロールによって多彩な音の質感や色感を生み出し、楽器もしっかりと鳴り響かせていた。緻密な音楽設計の上で、感情を大きく表出。演奏の精度もひじょうに高い。
(10月10日午前・スタインウェイ)

David Khrikuli(ジョージア)
David Khrikuliは2001年生まれ。子どものころから天才少年と呼ばれていたそうだ。落ち着いた打鍵は、あたたかく重みを帯び、聴衆を作品の内奥へといざなっていく。「24の前奏曲」においても、さまざまな性格の24曲を一つのしなやかな流れに束ね上げ、スケールの大きな音楽を繰り広げた。
(10月10日午前・スタインウェイ)

イ・ヒョク(韓国)
2000年生まれ。ロン=ティボー国際ピアノコンクール優勝者で、前回のこのコンクールのファイナリスト。基本に忠実で、安定感に秀でたパフォーマンス。感情表出も絶妙にコントロールし、作品を手堅くまとめ上げている。
近年、思い入れたっぷりの「スケルツォ第2番」の演奏が多いなか、彼のこのスケルツォにおいては喜怒哀楽の表情がとても自然で、素顔のショパンを見た思いがする。
(10月10日午後・スタインウェイ)

エリック・ルー(アメリカ)
1997年生まれ。リーズ国際ピアノコンクール優勝者で、前々回のこのコンクールでは第4位入賞。第1ステージと同じエリアで彼のパフォーマンスを聴いていたが、その時よりも音量や音の重みは抑えられていたと思う。彼のタッチは確信に満ち、音に一つひとつを刻み込んでいくようなその演奏は、言葉では言い尽くせないほどに美しい。
「ワルツ第7番」では、淡い情感に訴える表現で、聴くものの心に深く静かにしみわたる。
(10月11日午前・ファツィオリ)

Tianyao Lyu(中国)
このコンクールでは、中国のティーンエイジャーの活躍も注目を集めている。2008年生まれの彼女はその代表的な存在。音の質感や色合いを自在に表わし、スケールの大きな演奏を披露。輝きに満ちた美しい音や伸びやかな情感も彼女の魅力。
(10月11日午前・ファツィオリ)

Piotr Pawlak(ポーランド)
1998年生まれで、第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクールで第2位を受賞。数学者としても知られる。彼の演奏は、どこか懐かしさが漂う。楽器をたっぷりと鳴り響かせ、感情の起伏の大きな音楽を聴かせてくれた。独創性豊かな演奏であるが、その独特な解釈の点で賛否が分かれるかもしれない。作品の最終音とその次の作品の第1音がエンハーモニー的に結び付けられたプログラムも興味深い。
(10月11日・カワイ)

Zitong Wang(中国)
1999年生まれで、ブザンソン国際コンクール入賞者。筆者は、第1ステージから彼女に注目している。彼女の奏でる音楽には、どこか翳りがあり、演奏に独特な色合いをもたらしている。このラウンドの選曲は個性的であった。
「ノクターン」作品15-2における淡い感傷的な響きは、聴く者の心を捉える。そして、あまり演奏される機会のない《プレスト・コン・レジェレッツァ》では、卓抜な指さばきで愛らしい世界を披露。「24の前奏曲」から第24番では、ほとばしる情熱をダイナミックに表出した。
(10月12日午後・カワイ)

第3ステージには進めなかったけれど、印象に残ったピアニスト
ヨナス・アウミュラー(ドイツ)
1998年生まれ、ブラームス国際コンクール優勝者で、仙台国際音楽コンクールと浜松国際ピアノコンクールにおける第2位受賞者。このコンクールでも、とても構築的な演奏を披露した。深い思索から生み出された密度の高い音楽は、強い説得力を持つ。
「幻想曲」では、気高さ、誇り、勇壮さ、絶望、安らぎなど、さまざまな情感が描き出され、あたかも人間のドラマを聴く思いがした。
(10月9日午前・カワイ)

Kai-Min Chang(台湾)
2001年生まれで、前回のこのコンクールでは第2ステージまで進出。リーズ国際ピアノ・コンクール第4位を受賞した実力派。傑出したペダルワークは、好演に寄与していた。
「ピアノ・ソナタ第1番」は、このラウンドにおける優れた演奏のひとつに数えられる。この作品は、ショパン初期の習作であるが、彼はこれを手堅くまとめ上げ、同時にショパンらしい優美な趣も醸し出した。
(10月9日午前・スタインウェイ)

Xuehong Chen(中国)
地元の聴衆からひときわ大きな歓声が沸き起こったのが、1999年生まれのXuehong Chenのショパンだ。音の呼吸やテンポ、タッチ、そして奇をてらわない解釈など、ありのままのショパンの音楽を私たちに示してくれた。
明るく艶やかなサウンドに彩られた彼の《舟歌》は、若き日のダン・タイ・ソンの演奏を髣髴とさせる。やや音のパワーに欠いていたものの、作品の本質を捉えたパフォーマンスであった。
(10月9日午後・スタインウェイ)

関連する記事
-
インタビューワルシャワ・フィルのファゴット奏者がショパンコンクールを振り返る
-
インタビューワルシャワ・フィルのコンマスがショパンコンクールを振り返る
-
記事ピオトル・パヴラク、数学は音楽づくりにも影響あり!?
ランキング
- Daily
- Monthly
関連する記事
ランキング
- Daily
- Monthly
新着記事Latest